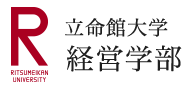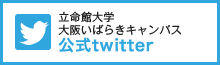井登 友一教授
Yuichi Inobori
- 研究分野
- サービスデザインによるイノベーションの研究
- 主な担当科目
- メディア・デザイン論、デザイン経営論
-
Q1現在の研究テーマ(または専門分野)について教えてください。
新しい価値(イノベーション)を生みだすデザインについて研究しています。「デザイン」と聞くと、皆さんの多くは工業製品やスマホアプリなどの色や形などの見た目を美しく、カッコよくすることを思い浮かべるのではないでしょうか。それらのことはデザインの重要な役割ですが、わたしが研究しているデザインは「目には見えない体験」や「触れることができない経験や感情」のようなものを主に対象にしています。人びとにとっての良い体験を実現し、これまでには存在しなかったような新しい価値=意味を生みだせるような製品・サービスやビジネスをつくる原動力となるようなデザインのあり方と方法論を「サービスデザイン」と呼びます。わたしは、様々な人びとや企業がこの「サービスデザイン」を活用することで、新しい価値づくりを実践するための理論や方法論の開発に取り組んでいます。
-
Q2どんな学生時代を送っていましたか。
高校生の頃にある有名なジャーナリストが書いた本をたまたま読んだことから新聞記者に憧れ、大学(学部)では文学部社会学科に所属し新聞学という学問を専攻しました。自分の好きな領域を勉強することは好きでしたが、同じく大好きだった音楽(ジャズなどの軽音楽)の演奏活動にも没頭し、友だちとの他愛のない会話に明け暮れていたらあっという間に大学の4年は過ぎてしまいました。何ひとつすごいことを成し遂げたわけではない、何でもない日々の繰り返しでしたが、今思い返すと人生におけるかけがえのないステキな4年間だったなあと感じます。
-
Q3現在の専門分野を志した理由・研究者になったきっかけを教えてください。
大学で色々なことを学ぶ中で、様々な現場(フィールド)に足を運び、そこにいる人や情報と関わることで社会がどうなっているのか?なぜそうなっているのか?を理解する社会調査のアプローチに強い興味を持ちました。それをきっかけに、人びとや社会のあり方を深く理解するためのリサーチ(デザイン・リサーチと呼びます)を通じて、より良い製品やサービスを考えるデザインやマーケティングを仕事にするようになりました。その後、20年以上デザインの実務家として仕事をする中で、もっと広い視野と学識からデザインについて研究したくなり、40歳を過ぎてから社会人として大学院に進み、デザインとイノベーションの関係について研究するようになり現在に至ります。
-
Q4高校生へメッセージをお願いします。
今の世の中では、「答えがはっきりしていてわかりやすいもの」や「すぐに役に立つこと」が好まれます。なぜなら「コスパ」いいからです。もちろん、それらは人間が賢く効率よく社会生活を送る上で大切なことではありますが、簡単に理解できることや、すぐに手に入れられるスキルはコスパがいいけれども賞味期限が短いものでもあります。すぐには答えが出ないような曖昧な問いや、そもそも決まった正解すらないようなことを一生懸命考え、自分なりの考えをひねり出すことは悶々としてスッキリしないし、しんどいことかもしれません。けれども、そのような経験を積み重ねることは、思考の足腰を鍛える何よりのトレーニングになります。社会に飛び込む前に大学で過ごす4年間は、一見コスパが悪いように見えたり、ムダに思えるようなことに対して、疑問や好奇心をフルに発動させて没頭できる貴重な時間です。ぜひ私たちと一緒に色々なことを探索しましょう。
■おすすめの書籍や映画
■書籍
・ジェームス W.ヤング『アイデアのつくり方』(竹内均(解説), 今井茂雄(翻訳), 1988年, CCCメディアハウス)
・梅棹忠夫『情報の文明学』(1999年, 中央公論新社)
■映画
・ジュゼッペ・トルナトーレ『ニュー・シネマ・パラダイス』1988年
・ロベルト・ベニーニ監督『ライフ・イズ・ビューティフル』1997年