オープンゼミナール2021
「多様性に騙されるな!
〜アートに隠された光と影〜」
南川ゼミ(チーム名:のりーず)
東山 真子さん、伊藤 佑珠さん、髙橋 栞奈さん、永井 友梨さん、山崎 智香恵さん
2021年度国際関係学部オープンゼミナールで「多様性に騙されるな!〜アートに隠された光と影〜」と題して発表を行った南川ゼミのみなさんにお話をうかがいました。
オープンゼミでの発表内容を教えてください。
近年、BLMなどをきっかけに国際社会において話題になっている「多様性」ですが、そもそも「多様性のある社会とは何なのか」という疑問を私たちは提示しました。アート界においても多様性を求める声が高まっていることに着目し、ジェンダー・人種・マイノリティの観点から多様性の光と陰について焦点を当て、その二面性について分析しています。
私たちは「真の多様性」とは、数字的な「システムによる平等」によって達成されるだけでは決して十分ではなく、お互いが「個人」をリスペクトし合える社会を目指すべきではないかと考えました。
発表テーマを選んだ理由は?
「多様性」は私たちのゼミ活動で取り組んでいる大きなテーマの一つですが、アートという分野に注目したきっかけは春学期のゼミ活動で取り扱った書に「多様性とアート」について書かれている章があったことです。私たちはグループで時間をかけて一つの大きな研究に取り組むのなら、研究発表の聞き手にとって馴染み深く、且つ斬新な切り口で研究をしたいと考えました。そこで、美術館(アート)という分野は馴染み深いが非日常感のあるテーマであり、私たちにとっても新しい発見になるのではないかと考え、「美術館(アート)×多様性」をテーマにしました。

当日寄せられた質問や意見、本番で印象に残ったことを教えてください。
私達の主張に関する深掘りや結論に対する疑問が多く寄せられました。また、BLM運動との関連について興味を持たれる方も多い印象でした。「多様性とアート」という研究対象に関する肯定的な意見が多くありましたが、一方でテーマ設定と内容に関する指摘など、私達では気づき得ない意見も多くあり、非常に勉強になりました。
本番で印象に残ったことは、テーマ設定に関心を持ち、聴きに来てくださった方が予想以上に多かったことです。世界共通語ともいえる「アート」をテーマにしたからこそ影響力が大きく、多くの方にとって多様性について考えるきっかけになったのでははないかと感じました。
本番を迎えるまでのストーリーを聞かせてください。
夏休みが始まる前からテーマと問いを決めて情報収集を始めたので、動き出しは早かったと思います。夏休み中もZOOMを使って10回以上会議をしました。その会議をスムーズに進行させるために、情報収集やスライド作成などは会議までに各々するようにしていました。
大変だったことは「多様性」とは何か、これからどんな多様性の社会を目指すべきなのか、といった抽象的なことを具体的にわかりやすく定義づけをすることでした。また、授業時間外での活動であるため、就職活動やサークル活動、アルバイトといった他の取り組みとの両立が、時間的・体力的にハードでした。
オープンゼミナールを通じて学んだこと、今後に活かせることがありましたか?
授業の課題レポートでは取り組まないレベルで深いところまで考えることができ、物事の本質を的確にとらえて深く考察するという点で、卒業論文を執筆するにあたっての良い練習となったと思います。
また、グループのメンバーと複数人で話し合って完成させることによって問題を多くの視点から見たり、考えたりすることができたのが新鮮でした。物事の流れを大まかにとらえたり、反対に細かい点を解明したり、更に視点を変えたりして物事を多角的にとらえることが研究に必要なのだと学びました。就職してからも、物事を多角的にとらえて論理的にそれらを説明する今回の経験は活かすことができると思います。
次年度参加チームへのメッセージをお願いします。
オープンゼミは、ゼミでの学びを深める最高の機会です。一つのことを研究し、深く考えることは簡単なことではありません。またチームで取り組むからこそ生じる問題や難しさもあると思います。ただ、やり遂げた後の達成感は大いにあります。ゼミのメンバーとの絆も深まりますし、自分の価値観や興味関心の幅もきっと広がります。参加して損することはないと思いますので、ぜひ挑戦してみてください!
南川ゼミの魅力を教えてください。
南川ゼミでは、様々な文脈における人種の壁を超えたダイバーシティのありかたについて熟考し、議論をしています。ゼミ生はテーマに関心を持っている学生が多く集まってくる印象ですので皆モチベーションが高いです。
授業は教科書を分担して読み、クラス全体で毎回ディスカッションする形式で進んでいきます。専門的な学びはもちろんですが、人間として今後大切になっていくことを学んでいる実感があります。
南川先生は、様々な立場から物事を捉え、難しい内容であっても生徒が理解しやすいよう例え話を織り交ぜながら分かりやすく説明をしてくれるチャーミングな教授です。クラスのテーマに関連する時事問題があれば紹介し、その問題の背景について解説してくれるなど、私たちの理解を深めるよう工夫して教えていただいています。
ゼミの雰囲気は、授業中は積極的に学び、休み時間は楽しく話せるようなメリハリのある雰囲気が特徴的です。教授やプレゼンをした学生に対して気軽に発言や質問が行き交う良い空気感があり、ゼミ生が一体となって理解を深めていけるような意欲的な姿勢をもつクラスだと思います。
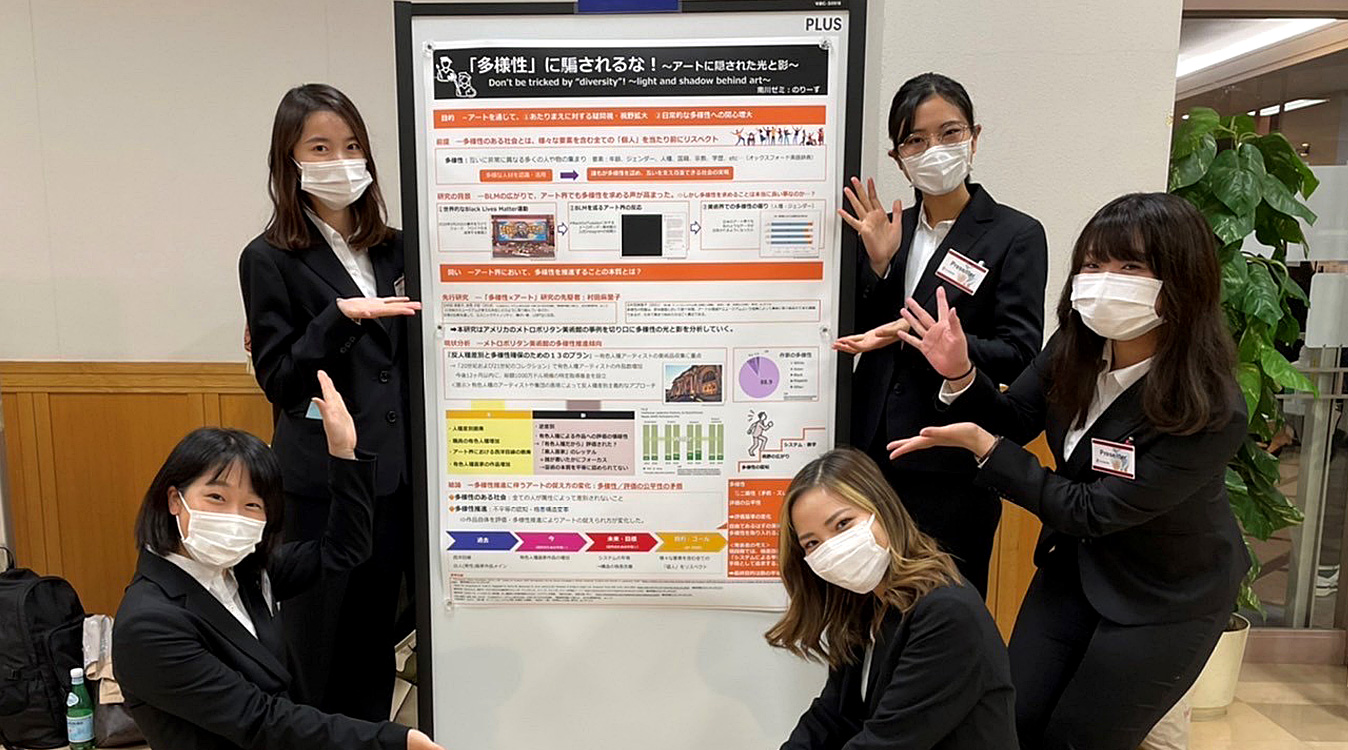
2022年3月更新
MORE INTERVIEWS
-
「東アジアの平和」をテーマに日中韓の学生が集う平和対話に参加。市民レベルで対話を続けることが緊張緩和につながるかもしれないという希望を持つことができました
井上 友佳理
国際関係学専攻 3回生2026.2.17
academics|ir_major|
-
オープンゼミナール2025「【もうええでしょう】「食い尽くし系夫」は何故食い尽くしをやめられないのか?」
鳥山ゼミ
(チーム名:純子先生、それ食べたかったんじゃないですか?)2025.12.19
academics|openseminar|
-
体操部の主将としての活動と学部の学びの両立。ゼミの海外フィールドワークが国連職員になりたいという夢に挑戦する勇気をくれました。
吉田 誇太郎さん
国際関係学専攻 3回生2025.11.17
studentlife|academics|athletics|ir_major|
-
国際寮のレジデントメンターとして多様な留学生と共に過ごした経験は、今後の人生においても大きな財産になると確信しています。
田畑 琴子
国際関係学専攻 4回生2025.11.6
studentlife|ir_major|
-
「実際に世界を変えられる人になりたい」という夢を実現するため「タイ・バンコク国際機関研修」に参加。現場を訪問し直接お話することで国連職員を目指す上で必要なこと学ぶことができました
森本 真彩
国際関係学専攻 1回生2025.10.29
studyabroad|international|ir_major|
-
蓄積してきた知識を実際の経験を通じて捉え直したいと考え、Peace Studies Seminarに参加。原爆や戦争、平和に関する自分の中での「あたりまえ」を再構築することができたと思います。
栗栖 慧さん
グローバル・スタディーズ専攻 4回生2025.10.23
studentlife|academics|gs_major|
