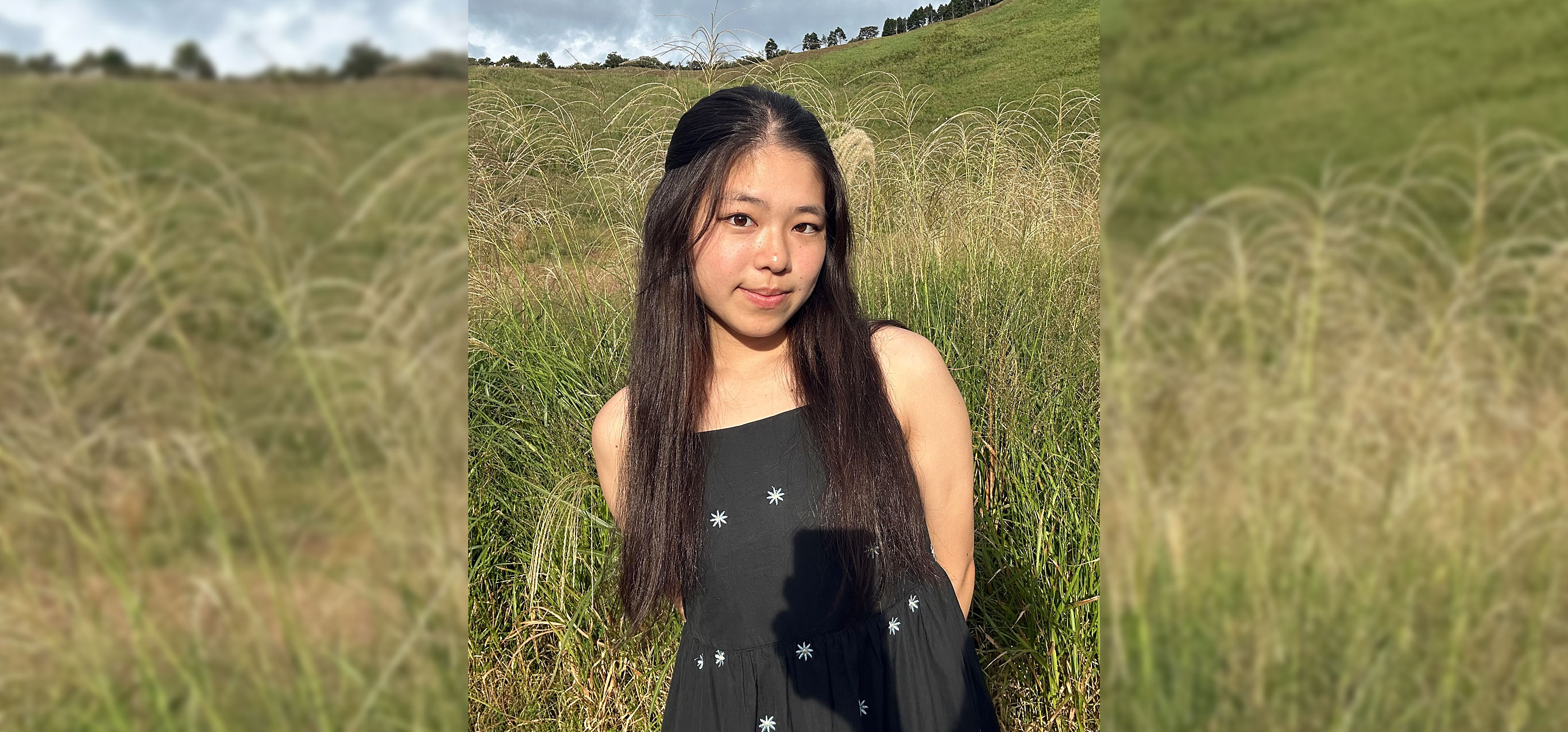
Peace Studies Seminar 広島訪問を終えて――歴史的な出来事を理解し伝えるためには、感情的なつながりや共感を深めることが大切だと実感しました。
大岡 莉子 さん
国際関係学専攻 3回生
本学部開講科目(使用言語:英語)「Peace Studies Seminar」の一環として、8月5日~8日に広島市で国内研修を実施しました。4日間の日程で学生たちは、平和記念資料館の訪問や被爆者の方から被爆体験を聴く会、平和祈念式典への出席、国連機関UNITARの訪問などを行いました。このフィールドワークに参加した一人、大岡莉子さんにお話を伺いました。
国際関係学部を志望した理由や入学前に学ぼうと思っていたことを教えてください。
大岡立命館大学の国際関係学部では、異なる視点や文化を理解し、国際社会に貢献するための知識を深められそうだと期待し、入学を決めました。私はアメリカで生活した経験があり、日本に帰国した際、広島・長崎への原爆投下や真珠湾攻撃についての平和教育に大きなカルチャーショックを受けたことがあります。米国と日本、両国の歴史を片方の国の視点から学んでいた時は「相手国が悪いことをした」と感じることが何度もあったため、同じ過ちを再び繰り返さないためには双方の視点から歴史を学ぶ必要性があると思いました。
高校で受けた平和学の授業でも「異なる視点から歴史を学び、異なる考え方を理解すること」の大切さを学んだので、大学でもこのビジョンを追求したいと感じていました。そのビジョンをもつのがまさに国際関係学部だと思いましたし、立命館大学は国際的な交流機会や研究資源が整っている点も魅力的だったため、本学部を志望しました。
今回、Peace Studies Seminarを受講した理由を教えてください。
大岡広島出身の私にとって、原爆投下の出来事は個人的にも歴史的にも非常に深い意味を持っています。また、広島での教育の影響を強く受けていたため、私は自然と日本が被害者であり、アメリカが加害者であると信じていましたが、高校時代に原爆投下に関する調査を進めていた中で、異なる国々が異なる視点を持っていることに気づきました。そして、ある原爆被爆者の方と話す機会を得た際、その時起きていた現実は日本政府が描くほど無垢ではないということを理解しました。
高校で平和学を学び、被爆者の方の体験や戦後の広島について深く知るための取り組みを行っていましたが、大学に進学してからはその関心を深める機会が少なくなっていました。そんな時に見つけたのがこの授業であり、私が長年抱いてきた原爆に関する理解をさらに深め、様々な国から集まった留学生と共に異なる視点から平和について考察することができる貴重な機会になると感じ、授業への参加を決めました。

広島でのフィールドワークで学んだこと、印象的だったことは何ですか。
大岡フィールドワークで学んだ最も重要なことは、歴史的な出来事の影響を理解し伝えるためには、実際に現地で体験し、個人的な物語に触れることが何よりも大切であるということです。理論的な知識や研究は学術的な基盤として必要不可欠ですが、歴史の感情的な側面を完全に捉えることはできません。今回、平和記念資料館を訪れたことで原爆を経験した人々の遺品や個人的な物語に触れることができましたし、平和記念式典に参加し、被爆者の方の証言を聞くことで、生存者の強靭さや勇気、そしてそのメッセージの重要性を改めて実感しました。
広島出身である私は、これまでも平和に関するプログラムやプロジェクトに参加する機会がありましたが、今回は新たな視点を見つけられるよう意識しながらフィールドワークに臨みました。被爆者の方のお話を聞いている時は、これまで大学で学んだ平和学や紛争研究の広範なテーマと結びつけながら聞くなど、以前とは異なる視点を見つけようと心掛けました。
結果、平和と核兵器廃絶を訴える責任感がより一層強まるとともに、歴史を理解することは単なる事実や数字を理解することだけではなく、人々の経験や感情に共感することが重要であるということも再確認することができました。
Peace Studies Seminarのおすすめポイントを教えてください。
大岡この授業では現地でのフィールドワークを通じて単なる知識の習得にとどまらず、感情的なつながりや共感を深めることができる点が大きな魅力です。平和記念資料館の訪問や被爆者の方から被爆体験を直接聞く機会があり、書物や講義では得られないリアルな経験をすることができます。実際にその場に立ち、被爆者の方の話を聞くことで、歴史が単なる過去の出来事ではなく、今なお続く人々の苦しみや将来への希望につながっていることを実感するはずです。
次に、この授業は学生が一人一人自分自身の探求テーマを設定し、それに基づいて学びを進めるというアクティブ・ラーニングを重視しており、この過程を通じて、自らの興味や関心に基づいてフィールドワークを計画し、実施する能力を養うことができます。この経験は、今後のキャリアにおいても非常に有用であり、国際機関や非政府組織、政府機関などで働く際に役立つスキルを身につけることができると考えます。
Peace Studies Seminarで経験したことは、今後の学習やご自身の活動、将来の進路にどのようにつながると思いますか。
大岡今回のセミナーで得た知識とスキルは、「米国と日本における平和学の違い」をテーマとしている私の卒業研究にとって非常に貴重なものとなりました。原爆に対する多様な視点を直接体験し、被爆者や国際平和活動に関与する人々の意見を理解することで、私の研究に深みと広がりを加えることができます。研究を進めることで、異なる国々やコミュニティが平和をどう捉え、どのような課題を共有しているかについて、より包括的な視点を持つことができると考えます。

大岡国連機関UNITARのオフィス訪問やシンポジウムを通じて得た国際平和活動や国際機関の実務についての理解は、私の将来のキャリアにとって非常に有益なものになりました。私は将来、国際関係の分野で働きたいと考えており、日本大使館や国際機関(UNICEF、UNITAR、JICAなど)への就職を目指しています。今回のUNITAR訪問を通じて、国際的な協力の重要性と、国際機関で働く際の具体的な方法についての実務的な洞察を得ることができました。
これらの経験は、私の学術的な探求や将来のキャリアにおいてより深い理解と実践的なスキルを提供してくれると確信していますし、平和と国際関係に対する洞察を深め、積極的な貢献をしていくための基盤となると考えています。

2024年12月更新
MORE INTERVIEWS
-
オープンゼミナール2025「【もうええでしょう】「食い尽くし系夫」は何故食い尽くしをやめられないのか?」
鳥山ゼミ
(チーム名:純子先生、それ食べたかったんじゃないですか?)2025.12.19
academics|openseminar|
-
体操部の主将としての活動と学部の学びの両立。ゼミの海外フィールドワークが国連職員になりたいという夢に挑戦する勇気をくれました。
吉田 誇太郎さん
国際関係学専攻 3回生2025.11.17
studentlife|academics|athletics|ir_major|
-
国際寮のレジデントメンターとして多様な留学生と共に過ごした経験は、今後の人生においても大きな財産になると確信しています。
田畑 琴子
国際関係学専攻 4回生2025.11.6
studentlife|ir_major|
-
「実際に世界を変えられる人になりたい」という夢を実現するため「タイ・バンコク国際機関研修」に参加。現場を訪問し直接お話することで国連職員を目指す上で必要なこと学ぶことができました
森本 真彩
国際関係学専攻 1回生2025.10.29
studyabroad|international|ir_major|
-
蓄積してきた知識を実際の経験を通じて捉え直したいと考え、Peace Studies Seminarに参加。原爆や戦争、平和に関する自分の中での「あたりまえ」を再構築することができたと思います。
栗栖 慧さん
グローバル・スタディーズ専攻 4回生2025.10.23
studentlife|academics|gs_major|
-
将来の夢は報道を通じて世界平和の実現に貢献すること。地元:長崎で学んできた平和学習の内容が他の地域では当たり前ではないことを実感した時、将来、この現状を変えたいと強く思いました。
川端 悠さん
国際関係学専攻 3回生2025.10.14
studentlife|academics|ir_major|