ニュース
最新のニュース
角本ゼミ集中セミナーが、「AI・デジタル技術による社会課題への法政策的アプローチ」をテーマとして民間企業のヒアリング調査等を実施しました
角本ゼミ(政策構想演習)では、3・4回生合同で「AI・デジタル技術による社会課題への法政策的アプローチ」をテーマとして研究を行っており、その一環として2025年8月25日~28日に東京都で複数の民間企業へのヒアリング調査を実施し、一橋大学大学院法学研究科での特別講義を行なっていただきました。
25日には、ソフトバンクとトヨタ自動車の合弁会社であるMONET Technologies株式会社自動運転事業部の横山英則様、石原隆弘様、事業統括部の仁木創様に、自動運転サービスの到達点と今後の可能性についてお話をしていただきました。特に、社会的課題の解決を重視するなかで、オンデマンド交通や、医療MaaS、行政MaaSに注力されていることを伺いました。また、弊ゼミからは、サービスによって蓄積される関連データの公共財性や、「自動車を運転する、所有する」文化の行く末等について質問し、丁寧にご回答をいただきました。
ソフトバンク本社
26日には、セイコータイムクリエーション株式会社を訪問し、サイネージ営業推進部の矢野雄一郎様、植竹彩子様、原佳奈穂様より、デジタルサイネージに関するサービスや実際の導入事例を詳細にご紹介いただきました。あわせて、デジタルサイネージの選挙利用の意義と課題に関する質問事項にもご回答をいただきました。選挙の場面における、紙媒体、SNSとのメリット・デメリットの比較をするなかで、設置費用、耐久性や設置場所、システム面での特徴など、デジタルサイネージに関する企業ならではの情報をご教示いただきました。
セイコータイムクリエーション株式会社へのヒアリング
27日午前には、株式会社電通 CXクリエイティブセンターの木幡容子様、データ・テクノロジーセンターの伊勢裕子様、森山知英子様、dentsu Japan データ & テクノロジー プレジデントの松永久様より、広告業界におけるAIの活用と人間の役割に関してお話を伺いました。具体的には、「AI For Growth 2.0」における「People Model」や「Creative Thinking Model」等の活用事例やその意義と課題、AIの台頭による働き方の変化、「人間の知」が生かされるべき領域、電通様が目指す今後の方向性等について、ご解説をいただきました。
株式会社電通
27日お昼には、株式会社BookLiveコミュニティ事業本部の横田容啓様に、イラスト投稿プラットフォームXfolioに関するお話を伺いました。そもそものサイト設立のご事情から始まり、AI生成物を投稿すること及びAIが投稿物を学習することを規約で規制するに至った経緯、「AIによってカスタマイズされたコンテンツは確実に増えていく」という今後の展望と、そのような環境下における「AIを使用せずに人間によって創作される著作物を投稿する場」の意義について、ビジネスの観点を交えながら、ご説明頂きました。
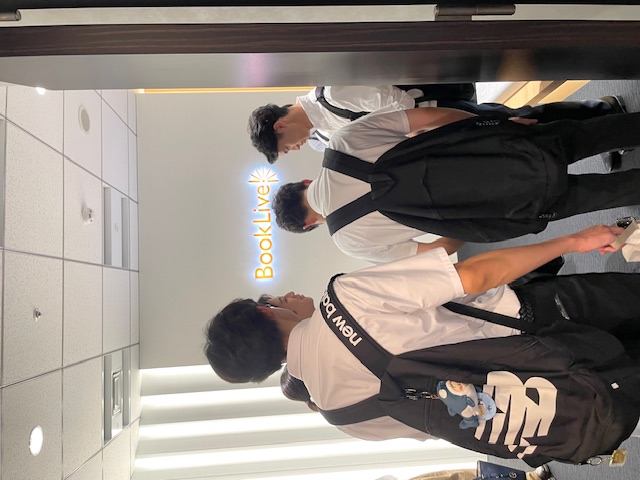


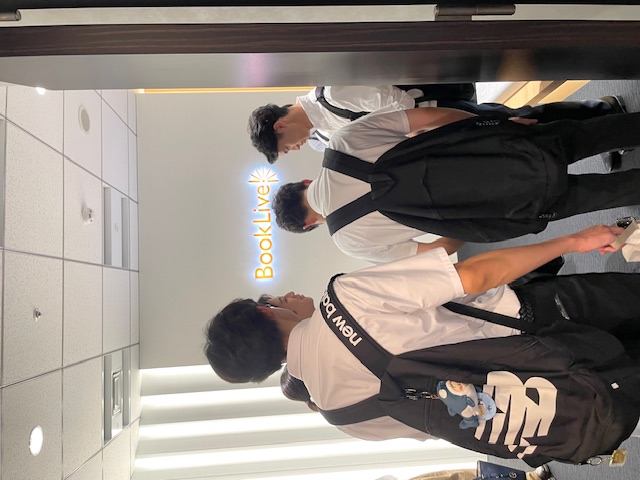
株式会社BookLiveへの訪問

BookLive子会社が運営するWeb漫画サイトで連載中の漫画キャラクター パグ太郎
27日午後には、株式会社Sapeetを訪問し、代表の築山英治様とエンジニアの堀ノ内司様にAI関連サービスを開発・運用するにあたっての情報管理や責任の所在に関するお話を伺いました。情報管理において特に配慮すべき点は、秘匿情報をAIの学習に使用されないようにすることである、とのご意見をいただき、顧客の利用ミスを防ぐために、システム等に「ガードレール」を作ることも心掛けているとのことでした。AIの判断に関する責任の所在については、現状、自律的に意思決定するAIは存在しないことから、AIはあくまで補助的なものであり、最終判断は人間が担うこととなるとご説明いただきました。また、同社はAIがデータを元に身体の姿勢分析を行い、将来の予測を踏まえて適切なエクササイズを提案するサービスを強みとしており、その体験もさせていただきました。
株式会社Sapeetへのヒアリング
28日午前には、高齢者の見守りサービスを提供する合同会社ネコリコを訪問し、代表の山中泰介様と営業企画部の高津賢一郎様より、製品の実演を交えたお話を伺いました。まず、コミュニケーションロボット「Bocco emo LTEモデル Powered by ネコリコ」については、マイナスの感情になることを言わない工夫や、会話のレベルを高度に設定しない理由等についてご説明いただきました。また、冷蔵庫の開閉を検知する「まもりこ」については、冷蔵庫の利用状況にあえて着目した経緯や意義等を学ぶことができました。
合同会社ネコリコへのヒアリング
28日午後には、株式会社viviONの「あおぎり高校」運営スタッフ様に、VTuberの人格権の保護をはじめ、業界の抱える諸課題についてお話をいただきました。具体的には、「VTuberのプライバシー保護」、「AI生成コンテンツやなりすまし等への対応」、「VTuberという存在をどのように捉えるべきかの解釈」等に関してご解説をいただいたり、意見交換を行ったりしました。
株式会社viviON
28日午後にはまた、一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻の得津晶教授(商法がご専門)に、デジタル資産の私法上の性質に関するお話をいただきました。具体的には、特定物(中古車)、種類物(プラモデル)、証券類、預金口座、金銭という従来からある財物と比較して、仮想通貨、セキュリティ・トークン(デジタル証券)、非代替性トークン(NFT)がどのように保護されるべきか、善意取得や倒産隔離等の場面について、代替物性に着目する視点から、ご解説いただきました。
得津教授による講義
今回の集中セミナーを通じて、AIをはじめとした先端的なデジタル技術が現代社会にもたらす発展と課題について、多くの知見を得ました。この度の調査等にご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。この経験をもとに、デジタル技術が抱える法政策上の課題を解決する手がかりを探りながら、今後の研究を進めていきます。

懇親会の様子

懇親会の様子
(文責:2025年度角本ゼミ3・4回生一同)