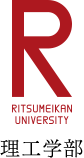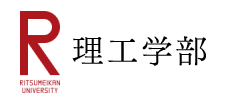荒木 努教授 ARAKI Tsutomu
- 所属学科
- 電気電子工学科
- 研究室
- 半導体材料科学研究室
- 学位
- 博士(工学)
経歴概要
1992年3月 大阪府立大学工学部金属工学科 卒業 1994年3月 大阪府立大学大学院工学研究科修士課程金属工学専攻 修了 1996年12月 大阪府立大学大学院工学研究科博士課程金属工学専攻 修了
研究について
- 研究分野・テーマ
-
21世紀を担う最先端の半導体エレクトロニクス研究
- 研究キーワード
-
窒化物半導体、結晶成長、ナノ構造、LED、太陽電池、パワーデバイス
- 研究概要
-
ガリウムナイトライドという新しい半導体の登場によって、青色発光ダイオード、白色発光ダイオードやブルーレイディスクなどが実現され、私達の生活は大きく変化してきました。さらにこの半導体の持つ潜在能力を全て引き出すことができれば、エネルギー、環境、健康・医療など私達が21世紀に抱える重要な課題を解決できる新しい光・電子デバイスを作ることができます。例えば、長寿命で消費電力の少ない照明光源、格段に変換効率の高い太陽電池、電気自動車技術を支える高効率パワーデバイス、小型で強力な殺菌用光源などが期待できます。私達の研究室では、将来のサステイナブルな社会実現に貢献できる半導体エレクトロニクスを創出するため、半導体材料の原子・ナノレベルの結晶成長から光電子物性・構造評価、デバイス作製にわたる研究を進めています。
-
原子のレベルで制御しながら半導体材料を作製する分子線エピタキシー装置
-
インタビュー
研究者になったきっかけ
家が電気屋さんだったので、子供の頃から父親に連れられて、屋根に登ってアンテナ工事やエアコンの取付け工事の手伝いをしていたことから、理科や工学の分野に自然と興味を持っていたように思います。理工学にもいろいろな分野がありますが、高校生の時にNEWTONという雑誌を読んで、超伝導やセラミックといった新しい材料に興味を持ち、大学では工学部金属工学科に進学。そのまま、博士課程まで進みましたが、卒業研究からあわせて修士、博士と6年間過ごした研究室が気に入って、自分もこういう研究室で学生達ともがきながら、勉強したり、実験したり、研究活動を続けられたらなあと好きなことを続けているうちに研究者という仕事に就きました。