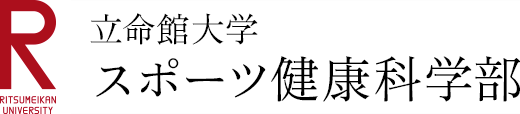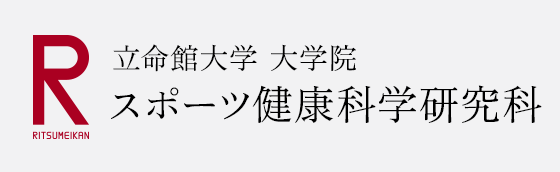2014.08.27 research
2014/08/24 キャンパスプラザ京都において、第2回「理系女子(リケジョ)的学び方、働き方、暮らし方」講演会・シンポジウムが開催されました。
8月24日(日)、キャンパスプラザ京都において、第2回「理系女子(リケジョ)的学び方、働き方、暮らし方」講演会・シンポジウムが開催されました。
基調講演を行ったのは、一般社団法人Mozilla Japan代表理事の瀧田佐登子氏。大学で酵母の研究をしていた瀧田氏が、全く畑違いのシステムエンジニアとして旧.日電東芝情報システムに就職して以来、3回の転職を経て、Firefox をはじめとする Mozilla 製品のマーケティングやオープンソースの普及啓蒙を目的とした非営利法人 Mozilla Japan を 2004 年に設立、2006年に代表理事になるまでのエピソードと、ブラウザの歴史をダイナミックに語っていただきました。その経験から、①あきらめない、②問題解決は一通りではない、③失敗は本当は失敗ではない、③希少価値こそチャンス、④Tryなければ結果なしという瀧田流の考え方を披露。世の中は3人集まれば変えられる、だからあきらめないで挑戦しよう!とメッセージが伝えられました。
続いてのパネルディスカッションでは、本学OGの小林製薬株式会社日用品事業部中嶋絵里奈氏、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社クラウドサービス部山根靖子氏がパネリストとして登壇。コーディネーターとして、本学スポーツ健康科学部伊坂忠夫教授が、女子中学・高校生・大学生、父母をはじめとする参加者を巧みに巻き込みながら、先輩理系女子の学生時代の学びや意識、現在の仕事の魅力に迫りました。中嶋さんからは大学での人生を変える素晴らしい教員との出会いについて、山根さんからは、中学・高校から取り組んできた吹奏楽の課外活動と研究との両立や海外留学について、熱く語られました。ディスカッションでは、テクノロジーが新たな未来を拓くこと、そしてその過程でユーザー自身がイノベーションを作り出すことやネットワークの世界でもリアルに触れる場面の重要性などがそれぞれの体験を交えて語られました。
参加者からは、「元気をもらった」、「男子にも聞かせたい」等の声が多数寄せられ、人類の未来に貢献する理系の仕事の醍醐味や、そこで活躍する女性の魅力が実感を持って伝わったようです。この日のシンポジウムが、参加者と社会のよりよい未来の実現に貢献できることを願っています。