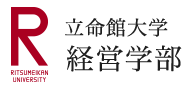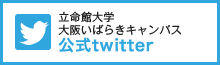NEWS
-
2026/01/06 教育・研究
「大学生によるIRに関するリサーチ・プレゼンテーション」に田中祥司ゼミが参加し、大阪観光局理事長賞を受賞しました。
2025年12月20日(土),大阪市内において「大学生によるIRに関するリサーチ・プレゼンテーション」が開催され,本学経営学部・田中祥司ゼミナールが参加しました。本企画は大阪府市IR推進局の主催により実施されたもので,関西の7大学のゼミナールが大阪IR(統合型リゾート)に関する研究成果を発表しました。
当日は,「IRがもたらす大阪・関西の未来」「世界における大阪・関西の立ち位置」「多文化共生やスマートシティの実現」「IRに対する懸念とその対策」などをテーマに,学生ならではの視点から調査・研究を行い,その成果が報告されました。
田中祥司ゼミナールは,「大阪IRを便利で楽しい場所に」をテーマに,カジノに対するネガティブイメージの払拭や,持続可能な発展に向けたブランド戦略について提案を行いました。その結果,「大阪観光局理事長賞」を受賞し,大阪観光局 理事長・溝畑宏氏より表彰状が贈呈されました。
本取り組みを通じて,IRをマーケティングおよびツーリズムの観点から主体的に考察し,社会課題に対する理解を深めるとともに,実社会に貢献する視点を養う有意義な機会となりました。
-
日本の建設業界の人材確保が全国的な課題となる中、立命館大学経営学部の守屋貴司教授担当のプレゼミ(以下、守屋プレゼミと略する)が、清水建設株式会社と連携して「Z世代に合った採用方法」を学生自らが提案する産学協働プロジェクトに取り組んだ。2025年度秋学期の約3か月にわたる実践型授業には、10月に、同社関西支店総務部長がゲストスピーカーとして登壇され、11月には、企業の内部にある採用課題を学生がオンラインで直接聞き取り調査をし、未来志向の提案にまで仕上げ、12月にはプレゼンするという意欲的な取り組みとなった。
プロジェクトの中核となったのは、10月27日に開催された清水建設による「キックオフ講義」である。この日、守屋プレゼミの教室には、清水建設関西支店総務部部長がゲストスピーカーとして登壇され、「清水建設の人と組織づくり、そしてZ世代採用における現場の課題」と題して講演を行った。同部長は、学生を前に建設業界を取り巻く環境の変化と、Z世代とのギャップに向き合う現場の実情を語った。
まず語られたのは、「BtoB企業でありながら生活インフラを支える重要な役割を担っているが、社名が表に出る機会は多くない。」との説明があった。 建設業界は長い歴史を持つ企業が多く、伝統や縁を重んじる文化は安定性・信頼につながる一方で、「変化が少ない古い業界」という印象も生まれやすいと語った。
続いて話題は、Z世代の就業観へと移った。同部長は、近年の学生の価値観の変化に触れ、「安定志向が強く、自分の思い通りにならないことに不安を抱えやすい」「会社への帰属意識が低く、転職に対する抵抗感も薄い」と指摘した。また、SNSや生成AIなどのツールを使いこなす一方で、「すぐに答えを求める傾向が強く、深く考える習慣が弱まりつつある」と現場で感じる課題も率直に共有した
しかし、同部長は、こうした特徴を「問題」と捉えるのではなく、「新しい可能性」と捉えていく必要性を強調した。「Z世代が持つ感性やスピード感は、企業にとって大きな資源になる。だからこそ、企業側も変わらなければならない。皆さんのリアルな感覚から“共感される採用施策”を提案してほしい」。この言葉は、学生たちの表情を引き締めると同時に、プロジェクトの方向性を強く印象づけた。
プレゼミの秋学期は、こうした企業側のまずリアルな声を受けて、ヒアリング調査研究の基礎から段階的に課題解決レベルアップするための論理的かつ実践的学習について学ぶこととなった。9月末から10月にかけて行われた授業では、企業研究や建設業産業関係などの文献検索の方法や課題解決テーマの立て方、採用研究の基礎理論の学習、インタビュー調査の設計などを系統的に学んだ。そして、プレゼミの学生は上場企業である清水建設の企業研究をし、清水建設へのヒアリングで聞くべき質問項目をグループごとに作成した。その過程で、採用戦略や企業研究の“裏側”を理解するための基盤が築かれていった
11月に入ると、学生たちは清水建設の人事部(採用グループの若手・中堅)に対して、1時間半にわたって、オンライン・ヒアリングを実施した。ヒアリングで学生が投げかけた質問は、実に多岐にわたった。企業側の清水建設の人事部(採用グループの若手・中堅)サイドの方々はこれらに真摯に回答し、学生の視点からの疑問を歓迎する姿勢を示した。「企業のリアルな採用課題を直接聞けたことで、提案内容に深みが増した」と学生たちは口を揃えた。
ヒアリングを終えた学生たちは、得られた情報を整理解釈しながら、清水建設の現状とZ世代の価値観との“接点”を模索した。分析の中心となったのは、学生側が「企業の魅力をどのように“伝える”か」ではなく、「企業の魅力をどのように“共感される形で感じてもらうか」を重視する視点も生まれた。企業広報や採用プロセスは、情報伝達の手法以上に“共感を生むストーリー性”が必要であり、その核心を模索する議論が各グループで活発に行われた。
12月に入ると、最終提案に向けた準備が本格化した。そのために、プレゼミの学生たちは、オンラインヒアリング調査の結果と企業の現状分析などを踏まえ、12月8日には、プレゼミで、このコンテストに向けてのプレゼミ合宿(O I Cセミナーハウス)を行い、アイディアだしからP O W E R P O I N Tの作成、さらには、規定の10分間の時間の中でどう訴求力のあるプレゼンを行うことができるかの予行練習を繰り返し行った。
12月15日に開催された最終提案ピッチでは、同社清水建設関西支店総務部長に加え、本社人事部採用グループ長も立命館大学を訪れ、プレゼミの5チームによるプレゼンテーションを審査した。当日は、実現可能性・新規性・共感性・インパクトなどが総合的に評価され、学生たちは本番さながらの緊張感の中で限られた時間の中で、立命館大学経営学部のプレゼミ生たちが練った「清水建設のZ世代採用提案」の内容をプレゼンした。
同社清水建設関西支店総務部長・本社人事部採用グループ長からは、下記のフィードバックを得ることができた。そして、同社清水建設総務部長・採用グループ長によって、最優秀(1チーム)、優秀賞(1チーム)、佳作(3チーム)が決定した。
プロジェクトを終えた学生たちは、多くの学びを手にすることができた。建設業界という複雑な産業構造への理解、採用理論やオンラインヒアリング調査の手法の実践的習得、総務部長・人事採用責任者、人事採用の若手・中堅メンバーといった多世代の企業サイドの方々とのコミュニケーション体験、そして自らのキャリア観の深化である。また、今回のコンテストを通して、“採用の裏側(リアルな現実)”に触れたことで、「働くとは何か」「どのような職場で成長していきたいか」といった自身の問いにも向き合う時間が生まれた。
守屋プレゼミでは、今回の清水建設との協働を単なる“課題解決イベント”ではなく、2回生の就活前の大学生が社会と接続しながら学ぶ「問いを立て、共に未来を創る学習プロセス」として位置づけている。産学連携は企業の課題解決に寄与するだけでなく、学生にとっては実践知を獲得し、キャリア形成に直結する重要な経験となる。そして、課題探索から課題解決に至る論理構築能力を身につける実践教育を、産学連携で行うことを目的とした。この点は、同社の関西支店総務部長が理事として参画するエッジジソンマネジメント協会の目的とも繋がるものであろう。
建設業界の人材確保が叫ばれる中、Z世代の視点を取り入れた今回の取り組みは、企業と大学が互いに学び合うモデルケースとして大きな意味を持つことができるのはないかとの感触を得た。学生が生み出した提案の一つひとつが、今後の採用戦略の何かのヒントとなり、業界の未来を形づくる一助となることも期待される点でもある。
立命館大学経営学部守屋プレゼミは、今後も社会課題に向き合う実践的学習を推進し、学生の成長を支える教育活動を続けていく予定である。
<コメント>
清水建設関西支店 綿引総務部長
学生の皆さんが当社や建設業界を調査・分析され、Z世代の特徴や考えをよく捉えた提案をしていただきました。5つのチームそれぞれのプレゼンテーションも工夫され、わかりやすく、かつ創意工夫に富んでおり、実際に取り組んでみたいアイデアも沢山あって、聞いていて非常にワクワクしました。私達も多くの学びをいただき、これからも守屋先生や守屋ゼミの皆さんと共創できることを楽しみにしています。今後の産学共創の学びのモデルとなる取組みとして大いに期待できるものです。
清水建設人事部採用グループ 村田採用グループ長
企業の採用活動は、実現可能性やリソースといった制約条件から発想しがちですが、学生の皆さんの枠にとらわれない提案は非常に新鮮で、私たち自身の思考の幅を広げてくれました。当社や建設業界の特性、Z世代の価値観についても丁寧に分析されており、Z世代当事者だからこそ生まれるリアリティと共感性の高い示唆が多く含まれていたと感じています。発表も要点を的確に押さえ、グループ全員で意見を持ち寄りながら作り上げてきた過程と熱量が伝わってきました。今回受け取った提案は大切なバトンとして受け止め、今後の採用活動の中で形にしていきたいと考えています。今後も皆さんとの共創の取組みができることを楽しみにしています。
-
2025/12/12 教育・研究
三井住友銀行営業本部長(立命OB)久津摩剛氏の2025年度公開授業を実施
2025年12月11日(木)に、SMBCコンサルティング株式会社との協定講座「経営学特殊講義β(BB)」における公開授業を実施しました。本協定講座は、SMBCグループの業務戦略に学びながら、リテール(個人や中小企業を対象とする小口の業務)から先端的な金融実務まで、総合的な金融知識の習得を目指すものです。
2025年度の第二弾となる今回は、三井住友銀行 執行役員 京都北陸法人営業本部長の久津摩 剛氏(’93経済卒)に三年連続で登壇いただき、「銀行ビジネスの醍醐味と立命館OBからのメッセージ」をテーマに講演されました。
冒頭には木下明浩学部長による講師紹介がなされ、学生時代にTV取材までされた“ある特技”にまつわる動画放映のほか、授業の前半では、「Ritzから三井住友銀行へ」「銀行の大企業ビジネスとは?」というアジェンダで、学生時代の実体験や就職後のキャリアパス、案件事例の紹介とともに、お客さま主語でビジネスを捉えることや、誇りや感謝の気持ちをもつことの大切さについてお話いただきました。
授業の後半では、「これからの時代をどう生きるか?」「後輩のみなさんへ」というアジェンダで、「地球儀」で物事を捉え考えることや、「どこを目指すか」を明確にし主体的に行動することの大切さをお話いただくとともに、「何事も楽しみながら前向きに人生を歩んでほしい」という激励のメッセージを頂きました。
終盤のQ&Aでは、仕事相手にあわせたアプローチの方法、お客さま主語と思うようになった転換点、部活動で後輩を指導する上でのアドバイス、若いうちから経営者目線を得るためにすべきこと等、OBと現役生ならではの意見交換が活発になされていました。
なお、本協定講座は2026年度も開講を予定しています。
-
2025/12/02 教育・研究
三井住友フィナンシャルグループCEO中島達氏の2025年度公開授業を実施
2025年11月27日(木)に、SMBCコンサルティング株式会社との協定講座「経営学特殊講義β(BB)」における公開授業を実施しました。本協定講座は、SMBCグループの業務戦略に学びながら、リテール(個人や中小企業を対象とする小口の業務)から先端的な金融実務まで、総合的な金融知識の習得を目指すものです。
2025年度の第一弾となる今回は、三井住友フィナンシャルグループ 取締役 執行役社長 グループCEOの中島 達氏が昨年度に続き登壇され、「SMBCグループの戦略とみなさんへのメッセージ」をテーマに講演いただきました。
冒頭には木下明浩学部長による講師紹介がなされ、授業の前半では、「SMBCグループの概要」として、海外市場を含め拡大発展し続けるグループの実態について、また、「SMBCグループの戦略」として、日本・アジア・資本市場の3本柱で持続的に成長するグループの展望について、それぞれ解説いただきました。
授業の後半では、「社会的価値の創造に向けて」として、「SMBCの森」や「シャカカチBOON BOON PROJECT」等の取り組み事例について、「SMBCグループが求める人材」として、“勤勉で意欲的な社員”がチームワークや個性を発揮できるための人財ポリシー等について、それぞれご紹介いただきました。
そして、「みなさんへのメッセージ」では、従業員にAIに慣れ親しんでもらうために制作された「AI中島社長」の紹介があり、また、Integrity, Passion, Solidarity,といったキーワード、そして「突き抜ける勇気。」というスローガンとともに、真正面から正々堂々と挑戦し続けることが大事だという、ラグビー経験者である中島社長らしい激励のお言葉を頂きました。
*上記資料は許可を得た上で掲載しています。
終盤のQ&Aでは、銀行としての改革と伝統のバランス、突き抜ける勇気をもって大学生のうちにすべきこと、活躍する著名人における共通点、大企業におけるリーダーシップ等、活発な質疑応答が行われていました。
なお、第二弾となる12月11日には、久津摩 剛氏(三井住友銀行 執行役員 京都北陸法人営業本部長)が登壇予定です。
-
2025/11/17 教育・研究
ドイツ・パッサウ大学のバーマイヤー教授とOICにて研究交流活動を行いました
経営学部シュルンツェ教授の招聘により、異文化経営分野の第一人者の一人であるドイツ・パッサウ大学のクリストフ・バーマイヤー教授が来日し、2025年10月29日~31日の間、OICにて様々な研究交流活動が行われました。
10月29日はシュルンツェ教授が主宰するManGeo研究グループのコロキウム「ハイブリッド・マネージャーから学ぶ」において、「多国籍企業における境界連結マネジャーの3タイプ」と題する発表が行われました。本コロキウムには、かつてパッサウ大学でヨーロッパ研究を専攻した、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事メラニー・ザクシンガー氏も出席されました。
バーマイヤー教授は、経営学部のいくつかの講義やゼミで、「建設的異文化マネジメント」に関する発表を行ったり、学生と意見交換を行ったりしました。修士課程および博士課程の院生とも研究について議論を行い、院生は方法論、概念、内容に関して助言をいただくことができました。
バーマイヤー教授は、日本滞在中、日本文化に深く根ざした「おもてなし」の精神に触れ、今回の滞在が自分に日本文化についての多くの洞察をもたらし、研究と教育のための異文化のインスピレーションを得ることができたと述べられています。
パッサウ大学のHPに掲載されているバーマイヤー教授の日本滞在レポート
https://www.geku.uni-passau.de/barmeyer/aktivitaeten -
2025/11/10 お知らせ
2026年度再入学試験要項に関して
再入学試験要項の詳細は下記リンクよりご確認宜しくお願い致します。 -
2025/11/05 教育・研究
2025年度 研究成果表彰制度の結果について
立命館大学経営学部・経営学研究科では、国際的な視野を持った研究を進めています。
特に研究成果(論文)の国際発信や学会賞受賞の対象となる図書・論文の発信は、
学部および大学院教育の質的充実を図る土台となるものと考えており、
この度、2025年度に特に優秀な成果を収めた以下の教員を評価・表彰し、
木下明浩学部長・研究科長より賞状が授与されました。(本制度は2023年度より開始)
【制度の概要】
(1)対象教員:本学経営学部専任教員
(2)対象成果(氏名はあいうえお順)
研究成果(論文)の国際発信(要件:Scopus採録雑誌への論文採択)
優秀賞:⾦昌柱教授
奨励賞:石井隆太准教授、菊盛真衣准教授、後藤智教授、HU KAIYI助教、苗苗准教授
-
Students of the Cross-cultural seminar supervised by Professor Rolf Schlunze interviewed Caroline やよい Frantzen on Friday, 10. Oct. 2025, at the OIC Learning Studio C271 about various cultural issues. The key learnings are listed below.
Most students noted the contrast between German directness and Japanese indirectness. They learned that understanding both communication styles is essential to avoid misunderstandings and foster collaboration. Students such as Ji and Odaka realized that intercultural competence involves not only understanding other cultures but also reflecting one’s own cultural norms. LEE and Yokokawa found the idea of creating a “third culture” particularly meaningful — a flexible identity that bridges multiple cultures. Her experience inspired students to value adaptability and fluidity in identity. Endo and Mizukado highlighted that empathy (omoiyari) and curiosity are the foundations of cultural understanding. Fujinami and Ji learned that speaking the same language doesn’t guarantee communication — shared values and respect are more important. To summarize, Caroline taught that intercultural communication is about balancing empathy, flexibility, and self-awareness — not just language proficiency.
Student also interviewed Caroline about her career motivation. Many students found that Caroline’s main motivation is to help people connect across cultures and make workplaces inclusive. Odaka, Kawahara, and Kurima learned that Caroline’s career path was shaped by curiosity and open-mindedness, not by a rigid plan. LEE emphasized Caroline’s advice about “branding oneself” through self-awareness and authenticity. Wang, Umeno, and Yamaguchi noted how networking and trust-based relationships created career opportunities for Caroline, such as her FIFA and JETRO work. Endo admired Caroline’s confidence in switching careers and working independently as a freelancer in Germany. Some students learned that Germany’s financial support for freelancers motivated Caroline to start her independent career. To summarize, her career motivation revolves around connection, self-realization, curiosity, and service to others, rather than status or stability.
The interview with Caroline covered multiple real-world topics — culture, career, and work — with authentic examples. The atmosphere was open and respectful, encouraging participation. Students gained practical insights into global HR, freelancing, and diversity. Her communication style was approachable and professional, modeling intercultural competence.
-
2025/10/09 教育・研究
Professor Tomasz Dorożyński served as a Visiting Professor at Ritsumeikan University, OIC
ポーランド・ウッチ大学トマシュ・ドロジンスキ教授が立命館大学 OIC にて客員教授として活動されました
ポーランド・ウッチ大学(University of Lodz)のトマシュ・ドロジンスキ(Tomasz Dorożyński)教授は、2025年6月1日から7月31日までの2か月間、大阪いばらきキャンパスにおいて、経営学部および経営管理研究科で客員教授として教育・研究活動を行いました。
ドロジンスキ教授は、学部では「Internationalization of firms」、研究科では「 Japanese MNEs in Central and Eastern Europe」の科目を担当し、企業の国際化や中・東欧における日本多国籍企業の展開をテーマとした講義が行われました。また、ドロジンスキ教授の尽力により、受講生はシュルンツェゼミの学生と合同で2025年大阪・関西万博を訪問した際、ポーランド館の「創造性の遺伝子」をテーマとした展示をVIPとして見学する機会を得ました。さらに、ドイツ館では循環型経済の理念を、中国館では人間と自然の調和を学びました。
さらに、本学の国際共同研究推進プログラムを通じて経営学部のシュルンツェ教授とともに、経営地理学研究グループとして数多くの研究活動を展開しました。2025年6月27日には、グループ独自に開発した「ManGeo3レベルモデル」を紹介するワークショップを実施し、経営方式の移転および多国籍企業の現地埋め込みについて議論されました。同ワークショップでは、本学学生がウッチ大学の学生とオンラインで意見交換を行いました。こうした研究活動の成果は、ポズナン(ポーランド)で開催されたIGU-CDES国際会議で共同発表され、また、国際ビジネス分野のトップジャーナルに論文として投稿されました。
ドロジンスキ教授の教育・研究活動は、立命館大学とウッチ大学との間で締結された学術交流協定の趣旨に沿い、両大学の関係強化と発展に大きく貢献しました。
Professor Tomasz Dorożyński, University of Lodz (Poland), was invited as a Visiting Professor by Ritsumeikan University to teach at the Osaka Ibaraki Campus, College of Business Administration, and the Graduate School of Business Administration for a period of two months, from June 1 to July 31, 2025. He delivered lectures for undergraduate, master's, and doctoral students, focusing on the internationalization of firms and Japanese MNEs in Central and Eastern Europe.
Professor Dorożyński also provided the opportunity for R+ students to visit the Polish Pavilion showcasing the “gene of creativity" at EXPO 2025 Osaka Kansai, where they were invited as VIPs. Students studied the concept of the circular economy at the German pavilion, and at the Chinese pavilion they explored the harmony between humanity and nature.
Professor Dorożyński carried out numerous research activities through the International Collaborative Research Promotion Program together with Professor Rolf D. Schlunze for ManGeo Research Group. On June 27, 2025, a workshop was conducted, introducing the original ManGeo Three-Level Model that investigates the transfer of managerial practices and MNE embeddedness. During the workshop, R+ students exchanged opinions with Professor Dorożyński’s students at the University of Lodz via ZOOM. His research efforts led to a joint publication disseminated at the IGU-CDES Conference held in Poznan, Poland; it has now been submitted to a leading IB journal.
Prof. Dorożyński’s research and teaching activities contributed to strengthening and developing the relations between Ritsumeikan University and the University of Lodz, in line with the goals stated in the bilateral agreement signed by both university rectors.
-
2025/08/26 お知らせ
未来を担う若者と新しいプリントの体験価値を創造 ichikara Labが主催する関西3大学合同プロジェクトの最終発表会を開催
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(代表取締役社長:足立正親、以下キヤノンMJ)の企業内起業ichikara Lab(イチカララボ)と関西大学商学部横山恵子ゼミナール、立命館大学経営学部中原翔ゼミナール、近畿大学経営学部山縣正幸ゼミナールは、これまでのプリントのカタチにとらわれない新しい体験価値の創造を目指してichikara Labが主催する関西3大学合同プロジェクト(以下、本プロジェクト)を実施し、2025年7月18日に関西大学梅田キャンパスKANDAI Me RISE(カンダイミライズ)にて最終発表会を開催しました。
本プロジェクトは、ichikara Labが日本国内のマーケティングを手掛けるミニフォトプリンター「iNSPiC/SELPHY」を題材に、デジタルとアナログを融合させたこれまでのプリントの在り方にとらわれない新しい価値創造を目指して、2025年5月23日より始動しました。ichikara Labは、さまざまな若年層と恒常的に価値創造に取り組んでおり、このたびさらなる挑戦に向けて初めて、複数大学のゼミナールとのコラボレーションを実現しました。本プロジェクトでは関西大学商学部横山恵子ゼミナール、立命館大学経営学部中原翔ゼミナール、近畿大学経営学部山縣正幸ゼミナールに所属する学生計13名が大学ごとのグループに分かれて、「従来のプリントのカタチにとらわれないデジタルとアナログを融合させた新しい価値を創造する」という課題に取り組みました。参加学生はichikara Labが提供する実践的なインプットセッションを経て、7月18日に開催した最終発表会にて新しい体験価値の提案を行いました。
関西大学のグループは、観光地やイベント会場だけで撮影できるオリジナルステッカーのアイデアを立案しました。これは、観光地などにミニフォトプリンターを設置し、その場で撮影した写真をスマホアプリと連携して、その土地ならではの背景をドット風やレトロ風など好みのデザインに加工して「ステッカー印刷」できるサービスです。プリントブースには「思い出ノート」が設置してあり、現地に訪れた人だからこそ感じた気持ちや情報を記入したり、「おまけプリント」として追加印刷されたステッカーを「思い出ノート」に貼ったりすることでアナログのコミュニケーションも楽しめます。定量データに加え、自らの実体験や丁寧なN1インタビュー※1によって練り上げた企画を立案しました。
立命館大学のグループは、近年、アニメ、マンガ、映画やドラマなどの作品に登場する場所をファンが訪れる「聖地巡礼」が注目されていることに着目し、ファンが単に聖地を写真に収めるだけではなく、プリントした用紙を貼付することで「自分だけの『巡礼帳』」を作成するアイデアを立案しました。この提案では、アプリ経由で聖地にチェックインすると、推しのキャラクターや登場人物と一緒に写真を撮って印刷できるARフォトフレームなど限定コンテンツが獲得できる工夫も凝らされており、ファンに「推し時間」をより長く楽しんでもらうための創造的な体験価値の生成を目指しています。デジタル手段を前提としつつアナログ体験を楽しみたい現代の若者らしい感性に寄り添った体験価値として、実際に制作した巡礼帳のプロトタイプも見せながら提案しました。
近畿大学のグループは、ライブハウスのような没入体験ができる特別な場所にミニフォトプリンターを設置して印刷体験を提供することで、非日常的瞬間の価値を延長させるというアイデアを立案しました。この提案では、デジタルが主流の日常生活のなかで写真を見返す時間が少ないことに着想を得て、撮影前後の体験を改めて掘り起こし、「非日常をすぐそばに」というコンセプトを設定しました。思い出を「撮って残す」だけでなく、プリントしてスマホケース内など「すぐそばに」置き続けることによるアナログの強みを再発見したアイデアで、導入場所へのサブスクリプション型サービス提供などビジネスモデルも提案しました。参加学生からは、「大学の枠を超えて発表できる機会があまりない中で、プロジェクトを通して同じ世代と交流しながら切磋琢磨することができ非常によい経験となった」、「ワクワクする未来をともに切り拓くというichikara Labの想いに惹かれて今回参加したが、デジタルとアナログを融合させた新しい体験価値の検討は難しくとてもやりがいのある課題だった」、「元々マーケティングに興味があり参加したが、どうしてもモノ消費だけで考えてしまうという自分の思考のクセにも気づくことができとてもよい機会となった」「企業やビジネスパーソンと何か活動をしてみたいと思い参加したが、特有の経験をすることができて大変満足している」など、多数の好意的な意見が上がりました。
今後ichikara Labではオープンイノベーションプログラムも活用しながら、本プロジェクトを通して大学生とともに創造した新しい体験価値や言語化したインサイトをワクワクする未来の実現へとつなげてまいります。
●ichikara Labオープンイノベーションプログラム:
https://corporate.jp.canon/profile/business/new-value-creation/ichikaralab/open-innovation※1.特定の1人の顧客(ユーザー)に対して深く掘り下げてインタビューを行うことで、本質的なニーズや価値観、行動の背景を明らかにする方法。
〈プロジェクト実施の背景〉
近年のデジタル化により利便性が高まる現代において、プリントの在り方は大きく変化しています。ichikara Labは、幅広い若年層と恒常的に活動する中で、デジタル時代に生まれ育った若年層にとってはプリントそのものが新鮮であり、物質感のあるアナログ体験だからこその楽しさを提供できると実感しています。ichikara Labでは、従来のプリントのカタチを超えた価値創造を通じてワクワクする未来を実現していくために、若年層やichikara Labの想いに共感していただいた企業などと積極的な共創活動に取り組んでいます。
〈プロジェクト概要〉
期間:2025年5月23日(金)~7月18日(金)
内容:
DAY1 オリエンテーション・アイデア発想ワーク
第1部では、参加学生同士の交流を図るコミュニケーションタイムや本プロジェクト参加におけるマインドセットを経て、ichikara Labの組織紹介や現在取り組んでいる課題など、今回のテーマ「自分たちも体験したいと思う新しいプリント体験の設計」の設定背景の理解を目的としたインプットセッションを実施しました。
第2部では、今回のテーマに対して「若者がプリントしたいと思わない理由」を起点にichikara Labが日頃活用しているフレームワークに沿ったアイデア発想ワークに取り組みました。DAY2 マーケティングプランニングワーク
企画立案に必要なマーケティングに関するインプットセッションを実施しました。キヤノンMJグループの原点である「顧客主語」の実践を目指して人の心を捉えるマーケティング活動とは何か、体験価値の設計に必要な考え方やインタビューの手法など実践的な内容を経て、中間発表に向けたグループワークを行いました。
DAY3 中間発表・フィードバック
第1部ではグループの異なる学生同士で中間案の共有とフィードバックを実施しました。同じ若い世代としてさまざまな意見を聞き、アイデアのブラッシュアップに取り組んでもらいました。また提案側でありながらも別案へのフィードバックを経験することで、俯瞰的な視点を持つ重要性や審査員の視点を知り、最終発表への活用を目指しました。
第2部では、各グループがブラッシュアップしたアイデアを中間案としてichikara Labへ発表しました。ichikara Lab担当者より丁寧なフィードバックを行い、最終発表に向けてアイデアを練り上げるポイントをともに言語化しました。
DAY4 最終発表・フィードバック
各グループより、自分たちも体験したいと思う新しいプリント体験について力強いプレゼンテーションが行われました。〈関西大学について〉
大学名:関西大学
学 長:高橋 智幸
所在地:大阪府吹田市山手町3丁目3番35号
Web :https://www.kansai-u.ac.jp/ja/〈立命館大学について〉
大学名:立命館大学
学 長:仲谷 善雄
所在地:大阪府茨木市岩倉町2-150(大阪いばらきキャンパス)
Web :https://www.ritsumei.ac.jp/〈近畿大学について〉
大学名:近畿大学
学 長:松村 到
所在地:大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号
Web :https://www.kindai.ac.jp/〈ichikara Labについて〉
ichikara Labは、若年層マーケティングの強化と新たな顧客層へのリーチを目指し、恒常的に幅広い若年層と活動しています。トレンドを生み出し波及する力のある若年層への本質的な理解を深め、いち早く未来につながるヒントを捉えています。「顧客の気持ちや生活に寄り添う新たな価値の提供」をミッションに若年層マーケティングから獲得したインサイトを活かした新規商品・サービスの企画・開発へ挑戦しています。
●キヤノンMJ企業内起業「ichikara Lab」WEBページ:
https://cweb.canon.jp/personal/ichikaralab/
●Xアカウント:ichikara Lab/イチカララボ【公式】(@ichikaraLab)
ichikara Labでは、これまでのプリントのカタチを超えて、人々がワクワクする未来をともに生み出していけるサービスや技術、アイデアを募集しています。お問い合わせは、ichikara Lab WEBページ最下部「CONTACT」よりお願いいたします。
●お問い合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先:キヤノンマーケティングジャパン株式会社広報部 03-6719-9093(直通)
ichikara Lab ホームページ :https://cweb.canon.jp/personal/ichikaralab/
関西大学ホームページ:https://www.kansai-u.ac.jp/ja/
立命館大学ホームページ:https://www.ritsumei.ac.jp/
近畿大学ホームページ:https://www.kindai.ac.jp/