英語教育学コース各教員をクリックすると、ライトボックスで詳細が開きます

David Coulson
研究領域
Applied Linguistics, Vocabulary Acquisition research
研究テーマ
My research has focused on vocabulary acquisition, cross-linguistic effects in language learning and academic writing instruction. I would be happy to advise students especially in fields close to these.
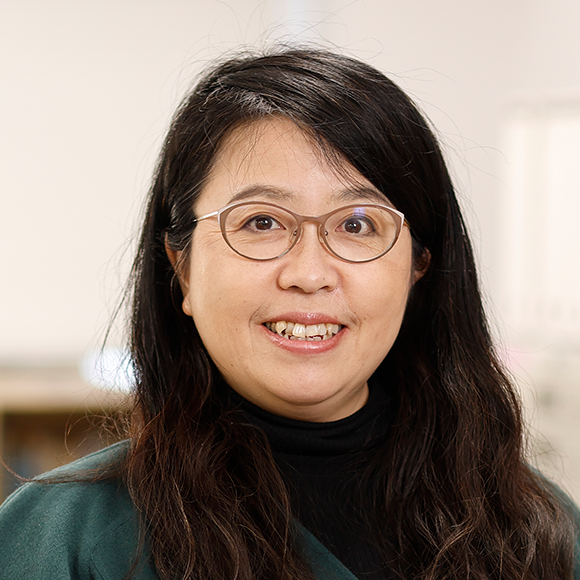
佐野 愛子
研究領域
英語教育、バイリンガル教育
研究テーマ
全ての言語資源を活用する言語教育を目指して
高校時代をイギリスで過ごし、マイノリティの立場を経験しながらバイリンガルとしてのアイデンティティを確立していった経験や、高校で英語を教えた教師としての経験、カナダでの子育ての中で子どものバイリテラシー教育について考えた経験などが今の研究のきっかけになっています。バイリンガルであること、バイリンガルになること、バイリンガルを育てることについて、とくにリテラシーの獲得に焦点を当てながら様々なコンテクスト(英語教育を含めた外国語教育、日本手話と日本語のバイリンガル教育としてのろう教育、外国にルーツのある子どもたちの日本語と母語のリテラシー教育、海外に育つ日本語を継承語とする子どもたちのバイリテラシーを支えるFamily Language Policyなど)で研究をしています。バイリンガルの子どもたちが、「○○語に課題のある子どもたち」と捉えられるのではなく、「多様な言語資源を持つ子どもたち」として評価され、そうした言語資源が十全に活用されるような教育のあり方について考え続けています。

清水 裕子
研究領域
言語教育における測定と評価、読解教材開発
研究テーマ
<テスト>と聞けば<苦い経験>を思い浮かべる方も多いかと。しかし、自分の力や特性を測定・診断し、より良い方向に導いてくれるものなら、なんだか受けてみたくなるのでは? 測定と評価を含む分野であるテスティングは、比較的新しい領域です。研究科の講義では、言語テストの作成や分析を体験していきますが、教材開発にもつながる情報も得られると思います。テスティングに興味を持つ仲間が増えることを楽しみにしております!

田浦 秀幸
研究領域
神経心理言語学・言語獲得と喪失、バイリンガリズム、英語教育学
研究テーマ
大きく分けて2分野の研究を進めています。第1のテーマは心理言語学分野に関するもので、バイリンガルの第2言語獲得・ 保持・喪失を扱っています。たとえば、「バイリンガルの人たちの脳構造は日本語モノリンガルに比べてどうなっているだろう?」等を探ります。第2の研究テーマは、中学・高校・大学の英語教育現場で続けてきた効果的な英語教育についての研究です。 理論研究と現場実践を車の両輪と考え、どちらにも偏らずそれぞれお互いに還元できる研究(たとえば、「英語の上達法に関する本は星の数ほどあるのに、一度覚えた(はずの)単語や文法項目をどうしたら忘れずにすむの?」等)を心がけています。

山崎 のぞみ
研究領域
英語教育学、語用論、談話研究
研究テーマ
英語学と英語教育学の橋渡しを目指しています。特に、語用論や談話分析の知見を援用し、またコーパス分析を併用しながら、会話に見られる周辺的な言語現象とコミュニケーションの関係を探っています。研究するうちに、論理的な書き言葉より話し言葉の方が実は構造が「複雑」であることがわかりました。それはなぜでしょうか。相手と即興的に繰り広げられる待ったなしの会話の言語には色々な仕掛けが隠されています。このような話し言葉研究を英語教育へ応用することによって、文法指導、インタラクション指導、コーパスを使った学習、言語活動、教材開発の分野に新たな視点を提供したいと考えています。
日本語教育学コース各教員をクリックすると、ライトボックスで詳細が開きます

大島 弥生
研究領域
日本語教育学、談話分析
研究テーマ
留学生に対する日本語教育、特にアカデミック・ライティングについての教育・研究を行っています。留学生が産出する文章の特徴を探る中で、読んだものや聞いたものなどの外からの情報をどう自己の文章に取り込み、情報への解釈や評価を表していくかに興味を持っています。留学生が目標とする学術論文ジャンルについても、その言語的特徴を探り、教材開発につなげたいと思っています。 同時に、レポートを書くプロセスにおいてお互いに書き手・読み手となって意見を交換する協働学習やジグソー学習の中で、どのような情報のやりとりが起こっているのか、何を学んでいるのか、という点も研究テーマとしています。

北出 慶子
研究領域
第二言語学習、言語教師の成長・研修、日本語教育、質的研究
研究テーマ
言語学習や言語教師の成長について社会や環境と主体との相互作用から捉えるアプローチで研究をしています。グローバル化やネット社会という急激な社会変化の中で、これからの言語学習、言語教育、言語教師の教育・研修は、どうあるべきかに興味を持っています。複数の言語・文化が身近に共存する時代には、どのような言語能力や言語教育が必要となるのでしょうか。それは、従来のものと、どのように違うのでしょうか。どうすれば、そのような力を育むことができるのでしょうか。これらの問いに答えるために、研究と教育的・社会的実践の両方に取り組んでいます。皆さんと一緒に、多くの人にとって住みよい社会の言語教育について考えるのを楽しみにしています。

平田 裕
研究領域
日本語学、言語変化、日本語教育学
研究テーマ
日本語教育学、日本語学が専門です。日本語教育においては、更に実践的な語学教育方法の追求、日本語学・言語学においては、文法の成り立ちにおける言語学的な必然性と、歴史的/社会的必然性(偶然性)の相関を研究していきたいと考えています。競合する語形/表現から生まれる使い分けや取捨選択、様々な言語/方言で見られる共通の現象、似ているけれども少し違う現象など、言語学で学んだ「ことば」の豊かさは、今の私の仕事の土台になっています。クラスでは「ことば」の多様性や豊かさを感じられるような教え方ができればと思っています。

道上 史絵
研究領域
日本語教育学、移民政策と言語政策
研究テーマ
日本で非日本語母語話者として生活する人々は、言語的な生存戦略を模索しながら日々の社会生活を営んでいます。こうした言語的実践を社会言語学的な視点から明らかにし、それを通じて、制度や政策を含むマクロレベルの社会構造を批判的に検証することを研究の中心に据えています。特に、移民政策や日本語教育政策に注目し、私たちが生きる社会をすべての人にとって住みやすいものにするために、日本語教育はどのような貢献ができるのか、その役割や可能性について研究しています。

吉川 達
研究領域
日本語教育学、第二言語習得論
研究テーマ
日本語を母語としない人への日本語教育、日本語学習者の日本語習得についての研究を専門としています。日本語の習得には、意味のある理解可能なインプットを多量に得ることが必要ですが、それを可能にする活動が多読や多聴です。多読や多聴がどのように学習者の日本語習得を促すのか、そのための素材をどのように作るのか、どのような形で教育実践に取り入れるかについて研究しています。また、生成AIやメタバースのような情報技術にも興味を持ち、それらを取り入れた日本語教育にも挑戦しています。
言語学・コミュニケーション表現学コース各教員をクリックすると、ライトボックスで詳細が開きます

岡本 雅史
研究領域
コミュニケーション研究、言語学(認知言語学・語用論)
研究テーマ
一貫してコミュニケーションとリアリティを二大研究テーマとしており、人間はいかにして言語・非言語を用いてコミュニケーションを行っているのか、世界をどのように言語によって分節化し、認知しているのか、さらにはどのようにして世界と現実感(リアリティ)を持って接することができるのか、等について言語・非言語の観点から考察・研究を進めています。近年は漫才対話に着想を得た《オープンコミュニケーション》という概念をベースに、漫才・コントから日常会話に至るまで、多様な相互行為場面の分析に取り組んでいます。
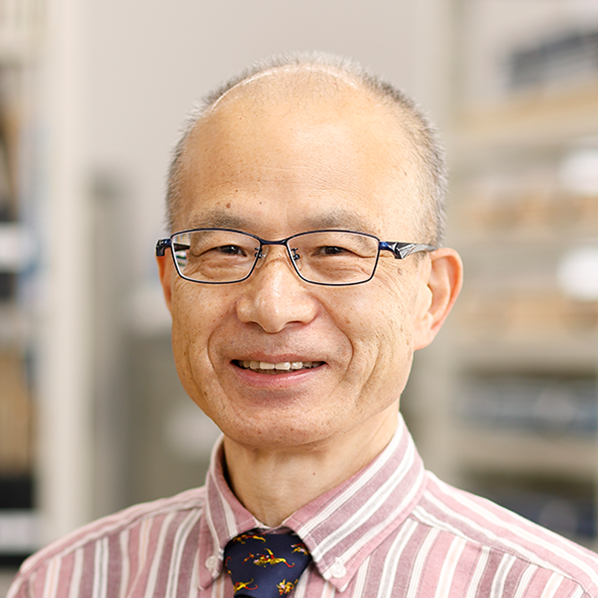
佐野まさき
研究領域
理論言語学、対照言語学、日英比較文法論
研究テーマ
「理論言語学」というと、なにか難しそうです。太郎君が公園にいることを英語ではTaro is in the parkと言いますね。太郎ではなく彼の自転車ならHis bike is in the parkです。両方ともならTaro and his bike are in the parkですね。でもなぜ今度はhis bikeという単数のものの後に、さっき使っていたisが来てはいけないのでしょう。日本語ではもっと困った、でも本質的に同じ現象が起こります。「太郎は公園にいる。」「彼の自転車は公園にある。」両方ともなら...「太郎と彼の自転車は公園にいる」「太郎と彼の自転車は公園にある」どちらもダメですね。さっきは「自転車は公園にある」でよかったのに、です。
言語は、それを使う私たちに対し、こんな困ったことが起こることに気を使ってくれないのです。オンライン授業の冒頭、パソコン画面の向こう側の学生さんに尋ねます。「音声は聞こえていますか?」「ビデオは見えていますか?」、まとめて尋ねようとすると、「音声やビデオは見えて、いや聞こえて...」、言葉に詰まってしまいます。英語でももちろん同じです。このようなことから、私たちの言葉のどのような性質が見えてくるでしょうか。これが理論言語学です。日英比較文法や対照言語学から見えてくる、私たちの言葉とはいったい何か、です。

城 綾実
研究領域
会話分析、コミュニケーション論
研究テーマ
私たちの日常は、言葉の選択のみならず、言葉を発する際の声の出し方、言葉ともに発せられる視線の動きやジェスチャーのような身体動作など、私たちが想像している以上にさまざまな資源を巧妙に積み重ねて成り立っています。私は、会話分析と呼ばれる観察科学を用いて、共同行為や活動に着目し、人々が社会性を育み維持するメカニズムの一端を明らかにする研究をしています。言語を行為を組み立てるための資源のひとつとして、身体を中心に道具や環境なども諸資源と捉えて緻密に記述・分析することで、相互行為の体系的な仕組みと状況固有的な特徴の両方に迫りたいと考えています。
こうした研究は、人とのふれあいやかかわりが重要な役割を担う広い意味でのサービス場面の研究にも応用可能です。現代社会の実際的な理解や諸問題解決への一助として、介護、医療、科学コミュニケーション場面などの研究もしています。

杉村 美奈
研究領域
言語学(統語論、統語論・形態論インターフェース)
研究テーマ
生成文法理論の枠組みにおいて、再構造化 (restructuring) 現象、「が」格目的語の認可条件、複雑述語 (complex predicates) 形成、主要部移動 (head movement) などが関わる統語現象を研究対象とし、それらの現象を説明する理論構築を行っています。主に英語や日本語を対象言語としていますが、研究対象に関連する他言語のデータも考察します。特に統語論と形態論が関わり合う言語現象に興味があり、語の仕組みや接辞の具現化に関わる問題を統語論においてどのように説明できるかなど、統語論・形態論インターフェース研究にも取り組んでいます。
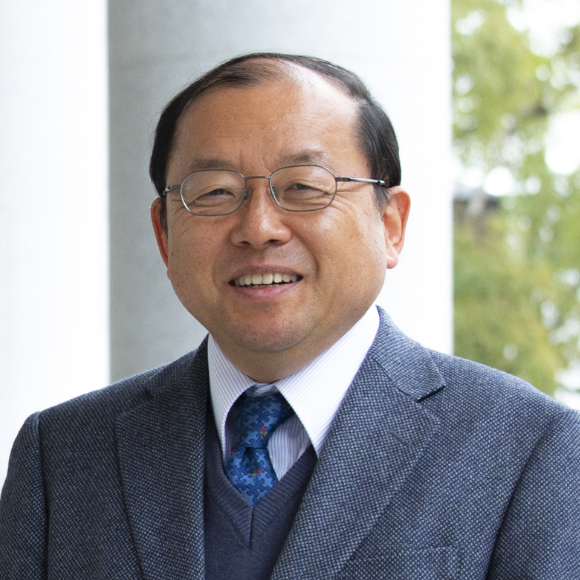
滝沢 直宏
研究領域
英語学・言語学
研究テーマ
研究領域は、英語学(特に文法・語法)及び言語研究のためのコーパス利用の方法論です。特に、(1)言語理論を踏まえた英語の文法現象の記述と説明、(2)言語の慣習的側面の記述と記述の方法論、(3)コーパスを正確に利用するための方法論に焦点をあてています。授業では、英語学とコーパス利用を有機的に関連させつつ、更に英語教育の現場も念頭におきながら、英語という言語を客観的に分析する理論的視点と分析に必要なテキスト処理技術の習得を目指します。コーパスは、決して「便利な」道具ではなく、使い方次第では有害でさえあり得ること、しかし厳密に利用すればとても大きな力を発揮し得ることを授業の中で伝えたいと思っています。
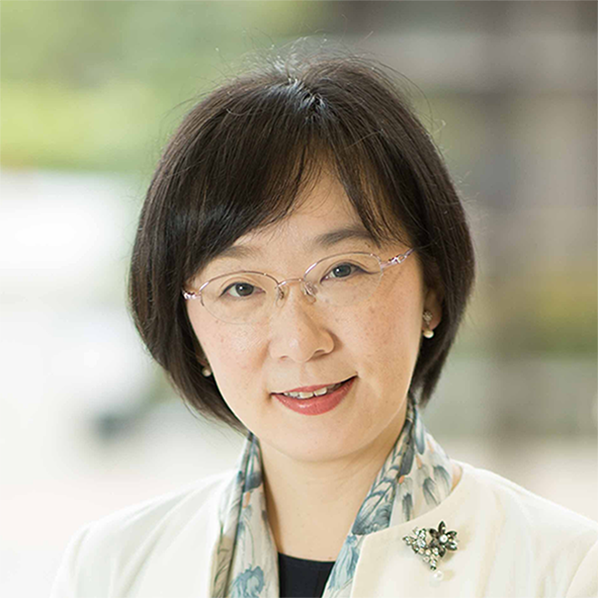
西岡 亜紀
研究領域
比較文学・文化、声と図像のメディア、文章表現教育
研究テーマ
詩や小説はどのようにして生まれるのかというシンプルな問いを、19 〜 20世紀の日本とヨーロッパを軸にさまざまな視点から追及してきました。文芸表現のテクスト分析や異文化間・異メディア間のテクストの対照分析、ライティング教育全般を専門としています。詩や小説などの文字のメディアはもちろん、絵解き・版画・紙芝居・マンガ・アニメーションなどの、民衆の文化伝達や言語教育を支えてきた声や図像メディアの表現研究も長い間続けてきました。近年は、新しい表現メディア環境のなかで多様化するフィクション全般に関心を持ちながら、これまでのフィクションの歴史性や思想性を未来にどのように継承していくかを問い続けています。多様な表現者や表現方法と出会うために、人に会い、各地に赴きます。
こうした研究を、新しい時代の言語表現実践を担う創作人材の育成や教育現場における表現部門の教員の育成といった社会の実践分野にも応用できるように、日々仲間とともに模索しています。
NEXT

