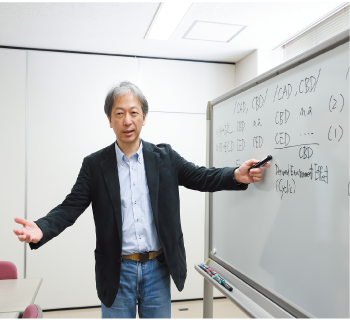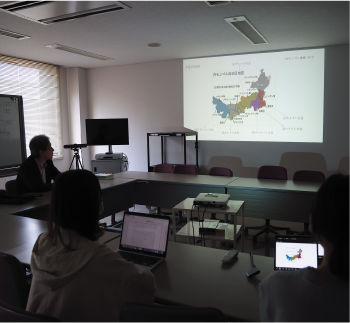英語教育学コース
English Language Education Course
01

カリキュラムの特徴
大学4年間で英語の一種免許を取得した(または、あと少しで取得予定の)段階から更に一歩深く英語教育学・英語学を学ぶことで専修免許を取得し、現場で高い専門知識・技量を持った英語教員として活躍できるカリキュラムを提供しています。
2026年度から、社会人入試で英語教育学コースに入学される方を対象に、夜間(6・7限)や土曜日に開講される授業をオンラインで受講し、オンラインのみで修了できるような仕組みを展開していきます。
英語教育学コースのコア科目に加え、修士論文に向けた研究指導科目もオンラインで受講可能です(ただし、履修可能科目に制限があります)。昼間に勤務されている方や遠方にお住まいの方も、休職せずに大学院を修了できる環境を整えています。
また、在学中に教育現場体験ができるように、近隣の府立高等学校でのインターンシップも提供しています。情報コミュニケーション・日本語教育学・言語脳科学等他のコース提供の講義も受講できますので、修了後に教職だけでなく研究職や一般企業就職等に幅広く対応しています。
英語教育関連科目(講義系)
外国語教育の基礎となる第二言語習得理論、その研究成果を踏まえた英語教育学総論、英語教育における語彙習得論、言語教育における測定と評価、カリキュラム設計とシラバスデザイン、そして、日本での英語教育において重要度が増している早期英語教育論などの科目を配置しています。また、外国語教育学新展開講義目も有用です。これからの英語教育を担っていく教員に必要な、高度な専門性を身につけることができるカリキュラムになっています。

英語学関連科目
英語の音声学・音韻論、文法論などの科目を配置しています。英語学に関しては言語学・コミュニケーション表現学コースで設定している内容も多く、意味論・語用論、形態論・統語論、英語語法文法研究、対照表現研究などが学べます。本研究科で学ぶことができる英語学の知識・分析方法は、英語教師にとって必須であるだけでなく、英語学分野の研究を深く続けたいと考える人にとっても重要な基礎となるものです。

実践・演習系科目
英語教育における実践力をつけるために、模擬授業や教材開発に関する科目、英語翻訳学演習、電子教材開発演習、英語教育インターンシップなどの科目を配置しています。また、「アカデミック・スキル」の科目では、プレゼンテーションやアカデミック・ライティングの力を養います。新しい統合型の英語技能学習指導は授業分析のための実践的科目であり、言語学・コミュニケーション表現学コースのコーパスによる言語分析演習も有用な科目です。

想定される進路
- 英語教員(小学校・中学校・高校・大学の英語教員)
- 博士課程進学(英語教育に関する分野)
- 教育・出版事業(企画/編集/開発分野、学習塾など)
英語教育学コースでは、現代社会のニーズに応えられる先進的な英語教育学の理論と実践技術・教育力、英語教育に関する知見を身につけることができます。このような能力を活かして主に下記のような進路で活躍する人材を輩出しています。

PICK Upインタビュー
社会人院生の仕事と研究の両立について、英語教育学コースのお二人の方にインタビューしました。2年間休職して在学中の中学校英語教員の方と、休職せずに2年間で修了した高校英語教員の方です。