在学生の声
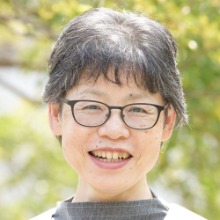
在学生の声01
奥村 美穂さん
英語教育学コース
(2024年4月入学)
Okumura Miho
高
校で英語教育に携わってきた中で常に悩んでいたのが、ライティング指導におけるフィードバックの方法でした。 現場の実践だけでは身につけにくい理論や指導方法を学んで、自分の教育スキルを磨きたいと考え、退職を機に大学院で学ぶことを選択しました。最初は研究テーマも定まらず不安でしたが、少しずつ楽しさを感じられるようになりました。例えば、ライティング指導において、文章の機能別の特徴を指す「ジャンル」という概念があります。実践を元にした先生の説明やクラスメートとの模擬授業を経るうちに、書く前の段階でのジャンルを意識した指導が、書いた後の効果的なフィードバックにつながることに気づき始めました。そう思うと、専門知識とは、万能レシピではなく、材料や調理器具に応じた調理法を考える土台になるものだと感じています。今後はさらに学びを深め、学習者によるライティング評価について研究を進めたいと考えています。

在学生の声02
日出 眞子さん
日本語教育学コース
(2024年4月入学)
Hiide Mako
学
部時代は副専攻として日本語教育を学び、卒業後はスウェーデンで日本語教師のインターンシップに参加しました。現地では初級のクラスを担当していましたが、文法や教授法に関する知識などが十分でないと感じ、より質の高い授業をするために、日本語教育や言語について改めて学びたいと考えていました。言語教育情報研究科では講義系の授業に加え、実践や演習系の授業を受けられるので、知識・経験共に成長できると考え、本研究科への進学を決めました。入学後は日本語教授法や日本語学、教材分析などを学び、日本語教育への理解を深められています。 また、1回生の春休みには日本語教育実習に参加し、初めて日本語で日本語を教える経験をしました。実習を経て、授業では何に焦点を当てるのか、言語教師として気を付ける点など非常に多くのことを学び、今後も日本語教育に携わりたいという気持ちが強くなりました。将来は大人だけではなく、子どもへの日本語教育や日本語支援を行いたいと考えています。
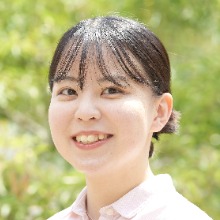
在学生の声03
閏間 詩音梨さん
言語学・コミュニケーション表現学コース
(2024年4月入学)
Uruma Shiori
学
部時代、普段使っている「エモい」という言葉の意味をうまく説明できなかったことをきっかけに、若者言葉の研究に興味を持ちました。現在は、若者言葉における程度副詞の用法について研究しています。言語の研究には、意味や音、文法など様々な観点がありますが、学部時代は自分がどの観点を追求したいのか決めきれずにいました。そこで、入学時ではなくM1の最後にゼミを決定できる立命館大学を選びました。M1の期間を通して、 専門科目では言語学の専門的な知識を吸収しつつ、「研究基礎論」の授業では、学びを踏まえた研究計画の見直しができたことが良かったと感じています。授業では、発言や質問がしやすい雰囲気の中で、先生方や他の院生と議論する機会が多いことが最大の魅力だと感じています。学んだ知識を用いて考えたり発言することで、より理解が深まることを日々の授業で実感しています。修了後は博士後期課程に進学したいと考えています。
修了生の声

修了生の声01
大矢 訓史 さん
英語教育学プログラム
2014年度修了
立命館守山高等学校専任教諭
Oya Satoshi
本
研究科での学びは私にとっては大変貴重であったと年々実感しております。授業の質だけでなく教授陣の熱心で 温かいサポートもあり、非常に充実した大学院生活を送ることができ、本研究科を選択したことに間違いはなかったと確信しております。学部を卒業して間もない頃は第二言語習得論に関する知識も皆無の状態でしたので、果たして自身の指導法は正しいのかどうかと日々悩んでおりました。理論は地図のようなものだと思っております。迷った際の拠り所ですから、本研究科にて理論も学びつつ研究を進めていくに連れ、自身の指導観においても霧が晴れるような感覚を持ち始めたことを覚えております。修了後は、いわゆる大学入試対策に力を入れる受験校と現任校である立命館守山高校を経験しましたが、どんな環境であれ指導において普遍的なものは存在するという実感も得ております。それはまさしく本研究科での学びが土台となっていることの証でもあります。
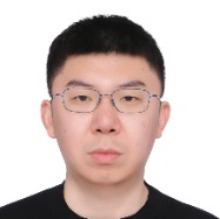
修了生の声02
CHEN Xiさん
日本語教育学プログラム
2017年度修了
内モンゴル師範大学外国語学部講師
Chen Xi
私
は現在、内モンゴル師範大学外国語学部日本語学科で教鞭をとっています。言語教育情報研究科では、日本語教授法や日本語学、そして日本語教育実習といった理論の勉強と実践的な教育実習が融合されており、今私は自信をもって教壇に立っています。修士論文を作成する過程で、先生との接し方から学術的な論文の書き方を学ぶだけではなく、言語研究という自分の仕事としてやり続けたい分野を見つけることができました。言語教育情報研究科のカリキュラムは非常に充実しており、コーパスや統計学などの言語関係に広く活用できる研究法もカバーしています。いろいろな授業で、自分の視野を広げ、より多角的に考えるようになりました。また、授業でのゲストスピーカーや学術講演会など、研究に関する最新の考え方を学ぶ機会もあります。言語教育情報研究科では、日本語を教える技能を身につけ、自分の目標を見つけることができます。

修了生の声03
木村 修平さん
言語情報コミュニケーションコース
2005年度修了
立命館大学生命科学部教授
Kimura Syuhei
私
は現在、立命館大学生命科学部などで展開している「プロジェクト発信型英語プログラム」の運営に関わっています。英語とICTを知的生産のインフラと位置づけるこのプログラムでは、言語教育情報研究科で学んだことが十二分に活用できており、同じく研究科を修了した同僚らとともにやり甲斐のある日々を送っています。英語とICTの両方を学べる研究科に進学したからこそ今の私があります。自分次第で多くの刺激とチャンスと人脈を手に入れられる場所ですので、後輩院生にはぜひアクティブかつ貪欲に、研究科のリソースを利用してもらいたいです。
NEXT