
国際関係学は、単に外国について学ぶのではなく、自国と他国の関係性や背景を多角的に理解する学問。日本を外からの視点で見つめ直すことで、世界を見る視野が広がりました。
岸本 幸弘 さん
国際関係学専攻 4回生
国際関係学専攻の岸本さんに、学部で学ばれている内容や将来の目標についてお話を伺いました。
国際関係学部を志望した理由を教えてください。
岸本高校時代、私はニュージーランドへ公費留学する機会をいただきました。滞在中、現地で発生したテロ事件を実際に経験したことが、私の進路選択に大きな影響を与えました。その日、授業中に校内のサイレンが鳴り響き、私たちは急いで机の下に隠れるよう指示されました。直前に近くのモスクで銃の乱射事件が発生し、最終的に51人が犠牲となる、ニュージーランド史上最悪の銃犯罪となったのです。避難中、私の目の前でヒジャーブを被った女子生徒が泣きながら誰かと電話で必死に話していた光景は、今でも鮮明に覚えています。
緊急帰国の飛行機の中で、私は「なぜ、あのような平和な場所で、無罪の人々に悲劇が起きなければならなかったのか」と考え続けました。この経験から、国や文化、宗教の違いによって生じる対立や暴力の背景を知りたいという思いが強くなりました。そうした問題を多角的に学ぶことができる場として、国際関係学に特化したカリキュラムを持ち、多文化的な学びの環境が整っている立命館大学 国際関係学部に魅力を感じ、志望しました。
入学してみて国際関係学部のイメージはどう変わりましたか。
岸本意外だったのは、国際関係学部が「世界を知る」以上に、「日本を深く理解する」ことができる学部であったという点です。入学前は、国際関係学とは、主に海外の政治・社会・文化について学ぶものだと考えていましたが、学びを進める中で、その認識は大きく変わりました。
国際関係学とは、単に外国について知るのではなく、自国と他国を相対的に捉え、両者の関係性や背景を多角的に理解するための学問であると気づいたからです。日本社会を外からの視点で見つめ直すことによって、自分の立ち位置や価値観を再構築するような経験ができ、結果的に世界を見る視野もより広がりました。

国際関係学部でどのようなことを学ばれていますか?
岸本クロス履修制度を活用してグローバル・スタディーズ専攻の英語開講科目である「Japanese Society」や「Japanese Culture」、「Japanese Politics」などを履修しました。これらの授業では、日本出身ではない教員が、日本の社会、文化や政治を国際的な視点から分析しており、私自身が「日本」について本当に理解しているのかどうかを問い直すきっかけとなりました。これらの授業を通して、「自分は思っていたほど日本のことを知らないのではないか」と気づかされ、自分が当然だと思っていた価値観や常識が、実は特定の歴史的・文化的背景に支えられていることを学びました。このような経験は、自国の姿をより客観的に見つめ直す貴重なきっかけとなりました。
学部で学ぶ中でどのような部分が成長したと考えていますか?
岸本最も身についたと感じているのは、「批判的思考力(Critical Thinking)」と「他者の立場に立って考える力」です。専攻の枠を越えた多様な国の学生達との学びの中で、多様な視点や価値観に触れることができ、自分の考えを相対化しながら深めていく姿勢が自然と養われました。
また、経済競争や文化的衝突、さらには武力紛争といった多様な「対立」が世界各地で常に存在しています。なぜそのような事態に至ったのか、そしてそれをどうすれば緩和できるのかを考える中で、「他者の立場に立って考えること」の重要性を強く実感しました。
国際関係学部という、留学生や異なる文化的背景を持つ学生が集う環境では、まさにこの姿勢を日常的に実践する機会が与えられています。もちろん、異なる立場を完全に理解することは不可能ですが、それでも理解しようと努める姿勢を持つこと自体に大きな意義と効果があると考えています。
さらに、日本国内および世界各地から学生が集うこの学部で異なる文化や背景を持つ人々と対話を重ねるなかで、私たち一人ひとりが国内外を問わず、自分自身の文化を代表する存在、いわば「小さな外交官」であることにも気づかされました。このような経験を通して、日々の発言や行動に対する責任感が高まり、自分自身の成長を強く実感しています。
現在取り組んでいる研究テーマについて教えてください。
岸本3回生からは社会学を学べるグローバル・スタディーズ専攻のRAJKAI, Zsombor Tibor先生のゼミに所属しています。卒業論文では日本における二重国籍を禁止する法律について、グローバル化が進む現代社会において、学生がどのように認識しているのかを明らかにすることに取り組んでいます。
国際関係学部の学生たちは、日常的に国際的かつ多文化的な環境に身を置き、グローバルな価値観や政治的議論に触れています。そうした学生たちがこの制度を時代遅れと捉えているのか、あるいは必要と考えているのか、またどのような矛盾や違和感を抱いているのかを探ると同時に、日本の単一国籍制度と、グローバル化によって広がる多国籍的・多文化的アイデンティティとの間に存在する緊張関係を明らかにしたいと思っています。本研究を通じて、将来的な政策や世論の変化に関する示唆を得ることを目指しています。
長期休暇中はどのように過ごしていますか?
岸本日本をより深く理解するために、長期休暇を利用して、あえてハードなチャレンジに毎回挑戦しています。
白戸圭一先生の講義の中で印象的だったのは、日本の医学生が「解剖学」を学ぶのは、人間の身体構造や器官同士の関係を理解することで、それぞれの症状に適した治療を施すためである、という話でした。そして先生はそれに続けて、「国際関係を学ぶ学生は、まず自国の社会構造や関係性を、社会学を通して理解するべきである」と語られました。私はこの考えに強く共感し、国際関係(International Relations)を真に理解するためには、まず「国内関係(Internal Relations)」すなわち自国の社会を深く知ることが不可欠だという思いに至りました。
その考えを実践に移すべく、富士山をはじめとする日本各地の山を登ったり、自転車で日本を横断したりといった体験を重ねてきました。中でも最も過酷だった挑戦は、野宿をしながら、あるいは知らない人の家に泊めていただきながら、東京から大阪まで徒歩のみで移動した旅です。このように、本を読むだけでは決して見えてこない日本の姿を、自らの身体と感覚を通して探ることによって、日本社会への理解をより深めてきました。
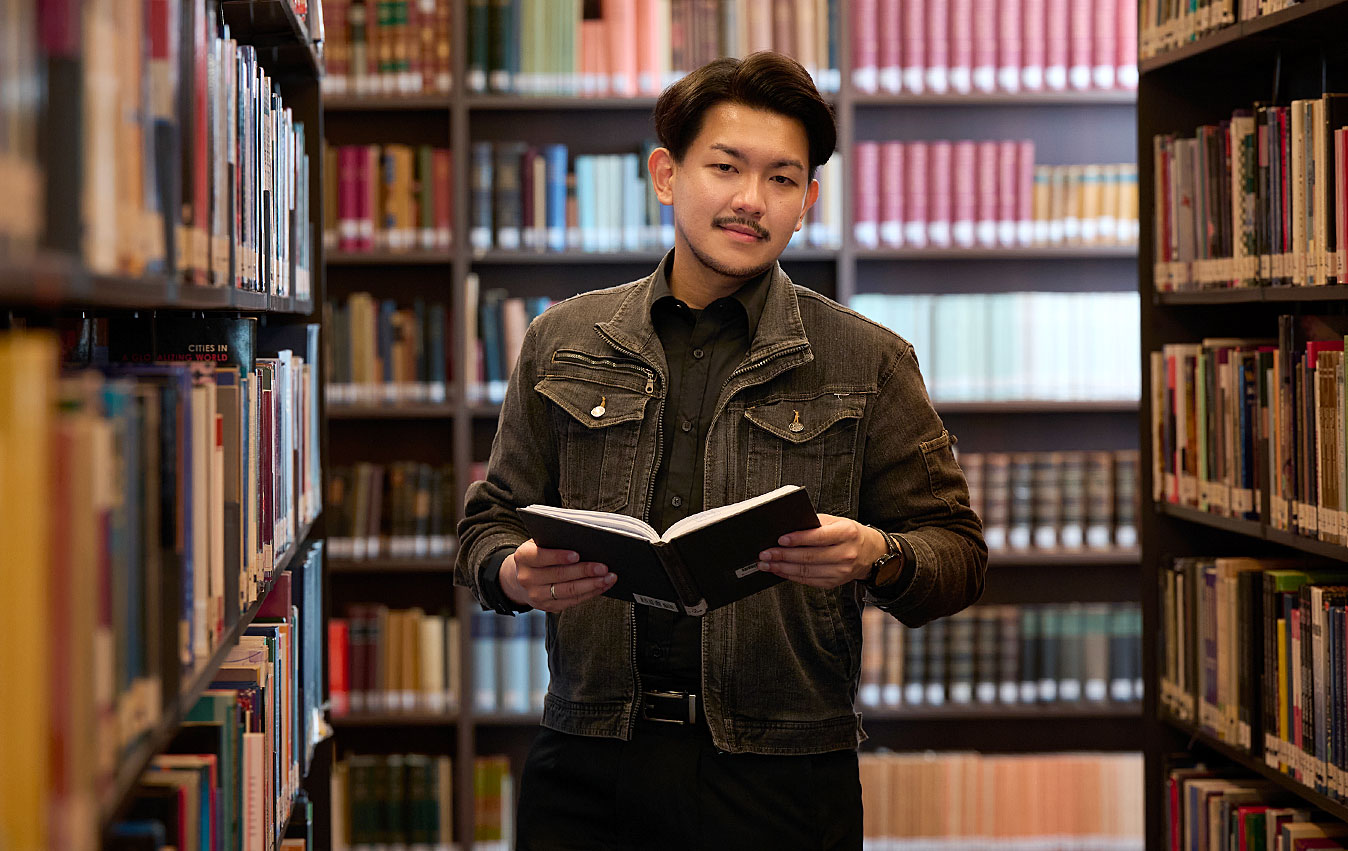
将来の目標を聞かせてください。
岸本卒業後はフィリピンに帰国し、記者として活動する予定です。フィリピンは発展途上国として大きな進歩を遂げてきましたが、いまだに日本ではあまり見られないような深刻な問題、たとえば路上で物乞いをする子どもたちや、罪のない人々が迫害されるといった現実が存在しています。大学で培った知識と経験を携えて故郷に戻り、自分にできることからまず行動を起こしたいと考えています。
目標を実現するために、フィリピンに関心を持つ日本人や在住者、旅行者に向けて、現地の情報を日本語で発信している情報通信企業のもとで、長期インターンシップに取り組んでいます。
国際関係学部を志望する受験生に対してメッセージをお願いします。
岸本この学部は特別な場所です。授業の質や内容はもちろんのこと、何よりもこの学部の最大の魅力は「学生」にあります。ここには、世界に羽ばたく国際人にふさわしい、型にはまらない自由な発想を持った仲間たちが集まっています。良い意味で“飼いならせない”、多様で個性的な学生たちと切磋琢磨できる環境がここにはあります。
受験生の皆さんに一つ伝えたいのは、志望する大学や学部に合格すること以上に、どのような結果であっても、自分がその環境の中でどのように行動し、どのような姿勢で学びに向き合うかのほうがはるかに大切だということです。本当に成功する人は、どのような状況にあっても、自分なりの道を見つけて前に進む力を持っています。大切なのは「勝つこと」ではなく、「決してあきらめないこと」です。どうか自分を信じて、しぶとく、そして誠実に前へ進んでください。心から応援しています。
2025年7月更新
MORE INTERVIEWS
-
「東アジアの平和」をテーマに日中韓の学生が集う平和対話に参加。市民レベルで対話を続けることが緊張緩和につながるかもしれないという希望を持つことができました
井上 友佳理
国際関係学専攻 3回生2026.2.17
academics|ir_major|
-
オープンゼミナール2025「【もうええでしょう】「食い尽くし系夫」は何故食い尽くしをやめられないのか?」
鳥山ゼミ
(チーム名:純子先生、それ食べたかったんじゃないですか?)2025.12.19
academics|openseminar|
-
体操部の主将としての活動と学部の学びの両立。ゼミの海外フィールドワークが国連職員になりたいという夢に挑戦する勇気をくれました。
吉田 誇太郎さん
国際関係学専攻 3回生2025.11.17
studentlife|academics|athletics|ir_major|
-
国際寮のレジデントメンターとして多様な留学生と共に過ごした経験は、今後の人生においても大きな財産になると確信しています。
田畑 琴子
国際関係学専攻 4回生2025.11.6
studentlife|ir_major|
-
「実際に世界を変えられる人になりたい」という夢を実現するため「タイ・バンコク国際機関研修」に参加。現場を訪問し直接お話することで国連職員を目指す上で必要なこと学ぶことができました
森本 真彩
国際関係学専攻 1回生2025.10.29
studyabroad|international|ir_major|
-
蓄積してきた知識を実際の経験を通じて捉え直したいと考え、Peace Studies Seminarに参加。原爆や戦争、平和に関する自分の中での「あたりまえ」を再構築することができたと思います。
栗栖 慧さん
グローバル・スタディーズ専攻 4回生2025.10.23
studentlife|academics|gs_major|