研究活動
「地域社会・文化と観光」
リサーチユニット
観光現象について、地理学を中心としながら、社会学や文化人類学の成果もふまえ人文・社会科学的な視座から学際的に研究しています。
研究のねらい
日本はもちろんのことですが、アジア、欧米、オーストラリアなどの世界各地の観光現象について、インタビュー法や質問紙調査法をはじめとする多様な調査手法をもとに研究を行っています。地理学を中心としながらも、社会学、文化人類学、経済学、経営学、環境学などの関連領域とも連携し、総合的現象としての観光の解明を行っています。
研究スタッフ
-

遠藤 英樹教授
研究テーマ
観光とポピュラーカルチャーに関する社会学的研究
専門分野
観光社会学、現代文化論
キーワード
ポピュラーカルチャー、メディア、モビリティ(移動)
「観光は地域に何をもたらすのか」「観光はメディア文化やポピュラーカルチャーとどのように結びついているのか」「グローバルな現代社会の中で、観光はどのような役割を果たしているのか」「観光は文化をいかに変容させるのか」「観光地で私たちは一体、何を見て, どのような経験を手に入れるのか」「観光における『遊び』の要素は、現代社会に何をもたらすのか」――観光現象に関する様々な問いを、社会学的な視点から追求しています。このように理論やフィールドワークをふまえた人文・社会科学的な観光研究を展開していくことで、現代社会のあり方をラディカルに(根底から)問い直そうと思っています。
小野 真由美准教授
研究テーマ
生きることをめぐるツーリズム・モビリティーズに関する文化人類学的研究
専門分野
文化人類学、観光人類学、東南アジア地域研究
キーワード
国際退職移住(international retirement migration)、 ライフスタイル移住(lifestyle migration)、ロングステイツーリズム、ケアの越境化
長期滞在型観光(ロングステイツーリズム)と国際退職移住、ライフスタイル移住に関する文化人類学的研究を行っています。特に、マレーシアとタイを中心に、東南アジアにおける日本人(若者や高齢者)の長期滞在・移住のあり様について長期フィールドワークを行ってきました。最近、フィリピンでの調査も開始しました。また、医療ツーリズムや高齢者向けの介護リゾートの生成にみられるケアの越境化について、その実態の把握とトランスナショナルな連関を明らかにすることに取り組んでいます。国際退職移住に関する研究は、ウェルネスやウェルビーイング、さらに、高齢者のもつ「迷惑をかけたくない」意識と自立・自律にどのように関わるのかについて探求しています。

河原 典史教授
研究テーマ
近代の植民地朝鮮・台湾とカナダをめぐる移住漁民
専門分野
歴史地理学、近代日本人移民史研究
キーワード
漁業、カナダ、移民
近代における漁村の変貌、漁民の移動や転業に関する歴史地理学的研究に取り組んでいます。西南日本から朝鮮半島や台湾に渡り、魚類缶詰やカツオ節などの製造業の展開を研究しています。カナダで活躍した日本人漁民の研究も行なっています。19世紀末に渡加した彼らは、当初はサケ漁に携わっていましたが、やがて捕鯨業、塩ニシン製造業や造船業にも携わりました。映画『バンクーバーの朝日』では、資料提供や監修のお手伝いをしました。また、近代における海水浴場の成立、魚食文化と地域振興など、海をめぐるツーリズムにも興味関心があります。
-

神田 孝治教授
研究テーマ
観光から近現代社会を探究する
専門分野
文化地理学、観光学
キーワード
イメージ、移動、観光地
観光は、楽しさ、憧れ、夢、欲望といったものと密接に関係した現象です。他なる場所にこれらと結びついたイメージが投影されるなかで、観光客が生じ、観光地が創造されるのです。また、観光地という場所は、観光客をはじめとする多様な移動を通じて創り出され、そして変化し続けています。そこで私は、観光客の地理的な想像力や、様々な空間的移動に注目して、観光地が社会的にいかに創造されているのか、またそれがどのように変容しているのかを研究しています。こうした研究は、観光という楽しさと関わるテーマを取り扱いながら、近現代社会の文化的・空間的な特徴を多角的かつ深く探究するものとなっています。
-

山本 理佳教授
研究テーマ
観光資源化のプロセスの研究
専門分野
文化地理学、景観論
キーワード
近代化遺産、産業観光
産業施設、戦艦、廃墟、廃線跡、空き家…今やどんなものでも「観光資源」となりえる時代です。私は、あるモノが観光対象となっていくプロセスを研究していますが、とくに上記であげたような、無用の長物や嫌われモノが、観光の有用な対象となっていく過程はとても興味深いものです。たとえば廃墟は、負のイメージのノスタルジックな価値への転換や莫大な費用をかけた保存整備など、様々な社会的状況や地域社会の動きが絡みつつ、ようやく観光資源となります。そうした背景や要因を一つ一つ丁寧に追っていくこと、あるいはひも解いていくことが、社会や地域を知ることにつながります。
研究成果
-
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)以後の観光」に関する研究
グローバルな移動(モビリティ)は世界に人、モノ、資本、イメージを移動させているとともに、ウイルスも移動させました。ドイツの社会学者ウルリッヒ・ベックは、ウイルス、気候変動などによる現代のリスクは国境を越えていく移動(モビリティ)の中で現れると主張しています。同時に観光は今後、デジタルテクノロジーを融合させつつ、地域の文化・自然等を「コンテンツ」にまで昇華させ、観光客に感動という情動を呼び起こしていきながら、世界に「歓待」を広げていく新たな役割を求められています。この研究では、観光が有する今後の課題と可能性が考察されています。具体的には(1)観光産業の動向に関する調査、(2)デジタルテクノロジーと観光の融合のあり方に関する調査研究、(3)これからの時代において観光が地域に対して果たすべき役割に関する研究です。
-
COVID-19以後の「デジタル=モバイルな時代におけるアジアの地域」に関する研究
社会のあり方は、大きくゆれうごいています。多くの「人」「モノ」「資本」「文化」「イメージ」「情報」等が国境を超え頻繁に移動する「グローバル世界」に、私たちは生きています。新型コロナウイルス感染症によって、2021年1月現在、「人」の移動はいったん停滞してしまっているように見えますが、これも次第に回復していくことでしょう。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)以後の移動(モビリティ)は、デジタルテクノロジーと密接に結びついて、新たなかたちの「グローバル世界」をさらに広げていきます。そのとき日本を含むアジア諸国は、こうしたグローバル化の結節点となっていくことでしょう。本研究では立命館大学人文科学研究所を重要な研究拠点とし、「デジタル=モバイルな時代のアジアの地域」のあり方を考察し、アジアにおいて観光がデジタルテクノロジーを融合させつつ、地域の文化、自然、暮らしとどのように交差していくのかを考えます。
-
「世界中の人々の共生を志向する観光」に関する研究
グローバルな現代社会を多様な他者とともに生きるためには、「差異性」や「新奇性」を積極的に受け容れる「開かれた思考」が必要になります。「開かれた思考」を醸成し「異なる価値観・文化・経験・民族・性・階層・信仰等を有する人々が共生するうえで、観光はどのような役割を帯びているのか」。これを考察する研究が、観光研究において強く求められています。本研究は価値観や経験等における多様な差異を越え、人々がしたたかに多様性(ダイバーシティ)を有しつつグローバルな世界の中で相互に共生することをうながす観光を検討します。
主な出版図書
-

ポップカルチャーで学ぶ社会学入門――「当たり前」を問い直すための視座
遠藤英樹(2021)/ミネルヴァ書房 -
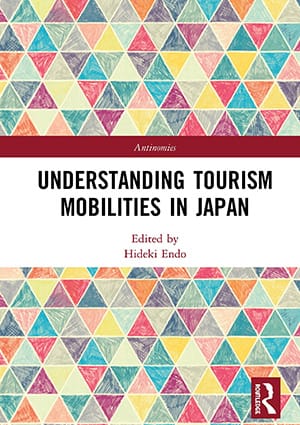
Understanding Tourism Mobilities in Japan
Hideki ENDO ed.(2020)/Routledge -

ツーリズム・モビリティーズ――観光と移動の社会理論
遠藤英樹(2017)/ミネルヴァ書房 -

カナダにおける日本人水産移民の歴史地理学研究
河原典史(2021)/古今書院 -
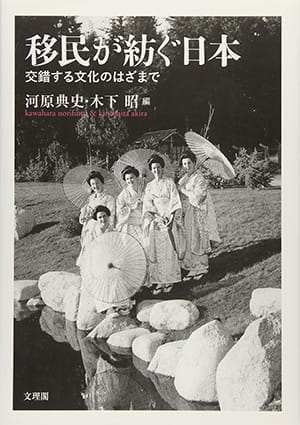
移民が紡ぐ日本――交錯する文化のはざまで
河原典史・木下昭編著(2018)/文理閣 -
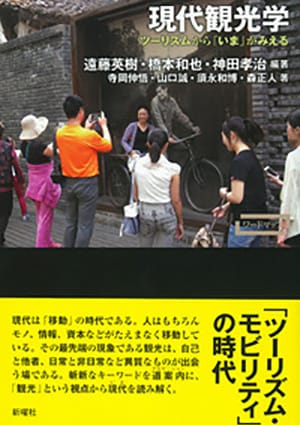
現代観光学――ツーリズムから「いま」がみえる
遠藤英樹・橋本和也・神田孝治編著(2019)/新曜社 -

ポケモンGOからの問い――拡張されるリアリティ
神田孝治・遠藤英樹・松本健太郎編著(2018)/新曜社
関連するシンポジウム
-
AI以後の人文・社会科学を問う
ZOOMウェビナー・YouTube動画限定配信
主催:立命館大学人文科学研究所 -
Malaysia on Tour with/after COVID-19――新型コロナウイルス感染症以後のマレーシア観光を考える――
YouTube動画限定配信
主催:立命館大学人文科学研究所 -
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)以後の観光研究
YouTube動画限定配信
主催:立命館大学人文科学研究所
