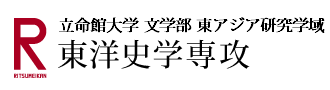立命館東洋史學
NEW!『立命館東洋史學』第47號を刊行しました。
このページでは過去号の目録を掲載しております。投稿規定に関しては、立命館東洋史學會のページをご参照ください。
リポジトリ公開
2019年6月18日より、立命館大学学術成果リポジトリ「R-Cube」にて、過去号のPDF公開を開始いたしました。現在30~46号が公開されています(一部未公開論文等あり)。
下記目録のリンクからご利用ください(46号以降掲載分は目録にリンクが貼られていませんので、「過去号のPDF公開」より検索してください)。
なお、R-Cubeに関するお問い合わせは、下記弊会連絡先までお寄せください。
バックナンバー
バックナンバーの販売もしております。
購入を希望される方は、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
※第18号以前・23号・41号の販売は致しておりません。
連絡先
〒603-8577京都市北区等持院北町 56-1
立命館大学文学部内 立命館東洋史學會
E-Mail:rits-eah◎gst.ritsumei.ac.jp
(◎を半角アットマークに直してメールを送信してください。)
『立命館東洋史學』目録
第47号(2025年)
| 論文 | 鷹取祐司 | 秦代における爵制的身分序列の形成 |
|---|---|---|
| 松本保宣 | 御前会議と文書行政の間 ― 唐代の政策決定過程についての一考察― |
|
| 鄧子琦 | 五代墓誌に見られる王朝の正統性に対する認識 | |
| 訳注 | 菅沼愛語 | 隋代和蕃公主に関する諸史料の訳注 ― 『隋書』『周書』『旧唐書』『新唐書』『資治通鑑』より― |
第46号(2024年)
| 論文 | 祁蘇曼 | 明代の司法上奏における「参語」 |
|---|---|---|
| 豊嶋順揮 | 明中期における朝貢貿易と中国社会 ― 会同館開市に関する規定の法整備過程から見る― | |
| 研究ノート | 鷹取祐司 | 秦漢時代の司寇・隷臣妾・鬼薪白粲・城旦舂 補遺 |
第45号(2022年)
| 論文 | 佐藤信弥 | 西周金文の製作意図について
―同一の事件について記録した金文より探る― |
|---|---|---|
| 猪俣貴幸 | 唐代後半期の太廟における「一帝一后」
―北宋多后配祔の背景― |
|
| 孫悦妍 | 唐代後半期における宮官の政治参与
―宋氏姉妹を例として― |
|
| 祁蘇曼 | 明代の問刑実務における「参語」
―『不平鳴稿』を題材に― |
|
| 研究ノート | 小野 響 | 西晋における単于
―元会儀礼における匈奴南単于の位置づけを中心に― |
| 特別寄稿 | 松本保宣先生のご還暦に寄せて
執筆者御芳名 石井和志・伊藤正彦・鵜島三壽・江川式部・岡部毅史・小野響・菊地俊介・塩卓悟・杉本史子・武田和哉・田中一輝・中村公大・平田茂樹・細井和彦・山本一之(敬称略五十音順) |
第44号(2021年)
| 論文 | 鷹取 祐司 | 漢代兵役考証 |
|---|---|---|
| 石井 和志 | 漢代「天下の母」考 | |
| 永田 拓治 | 漢晋期における仏教流伝と歴史叙述
―「書かない」という叙述行為― |
|
| 翻訳 | 増井 寬也 | オーウェン・ラティモア著「ゴルド族:松花江下流の“魚皮韃子”」 |
第43号(2020年)
| 論文 | 松本 保宣 | 五代後唐期の中興殿と延英殿 ―五代聴政制度初探― |
|---|---|---|
| 池田 修太郎 | 「西爐の役」がもたらしたもの ―清朝の打箭爐支配成立の一側面― |
|
| 研究ノート | 小野 響 | 烏桓における単于の導入
―三郡烏桓王権の変化と非漢族への単于授与― |
| 史料紹介 | 細井 和彦 | 翻訳:楊杰著『国防新論』(七) |
| 猪俣 貴幸 | 中央硏究院傅斯年圖書館藏明鈔本『條例全文』殘本三種について | |
| 訳注 | 赤羽 奈津子・猪俣 貴幸 | 吳士鑑「晉書斠注序」譯註稿 |
| 特別寄稿 | 富田 健次 | 金室完顔部の勃興―その構造面の試論的考察 |
第42号(2019年)
| 論文 | 豊嶋 順揮 | 明朝成化・弘治年間の海上密貿易をめぐる法整備 |
|---|---|---|
| 増井 寛也 | 八旗創設期のグサ分領制とその基底について ―特に動詞salibumbiとの関連から見た― |
|
| 史料紹介 | 細井 和彦 | 翻訳:楊杰著『国防新論』(四) |
| 書評 | 鷲尾 祐子 |
松島隆真『漢帝国の成立』 |
第41号(2018年)※在庫なし
| 論文 | 小野 響 | 後趙建国前夜 ―匈奴漢国家体制試論― |
|---|---|---|
| 陸 俊鋮 | 洪武年間に於ける明の東北アジア外交 ―東北アジアの国際情勢および洪武帝の対外戦略― |
|
| 研究ノート | 増井 寛也 | ジュシェン-マンジュ史箚記(続) |
| 新刊紹介 | 小野 響 |
岡部毅史『魏晋南北朝官人身分制研究』 |
| 田中一輝『西晉時代の都城と政治』 |
第40号(2017年)
| 論文 | 井上 充幸 |
汪砢玉の生涯 ―『珊瑚網』から見る明末の嘉興における文雅について― |
|---|---|---|
| 山田 崇仁 | 前漢前少帝の諱について | |
| 研究ノート | 増井 寛也 | ジュシェン-マンジュ史箚記二題 |
第39号(2016年)
| 論文 | 宮内 肇 | 一九二〇年代広東における宗族の自己改革論 ―五邑地域の族刊雑誌からみる― |
|---|---|---|
| 小野 響 | 前秦崩壊と華北動乱 ―淝水の戦い前後における関西と関東― |
|
| 松島 隆真 | 賈誼の対諸侯王の再検討 ―淮南問題と「地制」のあいだ― |
|
| 大西 啓司 | 西夏王国に於ける文化の継承問題について ―『聖立義海』に見られるタングート人の祖先の名と祖先神話をもとに― |
|
| 史料紹介 | 細井 和彦 | 翻訳:楊杰著『国防新論』(一) |
第38号(2015年)
| 論文 | 關 劍平 | 茶筅の起源とその確立 |
|---|---|---|
| 菅沼 愛語 | 隋代の和蕃公主と北方西方に対する隋の外交戦略 | |
| 猪俣 貴幸 |
皇后祔廟攷初探 ―別廟の系譜と唐睿宗の二后を中心に― |
|
| 増井 寬也 | 天命後半期グサ別ニルの数量的考察 | |
| 田中 一輝 | 玉璽の行方 ―「正統性」の成立と相克― |
第37号(2014年)
| 論文 | 松本 保宣 |
唐末五代前半の朝儀について ―入閤・起居・朝儀を中心に― |
|---|---|---|
| 増井 寬也 | ヌルハチ大妃ウラ=ナラ氏〈殉死〉考略 | |
| 服部 佐代子 | 小説『蹉跎歳月』から見た中華人民共和国における血統論 ―文学的フィクションと真実への一考察― |
|
| 研究ノート | 磯部 淳史 |
清朝皇帝と三藩―三藩研究のための覚書― |
| 史料紹介 | 大西啓司 手塚利彰 山田敕之 アラムス 黒田有志 |
「乾隆皇帝贈ダライラマ8世玉冊」について ―清朝・チベット関係史の一史料として― |
| 新刊紹介 | 阿路川 真也 | 菅沼愛語『7世紀後半から8世紀の東部ユーラシアの国際情勢とその推移―唐・吐蕃・突厥の外交関係を中心に―』 |
第36号(2013年)
| 論文 | 鷹取 祐司 |
漢代の居延・肩水地域における文書伝送 |
|---|---|---|
| 小野 響 |
前趙と後趙の成立 ―五胡十六国時代における匈奴漢崩壊後の政治史的展開― |
|
| 池田 修太郎 |
康煕年間の年羹尭 ―行政改革の面を中心に― |
|
| 研究ノート | 細井 和彦 | 『楊杰將軍文集』出版の持つ意味 ―「近代中国における歴史人物評価をめぐって」補遺― |
| 随筆 | 北村 稔 | 中国近現代史の探索 ―楽しくて苦しい(楽苦しい)― |
第35号(2012年)
| 論文 | 井上 充幸 |
平天仙姑小考―黒河中流域における水神信仰の過去と現在― |
|---|---|---|
| 鷲尾 祐子 |
走馬楼呉簡吏民簿と郷の状況―家族研究のための予備的検討― | |
| 増井 寬也 |
清初〈専管ニル〉再論 ―貂皮・人参採捕権の解釈を中心に― 正誤表 |
|
| 磯部 淳史 |
順治朝における側近集団の一考察 ―内三院・内閣、十三衙門を中心に― |
|
| 史料紹介 | 細井 和彦 | 楊杰講演『国防講話』解説と翻訳 |
第34号(2011年)
| 論文 | 落合 淳思 | 漢字の成り立ち |
|---|---|---|
| 増井 寬也 | <太陽を食べる犬>その他三則 ─ジュシェン人とその近縁諸族の歴史・文化・描─ |
|
| 研究ノート | 磯部 淳史 | 順治朝の後継者問題と康熙帝をめぐる旗王たち |
| 史料紹介 | 細井 和彦 | 『陸大月刊』目次と解題 |
第33号(2010年)
| 論文 | 本田 治 | 清代寧波沿海部における開発と移住 |
|---|---|---|
| 松本 英紀 | ある追悼文(二続) ─西安事件後の周恩来、張冲そして潘漢年─ |
|
| 史料紹介 | 『都城紀勝』訳注(二) |
第32号(2009年)
| 論文 | 松本 英紀 | 続 ある追悼文 ─西安事件後の周恩来、張冲そして潘漢年─ |
|---|---|---|
| 町田 吉隆 | 明代南京城牆磚瓦の生産と輸送について | |
| 増井 寛也 | マンジュ国〈四旗制〉初建年代考 | |
| 磯部 淳史 | 順治朝における皇帝・旗王関係についての一考察 ─順治八年~十二年の政局をめぐって─ |
|
| 田島 大輔 | 「滿洲国」初期の回民教育問題 ─「滿洲伊斯蘭協会」の事例を中心に─ |
第31号(2008年)
| 論文 | 鷹取 祐司 | 秦漢時代公文書の下達形態 |
|---|---|---|
| 阿路川 真也 | 唐代荊南節度使考 | |
| 役重 文範 | 漢代瑞祥考─皇帝・政治との関係─ | |
| 史料紹介 | 『都城紀勝』訳注(一) | |
| 追悼文 | 武田 和哉 | 日比野丈夫先生のご逝去を悼んで |
第30号(2007年)
| 論文 | 松本 英紀 | ある追悼文 ─西安事変前後の周恩来、張冲そして潘漢年─ |
|---|---|---|
| 大澤 直人 | 戦国楚の政権構造─戦国世族を中心に─ | |
| 磯部 淳史 | 清朝順治初期における政治抗争とドルゴン政権 ─八旗制度からの考察を中心に─ |
|
| 研究ノート | 田島 大輔 | 雑誌『回教』に就いて |
第29号(2006年)
| 論文 | 松本 保宣 | 唐の代宗朝における臣僚の上奏過程と枢密使の登場 ─唐代宮城における情報伝達の一齣 その一─ |
|---|---|---|
| 原田 三壽 | 漢代の百戯 | |
| 落合 淳思 | 日本語用文字コードに対応した甲骨文字フォント製作案 | |
| 研究ノート | 磯部 淳史 | 順治帝即位をめぐる黄旗旗人の動向について ─バブハイ断罪事件を例として─ |
第28号(2005年)
| 論文 | 本田 治 | 北宋時代の唐州における水利開発 |
|---|---|---|
| 松本 英紀 | 公開された秘密党員(下) ─楊度の入党をめぐって─ |
|
| 増井 寛也 | 満洲〈アンダ〉anda小考 |
第27号(2004年)
| 論文 | 松本 英紀 | 公開された秘密党員(中) ─楊度の入党をめぐって─ |
|---|---|---|
| 三谷 路夫 | 「盒」と「匣」の考察による「撞」と「印籠」の問題 ─『雅尚齋遵生八牋』を端緒として─ |
|
| 落合 淳思 | 殷・西周金文の起草 | |
| 山田 崇仁 | 『孟子』の成書時期について ─N-gramと統計的手法を利用した分析─ |
|
| 訳注 | 秋山 陽一郎 | 孫徳謙 劉向校讐學纂微訳注〔二〕 |
第26号(2003年)
| 論文 | 松本 英紀 | 公開された秘密党員(上) ─楊度の入党をめぐって─ |
|---|---|---|
| 松本 保宣 | 唐代常朝制度試論 ─吉田歓氏『日中宮城の比較研究』によせて─ |
|
| 本田 貴彦 | 西周金文における作器語句の分析 | |
| 鷲尾 祐子 | 前漢博士官の性格 ─僕射から検討する─ |
|
| 周 俊 | 「分治」と「統一」 ─中国における政治イデオロギーの葛藤─ |
|
| 研究ノート | 秋山 陽一郎 | 孫徳謙 劉向校讐學纂微訳注〔一〕 |
第25号(2002年)
| 論文 | 町田 吉隆 | 磚瓦焼成燃料に関する一考察 ─元代大都の「蓑城」をめぐって─ |
|---|---|---|
| 落合 淳思 | 神の一般形と古代中国の主神不在に関する考察 | |
| 沖田 道成 | クビライの徙民 ─懷孟の一例より─ |
|
| 吉本 道雅 | 左伝成書考 | |
| 周 俊 | 中国における連邦論の実例研究 ─「分治」思想の起源と梁啓超の「地方自治」─ |
|
| 書評 | 本田 貴彦 | 落合淳思著 殷王世系研究(立命館東洋史學會叢書一) |
第24号(2001年)
| 論文 | 本田 治 | 宋代都市における花卉園芸について |
|---|---|---|
| 武田 和哉 | 契丹国(遼朝)の北・南枢密院制度と南北二重官制について | |
| 周 俊 | 清末における中国の民主思想 ─その形成と特徴を中心に |
|
| 研究ノート | 牛根 靖裕 | 元代の鞏昌都總帥府の成立とその展開について |
| 鄭 宰相 | 荀子の「類」概念について |
第23号(2000年)※在庫なし
| 論文 | 本田 治 | 巻頭言 中村喬教授略歴 中村喬教授著作目録 |
|---|---|---|
| 中村 喬 | 食蛙について | |
| 三谷 路夫 | 宋代瓷製香炉の器題とその解題 ─鼎炉・鬲炉・乳炉─ |
|
| 大平 浩史 | 中国仏教の近代化を探る ─太虚の初期仏教改革活動─ |
|
| 周 俊 | 日中近代化の比較研究序説 ─経済、政治、文化の構造を中心に |
|
| 報告 | 棚橋 寛一 | 世界史授業と視聴覚機器利用の可能性 ─静止視聴覚資料の使い方について─ |
第22号(1999年) 大澤陽典名誉教授追悼号
| 追悼 | 中村 喬 | 序 |
|---|---|---|
| 故大澤陽典教授略歴 故大澤陽典教授主要論著・著作目録 |
||
| 松田 孝一 | 大澤先生の学問について | |
| 論文 | 松本 英紀 | 胡瑛について |
| 手塚 利彰 | グシハン一族と属領の統属関係 | |
| 周 長山 | 漢代の都市分布について | |
| 邱 榮裕 | 上海東亜同文書院院生の調査活動に関する研究 | |
| 研究ノート | 門井 由佳 | カレドニアンオリエント ─王立スコットランド博物館の東洋美術コレクション─ |
| 書籍紹介 | 船木 智之 | 『明代宦官政治』(衛建林、花山文芸出版社、一九九八年)に関する私見 |
| 追悼文 | 稲葉 一郎 | 大澤陽典先生の思い出 |
| 本田 治 | 大澤先生の事 | |
| 他、全8編 | ||
第21号(1998年)
| 論文 | 吉本 道雅 | 秦趙始祖伝説考 |
|---|---|---|
| 祁 小春 | 『蘭亭集序』に於ける悲哀情緒の考察 ─郭沫若の悲観説批判─ |
|
| 井田 一道 | ウェッデル事件と広州の夷務 | |
| 山田 崇仁 | 中国史学に於けるコンピュータ利用について(その2) | |
| 書籍紹介 | 門井 由佳 | 写真芸術と英国東洋美術研究の歩み ─『APOLLO』(March 1998, Vol.CXLII No.433) 特集《ORIENTAL ART》─ |
第20号(1997年)
| 論文 | 細井 和彦 | 鄧演達の二度目の出国渡欧 |
|---|---|---|
| 張 海英 | 中国における平民教育思想に関する一考察 ─李大釗の平民教育思想を中心にして─ |
|
| 研究ノート | 中村 喬 | 葷酒の「葷」について |
| 許 育銘 | 九一八事変後の国民政府と政治論争 ─「国難会議」の歴史的考察を通じて─ |
|
| 大野 美紀子 | フランス軍政期ベトナム南部における村落史料 ─田簿(dien pa)の紹介─ |
第19号(1996年)
| 論文 | 本田 治 | 宋代温州における開発と移住補論 |
|---|---|---|
| 藤井 彰一郎 | 党項人察罕の家系に関する一考察 | |
| 門井 由佳 | 中国美術における美人女性画 ─麻姑と東西美術交流─ |
|
| 山田 崇仁 | 中国史研究に於けるパソコンの利用について |
以下は、前身誌『立命館東洋史學會會報』になります。
※論文・研究ノートのほかに大会発表要旨や対談なども入っています。
なお、『會報』については販売をいたしておりません。
第18号(1995年)
| 中村 喬 | 破五「送窮」管見 |
|---|---|
| 井田 一道 | アヘン戦争における英国の割譲島要求 |
| 杉本 史子 | 清末における留日女子学生 |
| 黄 英哲 | 戦後初期台湾における文化再構築に関する一考察 |
第17号(1994年)
| 吉本 道雅 | 晋霊公 |
|---|---|
| 細井 和彦 | 鄧演達生家訪問記 |
| 三谷 路夫 | 中国瓷器の美術的価値と皇帝趣味 ─皇帝と御用器とのかかわり |
| 遠山 日出也 | 改革・開放期における中国共産党の女性政策 |
| 遠藤 祐子 | 「先令券書」の投げかけるもの ─漢代家族史の課題─ |
第16号(1993年)
| 小島 喜久男 | 大澤陽典教授略歴 大澤陽典教授と立命館東洋史学会について |
|---|---|
| 志田 穰 | 大澤先生の思い出 |
| 中村 喬 | 「東坡墨魚」 |
| 馬越 靖史 | 「関西学院大学図書館所蔵 内藤湖南・戊申旧蔵 殷周甲骨金文学関係文庫」小識 |
| 田中 理恵 | 朝鮮陶磁史上の転期 ─一四・五世紀の窯の性質とその変遷─ |
| 谷 秀樹 | 前漢武帝代における対外思想の変容過程について |
| 山田 崇仁 | 春秋呉の軍事制度に関する一試論 |
| 田口 容三 | 韓国近代史研究雑感 |
第15号(1992年)
| 中村 喬 | 三田村先生を憶いながら |
|---|---|
| 斎藤 忠和 | 斎藤忠和・町田吉隆・山本一之・武田和哉編 『東京夢華録(入矢義高・梅原郁訳注)索引』刊行に寄せて |
| 三谷 路夫 | 青花磁の絵画性と元代士大夫 |
| 千條 正人 | 中国古代天文学における星の変光記述について |
| 山本 一之 | 『東京夢華録』編集に参加して |
| 松本 英紀 | 「皇帝型権力」について |
第14号(1991年)
| 松本 英紀 | 講義余談 |
|---|---|
| 遠藤 祐子 | 唐代の伎 |
| 斎藤 真司 | 漢代における帝位継承の即位儀礼 |
| 廣居 健 | 中国酒雑見 ─まぜものにかかわって─ |
| 菊川 泰 | 『殷暦譜』再編成上の諸問題 |
第13号(1990年)
| 大澤 陽典 | 三田村名誉教授の訃 |
|---|---|
| 日比野 丈夫 | 三田村先生の思い出 |
| 布目 潮渢 | 三田村先生を偲んで |
| 大石 進 | “三田村教授追放”事件のこと |
| 稲葉 一郎 | 三田村先生の思い出 |
| 山本 徳子 | 三田村先生と音楽 |
| 亀谷 隆行 | 三田村先生を偲ぶ |
| 井上 泰也 | 宋代の鈔版をめぐって |
| 富田 健次 | 変容するイラン |
第12号(1989年)
| 大澤 陽典 | 漢代の二遺体と秦漢二代の地図 |
|---|---|
| 戸田 裕司 | ある「豪横」 |
| 武田 和哉 | 契丹族における社会構造について ─遼朝建国以前を中心に─ |
第11号(1988年)
| 本田 治 | 溜池雑考 |
|---|---|
| 細井 和彦 | 『少年中国学会について』 |
| 山本 一之 | 中国古代の正楽と俗楽の性格 |
| 町田 吉隆 | 造磚管見 |
第10号(1987年)
| 松本 英紀 | 「現代中国の実像」 孫文 |
|---|---|
| 城 孝広 | 「鄭州滞在記」 |
| 鵜島 三壽 | 鎮墓獣について |
| 増井 寛也 | 明代の野人女直について |
| 徳岡 仁 | 〔海外報告〕 北京留学の記 |
| 大石 進 | 立命館東洋史専攻『創設の頃』の想い出 |
第9号(1986年)
| 中村 喬 | 弄潮 |
|---|---|
| 大石 進 | 立命館東洋史専攻『創設の頃』の想い出 |
| 牧 秀明 | 漢代における救荒政策について |
| 斉藤 忠和 | 北京・上海・洛陽・西安を訪ねて |
| 梁 元喆 | 漢代良家子について |
| 三宅 通久 | 随想 『新学偽経考弁』のその後 |
第8号(1985年)
| 対談 東洋史専攻創設の頃〔2〕 | |
| 松田 徹 | 遼東公孫子政権に関する一考察 ─災異記事を視点として─ |
| 大澤 陽典 | 鎮江三山拝塔記 |
| 本田 治 | 研究ノート 嘗の帳簿 |
| 斉藤 忠和 | 宋代禁軍を中心とする剰員・帯甲剰員制解明へのアプローチ |
| 松本 保宣 | 唐代の詣闕上表について |
第7号(1984年)
| 対談 東洋史専攻創設の頃〔1〕 | |
| 海老名 俊樹 | 北宋に於ける凌遅処死制度をめぐって |
| 鈴木 明彦 | リンダン=ハンについて天命四年の書簡を中心に |
| 玉田 継雄 | 成都・重慶・武漢をたずねて |
| 松本 英紀 | 西園寺文庫所蔵の荘原和著『新学偽経考辨』について |
| 牧 秀明 | 漢代の華中・華南地方について |
第6号【復刊号】(1983年)
| 大澤 陽典 | 会報復刊に際して |
|---|---|
| 中村 喬 | 楊桃 ─木原先生を思う─ |
| 松本 英紀 | ある読書会の思い出 |
| 本田 治 | 卒論の頃 |
| 多和 史彦 | 中国での一年 ─とくに南京・太原を中心として─ |
| 金澤 啓明 | 北周時代における元始天尊(元始天王)神学の登場について ─北周甄鸞「笑道論」引用書より見て─ |
| 山原 茂 | 蘭蕙事始 |