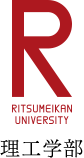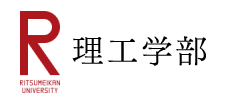藪 博之教授 YABU Hiroyuki
- 所属学科
- 物理科学科
- 研究室
- 理論物理学研究室「量子場の理論」
- 学位
- 理学博士(物理学)
経歴概要
1983年3月 京都大学理学部 卒業 1985年3月 京都大学大学院理学研究科物理学第二専攻修士課程 修了 1988年3月 京都大学大学院理学研究科物理学第二専攻博士後期課程 修了
研究について
- 研究分野・テーマ
-
場の量子論による研究、ミクロからマクロまで
- 研究キーワード
-
量子場の理論、原子核物理、量子原子気体
- 研究概要
-
電場・磁場のように空間の各点に物理量が対応するのが場で、その運動を記述する理論が場の量子論です。この理論は自然を理解するための最も基本的な方法で、それは原子核・素粒子や原子分子といったミクロな世界から、宇宙の構造といったマクロな世界にまでおよびます。また場の理論は自然界のシンメトリー(対称性)を考える上で基本的な手段となり、自然界の奥にある美しさを見せてくれます。そしてそれは超流動や超伝導といった現 象を通じて、マクロな世界にもひょっこりと現れてきます。この研究室では、場の理論を用いて、素粒子や原子核の世界のシンメトリーの問題や原子気体のボース凝縮状態など物質の新しい量子状態を理論的に解明するとともに、ガンマ線レーザーなど新技術への応用に対する基礎的研究を行っています。
-
Bose-Fermi混合凝縮体においてたくさんの量子渦がつくる渦格子(理論計算)
左がBose粒子凝縮体の渦、右は渦芯にトラップされたFermi粒子、
下の図では中心に巨大渦(Giant Vortex)が形成されている。
-
インタビュー
研究者になったきっかけ
私は中学の時「化学のドレミファ」(米山正信著、図書室にあるかもしれませんよ)という本にであって原子というものに興味を持ちました。「すべての物は原子という小さな粒からできている」という原子仮説に引かれ、一言一句ノートに書き写すようにして勉強しました。それじゃ化学でしょ、何で物理なんですかって。高校に入って、原子のことを知るために、その構造を理解する必要を感じいろいろ調べているうちに、そういった内容は化学ではなく物理で研究されていることがわかったからです。当時の私の高校は自由な所で学校の教科はほどほどに自分の決めた勉強ばかりしてました。受験勉強にも精出しましたが大学で原子、原子核、素粒子といったことを極めてみたかったからです。大学それから大学院と進んで研究三昧でした。世俗から逃れて好き放題やれてといった感じ。おもしろかったです。