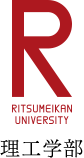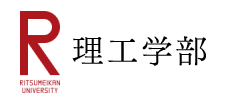清水 寧教授 SHIMIZU Yasushi
- 所属学科
- 物理科学科
- 研究室
- 計算基礎物理学研究室
- 学位
- 博士
経歴概要
1988年3月 早稲田大学理工学部物理学科 卒業 1990年3月 早稲田大学大学院理工学研究科物理及び応用物理学専攻博士前期課程 修了 1995年3月 東京工業大学大学院理工学研究科応用物理学専攻博士後期課程 修了
研究について
- 研究分野・テーマ
-
原子分子の運動に潜む非統計性を探る
- 研究キーワード
-
少数多体系のダイナミクス
- 研究概要
-
我々の周りの世界はミクロからマクロにいたるまで絶えず動きながらその姿を変えています。一見不変に見えるものもよく目を凝らせば、そこには非常に多様な動きがあります。我々の研究室では、原子や分子の世界での動きを計算機によって模倣し、それを数理の言葉で理解することを目指しています。特に原子の集合体である分子やナノクラスターとよばれる少数多体系における非線形な運動とそれに起因する非統計性を研究対象にしています。コンピュータの世界からこれらのダイナミクスの背後にある数理を理解し、そこから観測結果に新たな解釈、ひいては新たな実験を提案することが我々の目標です。
-
粒子シミュレーションによって再現したミルククラウン現象
-
インタビュー
研究者になったきっかけ
最初に入った研究室では、拙い質問をしつこく繰り返しても、同じ目線にたって相手になって頂いた斎藤信彦先生に強い影響を受けました。先生は、カオス的に振る舞う抽象的なおもちゃモデルを研究する一方で、たんぱく質の立体構造予測という、一見すると関連性のない研究を同時並行で進められていました。自然現象におけるカオス現象は、表面的にはランダムのように見えても、その背後には精妙な秩序構造(カオスの中の秩序)が存在することがその最大の特徴です。研究室生活を続ける中で、先生の過去の研究ヒストリーを理解するにつれ、なぜ先生が直接関連しないように見えるテーマを同時に進められているのか、自分なりに理解できました。先生の研究スタイル自体が、自らの研究対象であるカオス現象と同様、一見無秩序に見えても、一貫した秩序構造を持っていることの気づきました。研究対象の構造がそのまま研究者自身の興味のあり方や自然観にも結びつき、それによって独自のスタイルを成していることに、研究する人生の一つの究極形をみたような気がしました。 大学院になると、毎晩遅くまで研究室に残り、プログラムをかいたり、先輩や同級生の方々と議論をして過ごす時間が、何よりも楽しく感じました。その当時参加した研究会では、年齢、肩書きなどに関係なく、率直に、ときに激しく議論しながら理解を深める研究者の姿をみて、強い憧れを抱きました。たぶんこれらが今のようになったきっかけで、その後もカオスを深く掘り下げて理解したくてもぞもぞやっているうち、今に至ったという気がします。