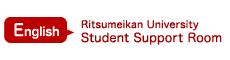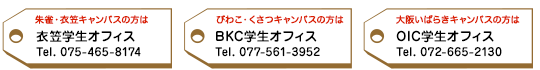大学は何をするところなのだろうか
2013年05月31日
コラム
大学のキャンパスには様々な意識の学生が通っています。明確な目標を持って目標に向かって行動している学生もいれば、なんとなく毎日を過ごしている学生もいます。明確な目標を持っていても、どうやって目標に向かって行動して良いのか悩んでいる学生もいれば、目標以外まったく見えず過ごしている学生もいます。では、大学とはそもそも何をするところで、何をすればよいのでしょうか?
私は、大学は自分の意思で「様々な経験を積むところ」だと考えています。高校生であれば、「○○をしなさい」と先生が明確に道を教えてくれたかもしれません。一方大学では、何をするかは自分自身で決めなければなりません。皆さんには学ぶ「自由」が与えられています。この「自由」は時には残酷です。ある人は悩み、ある人はサボり、ある人は一歩も動けなくなります。でも、学ぶ「自由」を通じて皆さんは飛躍的に成長します。
他人の助け、書籍の助け、メディアの助け、ネットの助けなど自身の意思決定のための様々なツールがあります。このツールを自発的に使いこなすことで皆さんは無意識のうちに、他人に相談する力(コミュニケーション力)、書籍を読み理解する力(論理的思考力)、メディアから必要な情報を抽出する力(問題発見能力)、ネットを使いこなす力(情報リテラシー)など大学生として必要な能力を身につけることができます。
しかし、これらの能力は受動的でパターン化された日常では容易に身につきません。つまり、大学在学中にどれだけ多くの「自発的な経験を積めたか」がポイントとなります。
講義で教授の話を聞く“だけ”、サークルで友達と話す“だけ”、図書館で本を読む“だけ”では、経験が偏り限定的な成長しか期待できません。つまり、目標を達成するために必要だと思うこと“だけ”を頑張っても、大学生としては十分な評価を得ることができないのです。余り興味がないと思うことも、進んでやってみよう!体験してみよう!という知的好奇心が様々な経験へと皆さんを誘い、大きな成長へとつながります。友達との遊びの中にも成長への鍵は潜んでいます。たまには違う友達と違う遊びを楽しむことも「様々な経験」という意味では大学生には有益だと思いますよ。
自発的に様々なツールを使いこなし、遠回りと思えることや、一見関係がないと思えることも積極的に経験をすることで、新しい目標が見つかったり、届かないと思っていた目標に思いの外近づいていたりします。
一度考えてみてください。自分は大学生としてどれだけの経験をつめたのでしょうか。
私は、大学は自分の意思で「様々な経験を積むところ」だと考えています。高校生であれば、「○○をしなさい」と先生が明確に道を教えてくれたかもしれません。一方大学では、何をするかは自分自身で決めなければなりません。皆さんには学ぶ「自由」が与えられています。この「自由」は時には残酷です。ある人は悩み、ある人はサボり、ある人は一歩も動けなくなります。でも、学ぶ「自由」を通じて皆さんは飛躍的に成長します。
他人の助け、書籍の助け、メディアの助け、ネットの助けなど自身の意思決定のための様々なツールがあります。このツールを自発的に使いこなすことで皆さんは無意識のうちに、他人に相談する力(コミュニケーション力)、書籍を読み理解する力(論理的思考力)、メディアから必要な情報を抽出する力(問題発見能力)、ネットを使いこなす力(情報リテラシー)など大学生として必要な能力を身につけることができます。
しかし、これらの能力は受動的でパターン化された日常では容易に身につきません。つまり、大学在学中にどれだけ多くの「自発的な経験を積めたか」がポイントとなります。
講義で教授の話を聞く“だけ”、サークルで友達と話す“だけ”、図書館で本を読む“だけ”では、経験が偏り限定的な成長しか期待できません。つまり、目標を達成するために必要だと思うこと“だけ”を頑張っても、大学生としては十分な評価を得ることができないのです。余り興味がないと思うことも、進んでやってみよう!体験してみよう!という知的好奇心が様々な経験へと皆さんを誘い、大きな成長へとつながります。友達との遊びの中にも成長への鍵は潜んでいます。たまには違う友達と違う遊びを楽しむことも「様々な経験」という意味では大学生には有益だと思いますよ。
自発的に様々なツールを使いこなし、遠回りと思えることや、一見関係がないと思えることも積極的に経験をすることで、新しい目標が見つかったり、届かないと思っていた目標に思いの外近づいていたりします。
一度考えてみてください。自分は大学生としてどれだけの経験をつめたのでしょうか。
学生部副部長
情報理工学部准教授
西浦 敬信
情報理工学部准教授
西浦 敬信