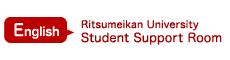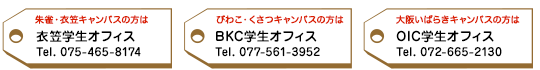夏休みになると
2013年08月07日
コラム
夏休みになると、NHKラジオ第1で、『夏休み子ども科学電話相談』というラジオ番組が午前中にあります。今年で30周年になる番組で、本にもなっています。私は数年前、たまたまこの番組を知って、とても面白くて、聞ける時はなるべく聞いています。
主に3・4歳から10歳を過ぎた頃の子どもが電話で専門家の先生に質問します。ジャンルは、野鳥、昆虫、植物、天文・宇宙、魚・動物などがあります。私が聞いた時は、「ツバメは渡り鳥だけど、同じ巣に戻ってくるの?」、「カマキリの上手な飼い方は?」、「どうして苦い野菜がある?」、「惑星は最後はどうなるの?」、「魚はどうやって寝ているの?」といった内容の質問がありました。
聞いていて、知ってる知ってると思う質問もあれば、そんなこと考えたこともなかった!という質問もあります。知ってる知ってると思っていても、専門家の先生のお話を聞くと、詳しくはそうなってたんだ、と新たな発見もあります。
でも私がもっと面白いのは、子どもと専門家の先生のやりとりです。「苦い野菜は何があるかな?」と専門家の先生に尋ねられて、「ピーマン…」と答えられる子どももいますが、ぱっとは出てこない子どももいます。「惑星って、どういうのがあるかな?」と尋ねられて、「うーん…わからない…」となる子どももいます。
子どもの質問にどう答えるかというのは、年齢に応じた理解の仕方がありますし、その子の体験している世界に沿って答えないと子どもは納得してくれません。例えば、3・4歳の子どもに「慣性の法則がね…」と言っても多分ちんぷんかんぷんです。でも、どうしてもそういう法則を持ち出してこないと答えられないこともあるし、大人が完璧に答えられないこともあります。大人の側が「わからないんだ」となることもありますし、「もっと大きくなったら習うよ」等、少し、今後の道筋を子どもに示すこともあります。
次々電話はかかってきて次の質問に移っていかないといけないし、大概の子どもはわからなくても、「わかったかな?」と大人に尋ねられたら「…わかった」と答えているように聞こえるのですが、それまでのやりとりの感じが、子どもも大人も苦心していて、聞いていてほほえましくなります。
30年も番組が続いていると、これまでの番組の中で内容としては似たような質問はたくさんあっただろうと思います。けれども、その子どもがその時に疑問に思ったというのはかけがえのないことですし、これまでと同じように答えたからといって、電話の先のたった一人のその子どもが理解してくれるかはわかりません。
電話なので、直接会っているのではなく、相手の様子はわからないし、質問に答える側も大変だと思うのですが、電話でのやりとりを聞いているだけでも、子どもがとても可愛いらしいです。
大学生の皆さんは、普段子どもと接する機会はあまりないかもしれませんが、夏休み中に、例えばこの番組を通して、子どもの体験している世界を垣間見るのも新鮮かもしれません。
主に3・4歳から10歳を過ぎた頃の子どもが電話で専門家の先生に質問します。ジャンルは、野鳥、昆虫、植物、天文・宇宙、魚・動物などがあります。私が聞いた時は、「ツバメは渡り鳥だけど、同じ巣に戻ってくるの?」、「カマキリの上手な飼い方は?」、「どうして苦い野菜がある?」、「惑星は最後はどうなるの?」、「魚はどうやって寝ているの?」といった内容の質問がありました。
聞いていて、知ってる知ってると思う質問もあれば、そんなこと考えたこともなかった!という質問もあります。知ってる知ってると思っていても、専門家の先生のお話を聞くと、詳しくはそうなってたんだ、と新たな発見もあります。
でも私がもっと面白いのは、子どもと専門家の先生のやりとりです。「苦い野菜は何があるかな?」と専門家の先生に尋ねられて、「ピーマン…」と答えられる子どももいますが、ぱっとは出てこない子どももいます。「惑星って、どういうのがあるかな?」と尋ねられて、「うーん…わからない…」となる子どももいます。
子どもの質問にどう答えるかというのは、年齢に応じた理解の仕方がありますし、その子の体験している世界に沿って答えないと子どもは納得してくれません。例えば、3・4歳の子どもに「慣性の法則がね…」と言っても多分ちんぷんかんぷんです。でも、どうしてもそういう法則を持ち出してこないと答えられないこともあるし、大人が完璧に答えられないこともあります。大人の側が「わからないんだ」となることもありますし、「もっと大きくなったら習うよ」等、少し、今後の道筋を子どもに示すこともあります。
次々電話はかかってきて次の質問に移っていかないといけないし、大概の子どもはわからなくても、「わかったかな?」と大人に尋ねられたら「…わかった」と答えているように聞こえるのですが、それまでのやりとりの感じが、子どもも大人も苦心していて、聞いていてほほえましくなります。
30年も番組が続いていると、これまでの番組の中で内容としては似たような質問はたくさんあっただろうと思います。けれども、その子どもがその時に疑問に思ったというのはかけがえのないことですし、これまでと同じように答えたからといって、電話の先のたった一人のその子どもが理解してくれるかはわかりません。
電話なので、直接会っているのではなく、相手の様子はわからないし、質問に答える側も大変だと思うのですが、電話でのやりとりを聞いているだけでも、子どもがとても可愛いらしいです。
大学生の皆さんは、普段子どもと接する機会はあまりないかもしれませんが、夏休み中に、例えばこの番組を通して、子どもの体験している世界を垣間見るのも新鮮かもしれません。
学生サポートルームカウンセラー