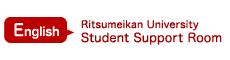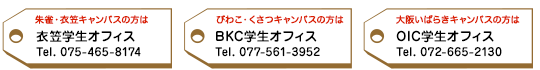カミナリ、石うす、よだかの星-心的リアリティということ
2013年11月11日
コラム
わたしは海辺の小さな集落で生まれ育ちました。四、五歳ごろのことだったと思いますが、あるとき、漁師たちが大きな空のドラム缶(漁船の燃料である重油を入れるもの)をゴロゴロ転がしているのを見ました。その大きな音がカミナリそっくりに聞こえたので、わたしはそれ以来、カミナリのゴロゴロは雲の上で鬼がドラム缶を転がす音なのだと思い込みました。鬼がドラム缶を転がして大音響を立てているというイメージは幼いわたしにとって強いリアリティがありました。
小一のときだったと思います。ある昔話を絵本で読みました。もしかしたら、授業中にテレビで見たのかも知れません。題名もストーリーもよくおぼえていないのですが、それはまわすと塩が出てくる石うすの話で、石うすは最後に海に沈んでしまうのです。でも、その後ずっと(そしていまでも)それは海の底でまわり続けていて、だから海水は塩辛いのだ、という話でした。
海の底に石うすがあって、いまでも塩を出しながらまわり続けているというイメージに、小一のわたしはとてもリアリティを感じました。田舎育ちのわたしにとって石うすは身近な生活道具でもありました。そのこともあってか、いつも見慣れている海の底で本当に石うすがまわっているような気がしたのです。その話は海水が塩辛い理由を説明するものとしても説得力があるように思いました。
中一のとき、国語の教科書に宮沢賢治の『よだかの星』が載っていました。有名な物語なのであらすじは省略しますが、ラストシーンがとても印象的でした。ほかの鳥たちにいじめられたよだかが、星の世界まで行こうと空をどこまでも高くあがっていきます。そして、意識がなくなる直前、自分のからだが燃えて光っているのを見ます。こうしてよだかは青く燃える星になるのですが、物語は次の言葉で終わっていました。
いまでもまだ燃えています。
この言葉を目にしたとき、わたしは夜になったら実際に空を見て確かめてみたい衝動のようなものを覚えました。いまもなおよだかの星は燃え続けている-そのイメージに確かなリアリティを感じたのです。
上で紹介したわたしの体験は、まあ、たあいもないものかも知れません。雲の上でドラム缶を転がす鬼も、海の底で塩を出し続ける石うすも、夜空で青く光るよだかの星も、現実ではありません。でも、当時のわたしにとってそれらはみな実在感に満ちたものだったのです。
物理的には存在していないものに感じる実在感を「心的リアリティ」と言いますが、そんなものを感じるというのは心というものの不思議さです。わたしたちは物理的-客観的な世界と心理的-主観的な世界という二重の世界を生きていると言えるでしょう。心的リアリティは、わたしたちの心を豊かにもし、苦しめもします。わたしたちが喜んだり悲しんだりするのは心理的-主観的な世界においてであり、心的リアリティはわたしたちが「生きている」ことにかかわっています。
ところで、いまのわたしはカミナリの音を聞いても「雲の上で鬼がドラム缶を転がしている」とは思いませんし、「海の底で塩を生み出す石うすがいまもまわり続けている」とは信じていません。でも、夜空のどこかでよだかの星がほんとうに青く燃え続けているのではないか-そんな気がいまでも少しするのです。
小一のときだったと思います。ある昔話を絵本で読みました。もしかしたら、授業中にテレビで見たのかも知れません。題名もストーリーもよくおぼえていないのですが、それはまわすと塩が出てくる石うすの話で、石うすは最後に海に沈んでしまうのです。でも、その後ずっと(そしていまでも)それは海の底でまわり続けていて、だから海水は塩辛いのだ、という話でした。
海の底に石うすがあって、いまでも塩を出しながらまわり続けているというイメージに、小一のわたしはとてもリアリティを感じました。田舎育ちのわたしにとって石うすは身近な生活道具でもありました。そのこともあってか、いつも見慣れている海の底で本当に石うすがまわっているような気がしたのです。その話は海水が塩辛い理由を説明するものとしても説得力があるように思いました。
中一のとき、国語の教科書に宮沢賢治の『よだかの星』が載っていました。有名な物語なのであらすじは省略しますが、ラストシーンがとても印象的でした。ほかの鳥たちにいじめられたよだかが、星の世界まで行こうと空をどこまでも高くあがっていきます。そして、意識がなくなる直前、自分のからだが燃えて光っているのを見ます。こうしてよだかは青く燃える星になるのですが、物語は次の言葉で終わっていました。
いまでもまだ燃えています。
この言葉を目にしたとき、わたしは夜になったら実際に空を見て確かめてみたい衝動のようなものを覚えました。いまもなおよだかの星は燃え続けている-そのイメージに確かなリアリティを感じたのです。
上で紹介したわたしの体験は、まあ、たあいもないものかも知れません。雲の上でドラム缶を転がす鬼も、海の底で塩を出し続ける石うすも、夜空で青く光るよだかの星も、現実ではありません。でも、当時のわたしにとってそれらはみな実在感に満ちたものだったのです。
物理的には存在していないものに感じる実在感を「心的リアリティ」と言いますが、そんなものを感じるというのは心というものの不思議さです。わたしたちは物理的-客観的な世界と心理的-主観的な世界という二重の世界を生きていると言えるでしょう。心的リアリティは、わたしたちの心を豊かにもし、苦しめもします。わたしたちが喜んだり悲しんだりするのは心理的-主観的な世界においてであり、心的リアリティはわたしたちが「生きている」ことにかかわっています。
ところで、いまのわたしはカミナリの音を聞いても「雲の上で鬼がドラム缶を転がしている」とは思いませんし、「海の底で塩を生み出す石うすがいまもまわり続けている」とは信じていません。でも、夜空のどこかでよだかの星がほんとうに青く燃え続けているのではないか-そんな気がいまでも少しするのです。
学生サポートルームカウンセラー