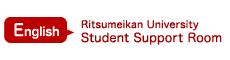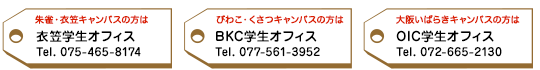『我』という漢字の話
2014年09月04日
コラム
立命館大学と聞くと真っ先に思い浮かぶ人として、白川静先生という方がいます。もう数年前にお亡くなりになりましたが、漢字学・東洋学の大巨人です。学生時代、ぼくは京都とは全く違う土地にいて立命館とは(ついでにまだ心理学とも)縁がなかったのですが、この先生の本にはとても興味をそそられました。例えば漢字の成り立ちの話。『尋』という字は、巫祝(シャーマン)が仮面(ヨ)をかぶり両手に呪具(口と工)を持ったいでたちで村々を巡り、踊り狂いながら神々の在りかをたずねてまわった姿であるとか、『道』とは危険に満ちた異界に通じるものであるため、邪気を祓うために首を掲げて歩いたとか・・・。そこに展開されていたのはシャーマニズムや呪術といった原始的な宗教に彩られた、様々な表情に満ち溢れる世界。当時ぼくはこの世界とは(っていうかそれを感覚して構成しているのは人間なのだが)単なる無機質な三次元の座標空間なんかではなく、本当はもっと多彩な表情を持っているんじゃなかろうか、なんてことを思いながら文化人類学とか読みかじったりしていたのですが、白川漢字学の世界には、同様の興味から様々に妄想を刺激されたことを覚えています。今日はそんな妄想のお話をひとつ・・・。
数年後の事です。その頃ぼくは臨床心理学を学ぶようになっていたのですが、ある時ふと思い出した漢字がありました。それは『義』という字の成り立ちに出てきた『我』という漢字です。『義』は“羊”と“我”から成り、神に捧げる犠牲の羊をさばき、牲体が神意にかなうものとして義(ただ)しいことを証明している様子を表している、“羊”は神に捧げる犠牲であり、“我”は人がノコギリを引いている姿である云々――。
――なるほど『我』とはノコギリ(を引く様)だったのか。
ぼくにはこの「我(とか自分とか自我とかの言葉で指されるもの)」とは「ノコギリ(刃物でありまた切る作用)」である、というお話は、非常に示唆に富むもののように感じられました。
自分というものは世界から分けられることで初めて成立します。そしてまた世界を切り分けてゆくことで、理解してゆく。世界は一つの事態ではなく、様々な事物に分かれている(分けている)ということを、一つ一つ切り分けてゆくことで、理解し構成してゆく。身で分けて、言葉で分けて・・・。「分かる」とは「分ける」であるという話がありますが、まさに『我』という漢字の成り立ち自体に、そういう作用が含まれていたのです。
そしてまた、より卑近なところで考えてみても、たとえば「自我に目覚める」とか「自我を確立する」とか、そういう作業には多かれ少なかれ、痛みや苦痛を伴います。まるで、保護と同時に干渉もして来る親という存在から自分を切り離すために、痛みをこらえながらギコギコと心のノコギリを引く・・といった場合のように。また友達や周囲から一旦自分を隔離して、サナギみたく閉じこもるということもあるでしょう。
でもそれらは当然の事態、当然の痛みだったのです。「我」とは、ノコギリなのだから。それは数千年前からある意味、宿命づけられ、また、保障もされている――もちろんクリティカルな、取り返しのつかなくなるような、そういうやり方はしてはいけないんだけれども、多少の痛みは仕方がないし、自然なことで、そこでの苦しみは、決して間違ってはいない、義(ただ)しいことなんだ――そんな気がしたのでした。
そして今回、この話を思い出しながら、自戒をこめてこんなことを思いました。真当に苦しんだり傷ついたり傷つけたりすることとは、義しいことである、けれどもそれこそが実は非常に難しい・・。「我」をもっと鍛えなきゃなぁ、と。
数年後の事です。その頃ぼくは臨床心理学を学ぶようになっていたのですが、ある時ふと思い出した漢字がありました。それは『義』という字の成り立ちに出てきた『我』という漢字です。『義』は“羊”と“我”から成り、神に捧げる犠牲の羊をさばき、牲体が神意にかなうものとして義(ただ)しいことを証明している様子を表している、“羊”は神に捧げる犠牲であり、“我”は人がノコギリを引いている姿である云々――。
――なるほど『我』とはノコギリ(を引く様)だったのか。
ぼくにはこの「我(とか自分とか自我とかの言葉で指されるもの)」とは「ノコギリ(刃物でありまた切る作用)」である、というお話は、非常に示唆に富むもののように感じられました。
自分というものは世界から分けられることで初めて成立します。そしてまた世界を切り分けてゆくことで、理解してゆく。世界は一つの事態ではなく、様々な事物に分かれている(分けている)ということを、一つ一つ切り分けてゆくことで、理解し構成してゆく。身で分けて、言葉で分けて・・・。「分かる」とは「分ける」であるという話がありますが、まさに『我』という漢字の成り立ち自体に、そういう作用が含まれていたのです。
そしてまた、より卑近なところで考えてみても、たとえば「自我に目覚める」とか「自我を確立する」とか、そういう作業には多かれ少なかれ、痛みや苦痛を伴います。まるで、保護と同時に干渉もして来る親という存在から自分を切り離すために、痛みをこらえながらギコギコと心のノコギリを引く・・といった場合のように。また友達や周囲から一旦自分を隔離して、サナギみたく閉じこもるということもあるでしょう。
でもそれらは当然の事態、当然の痛みだったのです。「我」とは、ノコギリなのだから。それは数千年前からある意味、宿命づけられ、また、保障もされている――もちろんクリティカルな、取り返しのつかなくなるような、そういうやり方はしてはいけないんだけれども、多少の痛みは仕方がないし、自然なことで、そこでの苦しみは、決して間違ってはいない、義(ただ)しいことなんだ――そんな気がしたのでした。
そして今回、この話を思い出しながら、自戒をこめてこんなことを思いました。真当に苦しんだり傷ついたり傷つけたりすることとは、義しいことである、けれどもそれこそが実は非常に難しい・・。「我」をもっと鍛えなきゃなぁ、と。
学生サポートルームカウンセラー