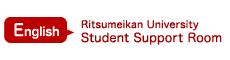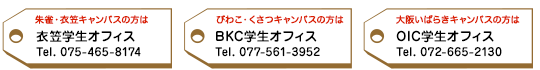理不尽をめぐる冒険
2015年01月07日
コラム
大学の授業で学んだことに関するコラムが、何本かありましたね。それを読みながら、授業の内容で覚えていることはあるかと考えました。恥ずかしながら、勉強に関することは、これといったものが思い当たりません。しかし、大学の基礎演習での先生の一言が、心に残っています。それは、「世界とは、理不尽なものだねえ・・・」というコメントでした。少人数制で、何かを学ぶというより、学生も先生も肩肘はらずに話すという雰囲気の中で、確か学生の1人が、社会的混乱が続く国々に住む人々の話をしていたときかと思います。どのような文脈でそのコメントになったのか、記憶は定かではないのですが、その言葉が、なぜか妙に心に響きました。
学生さんから薦められた某学園ものの漫画を読んでいて、その校訓が「勤労、協同、理不尽」であることを見つけました。映画化やアニメ化されたので、ご存知の方も多いかと思います。それを初めてみたときは、「学校なのに、勤労、そして、理不尽?」と少し抵抗感を覚えました。しかし、読み進むうちに、ふむふむと不思議に納得する自分がいました。
主人公は中学で挫折し、進学コースから逃げるように、家から遠方の農業高校に入学します。最初は、目的も夢もなく、農家を継ぐなど将来の目標が決まっているクラスメートに、劣等感をいだいていました。酪農科に所属したため、実習で家畜の世話に追われます。動物という命を預かる実習ですから、雨の日も雪の日も朝早くから遅くまで世話にくれるという、農業に縁のなかった主人公からすれば、理不尽な日常―勤労―がいきいきと描かれています。その中で、世話をしているうちに、情が移った家畜を食べることや、友人が、家計を支えるために、夢をあきらめて退学していくなど、理不尽なことにぶつかります。真剣に悩みながら、クラスメートや周りの人々とのかかわり―協同―を通して、徐々に自分にできること、やりたいことをみつけ、成長していく物語です。
残念ながら、理不尽な現状は、抗議したり、もがくことで、やすやすと変えることはできません。しかし、その現状に対する自分の感覚は、変えることができます。上記の実習のように、取り組めば乗り越えられるものもあれば、致し方ないと受け流したり、中には、主人公の友人のように、辛いけれど断念するしかないこともあるでしょう。ただのあきらめではなくて、断念したときは、苦しみや悲しみで一杯かもしれません。でも時間がたつにつれて、交錯する気持ちに折り合いをつけ、この辺が自分の限界と認めることで、そんな自分と和解できるのではないかと思うのです。
実は、大学生のころは、コメントの意味を考えたりはしませんでした。むしろ、若気の至りで、なんだか頼りなげな先生だなとさえ思っていました。それも、私の限界の1つだったのかもしれませんね。いくつになっても、限界を知るプロセスは、しんどいですが、みえてくると、なんだか少し楽になるような気がします。
学生さんから薦められた某学園ものの漫画を読んでいて、その校訓が「勤労、協同、理不尽」であることを見つけました。映画化やアニメ化されたので、ご存知の方も多いかと思います。それを初めてみたときは、「学校なのに、勤労、そして、理不尽?」と少し抵抗感を覚えました。しかし、読み進むうちに、ふむふむと不思議に納得する自分がいました。
主人公は中学で挫折し、進学コースから逃げるように、家から遠方の農業高校に入学します。最初は、目的も夢もなく、農家を継ぐなど将来の目標が決まっているクラスメートに、劣等感をいだいていました。酪農科に所属したため、実習で家畜の世話に追われます。動物という命を預かる実習ですから、雨の日も雪の日も朝早くから遅くまで世話にくれるという、農業に縁のなかった主人公からすれば、理不尽な日常―勤労―がいきいきと描かれています。その中で、世話をしているうちに、情が移った家畜を食べることや、友人が、家計を支えるために、夢をあきらめて退学していくなど、理不尽なことにぶつかります。真剣に悩みながら、クラスメートや周りの人々とのかかわり―協同―を通して、徐々に自分にできること、やりたいことをみつけ、成長していく物語です。
残念ながら、理不尽な現状は、抗議したり、もがくことで、やすやすと変えることはできません。しかし、その現状に対する自分の感覚は、変えることができます。上記の実習のように、取り組めば乗り越えられるものもあれば、致し方ないと受け流したり、中には、主人公の友人のように、辛いけれど断念するしかないこともあるでしょう。ただのあきらめではなくて、断念したときは、苦しみや悲しみで一杯かもしれません。でも時間がたつにつれて、交錯する気持ちに折り合いをつけ、この辺が自分の限界と認めることで、そんな自分と和解できるのではないかと思うのです。
実は、大学生のころは、コメントの意味を考えたりはしませんでした。むしろ、若気の至りで、なんだか頼りなげな先生だなとさえ思っていました。それも、私の限界の1つだったのかもしれませんね。いくつになっても、限界を知るプロセスは、しんどいですが、みえてくると、なんだか少し楽になるような気がします。
学生サポートルームカウンセラー