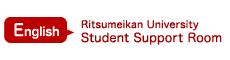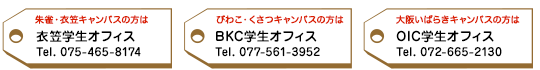強さの理由
2015年12月03日
コラム
パリで同時多発テロが発生して2週間、世界の情勢について連日メディアが伝える断片的な情報を、私たちは受け取っています。
みなさんは、どんなことを考えましたか?それぞれに、違う思いを抱いていることと思います。私は、またあらためて、世界の歴史、宗教や民族について、「知る」ことを続けなければいけないな、と強く思いました。
テロが起こる2週間前、ある学生さんから、一冊の本を借りました。『マララ~教育のために立ち上がり、世界を変えた少女~』(2014 岩崎書店)高等学校の課題図書にもなっていて、読んだ人もいるかもしれません。小学校高学年ぐらいからを対象に、字も大きく、やわらかい文章で読みやすい本になっています。
日本の私たちからすると、遠い異国の地に生まれたマララさんが、一人の女の子として、勉強をがんばったり、成績を気にしたり、友達関係で悩む、私たちと変わらない日常を生きる人だということが、とても新鮮に感じられます。そこから、彼女と一緒になって、その生い立ち~生活環境、周囲に起こる出来事、考えたこと~を追体験するかのように知ることができるところが素晴らしいと感じました。
貧困、紛争、難民問題が解決しない世界のしくみについて、それぞれがじっくりと考えていかなければいけないと思います。
さてここではカウンセラーとして、本から読み取れたマララさんの「心の強さ」が気になりました。タリバンから銃撃を受けたあと一命をとりとめ、その後も教育のために声を上げ続け史上最年少でノーベル平和賞を受賞したことは記憶に新しいですが、この本から、ここに至るまでのマララさんの生い立ちに、この勇気を生み出す土台と成長の過程を読み取ることができます。
彼女の母は字が読めませんが、父の夢を応援し、深い愛情でいつも家族を温かく支えています。父は、学校を経営しパキスタンの教育のために貢献している人で、自らに身の危険があっても反対勢力に声をあげていける強い信念の持ち主です。マララさんも、小さいときから学校になじみ、学校に特別な感情をもっています。
また父は、まだまだ女の子が教育を受けることが一般的でなく、男の子の誕生に比べて軽んじられる文化の残るパキスタンにおいて、マララさんの誕生を祝福し、教育を受ける権利、男の子と同じように外に出て活動をする権利を保障しています。そして、期待し、信頼しています。そのことによって、小さい頃から、女性が自由に生きられない社会について疑問を抱く感覚を身につけています。
そんな両親のもと、故郷のすばらしい自然環境のなか、幼少期をのびのびと過ごしていますが、小さいときから「頑固でのんきな性格」だそうです。「悪いことがあれば、必ずいいこともある」を信念に、周りの人の意見に流されず、どんな状況にも希望をみつけ、感謝する心が育っているようです。
また彼女が10歳のころ、タリバンが地域に侵攻を始め、政府軍との戦闘地域ともなり、昼夜の爆撃音、テロリズムの恐怖にさらされる生活を送っていますが、家族は生きることを、身に迫る危険を回避するだけでなく、可能性をみつけ、国のために行動する責任があると捉えています。
生まれたときから自然と心の内に宿っていくイスラムの精神も感じました。生活のなかに当たり前のようにあるものが、母親の「人と分け合うことを忘れてはだめよ」というような言葉や人を助ける行動に表れていると感じました。家庭や学校での学びに加えて、小さいときから神様に手紙を書くことによって、自分自身と対話しており、自分をより客観的にみる視点も養っているように感じました。
自分で考え、自分自身が信じる価値基準をもとに決断し、行動する。過酷な状況のなかでより強くなったこの「主体性」が、マララさんの心の強さなのだと感じました。そして行動するときには、尋常ではない「勇気」をもっていますが、自分を信じる強さ、また信仰する神様や家族に守られている「安心感」があってこそなのだと感じました。
この本から「心を強くする」ヒントをもらいながら、お会いする学生さんたちに強さをもって寄り添えるよう、自分自身も日々精進していきたい、と感じました。
※もっと詳しく知りたい人は、『わたしはマララ~教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女~』(2013 学研)もお勧めです。また感想は私見ですので違う見方もたくさんあると思います。
みなさんは、どんなことを考えましたか?それぞれに、違う思いを抱いていることと思います。私は、またあらためて、世界の歴史、宗教や民族について、「知る」ことを続けなければいけないな、と強く思いました。
テロが起こる2週間前、ある学生さんから、一冊の本を借りました。『マララ~教育のために立ち上がり、世界を変えた少女~』(2014 岩崎書店)高等学校の課題図書にもなっていて、読んだ人もいるかもしれません。小学校高学年ぐらいからを対象に、字も大きく、やわらかい文章で読みやすい本になっています。
日本の私たちからすると、遠い異国の地に生まれたマララさんが、一人の女の子として、勉強をがんばったり、成績を気にしたり、友達関係で悩む、私たちと変わらない日常を生きる人だということが、とても新鮮に感じられます。そこから、彼女と一緒になって、その生い立ち~生活環境、周囲に起こる出来事、考えたこと~を追体験するかのように知ることができるところが素晴らしいと感じました。
貧困、紛争、難民問題が解決しない世界のしくみについて、それぞれがじっくりと考えていかなければいけないと思います。
さてここではカウンセラーとして、本から読み取れたマララさんの「心の強さ」が気になりました。タリバンから銃撃を受けたあと一命をとりとめ、その後も教育のために声を上げ続け史上最年少でノーベル平和賞を受賞したことは記憶に新しいですが、この本から、ここに至るまでのマララさんの生い立ちに、この勇気を生み出す土台と成長の過程を読み取ることができます。
彼女の母は字が読めませんが、父の夢を応援し、深い愛情でいつも家族を温かく支えています。父は、学校を経営しパキスタンの教育のために貢献している人で、自らに身の危険があっても反対勢力に声をあげていける強い信念の持ち主です。マララさんも、小さいときから学校になじみ、学校に特別な感情をもっています。
また父は、まだまだ女の子が教育を受けることが一般的でなく、男の子の誕生に比べて軽んじられる文化の残るパキスタンにおいて、マララさんの誕生を祝福し、教育を受ける権利、男の子と同じように外に出て活動をする権利を保障しています。そして、期待し、信頼しています。そのことによって、小さい頃から、女性が自由に生きられない社会について疑問を抱く感覚を身につけています。
そんな両親のもと、故郷のすばらしい自然環境のなか、幼少期をのびのびと過ごしていますが、小さいときから「頑固でのんきな性格」だそうです。「悪いことがあれば、必ずいいこともある」を信念に、周りの人の意見に流されず、どんな状況にも希望をみつけ、感謝する心が育っているようです。
また彼女が10歳のころ、タリバンが地域に侵攻を始め、政府軍との戦闘地域ともなり、昼夜の爆撃音、テロリズムの恐怖にさらされる生活を送っていますが、家族は生きることを、身に迫る危険を回避するだけでなく、可能性をみつけ、国のために行動する責任があると捉えています。
生まれたときから自然と心の内に宿っていくイスラムの精神も感じました。生活のなかに当たり前のようにあるものが、母親の「人と分け合うことを忘れてはだめよ」というような言葉や人を助ける行動に表れていると感じました。家庭や学校での学びに加えて、小さいときから神様に手紙を書くことによって、自分自身と対話しており、自分をより客観的にみる視点も養っているように感じました。
自分で考え、自分自身が信じる価値基準をもとに決断し、行動する。過酷な状況のなかでより強くなったこの「主体性」が、マララさんの心の強さなのだと感じました。そして行動するときには、尋常ではない「勇気」をもっていますが、自分を信じる強さ、また信仰する神様や家族に守られている「安心感」があってこそなのだと感じました。
この本から「心を強くする」ヒントをもらいながら、お会いする学生さんたちに強さをもって寄り添えるよう、自分自身も日々精進していきたい、と感じました。
※もっと詳しく知りたい人は、『わたしはマララ~教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女~』(2013 学研)もお勧めです。また感想は私見ですので違う見方もたくさんあると思います。
学生サポートルームカウンセラー