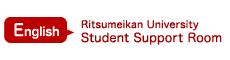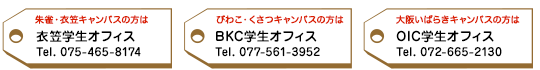SMAP解散報道から考える、喪うこととその再生について
2016年10月01日
コラム
この夏もいろいろなニュースがありました。その中でも、リオオリンピックの最中に日本中を駆け抜けたSMAPの解散報道は老若男女問わず、そこそこの衝撃を与えたのではないでしょうか。私自身も、特別に大ファンというわけではないのですが、音楽を聴くようになった小学校時代から思い返すと、SMAPの曲はつかず離れず耳に届いていたおり、切ない気持ちになりました。
今回の解散報道を、少し無理やり心理学らしく話してみると、“お母さんとお父さんの仲がうまくいかなくなって、子どもを家に置いてお母さんが出て行ってしまった家庭”のようだと考えることができるような気がします。末っ子の香取くんは、幼い頃からSMAPに入り、マネージャーの方をお母さんのように慕い、SMAPという家で活動していました。お母さんが家を出た原因は、姑と小姑との確執だったのでしょう。けれど、末っ子の香取くんからすれば、「なぜ、長男である木村くんがお母さんを守れなかったのか」と怒りを募らせても不思議ではありません。元々、香取くんは木村くんを尊敬し、慕い、憧れの対象として見ていました。だからこそ、母親を喪うという喪失体験に際して、一番一緒に戦ってほしい存在だったのではないでしょうか。父親不在のSMAP家で、お母さんを喪った香取くんの怒りが、父親代わりの木村くんにより強く向けられたのかもしれません。
四男の草彅くんは、末っ子の香取くんと仲良しなので、「香取くんの気持ちを尊重する」と考えても不思議はありません。三男の稲垣くんは、真ん中の子がとりがちな、“周りに合わせる”という行動をしています。次男の中居くんは、兄と弟たちの仲を何とか取り持とうと頑張ったのかもしれませんが、残念ながらそれは叶いませんでした。
大切な人を喪う(死別だけでなく、関係が途切れてしまうことも指します)ことによる悲嘆には、悲しみや無念さだけでなく、怒りの感情を伴うことが多いことが分かっています。そして、その怒りは、最も信頼できる人に向けられやすいのです。
喪失体験から回復するまでの道のりを“喪の作業”と呼びます。この“喪の作業”は、1.無感覚の段階(激しい衝撃に呆然とし、ショックを受けている状態)、2.否認・抗議の段階(喪失を認めようとせず、認めさせようとする者に抗議する状態)、3.絶望・失意の段階
(激しい失意、不安、抑うつといった心理的反応が現れる状態)4.再建の段階(喪失を次第に受け止め、事実と折り合いをつける状態)という過程を辿り、個人差はありますが、最後の段階にいくまでには莫大な時間とエネルギーを要します。私たちは生きている限り、喪失を繰り返します。いかに喪失を乗り越えるかということの重要性について、改めて考えさせられた夏でもありました。
今回の解散報道を、少し無理やり心理学らしく話してみると、“お母さんとお父さんの仲がうまくいかなくなって、子どもを家に置いてお母さんが出て行ってしまった家庭”のようだと考えることができるような気がします。末っ子の香取くんは、幼い頃からSMAPに入り、マネージャーの方をお母さんのように慕い、SMAPという家で活動していました。お母さんが家を出た原因は、姑と小姑との確執だったのでしょう。けれど、末っ子の香取くんからすれば、「なぜ、長男である木村くんがお母さんを守れなかったのか」と怒りを募らせても不思議ではありません。元々、香取くんは木村くんを尊敬し、慕い、憧れの対象として見ていました。だからこそ、母親を喪うという喪失体験に際して、一番一緒に戦ってほしい存在だったのではないでしょうか。父親不在のSMAP家で、お母さんを喪った香取くんの怒りが、父親代わりの木村くんにより強く向けられたのかもしれません。
四男の草彅くんは、末っ子の香取くんと仲良しなので、「香取くんの気持ちを尊重する」と考えても不思議はありません。三男の稲垣くんは、真ん中の子がとりがちな、“周りに合わせる”という行動をしています。次男の中居くんは、兄と弟たちの仲を何とか取り持とうと頑張ったのかもしれませんが、残念ながらそれは叶いませんでした。
大切な人を喪う(死別だけでなく、関係が途切れてしまうことも指します)ことによる悲嘆には、悲しみや無念さだけでなく、怒りの感情を伴うことが多いことが分かっています。そして、その怒りは、最も信頼できる人に向けられやすいのです。
喪失体験から回復するまでの道のりを“喪の作業”と呼びます。この“喪の作業”は、1.無感覚の段階(激しい衝撃に呆然とし、ショックを受けている状態)、2.否認・抗議の段階(喪失を認めようとせず、認めさせようとする者に抗議する状態)、3.絶望・失意の段階
(激しい失意、不安、抑うつといった心理的反応が現れる状態)4.再建の段階(喪失を次第に受け止め、事実と折り合いをつける状態)という過程を辿り、個人差はありますが、最後の段階にいくまでには莫大な時間とエネルギーを要します。私たちは生きている限り、喪失を繰り返します。いかに喪失を乗り越えるかということの重要性について、改めて考えさせられた夏でもありました。
学生サポートルーム カウンセラー