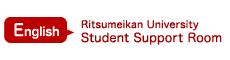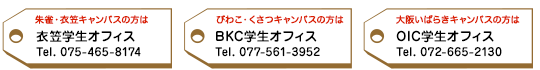新しい環境に入るという体験:私と世界の関係を考える
2017年04月03日
コラム
この春新たに大学生になられた方も多いことでしょう。ところで「大学生(大学院生)」には人生で何度でもなれます。つまり卒業後に社会人経験を積んでから再び入学するという場合です。じつは私もその一人で、現在カウンセラー&学生の二重生活を送っています。今回は4月にちなみ、私の記憶に新しい再・新入生体験から考えたことを書いてみましょう。
10数年の社会人生活を経て2度目の大学院入学を果たした私は、初日の全学新入生オリエンテーションに出席しました。広い会場の大半を占めるのは年下の若者たち。まあそれは想定の範囲内でしたが、驚いたのは、実際にその状況にいると自分が急に気弱になったことでした。余裕で笑いさざめく若者たちに囲まれていると、なんだか彼らがまぶしく見え、身の置き所がないように感じ、視線は下を向き、体も縮こまってしまいます。合格通知を受け取って新生活にワクワクしていたときの自分とは、なんと違うことでしょう。
そのあと社会人学生の集まる所属コースのオリエンテーションでようやく同志と知り合ったわれわれ中年新入生たちが、速やかに連帯したのは言うまでもありません。授業日は身を寄せ合って行動し、それ以外でもメールを飛ばしあってあらゆる疑問や不安をシェアする日々。しかしそうしているうち、研究室や学食などで現役学生に混じって過ごすことも特段気にならなくなり、むしろこの“異文化”体験がけっこう面白く感じられるようにもなったのでした。(何しろ普段カウンセラーとしてお話を伺っているイマドキの学生生活を、自ら体験学習しているわけですからね。たいへん勉強になります)
このような新環境への適応過程は、なんら珍しいものではありません。しかしここで起きていることを詳しく見ると、それは「世界」と「私」の関係の転換であることが分かります。私がひとりで全学オリエンテーション会場にいたときには、周囲の世界はとてもよそよそしく感じられ、世界の外側にはじき出されそうになった私はただ圧倒されるばかりでした。が、「同じ経験を分かり合える他者」を得たことによって、私は彼らと共に少しずつ世界の内側に位置づき、そこで面白みまで感じられるようになったわけです。ここで、私自身は何ら変化していないにもかかわらず、自分と世界とのつながりが危うくなると途端に自信が失われてしまったというのは、大変興味深いことです。そして自分と世界を再びつなぎなおす端緒となったのが、経験を分かり合える他者の出現であったということも。
「他の人たちは皆、新しい環境で簡単に友達を作って、充実した日々をすんなり始めている・・・」と、自信をなくしたり、居場所のなさを感じたりする新入生は多いものです。しかし、あるとき新入生が多く集まる場でいろいろ尋ねてみて分かったのですが、実際のところ彼らはお互いにかなり共通した不安や悩みを抱えているようなのです。たとえば「新しく友達を作れるか不安だ、苦手だ」という人は実は大多数にのぼるのですが、しかし多くの人はそれを無理に覆い隠して笑顔を作り、前もって必死に考えておいた「さりげなく声をかける」ための様々な作戦を実行に移しているらしいのです。そのため、何かのきっかけで「なーんだ、皆、同じように不安なんだ」と、互いの気持ちを共有できる機会があると、すっと気持ちが楽になる人が多いようです。
「隣の芝生は青く見える」ということわざがありますが、新入生のあいだで起きているのも同じような錯覚と言えそうです。このような錯覚が生じるのは、大学という場が、年代や背景など多くの点で同質性の高い人々が大勢集うところであることも関係しているでしょう。同質性の高い集団におかれると、人は自他の違いに敏感になってしまい、そこで自分と周囲の皆(世界)の間に距離が生じます。すると急に自分は「ひとり」で、ちっぽけで弱い存在に感じられる。しかもそうなってしまうと「自分は周りと違う」→「だから他の人には自分の気持ちは分からない」となって、結果的にひとりで悩み続ける、という負の連鎖に陥ってしまうこともよく見られます。
この連鎖から解放されるうえで有効なのは、経験を分かり合える他者を得ることのようですが、あまりにも大勢の学生がひしめくキャンパスでは、そのような相手とうまく出会えず途方にくれている人もいることでしょう。学生サポートルームでは、個別面接やグループ企画を通じてそのような皆さんの手助けをしていますので、よかったらぜひご利用ください。
10数年の社会人生活を経て2度目の大学院入学を果たした私は、初日の全学新入生オリエンテーションに出席しました。広い会場の大半を占めるのは年下の若者たち。まあそれは想定の範囲内でしたが、驚いたのは、実際にその状況にいると自分が急に気弱になったことでした。余裕で笑いさざめく若者たちに囲まれていると、なんだか彼らがまぶしく見え、身の置き所がないように感じ、視線は下を向き、体も縮こまってしまいます。合格通知を受け取って新生活にワクワクしていたときの自分とは、なんと違うことでしょう。
そのあと社会人学生の集まる所属コースのオリエンテーションでようやく同志と知り合ったわれわれ中年新入生たちが、速やかに連帯したのは言うまでもありません。授業日は身を寄せ合って行動し、それ以外でもメールを飛ばしあってあらゆる疑問や不安をシェアする日々。しかしそうしているうち、研究室や学食などで現役学生に混じって過ごすことも特段気にならなくなり、むしろこの“異文化”体験がけっこう面白く感じられるようにもなったのでした。(何しろ普段カウンセラーとしてお話を伺っているイマドキの学生生活を、自ら体験学習しているわけですからね。たいへん勉強になります)
このような新環境への適応過程は、なんら珍しいものではありません。しかしここで起きていることを詳しく見ると、それは「世界」と「私」の関係の転換であることが分かります。私がひとりで全学オリエンテーション会場にいたときには、周囲の世界はとてもよそよそしく感じられ、世界の外側にはじき出されそうになった私はただ圧倒されるばかりでした。が、「同じ経験を分かり合える他者」を得たことによって、私は彼らと共に少しずつ世界の内側に位置づき、そこで面白みまで感じられるようになったわけです。ここで、私自身は何ら変化していないにもかかわらず、自分と世界とのつながりが危うくなると途端に自信が失われてしまったというのは、大変興味深いことです。そして自分と世界を再びつなぎなおす端緒となったのが、経験を分かり合える他者の出現であったということも。
「他の人たちは皆、新しい環境で簡単に友達を作って、充実した日々をすんなり始めている・・・」と、自信をなくしたり、居場所のなさを感じたりする新入生は多いものです。しかし、あるとき新入生が多く集まる場でいろいろ尋ねてみて分かったのですが、実際のところ彼らはお互いにかなり共通した不安や悩みを抱えているようなのです。たとえば「新しく友達を作れるか不安だ、苦手だ」という人は実は大多数にのぼるのですが、しかし多くの人はそれを無理に覆い隠して笑顔を作り、前もって必死に考えておいた「さりげなく声をかける」ための様々な作戦を実行に移しているらしいのです。そのため、何かのきっかけで「なーんだ、皆、同じように不安なんだ」と、互いの気持ちを共有できる機会があると、すっと気持ちが楽になる人が多いようです。
「隣の芝生は青く見える」ということわざがありますが、新入生のあいだで起きているのも同じような錯覚と言えそうです。このような錯覚が生じるのは、大学という場が、年代や背景など多くの点で同質性の高い人々が大勢集うところであることも関係しているでしょう。同質性の高い集団におかれると、人は自他の違いに敏感になってしまい、そこで自分と周囲の皆(世界)の間に距離が生じます。すると急に自分は「ひとり」で、ちっぽけで弱い存在に感じられる。しかもそうなってしまうと「自分は周りと違う」→「だから他の人には自分の気持ちは分からない」となって、結果的にひとりで悩み続ける、という負の連鎖に陥ってしまうこともよく見られます。
この連鎖から解放されるうえで有効なのは、経験を分かり合える他者を得ることのようですが、あまりにも大勢の学生がひしめくキャンパスでは、そのような相手とうまく出会えず途方にくれている人もいることでしょう。学生サポートルームでは、個別面接やグループ企画を通じてそのような皆さんの手助けをしていますので、よかったらぜひご利用ください。
学生サポートルームカウンセラー