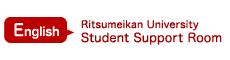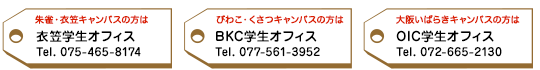雪の結晶
皆さんは好きな模様や形、デザインはありますか?ハート、星、水玉、クロス、花柄、チェック、アーガイル、ストライプ等々、世の中にデザインは溢れています。その中でお気に入りのものがある人もいれば、むしろ無地が良いという人もいるかもしれません。
私は子どもの頃から、どういうわけだか雪の結晶が好きでした。雪の結晶がデザインされたアクセサリーや小物があるとつい足を止めて見入ってしまいます。雪の結晶デザインのものがあるだけで、ちょっとテンションがあがるほど雪の結晶好きを自負しておりますが、実物を見たことは残念ながらなく、そもそも雪の結晶とは何なのか、知っている様でたいしたことは知らないのでした。
前回の長澤先生のコラムにも触発され、文系だからと自らにレッテルを貼り理系分野への苦手意識を持っている私ではありますが、大好きな雪の結晶について調べてみることにしました。改めて考えてみると、雪の結晶も自然科学にあたるのですよね。
まず、「雪の結晶とは何か?」
調べてみると、この問いの立て方自体が少々ずれていることが分かりました。空から降る雪は直径2~3mmの結晶から出来ていて、それを顕微鏡やルーペで拡大すると、某食品メーカーの印でお馴染みの雪の結晶の形が見えるというわけです。さきほど、実物を見たことはないと書きましたが、それはただ私が「雪の結晶」として認識していなかった、その形として捉えていなかっただけで、雪の結晶は目の前に降り積もっていたのですね。
雪の結晶は降るときの大気中の条件によって形を変えますが、基本形として平らな六角形の「角板」と柱状の六角形の「角柱」の2種類に分かれることも分かりました。角柱バージョンがあったなんて!?驚きです。平面しかないものと思い込んでいました。そして、板状の雪の結晶は、六角形を基本として、星や花の形、樹枝の様に広がる形など、二つとして同じ形のものはないと言われるほど多様でした。
ここでまた一つ疑問がわきました。雪の結晶が模様として現れるようになったのはいつの時代なのだろう?
この答えは、わりとすぐ見つかりました。日本で初めて顕微鏡で雪を覗いたのは、下総古河藩の藩主、土井利位という人物でした。この人物が、結晶の形を写生して「雪華図説」という書物にまとめ、その絵がたいへん美しかったので、雪の結晶は「雪華模様」として着物や茶碗にあしらわれ、江戸の庶民の間に流行したそうです。
さらに調べていくと、六角形以外にないという説と、六角形以外にも存在する、という説があることがわかってきました。六角形以外の雪の結晶が存在することを綿密な観察を重ねて研究した人物がいたことに感銘を受けました。その研究者とは、中谷宇吉郎博士。「雪は天から送られた手紙」という詩的なことばを残した中谷博士について、そして雪華など数々の美しい異名を持つ雪の結晶について、興味はつきませんが、今回はこのあたりで筆を置きます。加賀市にある中谷宇吉郎雪の科学館に、博士がまとめた雪の結晶の分類表を見に行きたい。ささやかなこの夢が叶ったら、またこの場をお借りして報告したいと思います。