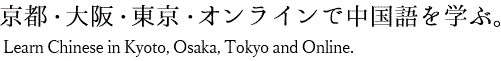ご挨拶
- TOP
- 立命館孔子学院について
- ご挨拶
立命館孔子学院理事長 仲谷 善雄
立命館では、1972年の日中国交正常化以前から、中国の大学や研究機関との交流を推進してまいりました。現在では、協定を結んでいる中国の大学・研究機関数は90を超え、学術交流・教員交流・学生交流が活発に行われています。立命館大学・大学院では1,800名を超える中国人留学生が学び、多くの学部・研究科では中国にかかわる多様な学問分野での教育・研究活動に取り組んでおります。
さて、本学は、2005年に北京大学との共同により日本で初めての孔子学院として立命館孔子学院を京都の地に開設しました。2006年に東京学堂、2008年には同済大学との協力により大阪学堂を開設、2014年にBKC学堂を開設しました。現在は京都、東京、大阪、滋賀にある6つの拠点およびオンラインで中国語教育事業、中国文化交流活動を行っています。
今年、立命館孔子学院は創立20周年を迎えます。記念事業の実施をはじめ、節目の年にふさわしい事業展開を図ってまいります。今後も、中国と日本が相互に協力し、互いの文化・言語・社会情勢を正しく理解し合うことは、両国の利益・発展につながるものと思います。立命館孔子学院は、平和的、学術的、文化的交流を通じて両国が友好関係を深めることができるよう、今後も言語教育・文化交流事業の更なる展開を目指し、中国と日本の架け橋として貢献できるよう努めてまいります。
(立命館孔子学院理事長/学校法人立命館総長/立命館大学長 仲谷 善雄)
立命館孔子学院学院長 中川 涼司
この20年間に日中関係はいろいろな意味でかなり変化しました。
日本の対中輸出額(中国の通関統計による対日輸入額ベース)は2005年の1004億6756万ドルから2023年には1608億2283万ドルへと60.1%増、日本の対中輸入額(日本の財務省『貿易統計』による対中輸入額)は2005年の1085億9392万ドルから2023年には1738億8691万ドルへとこちらも60.1%増でした。
中国人の訪日観光客(日本政府観光局(JNTO)データ)は2005年の82万2033人からコロナによる急減も経ながらも、2023年には637万6900人にまで急増しました。日本の海外旅行先(日本交通公社『旅行年報』)も2005年は339万人で行き先別で第1位で、2006年375万人、2010年にも373万人を記録しました。その後減少をしていきますが、それでもコロナ前の2019年には268万人が中国を訪れていました。コロナ禍とその後のビザ政策の原因で、回復は緩慢でしたが、2024年に再度、短期旅行ビザの免除が復活したことから今後復活が見込めます。
日本における中国人在留者(法務省『在留外国人統計』)も2005年には51万9561人でしたが2023年には82万1838人となって国別在留外国人数で最大になっています。日本人の海外在留者(外務省『海外在留邦人数統計』) のうちの中国在留者も2005年の11万4899人からさほど変化はなく、10万1781人とアメリカに次ぐ数です。
日本と中国の国民意識を探る第20回日中共同世論調査の結果が話題となり、日本の対中イメージ、中国の対日イメージの悪さが問題とされています。それはそれで大きな問題で、相互の理解に向けた努力が必要なのですが、イメージ調査以上に重要なのは実際にどのような関係を持っているかです。
立命館孔子学院が今後も引き続き、日中の相互イメージの改善と実際の関係の改善に貢献していかねばならないと考えています。
(立命館孔子学院学院長/立命館大学国際関係学部特命教授 中川 涼司)
北京大学学長 龚 旗煌
今後、立命館孔子学院は両大学の提携・努力のもと、必ずや更に輝かしい成果を収め、日本での中国語教育事業の拡大と日中間青少年交流の促進に貢献できるものと、信じております。そして我々両大学の友情の樹が永遠に茂り続けることを心より祈念いたします。
(北京大学学長 龚 旗煌)
同済大学学長 方 守恩
「士は以て弘毅ならざる可からず。任重くして道遠し」。国際情勢は日に日に複雑で変化が多く、同済大学は昔と変わらず、各国のパートナーと手を取り合い、国際理解と国際協力を促進するために「橋を懸け、道を切り開いていきます」。大阪学堂が引き続き文化使節の役割を果たし、「心を合わせ、科学を擁護し、革新をもってリードし、卓越性を追求する」新時代の同済文化を推進し、同済大学と立命館大学が人材育成及び科学研究領域において更に協力を促進し、グローバルな交流と相互学習を強化し、世界経済の繁栄と発展を図るためにより大きく貢献することを望みます。
(同済大学学長 方 守恩)