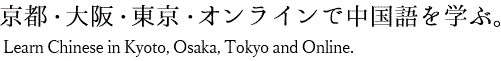立命館孔子学院 学院長コラム
- TOP
- 立命館孔子学院 学院長コラム
当コーナーは、当学院学院長に、中国に関する様々な話題についてお話しいただくコーナーです! 現在、立命館大学国際関係学部特命教授である中川涼司学院長は中国の経済、特にIT産業に精通されています。 そんな学院長に、どんどん語っていただきます!
※コラムタイトルをクリックすると内容をご覧いただけます。
宇野木洋名誉学院長による「考えてみチャイナ・中国のこと!?」バックナンバー
- その1 姓のトップ5の人口は合計4億人!-中国語の「百姓」の意味(2016年4月26日(火))
- その2 「烟酒」と「研究」-久々に経験した「白酒」乾杯攻撃!?(2016年5月24日(火))
- その3 「珈琲」と「咖啡」-「コーヒー文化」が定着するまで?(2016年6月26日(日))
- その4 北京という「現場」で見聞・思考したこと(1)-建党95周年・周恩来・習仲勲ほか(2016年7月27日(水))
- その5 北京という「現場」で見聞・思考したこと(2)-小瀋陽・中国大学事情ほか(2016年8月27日(土))
- その6 「春雨綿綿妻独宿」が示す漢字とは……?――文字に淫する中国の文化(2016年9月24日(土))
- その7 「倍返し」と沖縄――「倍」という漢字の原義にも関わって(2016年10月26日(水))
- その8 「日本笑星“馬上去・馬上来”小姐来津」――ささやかな思い出から(2016年11月30日(水))
- その9 トランプは「特朗普」か「川普」か?――新華社と「網民」の争い(2016年12月21日(水))
- その10 世界孔子学院大会(昆明)への参加報告――「国家プロジェクト」を実感?!(2017年1月24日(火))
- その11 「微信紅包」を知っていますか?――「春節」における新たな流行の誕生(2017年2月24日(金))
- その12 酒呑みのランキング――中国そして韓国、では日本は?(2017年3月24日(金))
- その13 「外滙兌換券〔FEC〕」の話――1990年代前半までの「幻の通貨」(2017年4月28日(金))
- その14 続・「外滙兌換券〔FEC〕」の話――「白卡」からオークションまで(2017年6月7日(水))
- その15 中国におけるノーベル文学賞をめぐって――莫言の次は…?!(2017年7月2日(日))
- その16 「配偶者」という言葉をめぐって――どう呼んでいますか……?(2017年7月31日(月))
- その17 関西空港20時間(!)滞在経験――LCCって何?!(2017年9月5日(火))
- その18 「四密碼森」って何?――中国語版「片仮名発音表記」(?)をめぐって(2017年9月30日(土))
- その19 「イトコ同士が結婚するなんて……?!」――中国における「イトコ婚」禁止(2017年11月7日(火))
- その20 「你好!…请抽烟!」からの急激な変化――中国の喫煙事情をめぐって(2017年11月30日(木))
- その21 世界孔子学院大会に出席して「ことば」を考える?!――「XIANYANG」と英語(2017年12月21日(木))
- その22 「干支」は「えと」だけを意味するのか?――「戊戌変法」120周年(2018年1月30日(火))
- その23 「羽生が勝って、羽生が負けた!」――日本人名の中国語読みをめぐって(2018年2月28日(水))
- その24 井上ひさし『シャンハイムーン』を観劇して――魯迅と日本人を考える(2018年3月30日(金))
- その25 中国現代文学生誕100周年!――魯迅の短篇小説「狂人日記」をめぐって(2018年5月8日(火))
- その26 恋する魯迅――17歳年下の女子学生との往復書簡(2018年6月9日(土))
- その27 「95後」なら知っている言葉――日本語由来の若者流行語?!(2018年6月30日(土))
- その28 急激に普及する中国シェア自転車サービス――「摩拝単車」神話(1)(2018年7月30日(月))
- その29 「先嘗試、後管制!」精神が起業を励ます?!――「摩拝単車」神話(2)(2018年9月2日(日))
- その30 今夏も台風には祟られた?!――「台風男・女」の中国語は?(2018年10月6日(土))
- その31 「日中不再戦」の碑をご存知ですか?――嵐山の新たな観光スポットに(2018年10月31日(水))
- その32 中国「網絡〔ネット〕文学」の現状から――小説がまだ「力」を持っている?!(2018年12月2日(日))
- その33 1980年代中国の本屋事情――目当ての本を買い込むのは大仕事だった…?!(2018年12月25日(火))
- その34 「よしなに!」が通じない?!――中国語で言えば「随便」か「酌情」か(2019年1月29日(火))
- その35 「1314520」って何でしょう?――数字語呂合わせの日中比較(2019年2月28日(木))
- その36 数字語呂合わせの補足――小野秀樹『中国人のこころ』を紹介する(2019年3月16日(土))
- その37 珍しい姓について?!――中国の「複姓」の話など(2019年4月24日(水))
- その38 コメントしておきたいこと二点ほど――「天安門事件」30周年にあたって(2019年7月16日(火))
- その39 日本における中国「大衆文学」の流行――史上初めての画期的な現象(2019年8月31日(土))
- その40 「行千里,致広大。」――人口世界第1位都市・重慶を堪能してきた!(2019年10月3日(木))
- その41 「生活垃圾分類〔生活ゴミ分別〕」状況について――上海の試みから・・・(2019年10月29日(火))
- その42 佐高信『いま、なぜ魯迅か』を紹介する(1)――「生きる指針」としての魯迅の言葉(2019年11月30日(土))
- その43 佐高信『いま、なぜ魯迅か』を紹介する(2)――「まじめナルシシズム」を捨て去っていくために(2019年12月26日(木))
- その44 「新冠」って何でしょう…?――新型肺炎の感染阻止へ(2020年2月2日(日))
- その45 1元=40円の時代…?!――33年前の天津の生活から(1)(2020年2月29日(土))
- その46 卒業式のなかった卒業生に送る言葉――伝えたかったこと(2020年3月31日(火))
- その47 武漢の女性作家・方方の「日記」から――「新写実主義」の真骨頂?!(2020年4月29日(水))
- その48 「潤沢な人員配置」としてのバスの車掌さん?!――33年前の天津生活から(2)(2020年5月29日(金))
- その49 web授業に対する初体験的実感?!――対面授業の意義を改めて考える(2020年6月30日(火))
- その50 「象棋」を知ってますか?!――真ん中に河が流れている中国将棋(1)(2020年7月31日(金))
- その51 将棋と似て非なる、でも興味が尽きない象棋――真ん中に河が流れている中国将棋(2)(2020年8月29日(土))
- その52 日本将棋は民主主義を体現していた?!――真ん中に河が流れている中国将棋(3)
- その53 「近代」と「現代」の違いとは?!――日本語と中国語におけるニュアンスの相違も視野に(2020年11月3日(火))
- その54 「権利」としての言葉という視点――コロナ禍の下における講義から…(2020年11月30日(月))
- その55 「丑」年はあまり良いイメージがないのでは?!――来年の干支から簡体字を考える(2020年12月25日(金))
- その56 「拝」の字にこだわってみた――「拝登総統」って誰でしょう?(2021年2月6日(土))
- その57 「拜登白等」から「顔色」を考える?!――白・赤・青・緑・黄など(2021年2月25日(木))
- その58 「打工人」とサラリーマン――「社畜」と「獣になれない私たち」?!(2021年4月3日(土))
- その59 使用頻度が高い中国語漢字ベスト5は「的/一/是/了/我」――「李姉妹ch」が「その合計出現率は10%」と述べる根拠は?!(2021年4月28日)
- その60 1980年代に体験した中国「電報」事情から(1)――「電報の話」の前には「電話の話」が必要だった?!(2021年6月8日)
- その61 1980年代に体験した中国「電報」事情から(2)――「ムカエタノム」の電報では、到着時間は伝えないのが常識?!(2021年6月26日)
- その62 1980年代に体験した中国「電報」事情から(3)――阪口直樹さん(当時・同志社大学助教授)の思い出も兼ねて……(2021年7月27日)
- その63 「台風煙花」上海上陸?!――アジアにおける台風の名前について(2021年8月31日)
- その64 ピンイン(拼音)表記についての雑談――漢字廃止の「夢」から始まった?!(2021年10月5日)
- その65 「もし魯迅が生きていたら」と問われた毛沢東の回答は?――魯迅生誕140年にあたって(2021年11月23日)
- その66 TVドラマ『日本沈没』から見えて来た中国の位置?!――新たな年に向けて(2021年12月25日)
- その67 「奥密克戎」って何でしょう…?――足掛け4年目のコロナ禍の収束に向けて(2022年2月10日)
- その68 中国作家協会・中国文学芸術界連合会って知ってますか?――習近平国家主席・李克強総理も参加する全国代表大会(2022年3月3日)
- その69 高さ3m×全長20mの絵画「一九四六」を知っていますか?――日中国交回復50周年を象徴する絵画展について(2022年3月26日)
- その70 中国のネット配信ドラマにハマる日々?!――『原生之罪――Original Sin』について(1)(2022年5月10日)
- その71 「網劇」の殺人事件から中国社会の一端を垣間見る?!――『原生之罪――Original Sin』について(2)(2022年6月30日)
- その72 謎の残る結末と池震役・翟天臨の「スキャンダル」をめぐって――『原生之罪――Original Sin』について(3)(2022年7月30日)
- その73 日中戦争とウクライナ戦争の類似性と危険性について――明治大学教授・山田朗先生の講演を聞いて考えたこと(2022年8月23日)
- その74 青樹明子著『家計簿からみる中国 今ほんとうの姿』を推薦する――お金の使い方から中国人の人生観から国家観までもが見えてくる?(2022年10月3日)
- その75 いわゆる「粉物」の注文の仕方について――35年前の「大失敗」の思い出から(2022年10月31日)
- その76 中国共産党員の現況から考えたこと――「二十大」を受けて(2022年11月30日)
- その77 「動態清零」って何でしょう?――「零」に触発されて考えたこと(2022年12月24日)
- その78 前回・前々回のコラムに対する修正ないし補足について――発表後に知ったこと(2023年2月22日)
- その79 日本はテレビ放送開始70周年、中国も意外に早く1958年初放送!――中国「電視〔テレビ〕」事情(1)(2023年3月26日)
- その80 名作ドラマ『北京人在紐約』の内容面以外(?!)における画期性について――中国「電視〔テレビ〕」事情(2)(2023年4月27日)
- その81 『北京人在紐約』周辺の話題を幾つか――中国「電視〔テレビ〕」事情(3)(2023年6月4日)
- その82 20世紀末中国におけるテレビCMの周辺――中国「電視〔テレビ〕」事情(4)(2023年7月15日)
*特別付録クイズ=「木神原鬱恵」って誰でしょう? - その83 「国字」(和製漢字)をめぐって――「特別付録クイズ」の正解発表も兼ねて(2023年7月29日)
- その84 愛新覚羅溥傑ってご存知ですか?(1)――ラストエンペラーの実弟と立命館(2023年9月27日)
- その85 愛新覚羅溥傑ってご存知ですか?(2)――追悼式典と畑中和夫先生(2023年11月23日)
- その86 愛新覚羅溥傑ってご存知ですか?(3)――葬儀への参加と「燕瀛比鄰航一葦」(2023年12月1日)
- その87 「龍」字は偏(ヘン)や旁(ツクリ)そして冠(カンムリ)にもなる?!――龍/龖/龘/
…(2024年2月14日)
- その88 中国における「上野千鶴子熱(ブーム)」――契機としての東大入学式「祝辞」(2024年4月17日)
- その89 祇園祭と中国――「動く美術館」=山鉾巡行の一側面(2024年7月31日)
- その90 深圳の日本人学校事件をめぐって――今こそ冷静な「対話」を……(2024年10月9日)
- その91 「巳年」=「蛇年」断想――安部公房のエッセイから考えたこと(2025年1月1日)
- その92 魯迅「藤野先生」を読んで改めて考えたこと――「日本と中国の民間交流を進める際の1つの模範例」として(2025年3月31日(月))
中川正之名誉学院長による「ちょこっと話しチャイナ」バックナンバー
- Vol.1 ちょっとしたニュアンスの差
- Vol.2 「思って」どうする?
- Vol.3 「思わず知らず」のむずかしさ
- Vol.4 「正之」と呼んで
- Vol.5 夏休みということで、手短に。
- Vol.6 出し惜しみ
- Vol.7 アシカ
- Vol.8 京都に4年
- Vol.9 「あっ!」という間の一年
- Vol.10 続「よっ!」
- Vol.11 「摂」(2012年2月25日(土))
- Vol.12 「中」(2012年3月27日(火))
- Vol.13 あなたのお父さん…?(2012年4月26日(木))
- Vol.14 「げに恐ろしや」(2012年5月26日(土))
- Vol.15 「初恋」(2012年6月26日(火))
- Vol.16 「伝統」(2012年7月26日(木))
- Vol.17 「ゴミが目に入った」(2012年8月25日(土))
- Vol.18 「何日君再来」(2012年9月26日(水))
- Vol.19 「さすらいジョニー」(2012年10月26日(金))
- Vol.20 「若者言葉」(2012年11月27日(火))
- Vol.21 よいお年を!(2012年12月25日(火))
- Vol.22 小心(2013年1月26日(土))
- Vol.23 別れの季節(2013年2月26日(火))
- Vol.24 年度末にあたり、あれやこれやと、まとまりのないことを(2013年3月26日(火))
- Vol.25 選択制限(2013年4月26日(金))
- Vol.26 中国雑感(2013年5月25日(金))
- Vol.27 医学用語(2013年6月26日(水))
- Vol.28 柿かトマトか?(2013年7月26日(金))
- Vol.29 愛の結晶(2013年8月27日(火))
- Vol.30 立命館孔子学院顧問 竹内実先生を悼む(2013年9月27日(金))
- Vol.31 中川先生在難中(2013年10月26日(土))
- Vol.32 実業と虚業(2013年11月26日(火))
- Vol.33 食在同済(2013年12月25日(水))
- Vol.34 馬上の象(2014年1月25日(土))
- Vol.35 家族愛と人類愛(2014年2月26日(水))
- Vol.36 「角」と「股」(2014年3月26日(水))
- Vol.37 興膳宏著『杜甫のユーモア ずっこけ孔子』(岩波書店2014年)(2014年4月26日(土))
- Vol.38 月と星(2014年5月27日(火))
- Vol.39 終活(2014年6月26日(木))
- Vol.40 第9回スピーチコンテストによせて(2014年7月26日(土))
- Vol.41 「あお」の話(2014年8月26日(火))
- Vol.42 苦瓜(2014年9月27日(土))
- Vol.43 美女(2014年10月25日(土))
- Vol.44 近況報告(2014年11月26日(水))
- Vol.45 「孔子学院中国政府手先説」について(2015年1月27日(火))
- Vol.46 王选:回忆北大数学力学系的大学生活―馬希文氏のこと―(2015年2月26日(木))
- Vol.47 中学時代のことから(2015年3月26日(木))
- Vol.48 壁咚(2015年4月23日(木))
- Vol.49 中国人のユーモア(2015年5月26日(火))
- Vol.50 ”圏”について(2015年6月26日(金))
- Vol.51 祭り(2015年7月28日(火))
- Vol.52 说有容易,说无难(2015年8月28日(金))
- Vol.53 写真を撮る(2015年9月25日(金))
- Vol.54 10周年記念式典(2015年10月20日(火))
- Vol.55 忘年会・懇親会・反省会(2015年11月24日(火))
- Vol.56 さわぐな!(2015年12月25日(金))
- Vol.57 最後に(2016年1月26日(火))
- Vol.58 中国語学習歴50年(2016年2月25日(木))
- 最終回 最後の最後(2016年3月25日(金))