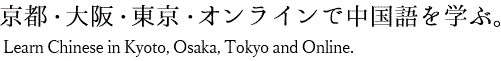■2025年という新しい年の「干支」は「巳」即ち蛇である。――なお、蛇足だが、「干支」という熟語は「かんし」と読めば「十干・十二支」の意味で、新しい年が「乙巳(きのと・み)」であることを指すが、「えと」と発音すれば「十二支」のみを意味して「巳年」を示すことは断わるまでもないだろう。
■さて、「巳年」の蛇だが、人間にとって不気味で恐怖心を抱かせる動物の代表格であることは間違いないのではないか。私も子供の頃から蛇は大の苦手だったが、その理由は、咬まれたら死に到る毒蛇が真っ先に念頭に浮かぶ恐怖からだろうと短絡的に考えていた。だが、高校生の頃だったか、ノーベル文学賞候補にもなったと言われる安部公房が、エッセイ「ヘビについて」(『砂漠の思想』講談社、1965年、所収/「講談社文芸文庫」版復刊、1993年)の中で、蛇は神出鬼没で手足もない異様な形状であるため容易に擬人化ができず、その生態を「自分自身の内的事件として想像し再現することができない」ことから「情緒の拒絶反応」が起こって恐怖心が生じるのだと書き記しているのを読んで、はたと膝を打った鮮明な記憶が残っている。
■安部公房は、更に、人間は「常識の壁」にしがみつくことで日常生活を安定させているが、それに頼りすぎると「日常の外」の存在が蛇や幽霊に見えてしまう危険性があることを指摘した上で、「現に、蛇と日常を共にしている、蛇つかいは、蛇に対してなんらの嫌悪も感じないという。そして、このことは、かならずしも実際の蛇だけにかぎったことではなく、政治的な蛇、思想的な蛇、文化的な蛇、その他さまざまな蛇についても、同様にあてはまることなのではあるまいか」とも続けているのだ。自己とは異なる「他者」への差別・偏見が発生する人間の心理構造を、蛇を例に分かりやすく提示しているのではないだろうか。
■NPO法人「言論NPO」が毎年実施している日中共同の世論調査結果(2024年12月2日公表)によれば、互いの国に親近感を持てない人の割合は、中国人で87.7%(前年度比/24.8%増)、日本人で89.0%(3.2%減)と日中ともに9割近くに上るという、些かショッキングな結果が示された。遂にここまで来てしまったとしか言いようがないのだが、こうなるには日中それぞれに、種々の原因・理由が存在するのも確かだろう。日本人の私としては、その最大のものの1つが、この間、日本政府は「台湾有事」を殊更に煽って中国をいわば「仮想敵国」に位置づけて、敵基地攻撃能力の保有や防衛費の大幅増という軍拡に踏み出す口実としてきた点にあるのは、残念ながら間違いないと考える。「仮想敵国」に親近感を抱く日本人はいないだろうし、「仮想敵国」と見なしている国に親近感を持つ中国人もいないだろう。――もちろん、中国政府に問題がないなどとは全く考えていない。大国主義・覇権主義的な対外姿勢と民主主義・人権に対して抑圧的な対内動向には、私なりの異論はあるし、それなりに発言もしてきたつもりである。ただし、上述したような日本人の中国認識の背景には、安部公房の言う「常識の壁」の論理が機能し、しかもマスコミがそれを煽っているのも確かだと、今、改めて考えている。
■孔子学院の目的・役割は、日本の市民・学生に向けて中国語教育や中国文化を発信することを通じて、日中双方の草の根レベルからの相互交流・相互理解を深めていくことにあるだろう。いわば等身大の中国そして中国人の姿を知らしめていく上で、孔子学院が果たす役割は極めて大きいように思う。――ここまで蛇を、人間に恐怖心・嫌悪感を引き起こすものとしてのみ論じてきた。しかし、蛇には「脱皮」という生態が存在しており、古いものを脱ぎ捨て新しくなっていくことの象徴としてのイメージも存在する。本年10月に創立20周年を迎える立命館孔子学院も従来の活動のあり方を刷新させながら、中国に対する「常識の壁」を打破していく活動を模索していく必要があるだろう。以上、巳年の決意としたい。
■なお、昨年2024年は安部公房生誕100周年だった。またこの「みチャイナ」の文章は、日中友好協会京都府連合会の機関紙『日中友好新聞(府連版)』第342号(2025年1月号/1月1日付)に掲載した、会長による「新年挨拶」と重なっている部分があることも付記させていただく。
|