
学内外で平和構築について考え、行動する様々な活動に参加。これからも核兵器に頼らない平和を創る仕事に関わり続けたいと考えています。
倉本 芽美 さん
国際関係学専攻 4回生
大学内外で平和構築に関わる活動を積極的にされている倉本さん。これまでに取り組まれた活動についてお話を伺いました。
国際関係学部を志望した理由を教えてください。
倉本国際的な視点から「平和」について考えたいと思っていたからです。中学・高校では世界史の授業で戦争について学ぶことが好きだったのと同時に「平和」に興味がありました。しかし、具体的な「平和」の形を見つけることができず、それを見つけたいという思いから国際関係の中で平和学を学べる立命館大学 国際関係学部を志望しました。また、大学入学以前は机上で完結する学習が多く、探究学習など実践的な活動や学びをしてこなかったので、大学では実際の行動を伴う何か夢中になれることを見つけたいという思いがありました。
大学内ではどのような活動に力を入れてこられましたか?
倉本入学してすぐ、みらいゼミ「なぜ戦争が起きるのか考える」に参加し、多角的に戦争が起きる要因を捉えるための文献購読やディスカッションを行いました。2ターム目では自分がゼミの立ち上げ人となり、ゼミの方向性の決定や、メンターの先生とのやりとり、報告書作成などを行いました。先輩方もいるゼミで、1年生で立ち上げ人として活動できた経験は大いに自分自身を成長させてくれたと思います。
2023年夏からは立命館大学国際平和ミュージアムの学生スタッフとして活動を始めました。学生スタッフの仕事は大きくガイド業務と資料整理業務に分かれ、私はガイド業務を担当しています。ガイドの仕事では、展示物について来館者に解説をするだけではなく、来館者と展示の対話のためのファシリテートを行い、来館者が退館後、平和創造の主体者の一人となれるようなガイドを務めています。
2024年11月に中満泉国連事務次長を本学にお招きした際には、当日の企画運営やそれまでのプレ企画の準備にも携わりました。この際、中満さんがユースの貢献について強調されたように、国際平和ミュージアムでも学生スタッフが重要なアクターとなっています。学生スタッフが積極的・本質的にミュージアム運営に関与できるよう、イベントでの学生の関わり方を工夫したり、ミュージアム運営の三者会議設置を依頼したりするなど、事務局との丁寧なやり取りを進めています。
また、3回生からは国際政治を学べる足立 研幾先生のゼミに所属しています。理想論だけを語る平和活動で終わらせないために、国際政治の理論と現実を仲間と理解しながら、大学卒業後も活かせる専門的な学びの時間をこれからも作っていきたいと考えています。またゼミ長として、ゼミをまとめる仕事も良い経験となっています。
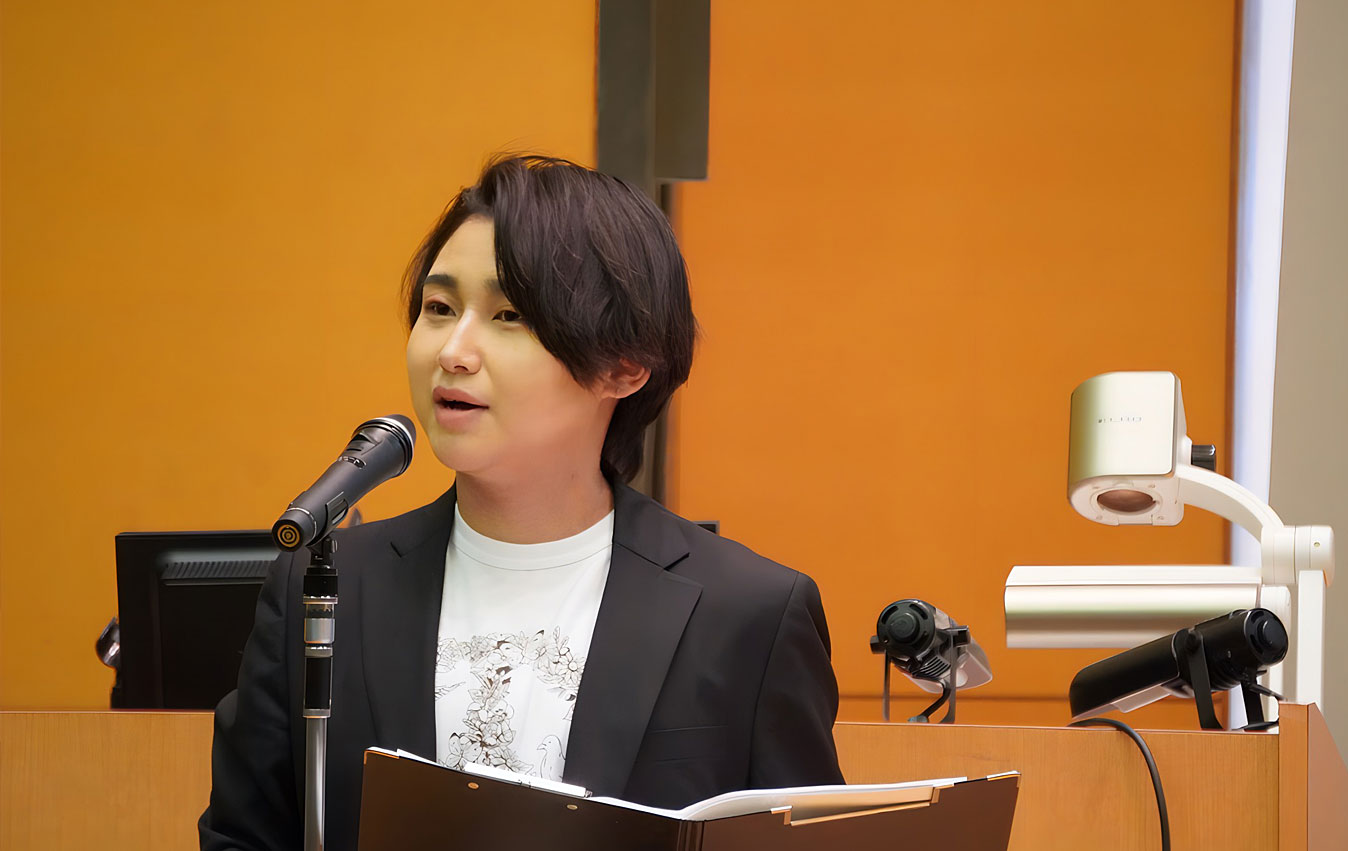
大学外ではどのような活動をされていますか?
倉本市民社会の立場から、核兵器を必要としない平和な社会を創る活動を行っています。最近あった2つの大きなイベントでの活動を通して私の活動紹介をさせていただければと思います。
私は核兵器をなくす日本キャンペーンというNGOに学生スタッフとして勤務しています。このキャンペーンは、日本の核兵器禁止条約への批准を目標に、政治へのアプローチと市民へのアプローチの二本柱を掲げ、2030年まで活動を行う団体です。私は市民へのアプローチ業務に関わることが多く、月に2,3回発行するメールマガジンの作成やイベント企画、日常のSNS広報などを行っています。
2025年2月には「被爆80年 核兵器をなくす国際市民フォーラム」を開催しました。このフォーラムは、被爆80年のはじまりに、年齢、性別、肩書、出身地なども超えた人々の連帯によって、核兵器をなくす機運を今一度高めるために開催しました。国内外から核兵器問題に関わる専門家や活動している人々を招き、1日目は全体セッションを、2日目は約40の分科会を開催。2日間で、対面・オンライン合わせて約900名の方にご参加いただきました。私自身は、広報活動やユース分科会企画の運営、当日の総合司会などを務めました。仕事を遂行する傍らで、改めて第一線で活躍している専門家の話を聞くことができ、とても学びの多い2日間となりました。
もう1つは、1回生の10月からKNOW NUKES TOKYOというユース団体に所属しており、今は共同代表を務めています。核兵器のない世界をデザインする団体として、平和教育やイベント開催、SNSでの情報発信などを行っています。2025年1月からは核兵器禁止条約第3回締約国会議への日本政府のオブザーバー参加を求めるオンライン署名を、未来アクションキャンペーンを中心に10つのユース団体と共に実施しました。約1ヶ月で7万筆以上の署名を集め、外務大臣へ署名を手交しました。
倉本2025年3月には核兵器禁止条約第3回締約国会議に参加しました。今回の会議には163のNGOが参加し、この数は増加傾向にあります。条約成立時から市民の貢献が大きく、今でも核兵器禁止条約には多くのNGO、市民が関わっており、それを体感したいという思いから今回の締約国会議に参加しました。
私の現地での動きは主に3つ。1つ目は、日本への中継配信です。会議期間中、専門家による会議解説や市民の動きについて伝える中継配信を行いました。私自身もその中継に出演しながら、現地からの登壇者や配信運営スタッフのアシスタントを行いました。2つ目は、日本の参加者の活躍の記録です。日本からも多くの人々が参加し、本会議での発言やサイドイベントの開催など、現地での多くの活躍がありました。私はそうした活躍を写真やレポートに残す仕事を担いました。3つ目は、世界中の核兵器を本気でなくそうとしている仲間との交流です。特に同世代と繋がり、意見交換できたことはとても有意義で、今後もこの繋がりを活かした活動を行っていきたいと思います。
会議期間全体を通して、核兵器を廃絶しようとする着実な議論を体感することで、国際社会は機関ではなく人が形成しているのだと改めて実感することができました。

卒業後の進路はどのように考えていますか?
倉本核兵器に頼らない平和を創る仕事に関わり続けたいと考えており、卒業後は今関わっているNGOに変わらず勤務することを予定しています。核兵器をなくす仕事には、研究機関に勤めたり、政治家になったりと様々な選択肢がありますが、まずはNGOの現場で働き、最終的に自分の強みが行かせる場所に身を置きたいと考えています。
様々な活動を通じて感じる国際関係学部の良さはどのようなところだと思いますか?
倉本自分自身の特権性と弱者性を同時に感じることができる点だと思います。これは核兵器禁止条約締約国会議に参加して世界のユースと共有したことでもありますが、国連で核兵器をなくす議論に参加できることはかなり特権的です。同じように立命館大学 国際関係学部で学べることも特権的だと思います。なぜなら立命館大学の国際関係学部は国際関係を学ぶには恵まれすぎているほどの環境が整っているからです。
一方、学部で国際的な諸問題を学ぶ中で、問題の解決に貢献できない歯がゆさを感じたり、自分自身が問題の被害者であると気づいたりすることがあるかもしれません。国際関係学部には様々な考えやバックグラウンドを持つ学生が集っているため、自分のことを弱者と感じてしまう機会に出会うこともあると思います。自分自身の特権性と弱者性を同時に感じることで、これまで自分がいかに小さな世界に生きてきたのかと実感させられることもあるでしょう。
国際関係学部ではその感じ取った自分自身の「弱者性」を克服するために、恵まれた環境で国際関係学を学ぶことができるという「特権性」を大いに活用することができます。こうした問題解決実践の基盤を創ることができるのがこの学部の良さだと思います。

国際関係学部を志望する高校生に対してメッセージをお願いします。
倉本まずは、一生懸命に勉強ができる場所があること、立命館大学 国際関係学部を進学先の選択肢の一つに置けること、自分の夢を応援してくれる人がいることに感謝をしてほしいと思います。また、志望大学・学部に合格することよりも、進学先や置かれた環境で何をするのかが最も大切だということをお伝えしたいです。
私自身は、第一志望の大学に不合格となった結果、立命館大学 国際関係学部に入学することとなりました。当時はかなり落ち込みましたが、今では自分が本気で取り組みたいことを見つけることができています。国際関係学部には、皆さんのやりたいことを叶えてくれる先生やプログラム、施設などが豊富にそろっています。しかし、それらは全て自分から取りに行かなければ自分のものになりません。自分から能動的に動けば動くほど自分の世界を広げることができるのが立命館大学 国際関係学部です。自分自身の関心や問題意識に敏感となり、大学内外の多くの出会いから刺激を受ける大学生活を送っていただければと思います。
2025年4月更新
MORE INTERVIEWS
-
オープンゼミナール2025「【もうええでしょう】「食い尽くし系夫」は何故食い尽くしをやめられないのか?」
鳥山ゼミ
(チーム名:純子先生、それ食べたかったんじゃないですか?)2025.12.19
academics|openseminar|
-
体操部の主将としての活動と学部の学びの両立。ゼミの海外フィールドワークが国連職員になりたいという夢に挑戦する勇気をくれました。
吉田 誇太郎さん
国際関係学専攻 3回生2025.11.17
studentlife|academics|athletics|ir_major|
-
国際寮のレジデントメンターとして多様な留学生と共に過ごした経験は、今後の人生においても大きな財産になると確信しています。
田畑 琴子
国際関係学専攻 4回生2025.11.6
studentlife|ir_major|
-
「実際に世界を変えられる人になりたい」という夢を実現するため「タイ・バンコク国際機関研修」に参加。現場を訪問し直接お話することで国連職員を目指す上で必要なこと学ぶことができました
森本 真彩
国際関係学専攻 1回生2025.10.29
studyabroad|international|ir_major|
-
蓄積してきた知識を実際の経験を通じて捉え直したいと考え、Peace Studies Seminarに参加。原爆や戦争、平和に関する自分の中での「あたりまえ」を再構築することができたと思います。
栗栖 慧さん
グローバル・スタディーズ専攻 4回生2025.10.23
studentlife|academics|gs_major|
-
将来の夢は報道を通じて世界平和の実現に貢献すること。地元:長崎で学んできた平和学習の内容が他の地域では当たり前ではないことを実感した時、将来、この現状を変えたいと強く思いました。
川端 悠さん
国際関係学専攻 3回生2025.10.14
studentlife|academics|ir_major|