
卒論やインターンで必要な統計知識を専攻の枠を超えて積極的に修得。クロス履修制度のおかげで知見の幅を広げることができました。
藤野 拓人 さん
グローバル・スタディーズ専攻 4回生
クロス履修制度を活用し、異なる専攻の科目を積極的に履修してきた藤野拓人さん。そこで得た知識を卒業研究やインターンシップでどのように活用してきたのか、また、卒業後の進路についてもお話を伺いました。
立命館大学 国際関係学部を志望した理由を教えてください。
藤野高校の時から漠然とグローバルに働きたいという夢を持っていたため、英語で授業を受けられる国際関係学部のグローバル・スタディーズ専攻を志望しました。本学部では、世界のあらゆる問題に対して様々な学問から考察することができると知り、魅力的に感じました。また、勉強だけでなく部活動にも集中できる環境に惹かれ、立命館大学への入学を決めました。
入学してみて国際関係学部のイメージはどう変わりましたか。
藤野幅広く国際的な学びができるという印象を持って入学しましたが、想像以上に幅広く、興味のある学問を深く追求できる環境が整っていると感じています。先生方の中にはユニークな経歴をお持ちの方も多くいらっしゃり、講義に出席することが一つの楽しみになっています。また、コロナ禍が明けてからは留学生と交流する機会も大幅に増え、衣笠キャンパスの恒心館(国際関係学部の校舎)付近は、良い意味でまわりとは異なる、国際的な雰囲気を楽しむことができます。
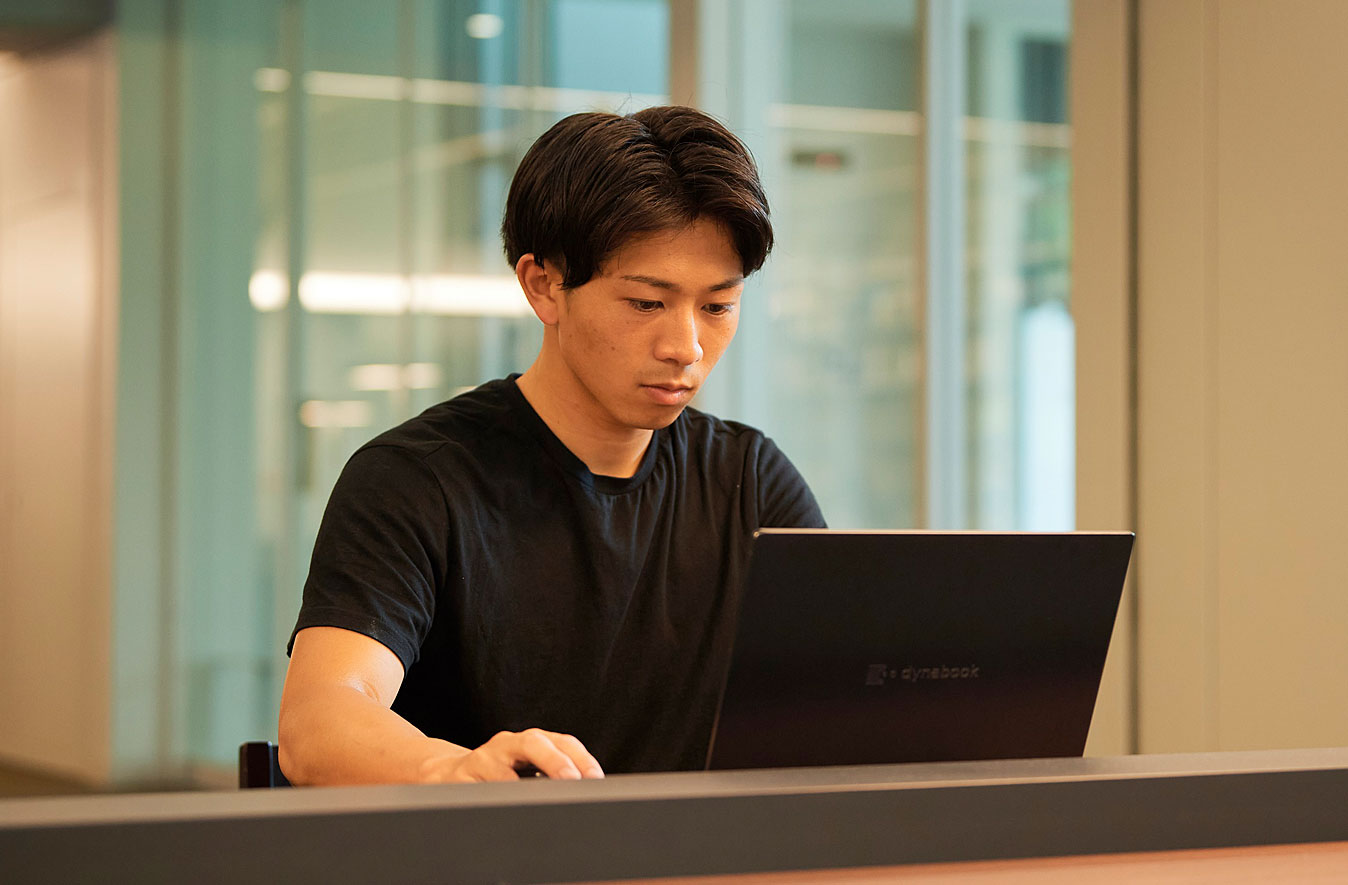
藤野さんはグローバル・スタディーズ専攻でありながら、クロス履修制度を利用して国際関係学専攻の授業も履修されています。
藤野はい、基礎統計学や社会統計論を学びたいと思い、グローバル・スタディーズ専攻では開講していない、国際関係学専攻の授業を積極的に履修しました。統計学の勉強を始めたのは、インターンシップや自分の卒業論文を執筆する上で必要不可欠だと感じたからです。特に私が所属している植松大輝先生のゼミでは開発経済学や統計学を専門に扱うのですが、足りない知識を国際関係学専攻の授業で補うことができました。
このようにクロス履修制度は、自分の学びたいジャンルに応じて両専攻の授業を横断することができ、自分の知見の幅を広げられる素晴らしい制度だと思います。
卒業研究ではどんなテーマに取り組んでいるのでしょうか。
藤野卒業論文では、マレーシアの交通死亡事故について研究しています。具体的には、交通教育や法規制などが新興国の交通死亡事故においてどのようなインパクトを与えるか、について調べています。最終的には、新興国における事故死者数を効率よく減らすための施策を、ソフト面から考察していきたいと思っています。
藤野さんはJICAでインターンシップを経験されていますね。どんなことをされたのか、教えてください。
藤野JICAでのインターンでは主に社会基盤部内での調査業務に携わりました。今後、JICAが交通安全の案件をリードしていくために、民間企業、政府機関や国際機関が今までどのようなことに取り組んできたのかを調査しました。また、実際にJICAが主催する留学生セミナーに参加する中で、現地のインフラの未来を担う留学生と意見交換を行うなど貴重な経験をすることができました。このインターンの経験は、現在執筆している卒業論文でも活用しています。
就職活動はいかがでしたか。卒業後の進路について教えてください。
藤野グローバルな環境で仕事をしたいというかつてからの目標を実現させるために、来年度より総合商社に進むことを決めました。総合商社内でトレーディング業務や事業投資を経験する中で、常に世の中に付加価値を与えられるビジネスパーソンになれるよう励んでいきたいと思います。また、どこの部署においても、社内外問わず、コミュニケーションが重要視される仕事だと思いますので、今後も積極的に様々な方から話を伺い、自分の価値観を広げ続けたいです。
2024年7月更新
MORE INTERVIEWS
-
オープンゼミナール2025「【もうええでしょう】「食い尽くし系夫」は何故食い尽くしをやめられないのか?」
鳥山ゼミ
(チーム名:純子先生、それ食べたかったんじゃないですか?)2025.12.19
academics|openseminar|
-
体操部の主将としての活動と学部の学びの両立。ゼミの海外フィールドワークが国連職員になりたいという夢に挑戦する勇気をくれました。
吉田 誇太郎さん
国際関係学専攻 3回生2025.11.17
studentlife|academics|athletics|ir_major|
-
国際寮のレジデントメンターとして多様な留学生と共に過ごした経験は、今後の人生においても大きな財産になると確信しています。
田畑 琴子
国際関係学専攻 4回生2025.11.6
studentlife|ir_major|
-
「実際に世界を変えられる人になりたい」という夢を実現するため「タイ・バンコク国際機関研修」に参加。現場を訪問し直接お話することで国連職員を目指す上で必要なこと学ぶことができました
森本 真彩
国際関係学専攻 1回生2025.10.29
studyabroad|international|ir_major|
-
蓄積してきた知識を実際の経験を通じて捉え直したいと考え、Peace Studies Seminarに参加。原爆や戦争、平和に関する自分の中での「あたりまえ」を再構築することができたと思います。
栗栖 慧さん
グローバル・スタディーズ専攻 4回生2025.10.23
studentlife|academics|gs_major|
-
将来の夢は報道を通じて世界平和の実現に貢献すること。地元:長崎で学んできた平和学習の内容が他の地域では当たり前ではないことを実感した時、将来、この現状を変えたいと強く思いました。
川端 悠さん
国際関係学専攻 3回生2025.10.14
studentlife|academics|ir_major|