
高校時代から関心を持っていた外交の世界。学部での学びを通じ、外務省専門職に内定。
余頃 彩香 さん
国際関係学専攻 卒業生(2023年度卒業)
卒業後、外務省専門職の採用試験に合格した余頃さん。外務省を目指したきっかけや、4年間の学びの集大成である卒業研究についてお話をお伺いました。
外務省専門職を目指そうと思われたきっかけを教えてください。
余頃外交そのものに興味をもったきっかけは、高校時代に東京にあるドイツ連邦共和国大使館を訪問したことです。大使館の職員の方々がいきいきと仕事をされていたので、大使館の仕事や外交に興味が湧きました。
具体的に外務省専門職員を目指すようになったのは大学時代です。学部の授業やプログラムで元外交官の方々からお話を伺ったことで、外交の面白さを感じるようになりました。また、外務省の説明会で外務省の中にも様々な職種があることを知り、中でも外務省専門職員の仕事に魅力を感じ、志望しました。
合格するまで準備したことや、国際関係学部での学びで役立ったことがあれば教えてください。
余頃当たり前のことですが、試験科目の勉強をしました。国際関係学部では、国際法や憲法など外務省専門職員試験で必要な科目を学ぶことができます。試験科目を受験科目として勉強する前に、授業で触れることができていたことで、試験勉強の際も理解が深まりました。
外務省で実現したいこと、挑戦したいことはありますか?
余頃まだ入省していないので、私に与えられる役割が何になるかは分かりませんが、何になったとしても地域の専門家として相手国・地域をよく理解したうえで働きかけられる外交官になりたいです。そのためにも、何歳になっても学び続けたいです。
余頃さんは卒業論文に人一倍力を入れて書き上げられたと伺っています。どんなテーマを研究されたのでしょうか。
余頃日本における国際宇宙ステーション(International Space Station:ISS)計画の決定について、国際政治学の理論を用いて分析しました。ISS計画は、その規模の⼤きさから意思決定が複雑化し、計画は⻑期化、費⽤も増⼤していました。計画の先⾏きが危ぶまれる中で、⽶国や欧州は国内の経済状況や政治的事情からISS計画を縮⼩していた一方、日本では当初の計画を維持していました。私はこの点に着目し、⽇本のISS計画の参加目的および取り得た選択肢を検討することで、日本の意思決定の背景を探ろうと試みました。
卒業論文の作成はどのように進めましたか。研究の過程で大変だったことや工夫した点を教えてください。
余頃卒業論文の作成は、リサーチクエスチョンの設定、リサーチクエスチョンに応えるための分析・考察、文章化の順で行いました。その過程で苦労した点は3点あります。1つ目は、とても長い文章を書くことです。卒業論文は約2万字の長文で、私にとっては人生最長の文章作成でした。長い文章はたくさんの内容を詰め込める一方で、首尾一貫した文章を書くことが難しくなります。普段よりも入念に構成を練り、ゼミ担当教授の足立研幾先生に構成を確認していただきました。
2つ目は、研究を始めるにあたり重要となるリサーチクエスチョンの設定です。当初、自分の関心や問いが学問的に的外れではないか、という不安があったのですが、卒論で扱いたい分野・テーマを研究されている先生の授業を受けたり実際に質問したりと、扱いたいテーマへの理解を深めることで、適当な問いとは何かを徐々に見いだすことができました。
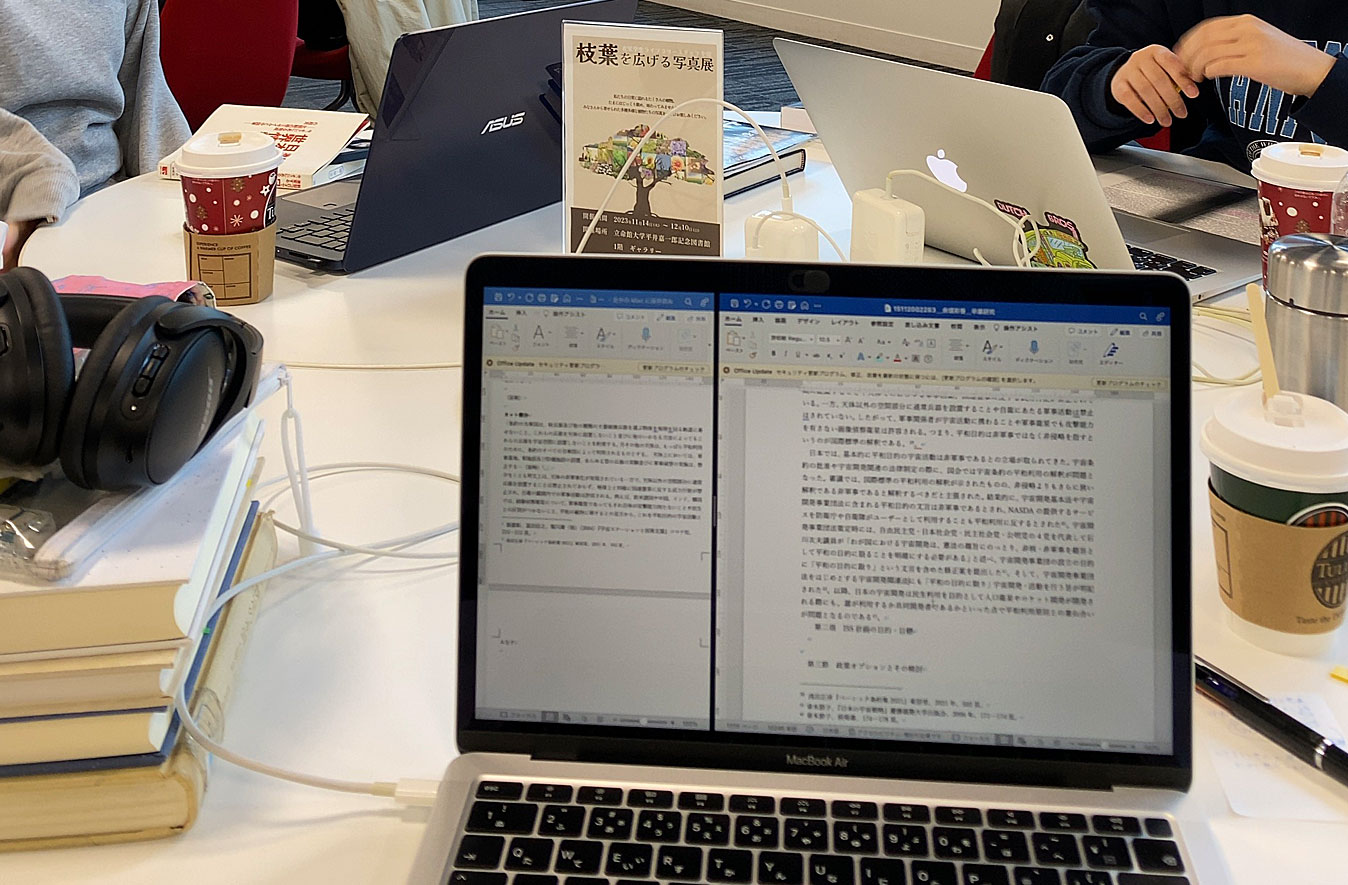
余頃3つ目は資料集めです。用いたい資料が意外と簡単には手に入りませんでした。立命館大学の図書館は書籍、論文等が充実している一方で、政府資料などの一次資料を用いる際には国立国会図書館に出向く、あるいは資料の開示請求をする必要がありました。関西の国立国会図書館は少し足を運びづらい場所にあるのですが、同じゼミの学生と一緒に行ったことで、遠足気分で楽しむことができました。
卒論は基本的に個人で作成するものですが、友人や同じゼミに所属している仲間たちの存在も大きな助けになったと思います。時には行き詰まることもありましたが、同じく卒業論文に取り組む彼らと心境や進捗状況を話していると「頑張らなくては」と励まされました。
卒業研究を通して「身についた」と感じることを教えてください。
余頃まず、自分の興味・関心を追求する楽しさを改めて感じました。日常生活で気になることをインターネットで検索することはあっても、一次資料にあたるために遠くへ赴いたりインタビューしたりすることはなかなかないのではないでしょうか。普段ならば手を伸ばさない本や手間暇かけて手に入れた資料を読んで得た知識は、知る喜びを改めて感じさせてくれました。

余頃また、課題への取り組み方にも成長があったと思います。以前は何か課題に直面すると、ひとりで考え込むことが多かったのですが、卒業論文を書く過程で、上手にこなしている人の方法を取り入れたり、他の人にアドバイスをもらったりすることを覚えたように思います。大学入学当初は、学問的な文章を書くことが得意ではありませんでしたが、論文の書き方を指南する書籍やライティングサポートなどを利用し、少しずつ身につくようになりました。卒業論文はこのような進歩の集大成だったと思います。
最後に、国際関係学部を志望する受験生に対してメッセージをお願いします。
余頃国際関係学部は、自分の興味・関心を追求できる良い環境だと思います。何か学びたいことがある方は、思う存分、興味・関心を追い求めることができますし、まだ自分の勉強したいことが見つかっていない方にも国際関係学部はおすすめです。本学部では、政治や経済、文化など国際関係を形作る様々な分野を横断的に学ぶことができるからです。その中で、新たな興味・関心を発見することができるはずです。
2024年9月更新
MORE INTERVIEWS
-
国際関係学は、単に外国について学ぶのではなく、自国と他国の関係性や背景を多角的に理解する学問。日本を外からの視点で見つめ直すことで、世界を見る視野が広がりました。
岸本 幸弘さん
国際関係学専攻 4回生2025.07.09
academics|ir_major|
-
入学前から楽しみにしていた「GSG」。専攻・学科問わず学年全体で国際交渉に取り組むので、コミュニケーション力の伸びは多くの人が実感できると思います。
北内 ひかりさん
グローバル・スタディーズ専攻 3回生2025.07.09
academics|gs_major|
-
友人は皆、学びに対して熱心なので入学前に理想としていた大学生活を送る事ができています。ハイレベルな英語の授業を頑張ったことで自信を持てるようになりました。
南 佳恩
国際関係学専攻 2回生2025.7.1
studentlife|academics|ir_major|
-
国際寮で1年間Resident Mentorとして活動。寮に住む留学生との交流を深めるだけでなく、自分自身の成長にもつなげることができました。
尾上 沙知保
グローバル・スタディーズ専攻 4回生2025.7.1
studentlife|academics|gs_major|
-
様々な力が身に付いた1回生時の「基礎演習」。将来の目標は「まちづくり」に関わること。地域活性化に関わる課外活動にも積極的に参加しています。
安井 悠
国際関係学専攻 2回生2025.6.26
studentlife|academics|ir_major|
-
多言語が使えることは将来、非常に有効になると思っているので、強みである語学力・コミュニケーション力を更に伸ばしていきたいと思っています。
田畑 和結斗
国際関係学専攻 2回生2025.6.26
studentlife|academics|ir_major|