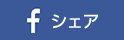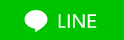国際シンポジウム「つぎの一歩へ:イノセンス運動の未来」を開催
6月15日(土)、立命館大学朱雀キャンパスにて、えん罪救済センター(IPJ)3周年を記念し、国際シンポジウム「つぎの一歩へ:イノセンス運動の未来」が開催されました。本シンポジウムは、台湾冤獄平反協会(台湾イノセンス・プロジェクト)など、えん罪救済に取り組むアジアの法律家・雪冤者も集まり、今後の日本の冤罪救済について討論されました。
第1部では、「アジアのイノセンス運動」として、羅秉成(ロ・ピンチェン)氏(無任所大臣,元台湾冤獄平反協会理事長)、ナムテー・ミーブーンサラン氏(タイ王国カーンチャナブリ県主席検事、イノセンス・インターナショナル・タイランド代表)の基調公演が行われました。羅氏は政府の大臣、ナムテー氏は検察官という立場で、えん罪被害の撲滅を目指すイノセンス運動に取り組まれており、実際の冤罪事例における活動を紹介されました。また、両国において、国・検察・弁護士などの司法関係者が垣根を越えて、証拠開示をはじめとした情報連携、科学的な鑑定制度を通じ、有機的に連携する司法制度改革が進みつつと報告され、その意義や今後の展望が述べられました。これについて、IPJ運営委員・京都弁護士会所属の石側亮太弁護士は、羅氏、ナムテー氏の取組に感動する一方、法制度や司法における立場が違っても、冤罪救済の価値は普遍的で当たり前であることから、自分の視野の狭さを感じたとコメントされました。
第2部では、「DNA型鑑定による雪冤-あるべき刑事裁判と再審を指して」として、DNA型鑑定に内在する課題についてパネルディスカッションが行われました。ディスカッションに先立ち、IPJ運営委員・京都弁護士会所属の遠山大輔弁護士からDNA型鑑定を取り巻く法制度の課題が提示されました。そして、パネリストの黒崎久仁彦氏(東邦⼤学医学部)は、DNA型鑑定の精度は極めて高いものの、それは正しいプロセスが踏まれていることが前提であり、現状ではそこに介在する人間は限定され、その鑑定プロセスの開示等の透明性に課題があると警鐘をならしました。同じくパネリストの徳永光氏もアメリカの事例を踏まえながら、DNAなどの鑑定の信頼性について科学的な検証を行う第三者機関が必要であると指摘しました。また、パネリストの後藤貞人氏(大阪弁護⼠会)は個人のDNAは公権力を使って取得したものであり、それが公共財であることを強調されました。
第3部では、「イノセンス運動がもたらしたもの」として、台湾にて最も著名な冤罪事件として知られ、昨年(2018年)に無罪判決を勝ち取った蘇炳坤事件の蘇炳坤(ス・ピンクン)氏が、残虐な拷問の過程、そして家族や台湾イノセンスプロジェクトとともに、無実を証明するべく、戦い続けた日々を、途中涙で言葉が詰まりながら語られました。また、布川事件の雪冤者である桜井昌司氏は、蘇氏との対談で当時を振り返りながら、日本でも台湾と同じ構造で冤罪が作られることを指摘し、共に無罪を勝ち取った喜びを分かち合いました。