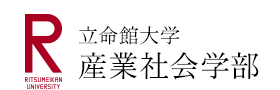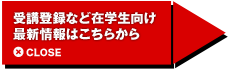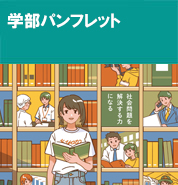ゼミナール紹介
2023年度開講 3回生ゼミ担当者・テーマ一覧
| 専攻 | 領域 | 担当者名 | 専門演習テーマ |
|---|---|---|---|
| 現代社会 | 社会形成 | 江口 友朗 | 世界の諸現象への金銭的理解: 制度・政策・雇用・貧困・文化等の違いがもたらすこと |
| 櫻井 純理 | 働き方・キャリア形成の課題と社会政策 | ||
| 中井 美樹 | ジェンダー・格差の視点から現代日本社会の課題を考える | ||
| 中西 典子 | 地域/ 地方の産業・政策・歴史・文化を探究する ― 郷土学×京都学×地域学への視座 |
||
| 永島 昂 大野 威 |
日本経済・企業と労働 | ||
| 柳原 恵 | ジェンダーの視点から社会を考える― 過去・現在・未来 ― | ||
| 吉田 誠 | 企業社会の変容と働き方の行方 | ||
| 社会文化 | 小澤 亘 | インクルーシブ社会研究: 誰でも読めるデジタル図書の可能性を探求する |
|
| 崎山 治男 | 社会問題の社会学 ― 感情労働と心理主義化する人間関係の病理 ― |
||
| 住家 正芳 | 多様な価値観と社会 ― 宗教とその周辺を手がかりとして ― |
||
| 孫 片田 晶 | 多文化共生社会の探究 ― 多様な人々が共につくる社会とは ― |
||
| 日暮 雅夫 | 現代社会におけるコミュ二ケーションと承認 | ||
| 三笘 利幸 | 社会理論・社会思想の可能性 ― 噴出する現代社会の問題にどう向き合うか |
||
| 環境社会 | 杉本 通百則 | サステイナブル社会を展望する ― サーキュラーエコノミーによる脱炭素社会の実現 ― |
|
| 竹濱 朝美 | 再生可能エネルギーと電気自動車に関する企業戦略の調査 | ||
| 永野 聡 | ソーシャルイノベーション・ソーシャルデザインの理論と実践 ― シェアリングエコノミー、ジェロントロジー、地域観光プランニング、震災復興エリアマネジメント、現代アートを活用した地域活性化 ― |
||
| 山口 歩 | 社会における公共空間の再構成の課題 | ||
| リム・ボン | 歴史都市・京都の都市政策課題に関する研究 | ||
| メディア 社会 |
文化と メディア |
瓜生 吉則 | <メディア>と<文化>の交差点を探る |
| 川島 隆 | メディアとジェンダー | ||
| 佐藤 彰宣 | 趣味とメディアの社会学 | ||
| 増田 幸子 | 映像メディア研究の視座 ~ジェンダー・エスニシティ・ナショナリズムから探る~ |
||
| 社会と メディア |
小泉 秀昭 | 現代広告の研究と実践 ― 論理的思考力、企画力、そしてプレゼンテーション能力を高める ― |
|
| 高橋 顕也 | 「メディアと社会」を理論的につかみとる | ||
| 趙 相宇 | メディアから社会の欲望や心情を読み取る | ||
| 根津 朝彦 | 戦後日本の歴史とジャーナリズム ― 現代社会の鍵となる戦後史と報道の魅力に迫る |
||
| 日高 勝之 | 社会と世界と自分の〈物語〉としてのメディア ~ 21 世紀をメディア作品から解読する~ |
||
| 福間 良明 | 戦後メディアで読み解く「戦後」 | ||
| 市民と メディア |
岡田 朋之 | メディアで社会を動かす ― メディア実践を通じた地域連携と情報社会の理解 ― |
|
| 坂田 謙司 | 音声メディアを社会学する | ||
| 柳澤 伸司 | ジャーナリズムとメディア倫理 | ||
| スポーツ 社会 |
スポーツ 文化 |
市井 吉興 | ライフスタイルスポーツ文化の研究: 新しいスポーツの誕生と発展のダイナミズムを探る |
| 松島 剛史 | 身近なスポーツ現象や謎を読み解く | ||
| スポーツ 社会 |
有賀 郁敏 | 余暇社会の歴史と現代 | |
| 金山 千広 | パラスポーツと共生社会 : スポーツの機会創出のための課題を紐解く |
||
| 権 学俊 | 近現代日本社会とスポーツイベント | ||
| 中西 純司 | スポーツ文化の普及学を考える | ||
| 子ども社会 | 現代社会と子ども | 御旅屋 達 | 子ども・若者の生きる「社会」とその現代的課題 |
| 柏木 智子 | 公正な民主主義社会形成と教育 ― ケア・寛容・連帯の社会学 |
||
| 野原 博人 | 学習環境のデザイン― 社会文化的アプローチ ― | ||
| 人間福祉 | 福祉社会 | 石倉 康次 | 社会の土台・柱としての社会福祉労働と社会福祉経営を考える |
| 丹波 史紀 | 変動期における社会政策 | ||
| 松田 亮三 | 社会経済格差と医療・福祉 ― 誰もが利用できる仕組みと取り組みに向けて |
||
| 臨床福祉 | 石田 賀奈子 | 「子どもの権利」のソーシャルワークの視点からの検討 | |
| 田村 和宏 | 障害児者の発達と生活 | ||
| 中村 正 | 身近な社会病理現象をとおして社会を考える ― 日常からの社会病理学と臨床社会学 |
||
| 三木 裕和 | 障害児の発達的理解と学校教育 | ||
| 学部共通ゼミ | 秋葉 武 | NPO・NGO の経営 | |
| 岡田 まり | 共生社会と社会福祉 | ||
| 景井 充 | ソーシャルデザインを通じて持続可能社会を構想する ―《 地域社会》のサバイバル ― |
||
| 金澤 悠介 | 論理と証拠で社会をつかむ ― 社会理論と社会調査で人々の意識と行動を解明する ― |
||
| 斎藤 真緒 | 家族・ジェンダー・セクシュアリティから考える現代社会 | ||
| 富永 京子 | 自分たちの身近から社会と政治を考える ― 買い物、おしゃべりから恋愛、アルバイトまで |
||
| 樋口 耕一 | ネットに広がる言葉と新聞報道の言葉 ― 飛びかう言の葉から「社会の心」を掴めるか? ― |
||
| 前田 信彦 | 教育・職業キャリアを考える | ||
| 筒井 淳也 | 国際比較の社会学 | ||
| 松島 綾 | 表象、レトリック、眼差し:「見る」を問い直す | ||
| 石田 智巳 | 語りとその変容 | ||
| 漆原 良 | 生物―心理 ― 社会的統一体として行動を捉える視点による人の潜在的可能性の探求 |
||
| 岡本 尚子 | ヒトの思考、行動、学習、心を科学的に考え、捉える | ||
| 春木 憂 | 子どもの論理と社会を結ぶ ―「 ことば」を通して子どもを見つめる ― |
||
| 長谷川 千春 | 医療のセーフティネットについて考える ~ケアを支える/ ケアする人を支えるということ |
||