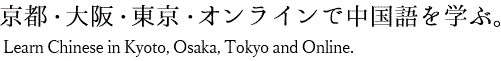これからの講座・イベント
- TOP
- これからの講座・イベント
- イベント詳細
2025年度北京大学・立命館大学連携講座「アニメ新時代:日中アニメーションの交差点」
王 洪喆 氏、中川 涼司 氏
時間:17:00~19:00 (16:30~受付開始)
場所:立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム、オンラインライブ配信
立命館孔子学院では、毎年、北京大学と協力し、連携講座を開催しています。
北京大学と立命館大学の経験豊かな講師陣が、中国文化・社会などについて幅広く分かりやすくお話します。
今年は立命館孔子学院設立20周年記念シンポジウムとして、「アニメ新時代:日中アニメーションの交差点」というメインテーマにて、2名の講師が掘り下げます。
(中国側講師による講演は、中国語・同時通訳となります。)
北京大学と立命館大学の経験豊かな講師陣が、中国文化・社会などについて幅広く分かりやすくお話します。
今年は立命館孔子学院設立20周年記念シンポジウムとして、「アニメ新時代:日中アニメーションの交差点」というメインテーマにて、2名の講師が掘り下げます。
(中国側講師による講演は、中国語・同時通訳となります。)
テーマ : アニメ新時代:日中アニメーションの交差点
第一部 基調講演
「鉄扇と火の鳥ー日中アニメ交流の歴史と未来」
王 洪喆 氏(北京大学ニュース・コミュニケーション学院准教授)※中国語・同時通訳
「中国アニメ産業の発展と日本市場への進出」
中川 涼司 氏(立命館大学国際関係学部特命教授)※日本語
第二部 パネルディスカッション
「アニメ新時代:日中アニメーションの交差点」
パネリスト:王 洪喆 氏、中川 涼司 氏(発表順)
進行役:加部 勇一郎 氏(立命館大学食マネジメント学部准教授)
会 場 : 立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム、オンラインライブ配信
定 員 : 対面100名、オンライン100名(事前申込制)
参加費 : 無料
<講演概要>
本講演では、20世紀初頭から現在に至るまでの日中アニメ産業の歴史的交流と協力に焦点を当て、技術、文化、ストーリーにおける両国の双方向交流の歴史をたどる。アニメーションの黎明期から、中国と日本のアニメーターは密接な関係を築いてきた。『西遊記 鉄扇公主の巻』(原題:铁扇公主)や『大暴れ孫悟空』(原題:大闹天宫)といった初期の中国アニメ作品は、手塚治虫など日本のアニメーションの先駆者たちに多大な影響を与えた。第二次世界大戦後の日本のアニメーション技術の発展とテレビアニメの台頭は、1980年代以降の中国アニメ産業にも影響を与え、中国の一人っ子世代の社会化プロセスにも大きな影響を与えた。
講演では、技術レベルでの相互作用(セルアニメやテレビシリーズ制作における日本の経験の中国への移転、デジタル時代の制作過程における双方の協力など)、文化レベルでの相互学習(中国の視聴者の審美や価値観に対する日本のアニメーションの影響、中国の伝統的な文化要素が日本のアニメーションに与えたインスピレーションなど)、ナレーションと美学の相互作用(キャラクター設定やプロット構成における借用と革新など)に焦点を当てる。 手塚治虫や宮崎駿といった日本の巨匠が中国アニメに与えた影響や、近年のスタジオジブリ、新海誠等の作品に対する中国における反応、『西遊記 ヒーロー・イズ・バック』(原題:西游记之大圣归来)、『ナタ~魔童降臨~』(原題:哪吒之魔童降世)、『黒神話:悟空』、『原神』といった中国のアニメやゲームが日本市場で引き起こした反響を考慮しながら、代表的な作品や事例における双方向の相互作用を分析する。共同制作、人材交流、映画祭や展覧会の交流など、協力の事例を分析することで、中日アニメ産業が競争と協力の中でどのように共に発展してきたかを明らかにする。この過程は、アニメ技術と芸術の融合と革新を反映するだけでなく、中日両国の文化交流の深化と民間における友好の架け橋の役割の証でもある。
また、大塚英志、東浩紀、宇野常寛といった日本の批評家たちの中国における翻訳と普及から、アニメーション研究と批評の分野における両国の交流を紹介し、関連する批評家たちの見解を比較分析する。
最後に、コンテンツ制作、技術革新、価値観における中国と日本のアニメーションの相互補完性を分析し、今後のグローバル化の中での「東アジアアニメーション共同体」の可能性を展望する。
<講師紹介>
遼寧省鞍山市生まれ。メディア史研究者、北京大学ニュース・コミュニケーション学院研究員、長期准教授、博士課程指導教官。中国鉱業大学にて材料科学・工学の学士号、北京大学でコミュニケーション学の修士号、香港中文大学でコミュニケーション学の博士号を取得。 中国美術学院現代芸術・社会思想研究所研究員、北京大学視覚映像研究センター研究員。
■「中国アニメ産業の発展と日本市場への進出」(中川 涼司 氏・立命館大学国際関係学部特命教授)
<講演概要>
中国のアニメ産業の出発点は遅くはないが、改革開放後に日本アニメが市場を席捲した。中国政府は2001~2005年の第10次5ヵ年計画において文化産業振興を打ち出し、アニメ産業はその柱の一つとなった。2006年からは放送時間規制、産業基地設置、補助金付与、専門人材育成機関設立などの多面的な支持の下で急速に発展し、テレビアニメの放送時間では世界第1位となり、アニメ映画としても2019 年の『ナタ~魔童降臨~』(原題:哪吒之魔童降世)が50 億元の空前の興行収入をあげた。日本市場への進出も進められている。2019年から日本でも上映された『羅小黒戦記』は日本で5億円以上の興行収入をあげている。また今年日本公開された『ナタ 魔童の大暴れ』(原題:哪吒之魔童闹海)は中国ですでに90億元以上の興行収入をあげ、日本でも好調な滑り出しを見せている。これらの中国アニメの発展と日本市場での反響などを明らかにする。
<講師紹介>
1960年兵庫県生まれ。1984年大阪市立大学大学院前期博士課程修了、1987年同後期課程単位取得退学。鹿児島経済大学(現鹿児島国際大学)、阪南大学を経て2000年4月から2025年3月立命館大学国際関係学部教授。2025年4月から立命館大学国際関係学部特命教授、立命館孔子学院学院長。
1997-98年中国社会科学院工業経済研究所客員研究員、2005-06年対外経済貿易大学客員教授。
キャンパスマップ: (創思館:30番)
(創思館:30番)
↓【教室受講】をご希望の方はこちらのフォームからお申込みください。
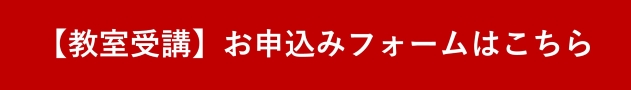
↓【オンライン受講】をご希望の方はこちらのフォームからお申込みください。

※お電話及び窓口でのお申込みはお受けできません。
※お申込み後のキャンセルは、受付メール内にあるキャンセル専用URLからキャンセルをしてください。(お電話でのキャンセルはお受けできません。)
※【オンライン受講】をお申込みいただいた方には、講座前日17時頃に孔子学院事務局から参加方法・Zoomへの招待メールをお送りします。当日正午までに届いていない場合は事務局(koza@st.ritsumei.ac.jp)までご連絡ください。なお、ご連絡いただく前に、念のため、迷惑メールフォルダ内もご確認ください。
※オンラインはライブ配信のみとなり、アーカイブ配信はありません。
以下のフォームより、質問内容をお送りください。
(受付締切:5月23日(金)17時)
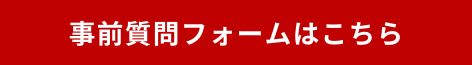
「鉄扇と火の鳥ー日中アニメ交流の歴史と未来」
王 洪喆 氏(北京大学ニュース・コミュニケーション学院准教授)※中国語・同時通訳
「中国アニメ産業の発展と日本市場への進出」
中川 涼司 氏(立命館大学国際関係学部特命教授)※日本語
第二部 パネルディスカッション
「アニメ新時代:日中アニメーションの交差点」
パネリスト:王 洪喆 氏、中川 涼司 氏(発表順)
進行役:加部 勇一郎 氏(立命館大学食マネジメント学部准教授)
会 場 : 立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム、オンラインライブ配信
定 員 : 対面100名、オンライン100名(事前申込制)
参加費 : 無料
講演概要・講師紹介
■「鉄扇と火の鳥ー日中アニメ交流の歴史と未来」 (王 洪喆 氏・北京大学ニュース・コミュニケーション学院准教授)<講演概要>
本講演では、20世紀初頭から現在に至るまでの日中アニメ産業の歴史的交流と協力に焦点を当て、技術、文化、ストーリーにおける両国の双方向交流の歴史をたどる。アニメーションの黎明期から、中国と日本のアニメーターは密接な関係を築いてきた。『西遊記 鉄扇公主の巻』(原題:铁扇公主)や『大暴れ孫悟空』(原題:大闹天宫)といった初期の中国アニメ作品は、手塚治虫など日本のアニメーションの先駆者たちに多大な影響を与えた。第二次世界大戦後の日本のアニメーション技術の発展とテレビアニメの台頭は、1980年代以降の中国アニメ産業にも影響を与え、中国の一人っ子世代の社会化プロセスにも大きな影響を与えた。
講演では、技術レベルでの相互作用(セルアニメやテレビシリーズ制作における日本の経験の中国への移転、デジタル時代の制作過程における双方の協力など)、文化レベルでの相互学習(中国の視聴者の審美や価値観に対する日本のアニメーションの影響、中国の伝統的な文化要素が日本のアニメーションに与えたインスピレーションなど)、ナレーションと美学の相互作用(キャラクター設定やプロット構成における借用と革新など)に焦点を当てる。 手塚治虫や宮崎駿といった日本の巨匠が中国アニメに与えた影響や、近年のスタジオジブリ、新海誠等の作品に対する中国における反応、『西遊記 ヒーロー・イズ・バック』(原題:西游记之大圣归来)、『ナタ~魔童降臨~』(原題:哪吒之魔童降世)、『黒神話:悟空』、『原神』といった中国のアニメやゲームが日本市場で引き起こした反響を考慮しながら、代表的な作品や事例における双方向の相互作用を分析する。共同制作、人材交流、映画祭や展覧会の交流など、協力の事例を分析することで、中日アニメ産業が競争と協力の中でどのように共に発展してきたかを明らかにする。この過程は、アニメ技術と芸術の融合と革新を反映するだけでなく、中日両国の文化交流の深化と民間における友好の架け橋の役割の証でもある。
また、大塚英志、東浩紀、宇野常寛といった日本の批評家たちの中国における翻訳と普及から、アニメーション研究と批評の分野における両国の交流を紹介し、関連する批評家たちの見解を比較分析する。
最後に、コンテンツ制作、技術革新、価値観における中国と日本のアニメーションの相互補完性を分析し、今後のグローバル化の中での「東アジアアニメーション共同体」の可能性を展望する。
<講師紹介>
遼寧省鞍山市生まれ。メディア史研究者、北京大学ニュース・コミュニケーション学院研究員、長期准教授、博士課程指導教官。中国鉱業大学にて材料科学・工学の学士号、北京大学でコミュニケーション学の修士号、香港中文大学でコミュニケーション学の博士号を取得。 中国美術学院現代芸術・社会思想研究所研究員、北京大学視覚映像研究センター研究員。
■「中国アニメ産業の発展と日本市場への進出」(中川 涼司 氏・立命館大学国際関係学部特命教授)
<講演概要>
中国のアニメ産業の出発点は遅くはないが、改革開放後に日本アニメが市場を席捲した。中国政府は2001~2005年の第10次5ヵ年計画において文化産業振興を打ち出し、アニメ産業はその柱の一つとなった。2006年からは放送時間規制、産業基地設置、補助金付与、専門人材育成機関設立などの多面的な支持の下で急速に発展し、テレビアニメの放送時間では世界第1位となり、アニメ映画としても2019 年の『ナタ~魔童降臨~』(原題:哪吒之魔童降世)が50 億元の空前の興行収入をあげた。日本市場への進出も進められている。2019年から日本でも上映された『羅小黒戦記』は日本で5億円以上の興行収入をあげている。また今年日本公開された『ナタ 魔童の大暴れ』(原題:哪吒之魔童闹海)は中国ですでに90億元以上の興行収入をあげ、日本でも好調な滑り出しを見せている。これらの中国アニメの発展と日本市場での反響などを明らかにする。
<講師紹介>
1960年兵庫県生まれ。1984年大阪市立大学大学院前期博士課程修了、1987年同後期課程単位取得退学。鹿児島経済大学(現鹿児島国際大学)、阪南大学を経て2000年4月から2025年3月立命館大学国際関係学部教授。2025年4月から立命館大学国際関係学部特命教授、立命館孔子学院学院長。
1997-98年中国社会科学院工業経済研究所客員研究員、2005-06年対外経済貿易大学客員教授。
会場のご案内
立命館大学衣笠キャンパス交通アクセス:https://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/kinugasa/キャンパスマップ:
お申込み受付期間
~5月29日(木)正午 ※定員になり次第、申込受付終了お申し込み方法
【ご注意】教室受講とオンライン受講はフォームが異なります。↓【教室受講】をご希望の方はこちらのフォームからお申込みください。
↓【オンライン受講】をご希望の方はこちらのフォームからお申込みください。
※お電話及び窓口でのお申込みはお受けできません。
※お申込み後のキャンセルは、受付メール内にあるキャンセル専用URLからキャンセルをしてください。(お電話でのキャンセルはお受けできません。)
※【オンライン受講】をお申込みいただいた方には、講座前日17時頃に孔子学院事務局から参加方法・Zoomへの招待メールをお送りします。当日正午までに届いていない場合は事務局(koza@st.ritsumei.ac.jp)までご連絡ください。なお、ご連絡いただく前に、念のため、迷惑メールフォルダ内もご確認ください。
※オンラインはライブ配信のみとなり、アーカイブ配信はありません。
事前質問受付
本講座では、お申込みいただいた方を対象に、事前に各講師への質問を受け付けます。以下のフォームより、質問内容をお送りください。
(受付締切:5月23日(金)17時)