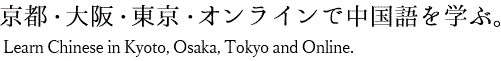これからの講座・イベント
- TOP
- これからの講座・イベント
- イベント詳細
第214回中国理解講座 「中国の書と日本の書」(東京学堂)
承 春先 氏(大東文化大学、東洋大学、立命館孔子学院東京学堂講師)
時間:13:30~15:00(13:00~受付開始)
場所:立命館東京キャンパス(サピアタワー8階)教室4&オンラインライブ配信
講座概要
「書」といえば「書道」という言葉を想起します。しかし、書と書道には違いがあります。なぜ書道と呼ばれるようになったのか、この「道」はどのような意味を表すのか、そして、中国語を勉強されている方であれば、中国語では「書法」と言うこともご存じのことでしょう。「書法」と「書道」にはどのような違いがあり、単に中国語と日本語の違いなのか、歴史や資料からこれらを紐解いていきます。それから漢字の「筆法」と文字の芸術としての「形」についても講義します。平仮名や片仮名は漢字に由来しますが、漢字からどのような影響を受けているのでしょう。仮名書と隷書についても触れ、専門的な内容も交えて説明します。「書」はまさしく日本と中国の共通する文化の一つです。話者は長く中国語を教えていますが、本講義では、話者の専門である「書」を通じて中国文化を知っていただき、私たちの身近な「書」の奥深さと趣を感じていただけたら嬉しいです。講師紹介
承 春先 氏(大東文化大学、東洋大学、立命館孔子学院東京学堂講師)上海⽣まれ、1988年来⽇、筑波⼤学⼤学院修了、芸術学修⼠。以降昭和⼥⼦⼤学、⼤東⽂化⼤学で中国語、書道、中国⽂化史教える傍ら愛知万博での中国語同時通訳等の通訳や翻訳の仕事に関わった。二十数年に亘り、中国語や中国文化について教鞭をとる。現在は東洋⼤学で中国語を、立命館孔子学院では社会人を対象に中国の時事や文化にも触れながらオンライン授業と対面授業で準上級・上級の講座を担当している。また、大東文化大学では中国語のほか、中国絵画演習、書論・鑑賞、地域連携センターでの「絵と書のコラボレーション」講座を担当。書道においては、大東文化大学「100年の書」教員出品、『齋藤筑後守記念碑』石碑書丹。月島書画会主催。国際文字文化普及協会会員。訳書に『経営就是改⾰』鈴⽊松夫著、『⼈為什么会⾔⾏不⼀』⻫藤 勇著、『汉字书法审美范畴考释』河内利治著(いずれも上海社会科学院出版社出版)がある。
定員
教室:30名 オンライン:70名(要事前申込)参加費用
無料お申込み受付期間
【教室受講】~1月16日(金)12時 ※定員になり次第、受付終了【オンライン受講】~1月23日(金)12時 ※定員になり次第、受付終了
お申し込み方法
【ご注意】教室受講とオンライン受講はフォームが異なります。↓【教室受講】をご希望の方はこちらのフォームからお申込みください。
※【教室受講】にお申込みいただいた方には、講座前々日の1月22日(木)に孔子学院事務局から会場のご案内メールをお送りします。入館方法が記載されていますので、必ずご確認ください。
↓【オンライン受講】をご希望の方はこちらのフォームからお申込みください。
※【オンライン受講】をお申込みいただいた方には、講座前日17時頃に孔子学院事務局から参加方法・Zoomへの招待メールをお送りします。当日開始1時間前になってもメールが届いていない場合は事務局(koza@st.ritsumei.ac.jp)までご連絡ください。なお、ご連絡いただく前に、念のため、迷惑メールフォルダ内もご確認ください。
※オンラインはライブ配信のみとなり、アーカイブ配信はありません。
※お電話及び窓口でのお申込みはお受けできません。
※お申込み後のキャンセルは、受付メール内にあるキャンセル専用URLからキャンセルをしてください。(お電話でのキャンセルはお受けできません。)
会場のご案内
立命館東京キャンパス交通アクセス:https://www.ritsumei.ac.jp/tokyocampus/access/※受付はサピアタワー3階、会場は8階となります。