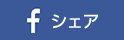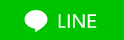Asia Week 展示プロジェクトレポート
「大学・学生・地域」知の循環を生み出す“わかりやすさ”の原点とは?
10月23日(日)、立命館大学の大阪いばらきキャンパス(OIC)で、「立命館でアジアとつながる国際交流フェスタ Asia Week」が開催された。文化体験やスポーツ体験、クラシックライブなどの多彩なイベントや展示を通じて、地域との繋がりを目指す同イベント。2022年は晴天に恵まれ、屋内外60を超える企画に約2,000名もの市民が足を運ぶ盛況ぶりとなった。
教員・学生・職員が一緒になって企画した研究展示で“来場者目線”を実現
公園に面したガラス張りの「フューチャープラザ」には、「大学の研究をのぞいてみよう!」という展示ブースが立ち上がっていた。実はこの展示、研究者である大学教員と、職員・学生がお互いに力を合わせて実現したもの。日ごろから研究をサポートする職員の立場から、取りまとめたのは、立命館大学 研究部 OICリサーチオフィス 岡本慎也さんだ。
「毎年12月に東京で行われているSDGsに関連するプロダクト展示会『エコプロ』というものがあります。立命館大学も毎年、研究の展示をやっていますが、昨年2021年は今回のAsia Weekでも中心的な役割を果たしてくれた北元さん、山根さんの2名に入ってもらい、展示を行いました。
エコプロの展示がとてもクオリティ高く、来場者にも好評だったこともあり、Asia Weekの開催にあたってはOICとしてもぜひ研究内容について発信したいと考えました。そこで、あらためて2人に協力してもらい、企画を固めていきました。
テーマについては、OICだけでなく他のキャンパス、学部を横断した企画がふさわしいと考え、林永周(イム・ヨンジュ)先生が進めている『カーボンマイナスプロジェクト』と、2021年4月に設立10年を迎えた『ゲーム研究センター』に決め、学内助成に申請を行いました。大学の研究成果について、教員・学生・職員が一緒になって取り組んだプロジェクトという意味でも、重要な取り組みだったと考えています」(岡本氏)
横たわる「大学と社会の距離」という問題 情報発信はどうあるべきか
Asia Weekは、地域に住む一般の方々が来場者の中心となる。大学での先進的な研究を、生活者にいかに伝えるか。カーボンマイナスプロジェクトの展示を監修した経営学部の林永周准教授は、その難しさを大きな課題として認識してきたという。
「大学の研究は、社会との距離がとても遠いんですね。その理由は、研究内容が特殊というケースもありますが、僕らが『専門用語で語ってしまっている』というのが非常に大きい。
例えば美術品は、芸術をよく理解している人が“キュレーション”することで、価値が的確に伝わり、価値を高めていきます。大学研究にも、情報のキュレーションが必要であり、それによって相互理解が生まれることが重要だと考えています。
特に、今回の展示テーマとなった『カーボンマイナスプロジェクト』などは、明確に目に見える対象が限られるため、共通認識が極めて持ちづらい研究のひとつです。今回は、学生たちとコミュニケーションを密にしながら、普段使っている『専門用語』が、いかにブレイクダウンされていくかを感じることができ、私にとっても発見の多いプロジェクトとなりました」(林准教授)
専門家だからこそ「なかなかうまく伝えられない」というジレンマは、多くの研究者にとっても実感のあることではないだろうか。ここからは、実際の展示について、学生の視点で迫ってみよう。
研究を“のぞきたくなる”クリエイティブを目指して 「カーボンマイナスプロジェクト」
政策科学部の北元柊人さんは、Asia Weekの展示における企画と、全体演出・マネジメントを担った。昨年のエコプロで岡本氏に声をかけられて、大学からの情報発信に関わるようになったという。
「エコプロは僕にとってとてもいい経験になりました。Asia Weekは地域の一般の方々がターゲットになるので、そのような来場者に研究を魅力的に見せるにはどうしたらいいかが、企画の出発点でした。
『研究をのぞいてみよう』というコンセプトは当初から持っていたので、『穴をのぞくと中にバイオ炭があり、CG合成の映像と説明が現れる仕組み』や『つまみの付いた不思議な箱を用意して触れてもらう仕組み』など、アクションに繋がるような演出には工夫を凝らしました。
林先生のおっしゃるとおり、研究内容は一般の方はもちろん、学生の僕たちにとってもすんなりとは理解できないことも多くあります。はじめに林先生からじっくり説明いただいて理解できるのですが、疑問がどんどん浮かんでくる。『CO2が出るタイミングはいつなのか』『枯れた木は倒れた木なのか、それとも立っている木を倒すのか』など、素朴な疑問を先生とキャッチボールしながら、『バイオ炭になるまでの循環をいかにわかりやすく見せるか』にこだわって、展示を作り上げていきました」(北元さん)
「難しいことを、クリエイティブの力でわかりやすく、楽しく表現したい」と話す北元さんにとって、大きな手応えとなったAsia Weekの取り組みだった。
ゲームがつなぐ「世代間コミュニケーション」のカタチ 「ゲーム研究センター」
「ゲーム研究センター」の展示は、映像学部 山根瑞生さんに話を聞いていこう。アニメーション映像を用いて難解な話題をわかりやすく解説する活動を行っている学生団体「Entervibe」でも活動するという山根さんは、展示全体のグラフィックデザインや体験手法のディレクターを務めた。
「2021年に設立から10周年を迎えた立命館大学ゲーム研究センターは、この分野で先進的な取り組みを進めてきました。ゲームが文化を越え、インフラになったり、メタバースといった社会性に発展しつつあるいま、過去と未来のゲーム研究を地域やより多くの方に知ってもらう絶好の機会だと思いました。
ビジュアル面でこだわったのは、アクリル板のキューブの中にゲーム機を入れ、時計回りに見ると年代を追えるようにレイアウトしたことです。時代の流れに合わせながらゲームの進化を見られるだけでなく、研究センターの『アーカイブプロジェクト』のアピールの意味もあり、かなりレアでマニアックなゲーム機を集められたのも、注目された要因だったと思います」(山根さん)。
懐かしのゲーム機が並ぶとあって、会場には多くの家族連れの姿が見られた。
「まず感動するのがお父さん・お母さん方でした(笑)。『これ、すごい!』と近づいてきて、子どもたちが『これ、何なの?』と会話が生まれていました。研究発表を展示する場でコミュニケーションを生み出すことは、目標のひとつでもあったので、すごくうれしかったですね」(山根さん)
展示全体の映像演出の効果については、林准教授も以下のように指摘する。
「僕はカーボンマイナスの仕組みについて数え切れないほど説明する機会がありますが、みんな『へえ』『ふーん』で終わるんです(笑)。その理由はCO2が目に見えず、実感が湧かないからです。今回、バイオ炭の上にビジュアルでCO2を重ねるなど、見えないものを見えるようにする工夫が盛り込まれたのは画期的だったと考えています」(林准教授)
大学の「見える化」が社会のイノベーションを促進する
大学で行われている難解な研究を、いかに“見える化”していくか。今回のAsia Weekにおける研究展示で取り組まれたコンセプトは、大学と社会の関わりにおいても極めて重要なものといえる。
「世の中にはいろいろな研究がありますが、最終的に研究成果が社会に受け入れられるかどうかが最も重要です。イノベーションがいかに社会に浸透するかは、人々が大学や企業の研究成果をどのくらい採択してくれるかで決まるのです。そのとき、一番大切なことは何かというと、『研究を正しく理解してもらえるかどうか』でしょう。
人間は、新しいものや変化を恐れるものです。今までの生活が変わるくらいなら、抽象的なものは採択しません。その結果、『今のままでいいよね』となってしまうと、革新性は失われてしまいますね。
大学というエコシステムの中で、大学がちゃんと方向性を持って、情報発信を支える。学生もその一員として関われるような仕組みが整備されていけば、もっとわかりやすいコンテンツが生まれ、研究成果が社会に還元される。このような情報発信の流れがもっと可視化されることによって、より良い社会へのハードルを下げることができると考えています」(林准教授)
大学というエコシステムの中で、教員、生徒、さらに地域や社会が関われる仕組みを作っていくこと。その積み重ねが、結果的に研究者たちのプレゼンスを高め、より豊かな社会を作っていく。Asia Weekにおける研究部の展示プロジェクトは、そのロールモデルとなり得る取り組みだったといえるだろう。