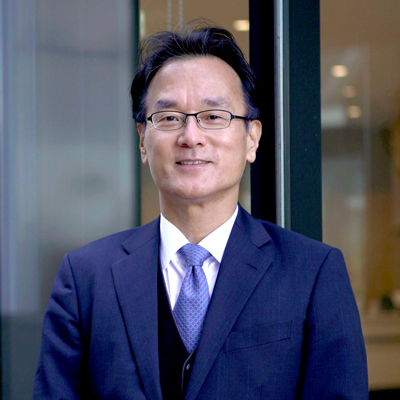世界最高峰の研究者「高被引用論文著者」に本学RARAフェロー2名が選出
総合科学技術研究機構の長谷川知子教授/RARAフェロー、荒井秀典教授/RARAフェローは、ともに、クラリベイト・アナリティクス社が発表した2025年度の高被引用論文著者(Highly Cited Researchers 2025)に選出されました。長谷川教授の選出は7年連続、荒井教授の選出は5年連続となります。
高被引用論文著者は、特定出版年・特定分野における世界の全論文のうち引用された回数が上位1%に入る論文を発表し、後続の研究に大きな影響を与えた研究者が選ばれます。今回もさまざまな研究分野で活躍する6,868名の研究者が選ばれました。長谷川教授、荒井教授は、一人の研究者が複数分野で論文を発表している場合の合計被引用件数で評価する「クロスフィールドカテゴリー」で選出されました。
長谷川教授は、エネルギー、経済、農業、土地利用、水利用などを統合的に解析するコンピューターシミュレーションモデル、いわゆる統合評価モデルを用いて、気候変動を中心とした地球環境問題に関連する研究を行っています。とりわけ、将来の温室効果ガスの排出量を見通し、その削減方策の検討、気候変動による影響の経済的分析などに取り組んでいます。
荒井教授は、国立長寿医療研究センター理事長として、 認知症・フレイル等の老年症候群に対する先進的な医療モデルの提供、医療・保健・福祉の人材育成を推進し、国内外のWell-being領域研究を牽引しています。立命館先進研究アカデミー(RARA)での活動においては、「デジタル技術を用いた産官学連携型フレイル予防プロジェクト 」、「 スティグマを有しやすい障害に対する社会的包摂のための手法開発(特に、認知症)」の2つの大きなテーマを掲げ、高齢者健康寿命を延ばしていくために、研究活動を進めています。
長谷川知子教授コメント
このたび、昨年に引き続き Highly Cited Researchers 2025 に選出いただき、大変光栄に存じます。今回を含むこれまでの選出は、主に、2014年に発表いたしました農業経済モデル比較プロジェクト(Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project; AgMIP)における一連の気候変動による農業影響評価研究、2017年に発表しました共通社会経済シナリオ(Shared Socioeconomic Pathways; SSPs)の開発および関連研究、さらに、国立環境研究所、京都大学およびアジアの研究者の皆様とともに進めてまいりましたアジア太平洋統合評価モデル(The Asia-Pacific Integrated Model; AIM)の開発・適用を通じた農業・土地利用部門の気候変動関連研究、ならびに多数の海外研究機関および研究者の皆様との多くの共同研究成果が結実したものと考えております。
長年にわたりご指導とご協力を賜りました共同研究者の皆様、また日頃よりご支援いただいております本学関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
今回の受賞を励みに、今後も本分野の発展に寄与するとともに、研究成果を社会へ還元していく所存です。

荒井秀典教授コメント
このたび、昨年に続きHighly Cited Researchers 2025 に選出いただき、大変光栄に存じます。これまで私たちの取り組みを支えてくださった共同研究者、所属機関の皆様、そして高齢者の健康長寿の実現に向けて日々努力を重ねておられる臨床・介護現場の方々に、心より感謝申し上げます。
今回の選出は、サルコペニア、フレイルに対する国際的、学際的な研究活動が多くの引用を頂いたことによるものと考えています。特に、アジアサルコペニアワーキンググループ(AWGS)による成果は2014, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023年に発表し、2025年には新たなコンセンサスをNature Aging誌に発表することが出来ました。これらの論文が数多くの引用を頂いたことが主な受賞の理由かと思いますが、それ以外にもフレイル、認知症など高齢者のWell-being向上に関わる多くの研究に携わることができ、共同研究者の皆さまに改めて、感謝の意を表したいと思います。サルコペニア、フレイル、認知症は、世界的な高齢化の進行に伴い、社会・医療双方において極めて重要なテーマとなっています。日本が世界に先駆けて直面している“超高齢社会”だからこそ、私たちの研究には国際的な責務と使命があると考えています。本受賞は、これまでの成果への評価であると同時に、より一層の科学的探究と社会実装への期待であると受け止めています。
今後も、デジタルヘルスによる産官学連携型健康寿命延伸プロジェクト、認知症などスティグマを有しやすい障害に対する社会的包摂に関するプロジェクトなど、基礎・臨床・公衆衛生・デジタルヘルスを統合した学際的アプローチを推進し、エビデンスに基づく介入と実装研究を通じて、高齢者一人ひとりの健康寿命延伸とWell-beingの向上に貢献していきたいと考えております。