ニュース
実践的に学ぶ
2026.02.05
上久保誠人教授の最新の論考がEAST ASIA FORUMに掲載されました。
上久保誠人教授の最新の論考がEAST ASIA FORUMに掲載されました。
オーストラリア国立大学(ANU)のクロフォード公共政策大学院に拠点を置く、アジア太平洋地域の分析プラットフォームです。単なるニュースサイトではなく、学術的背景に基づいた質の高い論評を専門家(学者、政策立案者、元外交官など)が発信する場です。
2月8日に日本が投票に臨む中、私は突然の総選挙が繰り返されるサイクルが民主的な説明責任を損ない、日本を「期待に基づく」政治の世界に閉じ込めていると論じます。全文はこちらでお読みいただけます。
https://eastasiaforum.org/2026/02/04/snap-elections-lock-japan-in-a-cycle-of-fragile-promises/
2025.10.29
吉田ゼミがウォーカブルシティを考える路上イベント「みちクル」に参加しました
側道の催し物スペースを利用した路上ゼミの風景
茨木市の「ツーコア・ワンパーク政策」には、阪急茨木市駅とJR茨木駅を2つの「コア」、元茨木川緑地公園一帯を1つの「パーク」と位置付け、それらにつながる交通を有機的に結びつけることで、コンパクトシティ化を進める狙いがあります。ゆくゆくは一方通行の自動車道を設けて、歩道や自転車道の幅を広くしようという構想もあります。
2025年10月25日午後、政策科学部吉田ゼミのメンバーと教員が集まり、最初に茨木市都市政策課職員さんから「ツーコア・ワンパーク政策」の意図と社会実験みちクルの実施状況が説明されました。ポスター展示では、2024年度PSエキスポで表彰された学生論文「中心市街地活性化に向けた駅間商業地の回遊性向上に関する政策的アプローチ分析」の紹介があり、また2024年度地域デザイン調査で考案されたまちづくり提案「地域に溶け込む学生寮」、「まちなか立ち寄り・サク飲みプロジェクト」、「響き合う知と感性の瑞雲空間」の紹介もありました。
後半の討論では、ゼミ生から2つのクエスチョンが提示され、少人数のグループで質疑応答や意見交換が行われました。クエスチョンは「JR⇔阪急 お互いにわざわざ行くん?どないしたらよう行くんかね?」、「2Core1Parkは茨木市の地震の際の防災機能を高めるか?」でした。学生同士の活発な質疑応答が展開し、まるで「路上ゼミ」、「青空ゼミ(曇天ゼミ?)」という状況でした。あいにく途中から雨天となりましたが、ゼミを終えた学生諸君は地域経済に貢献するため、バル参加店舗で夕食をとって懇親を深めました。

学生同士の活発な路上ディスカッション(茨木市役所提供)

催し物スペースの設営風景(金相憲提供)
2025.10.8
角本ゼミ集中セミナーが、「AI・デジタル技術による社会課題への法政策的アプローチ」をテーマとして民間企業のヒアリング調査等を実施しました
ソフトバンク本社
セイコータイムクリエーション株式会社へのヒアリング
株式会社電通
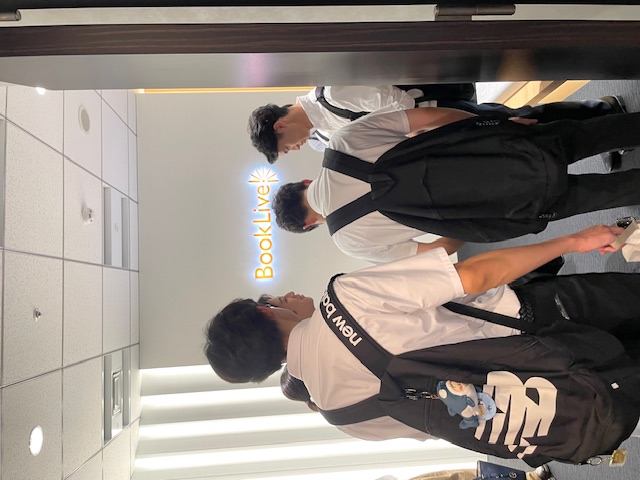
株式会社BookLiveへの訪問

BookLive子会社が運営するWeb漫画サイトで連載中の漫画キャラクター パグ太郎
株式会社Sapeetへのヒアリング
合同会社ネコリコへのヒアリング
viviONが手掛けるVTuberグループ『あおぎり高校』
得津教授による講義

懇親会の様子

懇親会の様子
2025.09.17
小田ゼミが集中セミナーとして在日パキスタン大使館を訪問しました
Abdul Hameed大使と小田教授
意見交換の様子
2025.09.09
研究実践フォーラム「南信州プロジェクト」が実施されました
フィールドとなった南信州・飯田市の天竜峡
飯田市街地のまち歩き(ソーシャルキャピタル・フィールドスタディ)
事例調査:子育てサロン・NPO法人おしゃべりサラダ(ソーシャルキャピタル・フィールドスタディ)

飯田市役所での移住政策のヒアリング

旧飯田測候所での移住コンシェルジュとの対話

空き家を改修した天竜峡の「HIGASA」での説明

遠山郷で地域おこし協力隊へのヒアリング
- 他大学の学生や地元高校生と行ったフィールドスタディは、普段の授業では味わえない刺激的な学びの連続だった。インタビューや体験を通して人の温かさやつながりを実感し、飯田の皆さんに「また会いたい」と思えた、学びだけでなく人との関わり方の大切さを感じることができた6日間だった。(濱谷さん)
- フィールドスタディでは、その土地に住む現地の高校生の視点や他大学の学生の様々な考えを交えながら、飯田市の活動について深く学べたため、とても貴重な経験となった。近年、各地で地域の人々の交流は薄くなっているが、飯田の人々は人との繋がりを大切にしているからこそ、たくさんの活動が行われているのだと現地で学ぶことができた。(畑さん)
- この夏、南信州プロジェクトに参加できたことは、私にとって有意義で多くの学びを得ることのできるものでした。飯田市の文化を守る強い思い、人とのつながりから生まれる移住のサイクル、ソーシャルキャピタルを発端とした市民活動など、これらはただのキーワードにしかすぎませんが、文献などを読んでいるだけでは得られないことを現地で肌に感じながら学ぶことができました。また、他大学の学生や現地の高校生とのグループワークが基本となるので、普段の大学生活では得られない刺激をもらうこともできました。このように、南信州プロジェクトは、普段の座学とは一味違ったことを学べる良い機会であったと私は、思います。(壽さん)
- 飯田市での調査を通じて学んだことは、「人とのつながり」の重要性である。飯田市では、困っている人がいれば、その分野に詳しい人が知人の紹介で支援する事例が見られた。こうした「人とのつながり」が市全体の活気を生み出しているのだと考える。(早瀬さん)
- 学輪フィールドスタディ、飯田市での独自調査どちらにおいても有意義な時間を過ごせました。文献を読むだけでは得られない知識がつくだけでなく、グループでひとつの目標に取り組む難しさや楽しさといった今後の社会生活に活かせるような経験ができる機会だと思います。(田中さん)
旧木沢小学校(遠山郷)
2025.07.17
上久保誠人教授が大和日英基金主催ウェビナーに出演
上久保誠人教授が、参院選後の日本政治の展望について、国際ウェビナーで講演を行います。主催は英国・ロンドンを拠点とする大和日英基金で、本講演は全世界へ向けたオンライン配信となります。視聴には事前登録が必要です。
-
テーマ:「参院選後の、日本の大衆迎合主義と新しい政治的分断」
(Populism and New Political Divisions in Japan after the Election) -
日時:2025年7月30日(水) 20:00(日本時間)/12:00(英国時間)
-
主催:大和日英基金(The Daiwa Anglo-Japanese Foundation)
-
使用言語:英語
-
開催形式:オンライン(要事前登録)
2025.03.07
世界自然遺産 知床の自然情報誌「SEEDS」に政策科学部の実習が紹介されました
2024.10.25
研究実践フォーラム「カナダ・プロジェクト」が実施されました Part2
トロント
現在のトロント本願寺

ガイダンスの様子(3階スペースにて)

ガイダンスの様子(本堂にて)

High Parkのようす

High Park内のリス

利用者に協力を呼び掛ける看板

High Park内の山峡

Downtown Yongeの様子

Downtown Yongeで食べたタイ料理
<CN Tower>
CNタワーはカナダ(トロント)のシンボルとも言える都市と国の歴史的、文化的象徴です。電波塔ですが、展望台やレストラン、アクティビティもあり観光地として有名です。また、CNタワー周辺は、シンボルのCNタワーを中心にリプレイ水族館やロジャースマーケット等があり、子供から大人まで多くの観光客がいました。
<Central Market>
CNタワーから少し離れたところにはセントローレンスマーケットというたくさんのお店が並ぶ屋内マーケットもありました。食材やお土産はもちろん、サンドイッチやエスニック料理でランチを食べることもできるため、様々な楽しみ方ができます。トロントに行った際には是非訪れてほしいスポットです。多くのスポットがあり、街中も華やかな都市部と言えるトロントは、最終滞在場所にぴったりだったと感じられました。

CNタワー

セントローレンスマーケットの様子
<トロントで印象に残ったこと>
私はトロントで印象に残ったこと2つについて書いていきます。
まず、トロントに滞在して2日目の朝の城戸先生による観光ツアーです。この日はお昼までは自由時間であったため、希望者のみこのツアーに参加しました。この日の参加者は私と友人1人で、城戸先生の出身校であるトロント大学と、コリアンタウンを訪れました。トロント大学には塀がなく、街に溶け込んでおり、これは立命館大学との共通点とも言えるでしょう。また、コリアンタウンに入ると、雰囲気がガラリと変わったことも印象的でした。コリアタウンではお昼ご飯にビビンバをいただきました。補足ですが、カナダでは食べきれなかった食材を持ち帰ることができます。これは環境保全の観点からも非常に画期的であると考えました。
コリアンタウンで筆者が食べたビビンバ
トロント大学内の様子

トロント大学内にいたリス

Rodney Haddow名誉教授とのミーティングの様子
2024.10.25
研究実践フォーラム「カナダ・プロジェクト」が実施されました Part1
モントリオール

モントリオール・ノートルダム聖堂

リトルイタリー ジャン・タロン市場

ICAOモントリオール本部

会議室
オタワ






ナイアガラ




執筆者:小田原、加藤、吉岡
2024.10.11
北海道の知床で環境、教育、観光をテーマに実習をしました

政策科学部の集中セミナー(桜井良ゼミ3回生)が、北海道の知床世界自然遺産地域で2024年9月9日から13日まで行われました。政策科学部の卒業生である知床財団の職員のガイドのもと、学生はヒグマが生息する森を歩き、野生動物と共存することの難しさや可能性を学びました。また世界自然遺産地域に隣接する斜里町立知床ウトロ学校で交流会を開き、ゼミ生が地元の小中学生や保護者に対して、勉強することの意味や大学生活について発表し、話し合いました。学生は、子どもたちの目線に立ってコミュニケーションをとることの大切さを学んだようです。
最終日には知床でホテル業を営む北こぶしリゾートと連携しワークショップを開催し、自然共生社会の実現に向けて、観光業にどのような役割が求められているのか、ゼミ生、北こぶしリゾート職員、そして地元の大学生(北見工業大学、東京農業大学[北海道オホーツクキャンパス])が議論しました。

