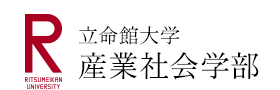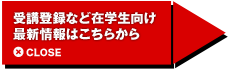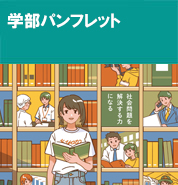プロフェッショナルに学ぶ
専門特殊講義Ⅱ
「エンタテインメント・ビジネス産業論」
2015年度大学コンソーシアム京都単位互換科目
(音楽関連団体共同寄附講座)
三枝 照夫(本学客員教授)
科目の概要
デジタル技術の進化とともに、映像(映画・アニメ)、音楽、書籍等の制作・流通を担うコンテンツ産業は新たな局面を迎えています。この産業は、他産業への波及効果も高く、成長の可能性のある産業であることから、世界各国がしのぎを削って競っています。また、エンタテインメント業界は、クールジャパンという世界において日本の文化がどのように発信され位置付けられているのかということにも貢献しています。これら国際的規模の動向を踏まえつつ、2015年度はエンタテインメント・ビジネスの基本をしっかりと勉強する1年とします。それぞれの分野で活躍している方々を講師とし、文化とエンタテインメントにおける現状と課題を探っていき、その最前線を業界の方々と共に考えていくこととします。
2015年度の講師・講義テーマ
(前期・後期各15回/講師・テーマラインアップは毎年変更されます)
【前期】
| 講師 | テーマ |
|---|---|
| 藤本草 氏(公益財団法人日本伝統文化振興財団 会長) |
日本の伝統音楽の基礎知識 |
| shungo.氏(作詞家、音楽プロデューサー) |
プロデュース能力の醸成 |
| 原口あきまさ 氏(ものまねタレント・北九州市観光大使) |
演者側からのエンタテインメント |
| 谷口元 氏(一般社団法人日本音楽出版社協会 専務理事) |
日本と世界の著作権事情(仮) |
| 小林和之 氏(株式会社ワーナーミュージック・ジャパン 代表取締役会長兼CEO) |
レーベルとは!(仮) |
| 西山勝 氏(株式会社エフエム大阪 常務取締役) |
ラジオと音楽(仮) |
| 元尾哲也 氏(株式会社スポーツニッポン新聞社 執行役員 東京本社 編集局編集総務 特集プロジェクトチーム担当) |
情報伝達の仕組み(仮) |
| 野辺優子 氏(合資会社エスポルト コーディネーター(映画)) |
アジア、ヨーロッパの映画事情(仮) |
| 中西健夫 氏(株式会社ディスクガレージ 代表取締役社長/一般社団法人コンサートプロモーターズ協会 会長) |
コンサートビジネスの現状と未来(仮) |
| 加藤裕一 氏(株式会社レコチョク 代表執行役社長) |
音楽、映像配信の今後(仮) |
| 中尾豊治 氏(株式会社さいたまアリーナ 代表取締役社長) |
イベント施設の今後の有り様(仮) |
| 松武秀樹 氏(一般社団法人演奏家権利処理合同機構MPN 副理事長/株式会社ミュージックエアポート 代表取締役社長) |
今、求められている音楽制作とは?(仮) |
| 椎名和夫 氏(一般社団法人演奏家権利処理合同機構MPN 理事長) |
音楽制作の現場(仮) |
【後期】
| 講師 | テーマ |
|---|---|
| 佐々木史朗 氏(株式会社フライングドッグ 代表取締役社長) |
アニメ音楽のプロデュースとビジネス展開 |
| 大澤信博 氏(株式会社EGG FIRM 代表取締役) |
アニメーション・プロデュースの全体像と企画・マーケティングの重要性 |
| 石塚真一 氏(漫画家) |
漫画の核心 |
| 白井勝也 氏(株式会社小学館 最高顧問) |
コンテンツのマルチ展開 |
| 堀口瑞予 氏(COMMUNICATION Design 代表) |
実践!すぐに役立つ ビジネスコミュニケーション・スキル |
| 堀義貴 氏(株式会社ホリプロ 代表取締役社長) |
プロダクションの事業展開 |
| 二村恒元 氏(元JVCエンタテインメント株式会社 常務取締役) |
著作権アラカルト |
| 片岡尚 氏(株式会社エフエムナックファイブ 常務取締役放送本部長) |
地方メディアとしてのラジオ |
| 野辺優子 氏(合資会社エスポルト コーディネーター(映画)) |
映画と音楽(仮) |
| 福原徹 氏(邦楽囃子笛方) |
笛の歴史(仮) |
| 鈴木しょう治 氏(企画制作プロデューサー、DJ) |
クラブミュージックの変遷(仮) |
| 國津洋 氏(株式会社第一興商 執行役員 経営企画部長兼社長室長) |
カラオケ業界の規模と今後(仮) |
| 反畑誠一 氏(音楽評論家) |
2016年のスーパースター |
授業の特徴
この講座は、2004年度に「音楽著作権ビジネス」を主テーマとした(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)からの寄附講座として開設されました。東京中心だった産学共同による研究講座が関西で初めて開講したのです。在校数が日本一を誇る京都における(財)大学コンソーシアム京都の「単位互換制度」が評価されたからです。2009年度からは、音楽関連団体による共同寄附講座として支援を受け、音楽、エンタテインメント業界のみならず、放送・出版メディア、コンテンツクリエーターなど、各分野の第一線で活躍されている方々が講師を務めるオムニバス形式の講義が行われてきました。
講義では、グローバルな環境下における日本のコンテンツ産業・文化の現状とデジタル技術との相関関係を基に、普段は接することが出来ないような講師陣が講義を行います。講義を通じて、地球規模で展開するデジタルコンテンツの最前線を学びながら、音楽産業のみならずクリエイティブなコンテンツ産業に関連する分野で活躍する人材を輩出し、さらに次代を担う人材育成の実務学習の役割も果たしました。今年度も未来志向の先端的なエンタテインメント産業の実践を学びます。
受講者へのメッセージ
この講座には、産業・社会学全般、知財経営学、メディア運営学、情報心理学などの多角的な観点があります。講義では、授業形式によりクリエイティブ産業の基本的な課題を見つけ、国際的規模で展開する日本のコンテンツ産業の現状について実務的かつアカデミックに学習することが理想です。このような分野について、体系的に思考が出来るのは、大学という学びのコミュニティならではのことと考えられます。
受講生にとっては、クリエイティブ産業の最前線で活躍されている第一人者からの講義は、専門知識の体得と針路を構築していく絶好の機会です。大学で学ぶということは、自らが主体的に考え、それを計画し、実行するということです。さらにこの授業を受講することで、自己を直視し将来の進路を視野に、日常生活と学びを結びつけていくことを期待しています。