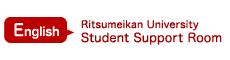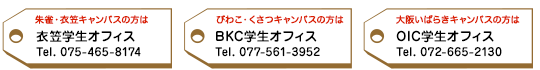2012.08.20
金環日食とヒッグス粒子から -世界や自分について考える
少し前の話題になりますが、今年5月21日に金環日食がありました。見た人も多いと思います。午前7時半ごろに日食が最大になったので、いつもは足早の通勤途中の人も少し立ち止まって見ていたり、子どもからお年寄りまで、たくさんの人が、わぁっ、と日食の様子に見入っていました。
今回のように広範囲で観測されたのは1080年(平安時代)以来、今度今回のような規模で日食が起こるのは300年後、とのことでしたが、そう聞いて、遠い昔の平安時代や未来を想像した人もいたのではないでしょうか。
はるか太古の昔から日食は起こっていて、この神秘的な現象を目の当たりにすると、目先の時間に追われて暮らしている日常の自分の時間とは違う、ゆったりとした時間が宇宙には流れている感じがしました。
もちろん金環日食は美しかったですが、普段は光り輝く太陽が昼間に隠れるのは、私は恐ろしくもありました。日食は太陽が「怪物に食べられる結果生ずる」ものであるとか、「世の終わり」を表すものとも考えられてきたようです(アト・ド・フリース(1974、邦訳1984)『イメージ・シンボル事典』)。平安時代の人は日食をどう捉えていたのでしょうね。
また今年7月4日には、ヒッグス粒子とみられる新粒子が発見された、という報道がありました。私は専門的なことはわかりませんが、ヒッグス粒子はこの世のあらゆるものに質量を与えたと考えられる素粒子のようです。私達の眼には見えないけれど、そのような粒子の働きで身の回りにある物が質量を持てているというのは、不思議な感じがしました。
金環日食やヒッグス粒子に触れて、こういうことが起こるのか、と、普段あまり考えずに暮らしているこの世界のそもそもの成り立ちについて考えさせられました。
世界の成り立ちについて考える、というと、大それたことのように感じられるかもしれませんが、小さい頃、“宇宙の果てはどうなっているんだろう、どんな世界なんだろう”など、少しでも考えたことがある人は割合いるのではないでしょうか。
世界の成り立ちについて考えることは、どこか、その世界の中に生きる自分について考えることともつながっているように思います。思春期の頃、“この世界はどうしてあるんだろう”とか、“なぜ、他の時代ではなくて今の時代に自分は生きてるんだろう”、“なんで自分は自分として生まれたんだろう”と自分や世界について考えたことがある人もいるのではないでしょうか。考える程度はさまざまでしょうが、このような問いは、これまでの自分にとっては当たり前で疑問にも思わなかったことに対して疑問を投げかけることでもあるので、自分というものが揺らがされ、不安な気持ちになったりすることでもあります。
世界や自分について考えるのは、しんどいこともありますし、普段の生活ですぐに何かの役に立つことではないかもしれませんが、自分という存在の大事なところに触れることだと思います。普段の生活は慌しかったりしますが、宇宙の時間など普段の生活とは異なる時間の流れを感じながら、少し立ち止まって、世界や自分について考えてみるのも時にはあってもいいのかもしれない、と思いました。
今回のように広範囲で観測されたのは1080年(平安時代)以来、今度今回のような規模で日食が起こるのは300年後、とのことでしたが、そう聞いて、遠い昔の平安時代や未来を想像した人もいたのではないでしょうか。
はるか太古の昔から日食は起こっていて、この神秘的な現象を目の当たりにすると、目先の時間に追われて暮らしている日常の自分の時間とは違う、ゆったりとした時間が宇宙には流れている感じがしました。
もちろん金環日食は美しかったですが、普段は光り輝く太陽が昼間に隠れるのは、私は恐ろしくもありました。日食は太陽が「怪物に食べられる結果生ずる」ものであるとか、「世の終わり」を表すものとも考えられてきたようです(アト・ド・フリース(1974、邦訳1984)『イメージ・シンボル事典』)。平安時代の人は日食をどう捉えていたのでしょうね。
また今年7月4日には、ヒッグス粒子とみられる新粒子が発見された、という報道がありました。私は専門的なことはわかりませんが、ヒッグス粒子はこの世のあらゆるものに質量を与えたと考えられる素粒子のようです。私達の眼には見えないけれど、そのような粒子の働きで身の回りにある物が質量を持てているというのは、不思議な感じがしました。
金環日食やヒッグス粒子に触れて、こういうことが起こるのか、と、普段あまり考えずに暮らしているこの世界のそもそもの成り立ちについて考えさせられました。
世界の成り立ちについて考える、というと、大それたことのように感じられるかもしれませんが、小さい頃、“宇宙の果てはどうなっているんだろう、どんな世界なんだろう”など、少しでも考えたことがある人は割合いるのではないでしょうか。
世界の成り立ちについて考えることは、どこか、その世界の中に生きる自分について考えることともつながっているように思います。思春期の頃、“この世界はどうしてあるんだろう”とか、“なぜ、他の時代ではなくて今の時代に自分は生きてるんだろう”、“なんで自分は自分として生まれたんだろう”と自分や世界について考えたことがある人もいるのではないでしょうか。考える程度はさまざまでしょうが、このような問いは、これまでの自分にとっては当たり前で疑問にも思わなかったことに対して疑問を投げかけることでもあるので、自分というものが揺らがされ、不安な気持ちになったりすることでもあります。
世界や自分について考えるのは、しんどいこともありますし、普段の生活ですぐに何かの役に立つことではないかもしれませんが、自分という存在の大事なところに触れることだと思います。普段の生活は慌しかったりしますが、宇宙の時間など普段の生活とは異なる時間の流れを感じながら、少し立ち止まって、世界や自分について考えてみるのも時にはあってもいいのかもしれない、と思いました。
学生サポートルームカウンセラー
2012.06.30
駅前の不動産屋さんで
先日,南草津駅近くの道を歩いていたら,不動産屋さんがあって,立命館大学生向けと思われる大きな看板が立ててありました。それは,今住んでいる部屋から別の部屋へ引っ越すことを考えてみませんか?と誘う内容のもので,その理由としてふたつのことが掲げてありました。(一字一句は覚えていませんが)一つ目は「大学が思ったより遠かった!」というもの。これは納得です。毎日通う訳ですから,より近いに越したことはありません。2回生になる時とか,大学院に進学が決まった時とか,いろんな節目で多くの人が一度は考えそうな理由です。
そして二つ目が「仲の良い友だちの部屋がすぐ近くだった!」。これは一瞬,反対の意味に取ってしまい,友だちの近くに引っ越したいということかと思って危うくびっくりしかけましたが,そうではなくて,友だちと距離を取りたいということですね。どちらかというと,こちらの方が納得はできます。プライベートはしっかり守りたいということでしょう。でも,せっかく仲の良い友だちなんだから,わざわざ引っ越ししてまで距離を取らなくても…という気もします。
特に僕は臨床心理士としてサポートルームでカウンセリングの仕事をする中で,「友だちができない」という悩みをたくさん,たくさん聴いてきたので,この宣伝文句には,なおさら印象深いものがあったのです。友だちって,作るのも大変だけど,出来たら出来たで,いろいろ気を遣うことがあるなあと。人と人との間の距離の取り方というのは人間にとって永遠の悩みの種ですね。
ここから先は想像ですが,このように引っ越しをしてまで距離を取ろうとする友だちとも,例えばTwitter上ではリアルタイムにつながっていないとダメ,とかあるのではないでしょうか?Twitterはフォローする/しないの二択ですから,サッパリしているとも言えますが,mixiやFacebookとかになると設定もけっこう複雑にしようと思えば出来るので,これまたいろいろ気を遣うことがありそうです。実際,ネット上での友人(たち)とのトラブルや,そこで生まれた不信感といった話も,カウンセリングの中でよく出てくる話題のひとつです。
大まかにいえば,リアルな(物理的な)世界では,きちんとした距離を取ってプライバシーを厳重に守りつつ,ネット上の(電子的な)世界では,出来る限りリアルタイムでつながっていたい(いないとまずい)というのが,多くの人たちの感じていることではないでしょうか。ネット上では発信する情報を意識的にコントロールできるというのが大きなポイントなのではないかと思われます。
僕は評論家ではないので,こういった世の中の動きを,道徳的・教育的(その他,何的にでも)良いとか悪いとかで判断するのではなくて,こういった動きが今後,人の心にどういった変化をもたらすのだろう,ということを注意深く見ていきたい,そして「面白そう」と思ったら自分も参加していきたい,と考えています。ただ,良かれ悪しかれ,いろいろ複雑になっているのは確かなようで,その複雑さにどう対処するかというところに,その人その人の個性が表れる,ということは言えそうです。
一方で,場所と時間を決めて,(物理的に)面と向かって,一対一で話し合うという,今となってはたいへん古風なカウンセリングの方法を,これからも大切にしていきたいと思っています。
学生サポートルームカウンセラー
そして二つ目が「仲の良い友だちの部屋がすぐ近くだった!」。これは一瞬,反対の意味に取ってしまい,友だちの近くに引っ越したいということかと思って危うくびっくりしかけましたが,そうではなくて,友だちと距離を取りたいということですね。どちらかというと,こちらの方が納得はできます。プライベートはしっかり守りたいということでしょう。でも,せっかく仲の良い友だちなんだから,わざわざ引っ越ししてまで距離を取らなくても…という気もします。
特に僕は臨床心理士としてサポートルームでカウンセリングの仕事をする中で,「友だちができない」という悩みをたくさん,たくさん聴いてきたので,この宣伝文句には,なおさら印象深いものがあったのです。友だちって,作るのも大変だけど,出来たら出来たで,いろいろ気を遣うことがあるなあと。人と人との間の距離の取り方というのは人間にとって永遠の悩みの種ですね。
ここから先は想像ですが,このように引っ越しをしてまで距離を取ろうとする友だちとも,例えばTwitter上ではリアルタイムにつながっていないとダメ,とかあるのではないでしょうか?Twitterはフォローする/しないの二択ですから,サッパリしているとも言えますが,mixiやFacebookとかになると設定もけっこう複雑にしようと思えば出来るので,これまたいろいろ気を遣うことがありそうです。実際,ネット上での友人(たち)とのトラブルや,そこで生まれた不信感といった話も,カウンセリングの中でよく出てくる話題のひとつです。
大まかにいえば,リアルな(物理的な)世界では,きちんとした距離を取ってプライバシーを厳重に守りつつ,ネット上の(電子的な)世界では,出来る限りリアルタイムでつながっていたい(いないとまずい)というのが,多くの人たちの感じていることではないでしょうか。ネット上では発信する情報を意識的にコントロールできるというのが大きなポイントなのではないかと思われます。
僕は評論家ではないので,こういった世の中の動きを,道徳的・教育的(その他,何的にでも)良いとか悪いとかで判断するのではなくて,こういった動きが今後,人の心にどういった変化をもたらすのだろう,ということを注意深く見ていきたい,そして「面白そう」と思ったら自分も参加していきたい,と考えています。ただ,良かれ悪しかれ,いろいろ複雑になっているのは確かなようで,その複雑さにどう対処するかというところに,その人その人の個性が表れる,ということは言えそうです。
一方で,場所と時間を決めて,(物理的に)面と向かって,一対一で話し合うという,今となってはたいへん古風なカウンセリングの方法を,これからも大切にしていきたいと思っています。
2012.05.31
つれづれ映画評
第一回「この森で、天使はバスを降りた」
先日、夜遅く一人で観た映画が心に残っているので、そのことを書きます。
その映画はタイトルを「この森で、天使はバスを降りた」といって、’98年(日本国内)リリースとやや古い作品なのですが、そのあまりに透明感あふれるタイトルに気圧されてこれまでは手に取ることができませんでした。観たい観たいとは思っていたのですがついスルーしてきたのです。しかし歳をとって少し鈍感になってきたのか、今回ようやく恥ずかしがらずにレンタルできました。
しかし驚いたことに、作品本編は邦題が漂わせる透明感とは全く別のところで勝負していました。冒頭のシーンによく表れていると思うのですが、それは“淡々とした電話の受け答え、機能性の低そうな事務室、たばこの煙”という、とてもタイトでソリッドな要素で構成されています。その後も実に重くシリアスな展開が用意されていて、天使とか森とかいう言葉に備えていた心をどんどん裏切ってくれます。と言って昨今の映画にありがちな、無駄に残虐だったり陰鬱だったりする作りではありません。むしろ登場人物の多くは少しでも良い生活をと望んでいるのに、なぜか少しずつ事態が良からぬ方に進むという昔ながらのメロドラマ的な作り方をしています。
前回のコラムで「自分はこれでよいという感覚を獲得して社会に出ていくこと」という言葉がありました。その意味で、この映画はとても悲しい作品です。登場人物の多くが、自分はこのままでよいと思うことができないでいるのです。舞台は米国メイン州の小さな寂れた町ですが、そこに流れ着いた主人公はたやすく人には喋れない秘密を抱えていて、何とか人生をやり直そうとしています。彼女は町の保安官のはからいでとある軽食堂(その名前が”Spitfire Grill”と言い、これが本来の映画タイトルにもなっています)に住み込みで働くことになるのですが、その店の女主人もまた人に言えない秘密を持っています。町自体がそもそも、このままでは寂れる一方なのにこれという産業が何もないという、閉塞感や無力感を抱えているのです。
このままではいけない。今の自分を認めることができない。そういった罪の意識にも似た悲しみがこの作品の奥底に流れています。淡々とした展開の中で時折その流れが表に出てくるのですが、なかなか解決には至らないまま物語はクライマックスへと向かいます。エンディングについては賛否両論あると思うのですが、それは、誰にとってもいくつになっても、ありのままの自分でよいと認めることがいかに難しいかを伝えているのかもしれません。
これだけ書くと何だか堅苦しい映画に思われてしまいそうです。まあ、だからふわっとした邦題にしたんでしょうね。けれどもこの作品は老若男女を問わず、自分の今のあり方について考えてみたい人にはお勧めの映画です。機会があれば、ぜひ手に取ってみてください。
「この森で、天使はバスを降りた」”The Spitfire Grill”
監督:リー・デヴィッド・ズロトフ
キャスト:アリソン・エリオット エレン・バースティン ウィル・パットン他
その映画はタイトルを「この森で、天使はバスを降りた」といって、’98年(日本国内)リリースとやや古い作品なのですが、そのあまりに透明感あふれるタイトルに気圧されてこれまでは手に取ることができませんでした。観たい観たいとは思っていたのですがついスルーしてきたのです。しかし歳をとって少し鈍感になってきたのか、今回ようやく恥ずかしがらずにレンタルできました。
しかし驚いたことに、作品本編は邦題が漂わせる透明感とは全く別のところで勝負していました。冒頭のシーンによく表れていると思うのですが、それは“淡々とした電話の受け答え、機能性の低そうな事務室、たばこの煙”という、とてもタイトでソリッドな要素で構成されています。その後も実に重くシリアスな展開が用意されていて、天使とか森とかいう言葉に備えていた心をどんどん裏切ってくれます。と言って昨今の映画にありがちな、無駄に残虐だったり陰鬱だったりする作りではありません。むしろ登場人物の多くは少しでも良い生活をと望んでいるのに、なぜか少しずつ事態が良からぬ方に進むという昔ながらのメロドラマ的な作り方をしています。
前回のコラムで「自分はこれでよいという感覚を獲得して社会に出ていくこと」という言葉がありました。その意味で、この映画はとても悲しい作品です。登場人物の多くが、自分はこのままでよいと思うことができないでいるのです。舞台は米国メイン州の小さな寂れた町ですが、そこに流れ着いた主人公はたやすく人には喋れない秘密を抱えていて、何とか人生をやり直そうとしています。彼女は町の保安官のはからいでとある軽食堂(その名前が”Spitfire Grill”と言い、これが本来の映画タイトルにもなっています)に住み込みで働くことになるのですが、その店の女主人もまた人に言えない秘密を持っています。町自体がそもそも、このままでは寂れる一方なのにこれという産業が何もないという、閉塞感や無力感を抱えているのです。
このままではいけない。今の自分を認めることができない。そういった罪の意識にも似た悲しみがこの作品の奥底に流れています。淡々とした展開の中で時折その流れが表に出てくるのですが、なかなか解決には至らないまま物語はクライマックスへと向かいます。エンディングについては賛否両論あると思うのですが、それは、誰にとってもいくつになっても、ありのままの自分でよいと認めることがいかに難しいかを伝えているのかもしれません。
これだけ書くと何だか堅苦しい映画に思われてしまいそうです。まあ、だからふわっとした邦題にしたんでしょうね。けれどもこの作品は老若男女を問わず、自分の今のあり方について考えてみたい人にはお勧めの映画です。機会があれば、ぜひ手に取ってみてください。
「この森で、天使はバスを降りた」”The Spitfire Grill”
監督:リー・デヴィッド・ズロトフ
キャスト:アリソン・エリオット エレン・バースティン ウィル・パットン他
学生サポートルームカウンセラー
2012.3.26
大学生とカウンセリング
みなさんはカウンセリングという言葉にどんなイメージを持っているでしょうか。「カウンセリング=精神的な病気の治療」と思っている人がいますが、カウンセリングで扱うのは、病気というよりもさまざまな心理的課題です。
青年期後期にあたる大学時代は、モラトリアム(猶予)と言って、自己形成のための試行錯誤が許される時期と考えられています。試行錯誤を経て「自分はこれでよい」という感覚を獲得して社会に出て行くことが青年期後期の課題で、このような感覚が根づくことをアイデンティティの確立と言いますが、大学生のカウンセリングでは、ほとんどの場合、この青年期的課題が関わってきます。
カウンセリングは、よくないところを治してもらうとか、解決方法を教えてもらうとかいったものではなく、自分で自分を見つめ、自分で課題と取り組むのをカウンセラーに手伝ってもらうことだと言えます。話をすることで自分を振り返り、少しずつ自力で前に進んで行く、そういう成長力が人間には備わっているのです。
自分について人に話すのは、自分では分かりきったことを人に伝える作業だと思うかも知れません。しかし、私たちは自分自自身についてそれほど分かっていないことが少なくありません。人に話すことには、まず、自分について人に伝えようとすることで、漠然としていたものがはっきりするという効用があります。
もうひとつの効用は、相手に分かってもらえると、「自分ひとりで悩んでいるのではない」と感じ、孤立感がやわらぐことです。そうして気持ちにゆとりが生まれると、上で述べた成長力が活動しやすくなるのです。
自分自身に関心が向く大学時代はカウンセリングに適した時期です。あなたも、自分の成長のためにカウンセリングを試してみてはいかがですか?
青年期後期にあたる大学時代は、モラトリアム(猶予)と言って、自己形成のための試行錯誤が許される時期と考えられています。試行錯誤を経て「自分はこれでよい」という感覚を獲得して社会に出て行くことが青年期後期の課題で、このような感覚が根づくことをアイデンティティの確立と言いますが、大学生のカウンセリングでは、ほとんどの場合、この青年期的課題が関わってきます。
カウンセリングは、よくないところを治してもらうとか、解決方法を教えてもらうとかいったものではなく、自分で自分を見つめ、自分で課題と取り組むのをカウンセラーに手伝ってもらうことだと言えます。話をすることで自分を振り返り、少しずつ自力で前に進んで行く、そういう成長力が人間には備わっているのです。
自分について人に話すのは、自分では分かりきったことを人に伝える作業だと思うかも知れません。しかし、私たちは自分自自身についてそれほど分かっていないことが少なくありません。人に話すことには、まず、自分について人に伝えようとすることで、漠然としていたものがはっきりするという効用があります。
もうひとつの効用は、相手に分かってもらえると、「自分ひとりで悩んでいるのではない」と感じ、孤立感がやわらぐことです。そうして気持ちにゆとりが生まれると、上で述べた成長力が活動しやすくなるのです。
自分自身に関心が向く大学時代はカウンセリングに適した時期です。あなたも、自分の成長のためにカウンセリングを試してみてはいかがですか?
学生サポートルーム副室長
応用人間科学研究科 教授
徳田完二
応用人間科学研究科 教授
徳田完二