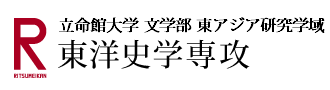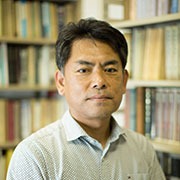古代・中世史ゼミ
授業紹介
このゼミは、太古から唐末五代までの諸問題を卒業論文で取り上げようとする学生を対象としています。ゼミの目標は、3回生は自分の卒業論文で考察する具体的課題の設定、4回生は卒業論文の完成です。そのために、受講生は半期に一回個人発表を行います。3回生前期では自分の興味関心のあるテーマに関する先行研究を整理・検討することでそのテーマを巡る研究上の問題点を確認し、3回生後期と4回生では自身の卒論研究の途中経過を発表します。他の学生・院生(このゼミには大学院生も特別参加)・教員の指摘や助言を踏まえて手直しし、自身の研究の完成度を高めてゆきます。
噂ではこのゼミが東洋史学専攻の中で一番厳しいそうですが、一番鍛えられるゼミであることは確かでしょう。一回の授業での発表者は一人だけで、発表後の時間は質疑応答を行います。発表者以外の受講生にも発表内容に関する質問が義務づけられていて、質疑応答で不充分な発言をすると却下され質問・回答のやり直しになることもあります。そうやって2年間をこのゼミで過ごすと、就職面接でどんな質問がきても的確に答えられるようになるし、圧迫面接など屁とも思わなくなるそうです(過年度卒業生の談)。
このゼミは、研究力だけでなく、逞しく生きる力をも養成するゼミなのです。
過去の卒業論文のテーマ
- 殷代における青銅矛の変遷について
- 殷墟甲骨文の特殊十干称謂の整理と研究
- 古文字「雹」の考釈
- 春秋期の会盟事例から見る陳の国際的な立ち位置
- 銀雀山漢墓竹簡孫子の整理小組の再検討
- 呂不韋伝に関する一考察
- 『史記』と『漢書』における游侠
- 前漢末王氏政権における元后
- 画像石に描かれた動物からみる地域の思想の類似点と相違点
- 公孫氏政権の歴代当主の性格に関する考察
- 蜀の北伐に関して
- 八王の乱勃発の原因について
- 前秦苻堅政権期における宗室的軍事封建制に関する考察
- 魏収による河東薛氏の評価についての考察
- 隋代の国際関係―開皇元年~開皇4年の対突厥政策について
- 煬帝の行動からみる隋代洛陽の都市機能について
- 隋唐長安城の禁苑について
- 七世紀新羅の真骨貴族内の派閥及びその対立の実態
- 中華王朝で生活したソグド人の実態について
- 部曲再考
- 武宗の意図と役割