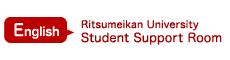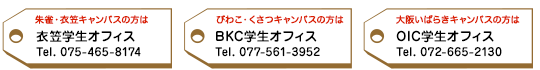2018.01.15
文系、理系に分ける意味
日本の大学では、学問を文系・理系に二分することが長い間慣例となっている。学際分野や文理融合領域も大いに広がってはいるが、大学入学時点においては、選択できる受験科目から文系と理系が明らかに区別されている。これには一体どのような意味があるのだろうか?
確かに学習方法上の特色から、いわゆる文系分野と理系分野である程度の区別をつけることが可能かもしれない。一般的なイメージからすれば、基本的な定理や約束事から出発して厳密な積み上げ型で成り立っている理系分野に比べて、文系分野では基礎から応用への展開がそれほど厳格ではなく、途中段階から参入してもある程度学習可能なように思われる。厳格な積み上げ型の理系の学問に比べて、文系の学問体系はある程度柔軟に見える。
しかしながら、文系分野でも基礎概念を曖昧なままにして応用・展開へ進むことは基本的に不可能である。基礎概念を正確に定義して共通の了解を確保して、また方法論についても論理的な手続きを経なければ、文系分野においても研究を発展させることはできない。文系分野は柔軟でそれほど厳密でなくてもよい、という観念があるとすれば、それは偏見である。
文系、理系への二分割が誕生した経緯については詳らかでないが、富国強兵のために有用な人材を短期間で効率よく育成する上で、このような二分割が有効であったのだろうか? あるいは、進路決定の判断基準として単純で便利だったからなのだろうか? いずれにせよ、大学受験段階で人間の適性を二つのタイプにグループ分けすることが制度として根付いているが、このようにグループ分けをしてレッテルを貼ることは、本人に自分の能力について偏見を持たせ、発達の可能性を大きく制限していると言わざるを得ない。
産業社会学部で統計学という理系的な科目を教えているのでこのようなことを感じるのかもしれないが、理由はそれだけではない。自分は文系だから理数的科目を学ぶ能力はない、学ぶ必要はない、という偏見を文系学部の学生が持っているとすれば(実際、そのように見えるが)、高度な科学技術が社会にますます大きな影響を与えている今日において、文系学生が将来の可能性を自ら閉ざすような偏見を捨てることが非常に重要になっていると感じるからである。(理系の学生にとっても、理系だから日本や世界の文化・歴史を知らなくても当然と考えるならば、大いに危険である)
もちろん、文系、理系それぞれへの適性はある程度は存在するだろうが、日本の場合、大学入試合格というペーパーテストへの適性によって決められる部分が非常に大きいのではないか。要するに、ある学問への知的興味・関心よりも、ペーパーテストで点数が取れるかどうかが学部選択の大きな理由になっている。かくいう私も、大学受験で文系を選択した際に、理科や数学では合格点が取れそうにないという都合からそうなった部分が大きい。そのような私が統計学を教えることになるとはまったく不思議であるが。産業社会学部の卒業生をみても、SEとして技術的な仕事をしている人はいるし、在学中から独学で腕を磨いて情報系のアルバイトをしている学生がいる。中には、理系の大学院に進学する学生もいる。
学問への向き不向きは、大学受験の問題が解けるかどうかで決まるものではなく、その分野への知的好奇心や意欲があるかどうかである。私は文系だから、理系だから、というレッテルを自分に貼って、自分の可能性を狭めることは、とりわけ20歳前後の若者にとっては大変もったいないことであると思う。文系学生についていえば、ある程度の理数系の素養を持つことは、将来のキャリアを拓くうえで極めて大きな力になる。教養科目で学ぶことができるので、少なくともアレルギー的な感覚は少しでも克服しておいて欲しいと思う。
みなさんも、受験やペーパーテストという眼鏡をすてて、大学で自然科学の入門科目をとって学んでみませんか? きっと新しい世界が開けると思います。
学生部長
産業社会学部教授
長澤 克重
2017.12.20
いつもの中の別世界、いつもの隣の別世界
知り合いが京都に来た時に、一応京都案内をし、そういった観光名所やイベントに行く機会が何度かありました。そうしているうちに、せっかくだから行ってみようと不思議と思い始め、今さらなのですが、この何年か、京都の観光名所に行ってみました。
祇園祭では、数々の鉾をまじまじと見て、それぞれの家にある美術品を出してお披露目しているのを見ました。鉾自体の飾りの美しさはもちろんですが、こんなに美しいものがこの家に実はあったのか、と驚くばかりでした。
少し足をのばして、ある山に行った時は、他の観光客の人達に混じって歩きながらも、少し山の中に入れば、動物のいる気配がしたり、周りに何か、普段接しないものがいる、という印象がしました。日暮れ時になると山の中は昼間とは全くの別世界でした。
私はお祭りや美術品のいわれ、その山の持つ歴史はよく知りませんが、普通に見える家の中に実は美しいもの・びっくりするような世界が潜んでいること、普段関わる場所の近くに実は別世界が広がっていることが印象に残りました。
定番のものは、これまでの歴史の中で生き残ってきているだけに、すごい力を持っていますね。
いつものことで普通に思えることの中に発見があるかもしれない、いつもの自分の活動範囲のすぐ隣に別世界が広がっているかもしれない、と思うと、少し怖くもありますが、今自分に見えている世界が全てではないかもしれないと思え、わくわくした気分になります。
秋になって観光しやすい季節になってきたので、わくわくしながら、もうしばらく京都の定番の所へ行ってみようかな、と思っています。
2017.12.1
日本人のこころ
展覧会の順路終盤に、師匠が作られた面があり、その前に立ったとき、何とも言えない雰囲気に思わず、す~っと引き込まれるような感覚になりました。『増女』という中年の女性の面でしたが、全部同じような造りのはずなのに、すっとした目元と、わずかに開いた口元の様子が何とも品があり、そして憂いのような、哀しみのような微笑みのような、そのような印象をもちました。
展覧会では能面をつける体験もあり、つけてみたところ、左右のわずかに開けられた穴から全体は見渡せず視界は極度に制限され、面のため自分の顔は隠れているということと、面の表情の様子が自分として見られるのだという不思議な感覚でした。
帰って家族に面をつけた写真を見せると怖がられて、その夜寝ている私の顔が一瞬そのお面のように見えて怖かったと言って笑い話になりました。やはりそれほどインパクトの強いものなんだと。怖いのは、それとは特定しないけど何となく女性の怨念のような、また憂いや悲しみの感情を感じさせるからなのか、またそう感じ取るのは、自分の心を映しているのかもしれません。私も普段、怒ったり、悲しんだり表情は七変化ですが、それよりもはるかに、一見無表情に見える静止したお面からこんなにも心が揺さぶられるとは、ほんの少しだけ、能面の魅力に近づきました。
そうなると、いつか能の舞台を見てみたいと、本屋で初めて古典芸能の棚で少し立ち読みし、なるほど、能とは亡霊の無念の物語、そして「省略の美」だそうです。舞台の背景もいつも同じ一本の「老松」のみ、でもそれは全ての自然を代表しているそうです。能の動きというのも、昔から同じ「型」が継承され、極限に簡略化した動きだそうです。そこには演じる人の主体性はなく、ただただ「型」を舞う。そのことが、観る人にとっては他のどんな具象物にも邪魔されることなく、情念そのものを受け取ることとなります。
「型」で思いついたのは、私は最近フラダンスを習っていますが、先生はあまり指導はされず、真似をするよう言われ後姿を懸命に真似ているつもりでしたが、先生のような滑らかな指の動きを見て感覚として力を入れずぶらぶらと揺すると、本当にみっともない動きになるということ、実はフラダンスも、優雅に見える手の動きは、指先にまで力が入り、練習が終わると手に汗をかいているぐらい、力を使っているのです。「型」について、何でもそうじゃないかと思いました。初心者のうちは、基礎を何度も繰り返してきっちりと体に染み込ませ、それが遠い将来熟練したときには、少し型と違ったものがおのずと表現される、それがプロの美しさなのだと思いました。
日本人は昔から、茶道や華道、絵画でも、余白を大事にしてきました。何もないから、たった一つあるものにすごく意味が浮き上がる。むしろ、そぎとってそぎとって、その先に、本当のもっとも豊かなものがあるのかもしれません。昨今の、物と情報にあふれた世界では、なかなか見落としがちなものに気づかされます。
私もつい、あれもこれもと欲張って、得ようとすることをせめて少し戒めて、今自分にできることをただただ続けていこう、そんな気持ちになりました。
2017.10.05
今しかできないこと
単位は必要最低限、取っていました。仲の良い友達もいたし、人間関係の距離感に悩んだりもしました。将来の夢も漠然とありました。それでも結局何をしていたかと問われると、「旅に出ていた」としか言いようがありません。実際に旅に出ていたのは1年間のうち2ヶ月程なのですが、旅が1年の基準で、今でも旅の印象が強いのです。
貧乏旅行をする、というよりも、なるべくお金をかけない旅行を計画したら結果的に貧乏旅行になってしまうサークルに入っていました。どこを旅したのかと聞かれると、富良野やら屋久島やら、いわゆる観光地の名前はいくらでも出てくるのですが、日常生活の中でふと思い出すのはそういった観光地ではなく、名もない交差点や上り坂、静かな砂浜、薄暗いトンネル、ちょっと寂れたスーパーの風景です。いつどこで目にした風景なのかも分からないのですが、その時の天気、風の具合と一緒に、その頃考えていたことを思い出します。
いろんな人に出会いました。汚さを見かねて泊めてくれた民宿のおばさん、双子の息子の区別がつかないおじさん、結局「めんこい」しか聞き取れなかった東北弁の家族、トラックの荷台に乗せてくれたおじいさん、夜の屋久島に分け入って行った高校生の男の子。今頃どうしているかな、と思います。民宿は津波で壊れたけど、おばさんは元気なようだし、トラックのおじいさんは今でも絶品炒め物を作っているだろうか。あの高校生は、どんな大人になっただろうか…。
私の記憶にあるあの道を、今も誰かが通っている。ちょっとだけ知り合ったあの人たちが、今もどこかで暮らしている。そう考えることが、私の思考の地平をさっと遠くまで広げてくれて、遠い土地に名も知らない自分の仲間がいるようで、嬉しくなります。今でも旅に出たい気持ちはあるのですが、時間的な余裕と体力と、それに気恥ずかしさが加わってしまい、なかなかあんな旅行をすることはできません。あの時、大学生の時期にしかできないことをしていたのだな、としみじみと思います。
過去のことを振り返って足が止まり、先のことを考えて足がすくむこともあると思います。そんな時、今しかできないことを思い切りやってみる、というのも一つの在り方かもしれません。今しかできないことにどんな意味があるのかは、おそらく、後からじわじわと分かってくるのだと思います。
2017.09.04
ガッツ石松に心理学を学ぶ(?)
この言葉、心理学の中でも、交流分析という、アメリカの精神科医エリック・バーンが1950年代半ばに考案した理論を基礎としています。バーンは、交流分析の理論の哲学として、「I am OK. You are OK.(私はOKである。あなたはOKである)」という立場の大切さを強調しました。これは、「誰でもその存在は尊重される」という意味で、「たとえある人物の行動がとうてい受け入れがたいものであっても、その人の存在そのものは肯定されるという前提」です(『TAベイシックス』より)。
「OK牧場」は、フランクリン・アーンストという人が、こうした考え方の移り変わりを視覚的に表す方法として考案されたものです。「わたし」と「あなた」が、「OK」なのか、「not OK」なのか、という2つの軸で、4つの領域に分けられています(図1)。生活していく中で、時にOKになったり、not OKになったり、揺れ動くものではあるのですが、目指す立場はあくまでも、「私はOK。あなたはOK.。」
そうは言うものの、実際に自分の日々を振り返ってみると、そういう風に考えることって、そうそう簡単にはいかない気がします。「私はOKでない、あなたはOKである」とばかりに、自分だけを責め、自己嫌悪でいっぱいになったり、「私はOKである。あなたはOKでない。」と、自分のことを棚にあげて相手を責めてしまったり、「私はOKでない。あなたはOKでない。」と、うまくいくとは思えずに投げやりになってしまったりすること、時にあったりしませんか?
人はそれぞれ、このOK牧場の中で、どうも落ち着きやすい場所、というものがあるようです。何かいきづまりを感じてサポートルームにいらっしゃる人には、「私」なり「あなた」(もしくは両方)が「not OK」になりやすい人が結構多いように思います。
そう考えた時、カウンセラーとしての私の仕事は、そうした人たちとの対話の中で、「私はOK。あなたはOK。」という領域を広げていくこと、そこにとどまる力をつけていくお手伝いをすることなのかな、と思います。
ちなみに、このコラムを書くにあたり、ガッツ石松さんのホームページをのぞき、「OK牧場」の誕生秘話を知りました。“OK牧場の決闘”という西部劇映画から来ているという説などもありますが、ホームページでは「OK!」と映画“ララミー牧場”の牧場を合わせて思わず叫んでしまったというエピソードがその始まりとして語られており、心理学とは一切関係はないようであるということを、最後の最後にご報告させていただきます。
参考:
深沢道子監訳(1991)『TA TODAY―最新・交流分析入門』
日本TA協会(2003)『TAベイシックス』
「ガッツ石松のホームページ OK牧場!」(http://www.guts-ishimatsu.com/)
2017.08.01
花戦さ
時は戦国時代。花と町衆を愛する風変わりな男がいました。その名を池坊専好といい、京都頂法寺六角堂の花僧でいけばなの名手(実在した人物だそう)。専好がいけた松は時の権力者であった織田信長の心を奪い、豊臣秀吉や千利休をもうならせたといわれています。専好は、人の顔と名前を覚えられないうえに口下手。秀吉や千利休という超がつくほど有名な人物の前でも、権力というものには全く興味なし。花をいけることが至福、いけばなをこよなく愛する男です。天真爛漫な専好を狂言師で有名な野村萬斎が面白おかしく、時にチャーミングに、時に凛々しく演じています。時は流れ、秀吉が天下統一を治めるという時代に変わります。秀吉の愛息子である鶴松が亡くなってしまったことを境にして、秀吉は正気を失い暴君になっていくのです。そして、己に意を唱える者どころか陰口を言った町衆に残忍な静粛を始めていきます。死に追いやられた者の中には、古くから秀吉を支え共に美を追い求めた友人である千利休や、専好を慕う町衆たちの姿もいました。専好は愛する人を守る為、平和な世を取り戻すために秀吉に一世一代の大勝負に望みます。刃で戦うのではなく、花で専好は秀吉の心を変えようとしたのです。専好は常々花のもつ力を信じていました。花にも色々な花があり、見た目は美しいけれど毒のある花もある。でも皆、花としての優劣はないと語ります。信長であろうと秀吉であろうと分け隔てのない信頼関係をもつことが大事だと・・・。武力で戦うのではなく、花によって心を開かせようという花戦さが始まるのです。
この映画には数多くのいけばなの作品が登場します。専好は松が大好きであったとされ、岐阜城の大座敷にて織田信長に専好が献上した大砂物が出てくるのですが、時の権力者である信長を“昇り龍”と表現し、松をダイナミックに扱い豪胆で勢いがある信長を見事に表していました。劇中に出てくるいけばなの作品は、どれも見事に物語の背景や専好の心を上手に表現しておりハッとさせられ感動します。専好が花をいける時間はまるでお風呂に浸かっているかのようにリラックスして、心から楽しんでいることが伝わってきます。そう、まるで花と対話しているようなのです。
この映画の題字にはダウン症であり書家である有名な金澤翔子さんという女性が書かれています。金澤翔子さんは“見る人を喜ばせたい”という純粋な心から生まれる書が多くの国境を越え人に感動を与えている方です。以前金澤翔子さんが特集されている番組を見たことがあるのですが、自分の身体の2倍3倍はある大きな用紙に一心不乱に書をかかれている姿がとても印象的でした。映像を見ていて私は“どうしてこの方はこんなに頑張れるのだろう。間違ったり失敗したら怖くないのかな?“と思わず考えてしまったのですが、翔子さんのお母様が”翔子はうまく書こうとか紙からはみだしちゃいけないなんて考えないんです。いつも皆さんに元気とハッピーをあげたいんです“と語られているのを聞き、何か言葉では表せない温かな気持ちが湧き起こりました。書が好き、何よりもそれを見てくれる人に元気になってほしい。そんな純粋な気持ちが人を動かすのだなぁ、と改めて感じさせられました。物語に出てくる専好も同じく、権力者であろうが町衆であろうが、どんな人々にも花を愛で、その花の力で元気になってほしいと願う花僧でした。金澤翔子さんにも似通う、専好の花を愛でる純粋な気持ちとこの題字がより一層心に響きました。
何か夏休みらしいお話を書こうとしていたのですが、ぜひとも皆さまにも観ていただきたいなと思いこちらで紹介させていただきました。皆さんにも何か一つ心に花が咲かせられるように・・。
2017.07.03
ミステリアスな場所
小学生の頃は、町の建設会社の倉庫に友だちとの「ひみつ基地」がありました。今思うと不法侵入だったのですが、学校帰りに友だちとそこに立ち寄っては、何か儀式のようなものをしたり、おしゃべりをしたりして、自分たちの世界を楽しんでいました。薄暗く、資材や道具が置いてある倉庫の中には、ロフトがあり、梯子を上ったそのロフトが私たちの場所でした。拾ってきた石や、つんできた花を飾って、誰にも知られない自分たちだけの空間を持つことが、嬉しくて、楽しくて、果てしない想像の世界を毎日繰り広げていました。
高校の頃は、学校の近くに林があり、その中に小さな「喫茶店」がありました。林の中にあったので、喫茶店に入る姿は誰にも見られず、店内は狭くて、暗く、コーヒーの匂いのする大人の場所でした。学校帰りに友だちとそこによっては、マスターを交えて話をしたものでした。その頃、小遣いはもらっていなかったので、たぶん、何も注文せずに、ただしゃべりに行っていたのではないかと思います。他愛のない話をしたり、恋愛の話をしたり、笑ったり、泣いたり。
「牢屋」「ひみつ基地」「喫茶店」は今はもう、そこにはありません。保育園は別の場所に移動してしまいましたので、園舎自体がなくなってしまいました。建設会社の倉庫も、当時から相当古かったのですが、解体されてしまったようです。喫茶店にいたっては、現実にあった場所かどうかもわからなくなってしまいました。というのも、その喫茶店の話を、同じ高校に通った妹にすると「そんな場所は知らない」と言うのです。林も今はありません。こうなると、もう自分の想像なのか、現実なのかもわからなくなりましたが、今でも鮮明に思い出せる光景と、におい、そしてその時に味わった気持ちは本物のような気がするのです。これらの場所が客観的に存在したのか、調べるすべはあるかもしれませんが、そんなことはあまり重要でなく、これが私の中に確実に存在することの方が大切な気がするのです。
学生サポートルームのコラムなんだから、何か心理学的なことを書いて結ぼうと思ったのですが、うまくいかないのでやめます。そんな、怖いけどワクワクする、怪しいけどノスタルジックな場所、あなたの中にも存在しますか?
2017.06.01
つれづれ映画評第五回「レヴェナント―蘇えりし者―」
舞台は1823年のアメリカ中西部ということですがオフィシャルサイトにそう書かれているだけで映画本編では一切説明されていません。説明されても、アメリカ史でも専門にやってない限り時代背景とかろくに出てこないですよね1823年とか。何かうまく状況が飲み込めないまま話が始まるんですが、その観ている側の軽い混乱にかぶせるようにネイティブアメリカンが主人公の一行を襲撃してきて、画面は突如、敵味方入り乱れる阿鼻叫喚の修羅場となります。この作品はアカデミー撮影賞をとってますが、その絵作りはかつて同様に戦闘シーンを入念に作り込むことで撮影賞をとった(と思われる)「ブレイブハート(1995)」や「プライベート・ライアン(1998)」に勝るとも劣らない出来栄えとなってます、私見では。ほんの数分の短いシーンなのに、当時の戦闘のあり方だけでなく、その時代の持つ残酷さ、秩序の無さ、自由奔放さといったものが感覚的に理解できるようにもなっています。
撮影賞も納得の絵作りは全編を通じて維持されます。そもそもロケーションがいいですね。「どこで撮ったの?」みたいな質問がネットでも散見されます。基本的に森と川の場面しかないんですが全く飽きない。昼間のシーンであれば銀灰色がかった白い画面に、そして夜のシーンであれば暗灰色がかった青い画面に、魅入られるからでしょうか。日本だとあまり見られない下生えが疎で先がどこまでも見渡せそうな森は、逆にどこからか常に見られているようで落ち着かなくなり、もし何かに追われたら身を隠すことなどできないんじゃないかと不安を煽ります。というところであれですね、あの熊のシーン。もうホント「どうやって撮ったの?」という。主役を務めたレオナルド・ディカプリオもあれほど絶体絶命度が高いシーンに出たことないんじゃないでしょうか。いやけっこう彼は死んじゃう役が多いんですけど。しかし後続のクリエイターにとっては果てしなくハードルが上がってしまいましたね。似たような場面を撮るとなれば、必ずこの作品の出来と比較されることになるでしょう。
ストーリーのほうも大丈夫です。復讐譚を成り立たせるに充分の悪っるい奴が出てきますから。アメリカ映画に出てくる悪役は本当に魅力的なキャラが多いですね。「ウォーキング・デッド」なんかも数シーズンごとに悪党集団が一新されボスキャラも変わるわけですが、毎回飽きさせずに物語を引っ張っている。力強くリーダーシップがあって頼り甲斐もあるしすごく賢い。でも最終的に心が通じ合わないんだろうなと思わせる怖さがある。この作品ではトム・ハーディがその役を演じていて、僕は知らなかったんですが最近いろんな作品で主役を張るようになってきた俳優さんらしいです。ちなみにイギリス人だと。大作の悪役にイギリス人を起用すると当たる、というジンクスがハリウッドにはあるそうで、そのパターンにも沿っていることになりますね。
と、色々書きましたが最初に述べたようにてんこ盛りの贅沢な作品です。サバイバルアドベンチャーと銘打ってるだけあって、随所に描かれる生きるための知恵がこれまた素晴らしい。概ねエグいんですけどね。ライフル弾の火薬を使って傷を焼灼する場面とか、こんなことする時代がかつてあったんやと半ば感動すら覚えます。古すぎる技術はもう誰も知らなくて画面で見ると却って斬新、と言うか。そして最後は、ばりばりの西部劇的展開へ。ハリウッドの御家芸が炸裂します。伏線のつなげ方も上手いんですよね。ハッピーでもバッドでもないエンディングは時に消化不良で終わったりしますが、この作品は違います。主人公がまとう、それまでの過酷で凄惨な行程に耐えた見返りとも言うべき気高さを、観る者の心にも与えてくれるでしょう。
こういう良作には、数年に一度は出会いたいものです。
「レヴェナント―蘇えりし者―」 “The Revenant”
監督:アレハンドロ・G・イニャリトゥ
キャスト:レオナルド・ディカプリオ、トム・ハーディ、ウィル・ポールター
2017.05.01
二十歳の君へ
さてこの本もお勧めではありますが、新たに興味深い本をみつけました。同じ著者の立花隆さんが、東大で教鞭をとるようになり、全学自由研究ゼミナールを開講。「見たい、聞きたい、伝えたい」を信条として、学生さんが自身の興味関心にしたがって研究を進め、調べて書くという内容。その様子が「二十歳のころ」、そして「二十歳の君へ」(文藝春秋)という本にまとまっています。2011年に出版された後者を最近読んだのですが、とてもおもしろく、夢中になって読みました。
内容は、東大生が16人の著名人、職業人にインタビューした第1章、立花隆氏による6時間の講義内容による第2章、そして14人の学生による、二十歳の手記の第3章で構成されています。
第1章は、ぼんやりした学生時代を過ごしながらも、「こういう環境でこういうふうに表現や仕事をしていきたい」という気持ちはあったというリリーフランキーさん(注:東大生に贈った手土産がぶっとんでいました。そのプレゼント内容は、読んでのお楽しみ。)はじめ、研究者、音楽家、デザイナー、漫画家、小説家などなど、現在活躍する素敵な大人たちの、ユニークな青年時代のエピソードを知ることができます。また、その多様な仕事内容やバックグランドは知的関心を刺激します。第2章は、立花氏による講義ですが、これまた、科学から文化・芸術まで幅広く、豊かな内容を、わかりやすく、おもしろく語っており、もっと知りたいという好奇心が、自然とわいてきます。
そして第3章の最後の手記は、私自身とても心揺さぶられたのですが、ゼミナールの学生たちが、それぞれの率直な考えや気持ちをつづっています。自分自身の経済的な苦労が研究テーマになっている人、大きな失恋に影響を受けた人、人嫌いとクソ真面目を直すためにバイトをはじめた人。それは確かに東大生らしいスマートな文章でつづられていますが、悩み、模索し、もがいてもいる姿は、ほかと変わらない、等身大の二十歳の青年たちだなあと感じました。また、学んで、卒業して、就職に向かうだけでなく、今この時間に思い悩むこと、それは時にしんどいことではあるけど、それがいかに大事なことか、自分自身の礎にもなる重要なことだと考えさせられます。
以下は、立花氏が講義の中で引用した、マラルメの詩です。
私たちは航海している
私の色々の友達よ
私はすでに船尾にいるが
君たちは豪奢な船首となり
雷と冬との荒波を切り開く
みなさんの二十歳、学生時代はどんなふうでしょうか。迷ったり、悩んだり、先が見えてこなかったり。そうした中から、荒波を切り開いて、自分の道がみえてきますように。
2017.04.03
新しい環境に入るという体験:私と世界の関係を考える
10数年の社会人生活を経て2度目の大学院入学を果たした私は、初日の全学新入生オリエンテーションに出席しました。広い会場の大半を占めるのは年下の若者たち。まあそれは想定の範囲内でしたが、驚いたのは、実際にその状況にいると自分が急に気弱になったことでした。余裕で笑いさざめく若者たちに囲まれていると、なんだか彼らがまぶしく見え、身の置き所がないように感じ、視線は下を向き、体も縮こまってしまいます。合格通知を受け取って新生活にワクワクしていたときの自分とは、なんと違うことでしょう。
そのあと社会人学生の集まる所属コースのオリエンテーションでようやく同志と知り合ったわれわれ中年新入生たちが、速やかに連帯したのは言うまでもありません。授業日は身を寄せ合って行動し、それ以外でもメールを飛ばしあってあらゆる疑問や不安をシェアする日々。しかしそうしているうち、研究室や学食などで現役学生に混じって過ごすことも特段気にならなくなり、むしろこの“異文化”体験がけっこう面白く感じられるようにもなったのでした。(何しろ普段カウンセラーとしてお話を伺っているイマドキの学生生活を、自ら体験学習しているわけですからね。たいへん勉強になります)
このような新環境への適応過程は、なんら珍しいものではありません。しかしここで起きていることを詳しく見ると、それは「世界」と「私」の関係の転換であることが分かります。私がひとりで全学オリエンテーション会場にいたときには、周囲の世界はとてもよそよそしく感じられ、世界の外側にはじき出されそうになった私はただ圧倒されるばかりでした。が、「同じ経験を分かり合える他者」を得たことによって、私は彼らと共に少しずつ世界の内側に位置づき、そこで面白みまで感じられるようになったわけです。ここで、私自身は何ら変化していないにもかかわらず、自分と世界とのつながりが危うくなると途端に自信が失われてしまったというのは、大変興味深いことです。そして自分と世界を再びつなぎなおす端緒となったのが、経験を分かり合える他者の出現であったということも。
「他の人たちは皆、新しい環境で簡単に友達を作って、充実した日々をすんなり始めている・・・」と、自信をなくしたり、居場所のなさを感じたりする新入生は多いものです。しかし、あるとき新入生が多く集まる場でいろいろ尋ねてみて分かったのですが、実際のところ彼らはお互いにかなり共通した不安や悩みを抱えているようなのです。たとえば「新しく友達を作れるか不安だ、苦手だ」という人は実は大多数にのぼるのですが、しかし多くの人はそれを無理に覆い隠して笑顔を作り、前もって必死に考えておいた「さりげなく声をかける」ための様々な作戦を実行に移しているらしいのです。そのため、何かのきっかけで「なーんだ、皆、同じように不安なんだ」と、互いの気持ちを共有できる機会があると、すっと気持ちが楽になる人が多いようです。
「隣の芝生は青く見える」ということわざがありますが、新入生のあいだで起きているのも同じような錯覚と言えそうです。このような錯覚が生じるのは、大学という場が、年代や背景など多くの点で同質性の高い人々が大勢集うところであることも関係しているでしょう。同質性の高い集団におかれると、人は自他の違いに敏感になってしまい、そこで自分と周囲の皆(世界)の間に距離が生じます。すると急に自分は「ひとり」で、ちっぽけで弱い存在に感じられる。しかもそうなってしまうと「自分は周りと違う」→「だから他の人には自分の気持ちは分からない」となって、結果的にひとりで悩み続ける、という負の連鎖に陥ってしまうこともよく見られます。
この連鎖から解放されるうえで有効なのは、経験を分かり合える他者を得ることのようですが、あまりにも大勢の学生がひしめくキャンパスでは、そのような相手とうまく出会えず途方にくれている人もいることでしょう。学生サポートルームでは、個別面接やグループ企画を通じてそのような皆さんの手助けをしていますので、よかったらぜひご利用ください。