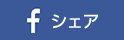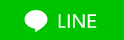【挑戦の向こう側】覇道を拓く主将の魂 立命館ラグビー、歴史的勝利の軌跡
2025年春、立命館大学ラグビー部は、創部史上初となる関西リーグ春季トーナメント優勝という快挙を成し遂げた。その歴史的瞬間を牽引したのは、主将を務める島選手(経営学部4回生)である。チームを勝利に導くまでの彼の道のりには、数々の苦難と深い思考、そして勝利への揺るぎない信念が刻まれていた。彼のラグビー人生を紐解き、その裏に秘められた真の強さに迫る。
大分から関西へ。ラガーマンの原点。
島選手のラグビー人生は、小学5年生の終わり、たまたまテレビでラグビーを見たことがきっかけで始まったという。何気なく「やってみたい」と漏らした一言を、父親は真剣に受け止め、ラグビースクールへ連れて行ってくれた。それまで柔道に打ち込んできた彼は、ラグビーの楽しさに魅了され、そのまま競技を続けた。大分県内にはラグビースクールが少なく、中学時代も引き続きスクールでプレーしたという。
中学校を卒業すると、ラグビーの強豪校である大分舞鶴高校へ進学。30年以上続いていた全国大会出場記録を途絶えさせるという悔しい経験も味わったが、3年生の時には、全国大会の舞台を踏むことができた。高校卒業後は就職しようと考えていたが、親からの「大学には行っておけ」という強い勧めもあり、進路を再考。その中で、大分舞鶴高校から立命館大学へと進学した関係者からの紹介が縁となり、立命館大学の練習に参加する機会を得、スポーツ推薦で立命館大学に入学することとなった。
大学ラグビーの洗礼
立命館大学に入学後、島選手は早々にその才能を開花させる。1回生同士の最初の練習試合で活躍し、その後すぐにAチームに昇格。1回生の春季トーナメント2回戦、同志社大学戦で早くも初スタメンを飾り、そこから現在まで継続して試合に出場し続けている。しかし、その道のりは決して平坦ではなかった。高校時代から抱えていた腰の怪我に加え、シーズン中に手首も負傷し手術も経験したという。特に2回生の頃は、怪我からの復帰後すぐに試合に出ることになったものの、チームメイトを信頼させる、納得させるようなプレーができていないと感じ、「精神的にしんどかった」と当時の心境を語った。
高校ラグビーと大学ラグビーの最大の違いは、「思考力」であると島選手は断言する。高校時代は目の前のプレーに集中していればよかったが、大学では80分間を通して試合全体を考え、相手の戦術まで読み解く力が求められる。自身のフィジカルだけでは足りないと感じた彼は、この「考える」という部分を磨くことに注力した。それは、単なる身体能力を超えた、ラグビーという競技の本質を理解し、自己を成長させようとする彼の貪欲な姿勢の表れであった。
主将就任への決意
3回生になった島選手は、チームの中心として活躍し、順調なシーズンを送っていると感じていた。しかし一方で、チーム全体に蔓延する「勝ちに対する雰囲気」の希薄さに、もどかしさを感じていたという。関西の強豪である京産大や天理大との試合前でも、「相手は強豪やし、負けても仕方ないか」という諦めのムードが選手に漂っていることに、彼は強い危機感を抱いていた。
そして、3回生秋のシーズンが終わり、彼らの代へと引き継ぎの時期が訪れる。主将は新4回生での投票によって決められ、島選手が選出された。実は、投票が行われる前に同期の中村選手と新チームについて話し合いをしており、中村選手から「お前がやった方がうまくまとまるんじゃないかな」と後押しされたことも、彼が主将を引き受ける大きな要因となった。彼は、みんなが受け入れて支えてくれるならやりたいと、前向きにその重責を担うことを決意した。
勝利への執念
主将として島選手が真っ先に変えようとしたのは、チームの「試合に対する勝ちへのマインド」だった。彼は「勝ちにこだわるチーム」を軸にチーム作りを進め、そのために具体的な行動を起こしてきた。特に重視したのは、上級生である4回生の意識改革である。1回生が新鮮な気持ちで入部してくる前に、彼らが従来の立命館の「ネガティブなマインド」に染まらないよう、4回生で徹底的に話し合った。そして、「1回生の気持ちが一番大事」という認識のもと、2・3回生にも呼びかけ、これまでのような負の雰囲気を決して見せないことを確認し合ったという。この粘り強い働きかけこそが、チーム全体のマインドセットを変えるための第一歩であった。
2025年春シーズンに向けては、これまでの「とりあえずやってみよう」という姿勢を捨て、相手を徹底的に分析し、秋のシーズンさながらの準備で臨んだ。戦術的な部分は、幹部選手が主体となって考えることを意識した。また、主体的な行動は、組織心理学の専門家である山浦 一保教授(スポーツ健康科学部)がチームに関わり、学生が自ら考えることを促してくれたことも大きく影響している。自ら考え、行動する主体性が、チームに新たな風を吹き込んだのだ。
歴史的勝利の舞台裏
春季トーナメント決勝の相手は、長年のライバルである京都産業大学であった。同志社大学戦での敗戦を経て、龍谷大学戦から着実に自信を積み重ねてきたチームは、京産大戦前には「行けるかもしれない」という確かな自信を感じていたという。
京産大戦では、「接点で引かないこと」と「ポゼッションを大事にすること」という二つの大きなテーマを掲げて臨んだ。試合序盤は硬さから失点し、先制トライを奪われたものの、それが逆にチームを吹っ切らせ、自分たちのラグビーを展開するきっかけとなった。後半に入ってもディフェンスラインの出足が落ちることはなく、タックルの精度も高かった。京産大のフォワードが徐々に疲弊していく中、立命館の選手たちは誰も疲弊する様子を見せず、それが「俺ら行ける」という精神的な余裕と確信につながったと島選手は振り返る。準備の差、そして精神的な強さが、歴史的な勝利を引き寄せたのである。
試合後、彼はマスコミに対し「立命館の歴史を一つ作れて嬉しい」とコメントした。「記者さんに誘導されました 笑」とはにかみつつも、初の優勝を素直に嬉しく感じ、主将としてチームのマインドを変え、結果を出せたことへの喜びを噛み締めていた。
秋を見据えさらなる高みへ
春の優勝という輝かしい結果にも、島選手は慢心することなく、既に秋のシーズンを見据えている。春の優勝後、練習の雰囲気から「春で満足してしまっている選手が出てきている」と感じ、再びチームを引き締める必要性を感じたという。秋に向けては、一つ一つのプレーの精度向上や、接点での課題克服を磨き上げていくことが目標だ。
島選手は、自身の性格を「負けるのが嫌、負けても仕方ないという姿勢が何より嫌だ」と語る。負けるにしても全力を尽くして負けるなら仕方ないが、努力もせず負けてヘラヘラしているような雰囲気は我慢ならないという。この価値観は、幼少期から勝負事にこだわり、親から「ハナから勝負しない姿勢で負けているのはダメだ」と強く言われてきた影響が大きいという。彼の厳しさは、チームを勝利へ導くための、彼の揺るぎない信念に基づいているのだ。
ラグビーを通じた成長
大学ラグビーを通じて最も成長したと感じるのは、やはり「思考力」であると島選手は語る。高校時代は思いつきでプレーすることが多かったが、大学に入ってからは、プレーはもちろん、主将としてチームを運営する中で、「なぜ?」を常に考える力が身についた。多様な意見の中から何を取り、何を捨てるべきかを判断する経験は、物事を深く考える力を彼にもたらした。
卒業後もラグビーを続け、社会人チームでプレーすることが決まっている。その舞台でも、「誰にも負けない選手」という根本は変わらず、派手なプレーではなく、泥臭く、貪欲に、ひたむきにプレーする“自分らしいスタイル”を貫きたいと抱負を語る。
秋の目標は、もちろん関西大学Aリーグ制覇である。春の優勝は単なる通過点であり、本番は秋だと語る彼は、全チームに勝ち切り、全国大学選手権で結果を出すことを見据えている。島選手の強靭な精神力と深い思考力、そして勝利への執念が、立命館大学ラグビー部をさらなる高みへと導くことは間違いない。彼の挑戦から、ますます目が離せない。