TOPICS
2022年のTOPICS
2022.02.24

国関係学部3名の教員が登壇するウェビナーが開催されます
国際関係学部の薮中先生、石川先生、渡辺先生が登壇するウェビナーが3月に開催されます。
在学生はもちろん、学外の方もご参加いただける講演です。
ご関心のある方は是非ご視聴ください。
各講演の申し込み方法は以下よりご確認ください(受講料は無料です)。

ウクライナをめぐる米露対立、台湾海峡で台湾有事はあるのか、米中関係の行方、
イランの核開発と中東情勢の行方、さらには北朝鮮の核・ミサイル開発の行方。
2022年の世界は過去数十年で最も危険な情勢となっている。
その根底にはアメリカが内向きになり、国内政治が分断されていることがある。
アメリカの力強いリーダーシップが不在となり、世界は混沌とする。
日本をめぐる安全保障環境も厳しさを増しており、米中が対立する中で、
日本は如何なる選択をすべきか、日本外交の針路を考える。
冷戦終焉後に人、モノ、金、情報が自由に世界中を移動することでグローバル化が
進んだ社会には、国家の安全保障だけでは守り切れない数々の課題が山積しています。
感染症や気候変動のように国境を越えて広がる課題が増える一方で、冷戦時代には
あまり注目されていなかった国内紛争も増えました。そこで登場してきたのが国家の
安全保障を補完する「人間の安全保障」という考え方です。
登場から既に20余年を経ていますが、人々を中心に据える安全保障の考え方は、現在、
私たちが直面している様々な問題への対応にヒントを与えてくれます。

地域的包括的経済連携協定 (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) を、
後退の例として、 “America First” に基づく NAFTA の改定 (US-Mexico-Canada Agreement)
およびイギリスのEUからの離脱 (“Brexit”) を考察します。
地域経済統合の交渉過程における、経済的利益のみならず、国内/国際政治的要因の重要性を分析します。
続きを読む
在学生はもちろん、学外の方もご参加いただける講演です。
ご関心のある方は是非ご視聴ください。
各講演の申し込み方法は以下よりご確認ください(受講料は無料です)。
ウクライナをめぐる米露対立、台湾海峡で台湾有事はあるのか、米中関係の行方、
イランの核開発と中東情勢の行方、さらには北朝鮮の核・ミサイル開発の行方。
2022年の世界は過去数十年で最も危険な情勢となっている。
その根底にはアメリカが内向きになり、国内政治が分断されていることがある。
アメリカの力強いリーダーシップが不在となり、世界は混沌とする。
日本をめぐる安全保障環境も厳しさを増しており、米中が対立する中で、
日本は如何なる選択をすべきか、日本外交の針路を考える。
進んだ社会には、国家の安全保障だけでは守り切れない数々の課題が山積しています。
感染症や気候変動のように国境を越えて広がる課題が増える一方で、冷戦時代には
あまり注目されていなかった国内紛争も増えました。そこで登場してきたのが国家の
安全保障を補完する「人間の安全保障」という考え方です。
登場から既に20余年を経ていますが、人々を中心に据える安全保障の考え方は、現在、
私たちが直面している様々な問題への対応にヒントを与えてくれます。
セミナーでご一緒に考えてみませんか。
本講義では、自由貿易協定 (FTA) や経済連携協定 (EPA) などの形で現れる地域経済統合
の進展、後退要因を、政治経済学の枠組みを用いて分析します。
進展の例として、環太平洋戦略的経済連携協定 (Trans-Pacific Partnership, TPP) および地域的包括的経済連携協定 (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) を、
後退の例として、 “America First” に基づく NAFTA の改定 (US-Mexico-Canada Agreement)
およびイギリスのEUからの離脱 (“Brexit”) を考察します。
地域経済統合の交渉過程における、経済的利益のみならず、国内/国際政治的要因の重要性を分析します。
2022.02.10

続きを読む
国際連携学科の特設ページが公開しました
アメリカン大学・立命館大学国際連携学科の特設HPが公開されました。
2018年度に開設した国際連携学科。
アメリカン大学と立命館大学の国際関係学部で2年づつ学ぶ、
学部レベルでは日本で初めてとなる「ジョイント・ディグリー・プログラム」です。
特設ページでは、これまでにない国際連携プログラムで学ぶ学生・教員への
インタビューを通じてプログラムのリアルを紐解きます。
2022.01.26


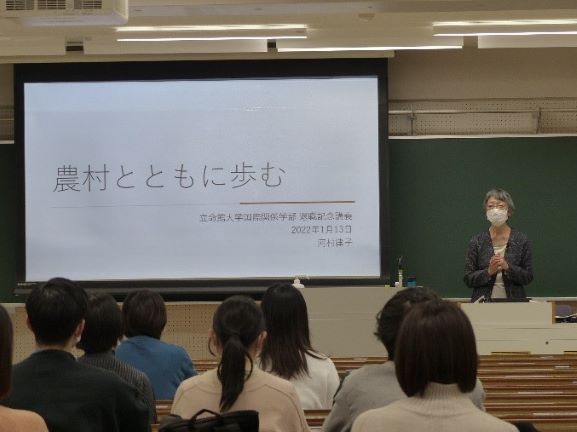
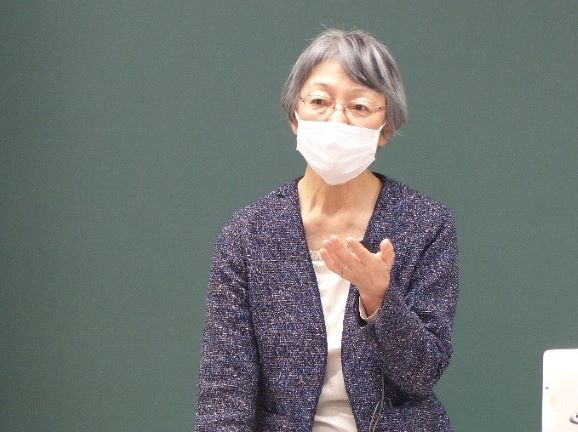

続きを読む
河村律子教授の退職記念講義を行いました
2022年3月末で定年退職を迎えられる河村律子教授の
退職記念講義を1月13日(木)に行いました。
「農村とともに歩む」というテーマで、これまでの河村先生の活動を紹介いただきました。
また、立命館大学で女性として初の学部長を務められている河村先生の学内での貢献も垣間見れる内容でした。
コロナ禍ということで対面+オンラインのハイブリッド型で実施しましたが、
多くの在学生・卒業生・教職員が集まり大変盛況となりました。
河村先生には2022年4月以降も特別任用教員として、
国際関係学部で引き続き教鞭をとっていただきます。
2022.1.7
続きを読む
ゲスト講義実施報告(JICA 安全管理部 課長:今井健様)
プロフェッショナル・ワークショップ(公務クラス)にて、JICA 安全管理部課長(前緊急援助隊 次長)である今井健氏をゲスト講師としてお招きし、政府開発援助(ODA)の枠内で実施されている緊急援助活動についてお話頂いた。
まず、開発援助の基本から始まり「ODAは投資investmentであり、returnを目指している」という国益を意識した活動であることを強調された。それに続き、緊急援助の基本原則として「災害主権」の概念(災害が発生した時、これに対処する第一義的責任は被災国政府にあり、他国からの援助は被災国の同意のもと要請に従って供与すべき)について説明があった。
実施体制としては、人(救援チーム、医療チームなど)、物(マイアミ、シンガポール、ドバイに救援物資の倉庫あり)、金(資金の捻出)を考えることが重要である。最後に「開発援助を広範に実施している日本は、それに加えて緊急援助を継続すべきなのか、継続するとすればその理由は何か?」を学生に考えさせるレポートの課題が出された。