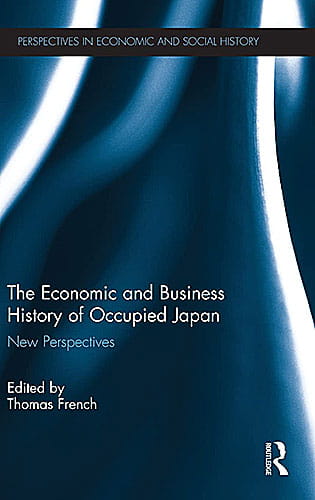連合国占領期の日本で何があったか
今の日本にどのような影響を与えるか

フレンチ トーマス ウィリアム国際関係学部 教授
占領が日本人の
アイデンティティに影響を及ぼし
新しい宗教が生まれ、
教育の内容も変わった
先生は主に連合軍占領期の日本について研究されているのですね
フレンチ 今、世界のさまざまな場所で混乱、対立、争いが生まれています。今後、社会をどう立て直すのかを考える時、私は、戦後の日本の歩みを知ることが、重要な示唆を与えてくれると考えています。
戦後の日本の歩みを知るには、連合国占領時代に何が起きたのかを知る必要があります。私は、膨大な一次資料や聞き取り調査をもとに、占領期の日本について詳細に研究を行いました。
日本は、占領によって、政治・経済・文化などさまざまな面で直接的・間接的に非常に大きな影響を受け、変化を経験しました。最大のものは日本国憲法でしょう。日本人のアイデンティティも揺らぎ、そのために新たな宗教もたくさん生まれました。教育の内容も変わりました。その影響は現在に至るまで続いています。
日本の食卓も占領期に大きく変化し、その変化が今まで続いています。今も朝食によく食べられているウインナーは占領期に米国から大量に輸入されたもの。食べ方が分からないので、レシピをラジオで紹介したり、進駐軍で働く日本人が広報したりしていたそうです。パスタ料理のナポリタンは、連合国軍最高司令官だったマッカーサーがあるホテルを訪れた際、シェフがありあわせの材料で作ったことが発祥とされています。

占領期に大きく変わった制度や生活習慣が今に続いているのですね。
フレンチ 一方で、戦前からあったものが、占領政策の影響を受けて大きく発展し、今につながっているものもあります。一つの例がオフロードの乗用車です。戦前の日本車は性能が低く、輸出できるようなものではありませんでした。戦争中は、国策として乗用車の生産を禁止し、トラックを量産。占領期の連合軍は米国ウィリーズ社の軍用車「ジープ」を使用していたのですが、占領終了前、日本政府は、現在の陸上自衛隊の前身である警察予備隊の車両として、日本人にも使いやすいオフロード用乗用車の開発を各自動車メーカーに要請します。その時に生まれたものの一つが、戦争中に量産していた小型トラックの車体を利用して四輪駆動にした「トヨタ・ジープ」でした。現在の「トヨタ・ランドクルーザー」の原型です。
朝鮮戦争による特需で得た潤沢な資金を投入し、米ジープの影響も受けて作られた高性能の国産軍用車でしたが、残念ながら警察予備隊には採用されませんでした。しかしそれがきっかけで、この車は徐々に日常使いにも適応したオフロード車にモデルチェンジしていきます。そして、運転のしやすさ、修理のしやすさから米国でも人気を博し、世界中に輸出されるようになりました。
戦前、そして1950年代初頭まで芳しくなかった日本の自動車産業が、占領の影響を受けた結果、米国や世界を席巻するロングセラーを産み出すようになっていったというわけです。

欧州が日本の現代史を知り、
日本の状況を理解すれば
日欧はさらに安定した関係を
構築できる
日本の占領期を研究対象にされたのはなぜですか?
フレンチ 父の同僚に日本史の研究家がいました。その人の本が家にたくさんあったことから日本への興味を持ったのです。ロンドン大学ロイヤルホロウェイ校で日本史を専攻し、1年間は京都の大学へ留学もしました。日本史に興味のある人にとって京都は天国。日本の生活を知ることもでき、私にとってとても大きな経験でした。
占領期の研究を始めたのは修士課程在籍中です。日本の安全保障について調べていくと、自衛隊や警察予備隊の初期の歴史について定まったコンセンサスがないことに気づき、それなら自分で調査しようと考えました。
イギリス人の先生が日本の近代史を研究されることにどんな意味があるとお考えですか?
フレンチ 私は日本人でもアメリカ人でもありません。双方から距離を保ち、異なる立場から研究をすることができます。
残念ながら今、世界ではさまざまな問題があり、戦争も増える傾向にあります。そのため、安全保障分野で国家間の連携やパートナーシップ関係がより多く結ばれるようになっています。英国と日本も、次期戦闘機の共同開発などで連携を深めていることが知られていますね。
現在、日本は米国と強固な同盟関係にありますが、今後は欧州との連携も増えていくでしょう。欧州は日本の現代史をもっと知る必要があると思います。今の日本は何ができて、何ができないのか、なぜ日本と周辺国の間に外交的な問題が残っているのかを多くの人が知ることが、より安定した関係の構築につながると思います。私は日本の近代史を研究することによって、日本の外交や安全保障、ひいては世界の平和に貢献したいと考えています。
先生のゼミについて教えてください
フレンチ 留学生、帰国子女の学生、ずっと日本に住む学生がほぼ同じ割合で在籍しています。日本の近現代の歴史と政治をテーマに、それぞれの経験に基づく多様な意見が出てくるため、さまざまな国の歴史を学ぶことができ、本当の意味での国際化が実現しているゼミです。
テーマは学生同士の投票で決まります。今年は「武士道の歴史とそれをめぐる神話」ですが、大日本帝国陸軍の歴史、太平洋戦争、ファシズム思想史、冷戦時代など、年ごとにさまざまなテーマをみんなで学んでいます。
学生に伝えているのは、できる限り一次資料にあたること、そして、今の考えによって過去を評価することをできる限り避けることです。歴史の現場にいるのは今の人ではなく、より厳しい時代に生き、当時の常識を持った人。これを忘れてはいけないと思います。
「連合国占領期の日本」に興味を持った方へ:BOOKS
Thomas French
New Perspectives on Peacetime Anglo–Japanese Military Relations: Old Friends, New Partners
Routledge(2025年)
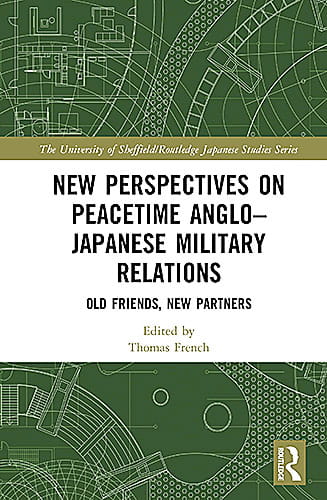
Thomas French
National Police Reserve: The Origin of Japan’s Self Defense Forces
Brill Academic Pub(2014年)
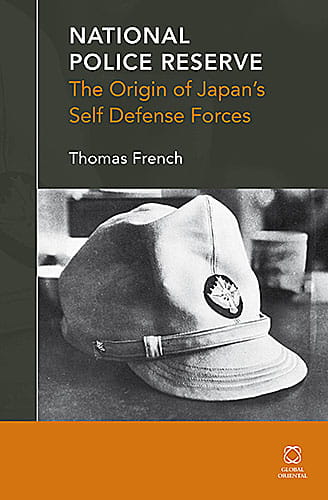
Thomas French
The Economic and Business History of Occupied Japan: New Perspectives
Routledge(2017年)