






文化人類学・医療人類学を専門とし、主に韓国や日本をフィールドに研究しています。文化人類学の研究が進んでいるアメリカで最先端の研究や研究者に触れ、自分の研究をアップグレードさせたいと、かねてから考えていました。
学外研究先を決めるきっかけになったのは、立命館大学総合心理学部とオクラホマ大学ソーシャルワーク学部が共同で学生交流プログラムを新設する計画があり、視察を兼ねてオクラホマ大学を訪問したことです。そこで「ぜひいらしてください」と歓迎されたことから、同大学で研究することになりました。
現地では、受け入れ先の先生に紹介していただき、大学の学生寮に入居しました。備え付けのキッチンで自炊する必要はありましたが、光熱費や家賃は比較的安価で、安心して生活することができました。私自身が「さまざまな人と交流したい」と希望したこともあって、割り当てられたのは、個室ではなく相部屋。ブラジルやポーランド、中国から来た博士課程の学生と、一緒に生活しました。互いの国の料理を作ってふるまったり、日常で他愛ない話をするのが楽しかったです。専門が近い学生と、互いの研究やアメリカの文化について意見を交わすこともあり、文化人類学者としても有意義な時間を過ごすことができました。もちろん生活習慣や文化の違いに困ったこともあります。中国人留学生が早朝から作る朝食のニンニクや山椒の強烈な匂いで起こされたこともありますが、それも良い思い出です。
大学のあるオクラホマ州ノーマンは、都心部から離れたのどかな町です。車がないと外出もままならないと聞いていたのですが、現地で同僚になった研究者の方が自転車を貸してくださったおかげで、心配していたほど日常生活に不便を感じることはありませんでした。寮で親しくなったドイツ人留学生の運転で、休みの日に一緒に博物館に出かけたり、さまざまな人との出会いが行動範囲を広げることにつながりました。
オクラホマ大学での研究滞在中、非常に有益だったのが、大学院の人類学の授業を聴講できたことでした。何より良かったのが、毎週授業のたびに出される課題に取り組んだことです。膨大な文献を読み、また関連文献を調べ、レポートを作成する中で、不足を感じていた英語力を徹底的に鍛えられたことはもちろん、それ以上に自分の研究とは直接関係のない幅広い分野の文献を数多く読めたことが収穫でした。
研究者・大学教員として忙しい毎日を送っていると、目の前の研究や執筆に関係ある文献を読むことに追われがちです。以前から、研究の基盤となる多様な知識の蓄積が足りなくなってきているという問題意識を持っていました。この機会にさまざまな文献や研究に触れ、視野や知識の幅を広げられたことが、今後専門研究を続ける上で見えない糧になると感じています。
また授業を受けて文献を読む重要性を再認識したことは、教員としても学びになりました。とりわけ文化人類学を学ぶ上では数多くのエスノグラフィーを読むことが欠かせません。帰国後、立命館大学で自分自身が授業を受け持つ際にも、この経験を教訓にしています。
滞在中にアメリカで開催された学会に参加し、海外の研究者と研究交流するなど、研究面でも今後に生かせる人脈をつくることができました。唯一計算外だったのが、アメリカは倫理審査が想像以上に厳しく、現地で調査を実施できなかったことです。次回はあらかじめ申請し、許可を得てから渡航するなど、事前準備をより綿密に行うつもりです。
今回の学外研究は、今まで以上に国際的に発信していく必要性を強く感じた半年間でもありました。知己を得た海外の文化人類学者たちと共同研究したいと思ったら、まずは自分の研究を相手に知ってもらわなければなりません。自分の研究の新規性や独自性を国際的に認識してもらう意味でも、これから英語の論文や英語での発表を増やしていこうと気持ちを新たにしています。
寮のルームメイトだった若いブラジル人学生が、「博士課程を終えたら、南アフリカ共和国でポスドクをするのもいいかもしれない」と語っていたことが、印象に残っています。いとも簡単に国境を超えるその発想の自由さに、大いに刺激を受けました。私も広い視野を持って研究を続けていきたいと思っています。


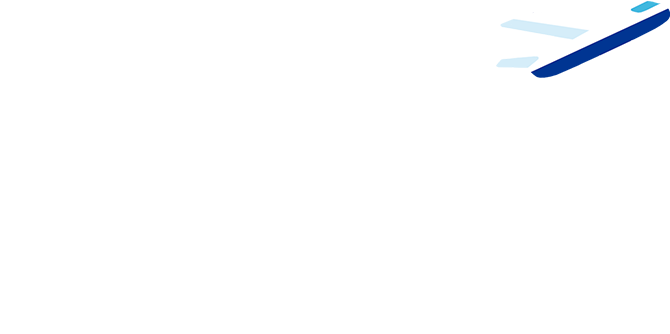
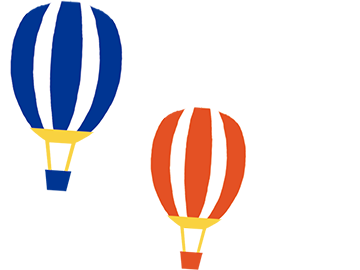
 バングラデシュ
バングラデシュ アメリカ
アメリカ シンガポール
シンガポール
 タイ
タイ
 韓国
韓国 中国
中国 イギリス
イギリス アメリカ
アメリカ アメリカ
アメリカ オーストラリア
オーストラリア スペイン
スペイン ドイツ
ドイツ オランダ
オランダ