





野生のネコ科動物の保全をテーマに、野生動物と人との共存について研究しています。研究対象地のバングラデシュでは、野生のネコ科動物が生息地の消失や捕殺などの脅威にさらされています。私は2017年からジャハンギナガル大学動物学部や政府と協力し、ネコ科動物の保全を目的として調査研究と保全活動に取り組んできました。
ネコの生息域内で生態を調査し、保全するべき資源を明らかにし、そうした自然資源をどのように守っていくか、方策を探ってきました。また、地域住民とネコ科動物がいかに共存するかも大きな課題です。研究対象としているスナドリネコという小型のネコが生息する湿地は、人間にとっても大事な生活の場です。これまでの研究から、地域住民は「スナドリネコは人に危害を及ぼす危険な動物」という誤った認識から、捕殺を行っていることがわかってきました。ネコ科動物と人の共存を可能にするには、こうした認識を変えていくことが不可欠です。
ネコ科動物を含めた食肉目に対する人の捉え方は、国によっても多様です。そこでその国や地域の文化の文脈に合わせて最適化するため、「食肉目と人との共存」に対する認識の違いに焦点を当て、バングラデシュとケニアで比較研究を行っています。とりわけ未来をつくる子どもたちの「自然」や「共存」に関する認識について質的調査を計画しました。バングラデシュの小学校での調査準備(現地のアシスタントや学生の調査トレーニング等)を実施するにあたり、ジャハンギナガル大学動物学部で共同研究者と打ち合わせするため、「女性研究者 国際共同研究活動支援制度」を活用して渡航しました。


ジャハンギナガル大学は、首都ダッカから大体30㎞のところにあります。道が混んでいなければ1時間ぐらいで到着しますが、渋滞の時は半日かかることもあります。今回は短い滞在だったため、毎日朝から夕方まで大学にて、共同研究者との綿密な打ち合わせと、実際の調査を担う現地のアシスタントや学生への指導を行いました。
同大学の教授とは、10年近く友人であり、6年以上にわたって共同研究してきた間柄です。今回の訪問にあたっても、彼の手配で、大学内の教員居住地区にあるゲストハウスに宿泊できました。民営のホテルより安く、また大学の教職員が住む治安の良いエリアにあるため、安心して過ごすことができました。ただし通常大学関係者以外は利用できないので、宿泊にはカウンターパートの協力が欠かせません。
大学近辺での移動手段は、主にリキシャと呼ばれる乗り物です。三輪自転車で、後ろに2名ほどの乗客が座り、運転手が自転車をこぎます。交通量が多く、渋滞は日常茶飯事のため、近距離なら自動車よりも安く速く移動することが可能です。ただ、移動できる場所が決まっているため、リキシャの乗り換えが必要なこともあります。
また留意しなければならないのは、バングラデシュは、総選挙前後などに政情が不安定になり、時には暴動が起きる危険があることです。そうした時期は渡航を避けるか、信頼できるカウンターパートと必ず一緒に行動するなど、状況を判断しながら安全面に注意が必要です。また国民の大部分がイスラム教徒なので、保守的な地域に入る際など、とりわけ女性は服装に配慮する必要があります。そうした留意点はあるものの、家族や友人との絆を大切にする温かい人が多いのがバングラデシュの魅力です。


今回の渡航から得られた成果の一つは、事前の想定が裏切られ、新たな研究の方向性が見えてきたことです。これまでの結果から、バングラデシュの村の子どもたちは「危険なスナドリネコがいなくなってほしい」と考えているだろうと予想していましたが、小学校での調査の結果、そもそも「湿地」を残したいとは思っていない可能性が出てきました。「母なる湿地」と呼ばれていた場所と子どもたちの関係が変化しつつあることが明確になったのは、大きな成果です。この結果をもとに、今年から地域の生態系への愛着の醸成を目指し、湿地環境教育プログラム開発に関する研究をスタートさせました。
もう一つの大きな成果は、共同研究に参加した現地学生の中に、「研究を継続したい」と希望する人が出てきたことです。長い進化の歴史を経て、今あるネコ科動物も自然環境もその国の宝です。その未来を自らの手で守っていこうとする学生が出てきたことは、とても嬉しい成果でした。
今回の研究は、事前に成果を想定できない挑戦的な課題でした。子どもたちの考えに合わせることで、現場により効果的に還元できるアプローチを検討するものであり、どう転ぶか不確実な部分が大きいものでした。「女性研究者 国際共同研究活動支援制度」なしには、挑戦できなかったと思います。挑戦的な研究を力強く後押しする制度のおかげで、保全に有用な研究を目指し、新たなステップを踏み出すことができました。
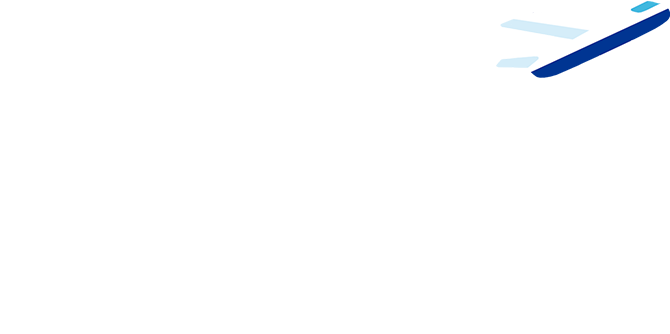
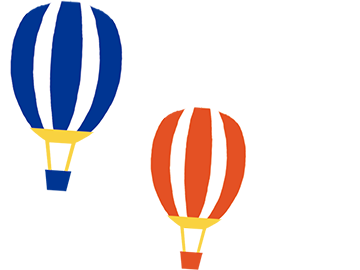
 バングラデシュ
バングラデシュ アメリカ
アメリカ シンガポール
シンガポール
 タイ
タイ
 韓国
韓国 中国
中国 イギリス
イギリス アメリカ
アメリカ アメリカ
アメリカ オーストラリア
オーストラリア スペイン
スペイン ドイツ
ドイツ オランダ
オランダ