





イギリスのスポーツ政策について研究しています。とりわけ2012年ロンドンオリンピック・パラリンピック(2012年ロンドン大会)が、イギリスや大ロンドン市のスポーツ政策にどのような「レガシー」をもたらしたのか、スポーツ政策の実践に与えた影響を明らかにしようとしています。またイギリスでは、近年、「ナイフクライム」といわれるような若年層の犯罪増加が社会問題になっています。スポーツ政策がこうした社会課題の解決やソーシャルインクルージョンの実現にどのようにアプローチしているかなど、イギリスのスポーツ政策やスポーツ文化の「今」を確かめたいと思い、今回の学外研究を決めました。
受け入れ先としてロンドン大学バークベック校を選んだ理由の一つは、スポーツ社会学、スポーツ政策の研究者で、以前から親交のある先生がいたことです。先生に依頼したところ、快く受け入れてくださり、リサーチフェローとして滞在が決まりました。肩書を得たおかげで、大学院生が使用する共同研究室や図書館など、学内施設に自由に出入りできただけでなく、関係者へのインタビューなどを行う際にも、スムーズに受け入れていただくことができました。まったく伝手のない大学にアプローチする場合、断られたり、費用がかかることもあると聞くので、学外にコネクションを築いておくことも重要だと実感しています。
バークベック校に魅力を感じたもう一つの理由は、学内にスポーツビジネスセンターが設置され、スポーツ専門のプログラムが開講されていることでした。滞在中は、同センターや大学院が開講する授業やセミナーを受講。スポーツジャーナリストやイングランドのプロサッカーリーグ・プレミアリーグのクラブで働く方などスポーツ業界に携わるゲストスピーカーから、イギリスのスポーツに関わる最新の情報やトレンドについて聴けたことは、得難い経験でした。

研究活動では、2012年ロンドン大会後、大ロンドン市が力を注いでいるスポーツを活用したシティプロモーションなどの政策に注目。その一環として毎年ロンドンで開催されているアメリカのプロアメリカンフットボールリーグ(NFL)の公式戦やここ数年、ロンドン・スタジアム(2012年ロンドン大会のメインスタジアム)で開催されているメジャーリーグの公式戦を観戦・リサーチしたのをはじめ、大ロンドン市を中心に行われるスポーツイベントについて調査しました。また青少年の社会的孤立や犯罪といった社会課題に対し、スポーツをツールとして、青少年の居場所づくりや社会的自立を支援する取り組みにも着目し、運営を担うボランタリー組織や自治体の関係者へのインタビュー調査を実施しました。
最大の収穫は、現地でしか得られない体験を通じた調査・研究を行えたことです。これまでの数日から数週間の短期間の調査研究とは異なり、今回は10ヵ月間という長期にわたって滞在し、生活する中で課題の背景にある社会状況を肌で感じたり、実際にスポーツイベントを観戦・体験することで、より深く、実態に迫ることができました。
調査だけでなく、週末や休日には、プレミアリーグ、女子プロサッカーやラグビー、競馬やボート競技といったイギリスで伝統的に盛んなスポーツを観戦したり、テニスやクリケットなどのスタジアムツアーや施設ツアーにも参加し、日本とは異なるイギリスのスポーツ文化に触れられたことも、研究を根底で支える糧になったと感じています。

10ヵ月間の滞在中は、日系の不動産会社を介して単身者向けの部屋を借り、地下鉄と徒歩で大学のキャンパスに通う毎日でした。住まいのあるノース・ロンドンは、日本人を含め、外国人が多く住むエリアで、近くの大手スーパーマーケットには日本食材も充実しており、安心・快適に生活できました。また大学の夏休み期間中には約1ヵ月間、日本から家族が来訪。妻と二人の娘とともに、ロンドンの名所を巡ったり、2泊3日でケンブリッジまで小旅行をするなど、余暇も楽しむことができました。
大変だったのは、やはり日本とは比べものにならないほど物価が高いことです。借りた部屋の家賃は、日本円で月30万円以上。スターバックスやファストフード店でも1000~2000円はかかるため、ひんぱんに外食するのは難しく、ふだんは自炊していました。
現地での滞在費用を含めると、大学の助成やサポートだけで学外研究にかかる費用すべてを賄うことは困難なため、学外研究を検討する際には、例えば比較的物価が安い地方の大学を選ぶなど、研究目的とのバランスを考えて計画を立てる必要があります。私自身は、ある程度の費用はかかっても、「それだけの価値があった」と思える研究成果や体験を得られたので、「行って良かった」と思っています。
学外研究期間中に、研究成果を複数の論文にまとめることができました。また今回の調査をもとにして、今後、先進国における社会課題解決のツールとしてのスポーツの可能性について研究を深めるほか、受け入れ先の先生と共同で、プロサッカークラブによる地域貢献や社会課題解決に向けた取り組みについて日英比較研究を行うことも計画しています。今回の学外研究で得た成果をさらなる研究につなげていくつもりです。

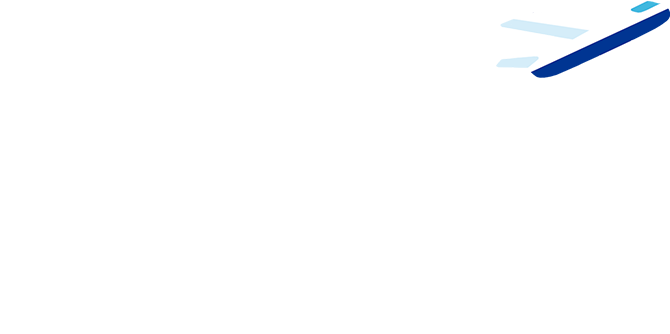
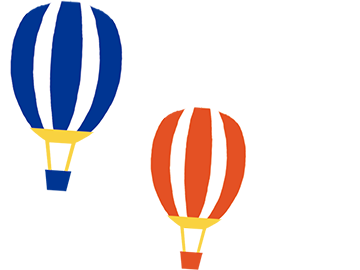
 イギリス
イギリス バングラデシュ
バングラデシュ アメリカ
アメリカ シンガポール
シンガポール
 タイ
タイ
 韓国
韓国 中国
中国 イギリス
イギリス アメリカ
アメリカ アメリカ
アメリカ オーストラリア
オーストラリア スペイン
スペイン ドイツ
ドイツ オランダ
オランダ