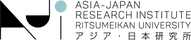アジア・マップ Vol.01 | 東ティモール
《エッセイ》
東ティモールと私
東ティモールとの出会い
東ティモールという国について私が関心を持ち始めたのは、実に大学1年生になって半年ほど経った2006年の後半だった。それは2002年の東ティモール「独立回復」後、初めての国内紛争があった年で、国連の平和構築事業の「挫折」として耳にしたのだと思う。そして次の年には、国内紛争時の国連事務総長特別代表だった長谷川祐弘先生が責任を取られて辞職し、私の母校である法政大学に教授としてやってきた。長谷川先生の生徒となったことは、私の人生においては大きな転換点だった。
それまで東ティモールに関心を持たなかったというのも不思議なことだ。私は幼少期、1991年をインドネシアのバリ島で過ごし、かの土地の人々に対してある種の愛情を感じていた。その年は、国際的センセーションを起こしたインドネシア軍によるティモール人への発砲事件(サンタクルスの虐殺)があり、バリ島ではフェルナンド・ラサマ・アラウジョ、後に東ティモール国会議長となる学生運動家が逮捕されていた。その後私は、インドネシア軍による占領のことも、東ティモール人の抵抗運動のことも、超国家的な人権ネットワークの活動のことも知らないまま育ち、中高生になった頃には既に東ティモールが独立国家になっていた。
2007年に長谷川先生の生徒になり、夏休み中の研修旅行として初めて東ティモールを訪問することとなった。バリが好きだったように、東ティモールもすぐに好きになった。2年後の2009-2010年には大学を1年間休学し、東ティモール国連選挙支援チームに勤務していた。このような過程で、私は首都ディリでの生活経験を蓄えつつ、当時読むことができた東ティモール関連書籍(例えば松野明久先生の「東ティモール独立史」、Jill JolliffeのEast Timor、Geoffrey GunnのTimor Loro Sae等)を読んでいた。どれもインドネシア軍による東ティモール占領(1975-99年)に反対する国際的運動の経験に基づいて書かれた作品である。
ティモールでの経験
東ティモールの公用語であるテトゥン語やポルトガル語を習得し、彼らの社会で生活する中で、(国連職員を含む)国際的な活動家たちの歴史感覚とティモール人の社会的事実との間には、微妙な齟齬があるのではないか、と感じることが多くなった。このような齟齬は、実に思いがけないときに発覚するものだった。
例えば、空き地でティモール人の若者たちとインドネシア産ワインを飲んでいた時のこと。グラスをひとつしか持っていなかった私たちは、数滴を大地の女神に捧げた後、一杯ずつ回し飲みにした。ある人が誤ってグラスを落として割ってしまった。「ウイスネーノ!(インドネシア領西ティモールにある飛び地、オイクシの言語で「神」)!」と叫ぶ。すると、神学論議が始まる。彼が問うには、「神はどちらに住まわれるか」、私は答えて、「神は遍在される」と答える。すると、彼は言う、「それは外国人の答えだ。ティモール人なら、ティモールにいると答えるはずだ」。そこで私は、「ティモールのどこですか」と聞く。すると、「インドネシア領西ティモールだ」という答えが返ってくる。
東ティモール人対外国勢力という歴史観に基づく作品しか読んでこなかった当時の私には、彼らの言っていることの意味がわからなかった。しかし、東ティモールの人々にとってインドネシア領ティモールが特別な意味を持った地理的空間だということは、後に文化人類学者の作品(例えばTherikのWehali等)や各国の歴史史料を読んでいくことで、理解できるようになった。
また元独立派ゲリラの家の2階に居候していた時にはこんなこともあった。夜になると、家族全員がテレビでインドネシアのメロドラマを観ている。元ゲリラの家父長は居候の私と一緒に部屋の隅っこに座っている。彼の妻と子供たちは、にこにこと笑っている。私が元ゲリラに「インドネシア語がわかるのですか」と聞いてみると、「わからない」と返ってくる。彼が言うには、「私はジャングルにいたからポルトガル語はわかるけれど、インドネシア語教育を受けた家族と違ってインドネシア語はわからない」とのことだった。
また当時はインドネシア側の国境地帯であるアタンブアに多数の「難民」がいて、彼らと話してみると、「私たちはティモールの子供で、インドネシア人」と言っていた。これらは「外部」としてではなく、東ティモール人自身の中のインドネシア性のようなものを感じさせられる出来事だった。
エピソードを上げ続ければきりがないが、最後は国連統治に対する私の見方を変えたもののひとつだ。国際連合では、国際職員と現地職員との間に8対1から10対1程度の給料格差を設けている。私は「国際職員」としての正規の給料を受け取ってはいなかったが、ティモール人職員の給料に関する愚痴を聞くのが日課のひとつだった。歴史家になってから知ったことだが、ポルトガル植民地時代のイベリア系職員と現地人職員の給料格差は2対1で、国連時代よりも遥かに小さかった。国連主導の選挙をボイコットし続けた村もいくつかあったが、彼らが主張していたこととは、「国連は新植民地主義だ」というものだった。このようなティモールでの実務経験のおかげで、私は外からの言説に懐疑心を抱き、ティモールにおける長期的な持続や変化に関心を持つ社会史家となった。
研究者としての考え
研究分野としての東ティモール史は、今世紀に入ってから開拓され始めた新たなフィールドだ。そこでは、様々な方向性を追求する余地が残されている。
長期的な観点から東ティモール社会の歴史を研究すると、インドネシアに対する抵抗運動史とはやや異なる面が見えてくる。例えばティモール島は、しばしば「歴史過程から隔絶された島」と形容されることがある。しかし、この島は小スンダ列島の東端に位置しており、島しょ部東南アジアやオセアニア、そしてより広いアジアの交易に白檀・蜜蝋・奴隷・なまこ等の産地として参加してきた。「インド化やイスラム化の過程からも置いてけぼりにされた」と形容されることもあるが、これも程度の問題だ。一例として、マリ・アルカティリ元首相を輩出した「アルカティリ」は、元を辿ればイエメンに行きつくムスリムの家系だが、彼らは島しょ部東南アジアの様々な地域に広がっている。「歴史から隔絶された」というのは、本国から隔絶されたポルトガル人植民者、インドネシア時代に外部から考察した活動家たちの視点だ。
また、この国の戦争の歴史についても、神話のような「一度だけの悲劇」だとは考えていない。いくつかの特殊事情(複数の外国勢力の役割、国境が引かれた島であること、難民の役割、ティモール人の戦争参加)がその繰り返しを特徴づけてきたと考えている。インドネシアによる侵略が最も有名ではあるが、各時代の研究を比較検討するならば、ポルトガルによる19世紀末からの植民地戦争(特に1911-12年のマヌファヒ戦争)、連合国と日本が介入した第二次世界大戦(1941-45年)、そしてインドネシアによる侵略(1975-99年)は、その破壊の程度や戦争の形式などにおいて、類似する点の多い戦争だったと考えている。いずれも、人口の1割から4割強が失われた凄惨な戦争で、外国勢力とディアスポラのティモール人が介入し、ティモール人同士の競争と各国の利害が絡み合う戦争だった。
西洋や日本の社会史と同じように「ティモールの歴史をティモールの文脈において」書くということは、簡単なことではない。というのは、ティモール人自身が史料を残すようになったのは、つい最近のことだからだ。ティモール史の出来事や社会の変容、人々の思想を明らかにするには、昔の植民者たちが残した史料を批判的に検討し直すことと同時に、文化人類学と対話したり、隣接する地域との比較によって類推したり、ティモール人たちの神話や伝承と史料を比較検討したりすることも重要だ。東ティモールと外国勢力の国際関係史を越えて、彼らの社会史を書くには、新しい研究手法や各国史料の比較・統合が今後求められる。
参考文献
松野明久『東ティモール独立史』早稲田大学出版部、2002年
CAVR. Chega! Final Report of the Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation, Volume 1
(Jakarta+ KPG in cooperation with STP-CAVR, 2013).
Gunn, Geoffrey.Timor Loro Sae: 500 Years. Macao: Livro do Oriente, 1999.
Hägerdal, Hans. Lords of the Land, Lords of the Sea; Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor,
1600-1800. Leiden: KITLV Press, 2012.
Jolliffe, Jill. East Timor: Nationalism and Colonialism. St. Lucia: University of Queensland Press,
1978.
Pélissier, René, Timor em Guerra: A Conquista Portuguesa, 1847-1913 (Lisboa: Editorial Estampa, 2007).
Therik, Tom. Wehali: The Female Land: Traditions of a Timorese Ritual Centre (Canbberra: Pandanus Books,
2004).
Tsuchiya, Kisho, "Constructing East Timor: History, Identity, and Place, 1850-1999." PhD Dissertation,
National University of Singapore, 2018.
-"Converting Tetun: Colonial Missionaries' Conceptual Mapping in the Timorese Cosmology and Some Local
Responses, 1874-1937." Indonesia 107 (April, 2019), pp. 75-94.
-"Indigenization of the Pacific War in Timor Island: A Multi-language Study of its Contexts and Impacts."
War & Society 38, issue 1 (2019), pp. 19-40.
-"Southeast Asian Cultural Landscape, Resistance, and Belonging in East Timor's FRETILIN Movement, 1974-75."
Journal of Southeast Asian Studies 52, no. 3 (2021), pp. 515-538.
書誌情報
土屋喜生「《エッセイ》東ティモールと私」『《アジア・日本研究 Webマガジン》アジア・マップ』1,TL.2.01(2023年3月22日掲載)
リンク: https://www.ritsumei.ac.jp/research/aji/asia_map_vol01/easttimor/essay01/