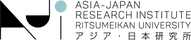アジア・マップ Vol.01 | カザフスタン
《総説》カザフスタンという国
<概要・自然・都市>
カザフスタン(カザクスタン)共和国Қазақстан Республикасыは、272万4902平方キロメートルという、世界第9位、日本の7倍以上の面積を誇る大国である。ただし人口は1919万人(2021年国勢調査)で、日本の6.5分の1弱であり、人口密度は1平方キロメートル当たり7.0人と低い。これは、国土の大半が広大な砂漠とステップ(草原)から成り、人が集住できる地域が限られているからである。
とはいえ、カザフスタンの自然は砂漠とステップに限らず非常に多彩である。南東部には天山山系の山脈(イリ・アラタウ山脈など)が連なり、中国およびクルグズスタン(キルギス)との国境に聳えるハン・テングリ山は海抜6995メートルである。山間には、グランドキャニオンに比されるシャルン峡谷や、神秘的な湖もある。東部のアルタイ山脈からはエルティス(イルティシュ)川がカザフスタン北東部を流れ、ロシアに出てオビ川に合流する。南部には天山山系のクルグズスタン側を水源とする大河シルダリヤが流れるが、ソ連時代に行われた流域の農地開発により、シルダリヤとアムダリヤが流れ込むアラル海は大幅に縮小してしまった。他方西部には世界最大の湖であるカスピ海に面する低地が広がり、最も低い窪地は海抜マイナス132メートルだが、白亜の台地や崖などの珍しい景色も見られる。
都市は、歴史的な定住民地域に近い南部を除けば、ロシア帝国期以降に建てられたものが多いが、後述の未来的都市アスタナのほか、雪をいただく山脈の麓にある旧首都・最大都市のアルマトゥ、イスラームの聖者ヤサウィーの廟があるトルキスタン、教会を含めロシア帝国期の建築が多いウラリスク、ロシア帝国期のタタール人の影響を示すモスクが残るセメイ(セミパラチンスク)など、それぞれ趣がある。
<歴史:遊牧国家からロシア帝国へ>
歴史的には、現在のカザフスタンに当たる地域は何よりも遊牧民の活動領域であった。紀元前には、スキタイと同系のサカなど、東イラン系の言語を話す遊牧民が主であり、各地に古墳を残している。ある古墳から出土した全身を金製品で装飾された人骨は、「黄金人間」として知られる。しかしその後、テュルク系の言語を話す遊牧民がモンゴル方面から来住し、先住民と混血していくプロセスが長く続いた。
特に1210年代から20年代前半のモンゴル軍による征服の結果、この地域がモンゴル帝国に包含されたことは、その後の歴史に極めて大きな影響を与えた。現カザフスタンの大部分はチンギス・カンの長男ジョチとその子孫の所領であるジョチ・ウルス(ロシアとの関係では金帳汗国などと呼ばれる)、南部・南東部は次男チャガタイ家のチャガタイ・ウルスの一部となった。遊牧民の重要な社会単位である部族も再編され、人々の大部分はテュルク系でありつつ、少なからぬ有力部族がモンゴル系の名前を持つものになった。また、現カザフスタンの南部には以前からイスラームが浸透していたが、ジョチ・ウルスとチャガタイ・ウルスの支配者の改宗により、他の地域にも徐々にイスラームの影響が広がっていった。モンゴル帝国が分裂してからも、チンギス・カンの子孫が君主など社会の上層部を形成すべきたという考えは長く残った。今でも、チンギス・カンの子孫(トレтөре)を名乗るカザフ人と出会うことは珍しくない。
1460年代、旧ジョチ・ウルス東部を支配していたジョチの末裔たちの間で争いが起き、その一部が旧チャガタイ・ウルス東部のモグーリスターンに移って新しい政権を建て、そこから再び旧ジョチ・ウルス東部に勢力を広げていった。現在のカザフスタンにほぼ相当する領域を統治したこの政権がのちにカザフ・ハン国と呼ばれ、その治下の遊牧民もカザフ(カザフ語ではカザクқазақ)人と総称されるようになった。
17世紀からモンゴル系のジュンガルとの激しい戦いを繰り返したカザフ・ハン国では、1710年代以降、複数のハンが地域ごとに並立するようになり、そのうち西部を拠点とするアブルハイル・ハンは国内外での立場を有利にするために、北方の強国ロシア帝国に接近した。彼が求めた一時的な同盟ないし保護関係を、ロシア側は1731年にロシア皇帝への「臣従」として定式化し、その後他のハンたちの臣従も受け入れていった。当初この臣属関係は形式的なものであったが、ロシアは要塞建設、ハン家の内紛の扇動、ハン任命権の掌握などを通して、カザフ人を徐々に従属させていった。それでも18世紀後半に至るまで、中部を拠点とするアブライ・スルタン(1771年からハン)がロシアと清帝国の間でバランス外交を行うなど、カザフの自立性はかなりの程度保たれていた。しかしロシアは1822年に中部、24年に西部のハン制を廃止し、カザフ草原への支配を確立した。
ロシア帝国による支配強化の過程ではしばしば反乱が起きたが、ロシアを通じて近代的な知識・文化を取り入れようとするカザフ人たちも現れ、学者ワリハノフ(1835–65)や詩人アバイ(1845–1904)らが活躍した。しかし1890年代後半以降、それまでロシア系農民により半ば自然発生的に行われていたカザフ草原への植民を帝国政府が強力に推進し、遊牧民の多くの土地が奪われるようになると、帝国の利益とカザフ人の利益の違いが目立っていった。
<ロシア革命期の自治の試みとソ連時代の苦難>
ロシア帝国の支配下で文化・社会改革によって漸進的な自立化を図っていたカザフ知識人たちは、1917年の二月革命による帝政崩壊後、民族自治の準備を進めた。そして十月革命でのボリシェヴィキによる中央政権奪取の影響を避けるために、12月に急遽、自治政府アラシュ・オルダを設立した。その後のロシア内戦の中で、アラシュ・オルダは基本的に、隣接するシベリアやウラルで力を持っていた白軍諸勢力と協調したが、自治を認められず苦境に立たされた。打開策の一つとしてアラシュ・オルダの活動家たちは、シベリア出兵でロシア極東・シベリアに来ていた日本の外交官や軍人と接触し、日本政府にアラシュ・オルダの国際承認と武器援助を求めた。彼らは、ロシア人との交渉では封印していた独立への希求やロシア人への不信を、日本人に対してはあからさまに語った。しかし白軍政権下でのロシアの復興を目標としていた日本政府は、彼らの求めに応じなかった。
アラシュ・オルダは1920年春までに消滅し、カザフスタンはソヴィエト・ロシア(1922年からソヴィエト連邦)の支配下に入った。ソ連の民族政策については、少数民族の言語を文章語にし、非ロシア人の共産党幹部を育成したことなどアファーマティヴ・アクション的な面を評価する研究者もいるが、少なくともカザフ人の場合、ソヴィエト政権が与えた自治の程度は、政治面でも文化面でも、カザフ人自身が進めていた自治運動・文化運動の目標をはるかに下回っていた。1936年にカザフ共和国が連邦構成共和国となって得た「主権」も、名目的なものだった。また、1930年代前半には、食糧徴発・遊牧民定住化・農業集団化による大飢饉で百数十万人のカザフ人が死亡し、中央アジア最大の民族だったカザフ人の人口はこれ以後、ウズベク人を下回るようになった。さらに1930年代後半には、革命期から活躍していたカザフ人政治家・知識人のほとんどがスターリンの大テロルにより処刑されるという悲劇が起きた。1949年から89年まではセミパラチンスク州(現アバイ州)で核実験が繰り返され、住民に大きな健康被害を与えた。
1953年にスターリンが死んでからは社会情勢が安定したが、54年から60年代初めのいわゆる処女地開拓でさらに多くの非カザフ人が流入したほか、教育を含めロシア語を使う場が拡大され、都市ではカザフ語を話せないカザフ人が増えるなど、ロシア化が進んだ。他方で、カザフ共和国のカザフ人エリートは着実に力をつけ、1960年代頃から伝統文化への関心も高まるなど、目立たない形での自立化も進んでいった。
1985年にソ連共産党書記長に就任したゴルバチョフのもとで行われたペレストロイカ(立て直し)政策は、当初はロシア以外の共和国への統制強化の側面を持った。カザフスタンでは1986年12月、地元に全く縁のないロシア人が共産党第一書記(共和国の事実上のトップ)に就任したことに反発する市民・学生の集会が治安部隊によって残酷に鎮圧され、それまで「解決済み」とされていたソ連の民族問題を明るみに出す事件となった。しかし、1989年6月に共産党第一書記に就任したカザフ人のナザルバエフ(90年4月からは共和国大統領を兼務)は、ソ連の分権化の流れの中で共和国の権限拡大と経済改革に取り組み、ソ連全体でも注目される政治家になった。
<独立後の複雑な歩みとさらなる発展の可能性>
ソ連解体が事実上決まった後の1991年12月16日に独立を宣言したカザフスタンは、ソ連崩壊による経済的ショックを極めて激しく受けたが、社会的な安定は比較的よく保たれた。独立前から引き続いて大統領を務めたナザルバエフは独立国家建設と諸改革に取り組んだが、次第に強権的な面も見せ、特に1995年には大統領権限を大幅に強化し権威主義体制を確立した。経済的に苦しい中でも外資を積極的に呼び込んで進めた天然資源などの開発は2000年代に実を結び、世界的な石油・ガス価格の高騰もあってカザフスタンは急速に経済成長し、2010年代にはGDPでウクライナを追い抜いて、旧ソ連地域でロシアに次ぐ経済大国となった。国際通貨基金(IMF)によれば2023年の一人当たりGDPは1万2310ドルで、ピーク時の2013年より下がっているものの、カザフスタンが中進国の地位を確立したことは間違いない。
ナザルバエフの施策の中でカザフスタンという国のあり方に大きな影響を与えたものの一つが、遷都である。1997年12月に、南東部のアルマトゥから中北部のアクモラ(現アスタナ)に首都を移したのである。巨額の費用をかけて遷都した理由についてはさまざまな説明や憶測がなされてきたが、最も重要な理由の一つは、ロシア帝国・ソ連期に植民が進められロシア人が多数を占める地域となっていた北部・北東部に近い場所に首都を置いた方が、分離主義を抑制し国土の一体性を保つのに有利だということであろう。その後の人口増加を吸収する大都市としてアルマトゥだけでは足りなかったことも、今から見れば明らかである。アスタナでは、黒川紀章による都市設計を基礎に、斬新ないし奇抜なデザインの建物が多く建てられ、近未来的な雰囲気の街になっている。
カザフスタンの人口は近年急増している。1990年代にはロシア人、ドイツ人などが国外に移住して人口が減少し、中国やモンゴルからのカザフ人の移住でもその穴を埋められない状態であった。しかし2000年代以降、経済が成長すれば出生率は下がるという常識に反し、カザフスタンはより貧しい他の中央アジア諸国と同程度以上の出生率を維持しており、2023年の国連推計による合計特殊出生率は3.0である。カザフ人の多い南部・西部では特に高く、トルキスタン州では4.52という驚異的な数字である(2022年、カザフスタン統計局)。この結果、カザフスタンの人口もカザフ人比率も大きく増えており、1989年、1999年、2021年の国勢調査データを見ると、人口は1654万人から1495万人にいったん減った後1919万人となり、カザフ人比率は39.7%から53.4%、70.4%へと伸び、ロシア人比率は37.8%から30.0%、15.5%へと大きく減った。また2021年現在、29歳以下の人々が人口の49%を占めている。
ソ連時代にロシア人などが来住しただけではなく、第二次世界大戦前後に対敵協力の疑いを着せられた少数民族がロシアなどからカザフスタンに追放されたため、独立当初のカザフスタンは著しい多民族性が特徴だったが、今やカザフ人という一つの民族を中心とする国であることが明瞭になった。今でもロシア語は広く使われているものの、カザフ語を使うべきだという雰囲気が強まり、実際の使用頻度も増している。同時に、人口および人口構成の急激な変化が、大都市周縁部への貧困層の集積など、さまざまな社会問題と結びついていることも言うまでもない。
社会・経済の著しい変化に対し、政治面ではナザルバエフの超長期政権が続いた。開明的かつ安定した政治を行う指導者というイメージのあったナザルバエフも、年を経るにつれ、個人崇拝の演出や腐敗など負の面が目立つようになり、国民の閉塞感を招いた。2019年3月に彼はついに大統領の座をトカエフに譲ったが、初代大統領としての特権とさまざまな面での権力を維持した。しかしこの「院政」は政権内部での隠れた権力闘争を生んだと見られる。そして2022年1月、市民の社会・経済問題とナザルバエフへの反感が結びついて各地で集会が開かれた際、恐らくはこの権力闘争が作用してアルマトゥなどで暴動・動乱が起きた。
トカエフはこの試練を乗り切り、ナザルバエフを失脚に追い込んで権力を固めた。しかし動乱の際に安全保障条約機構(CSTO)の平和維持部隊(武力行使はしなかった)を派遣してトカエフに恩を売ったロシアのプーチン政権が、翌2月にウクライナ侵略戦争を始めたことは、彼にとって新たな難題となった。だがトカエフは動じず、ロシアとの友好関係を維持しつつも戦争とは明確に一線を画し、ウクライナの領土的一体性を支持し、カザフスタンが欧米の対露制裁の抜け道とならないための施策を取っている。これまで基本的に親ロシア的だった国内世論も、ロシアへの警戒感を急速に強めている。かつてカザフスタンは、隣国ロシアと他の大国の利益が大きくは矛盾しないことを前提に「多ベクトル外交」を展開したが、今や対立する諸大国の間で生き延びるための新たな多ベクトル外交が必要となっている。
このように国内外にさまざまな課題を抱えるカザフスタンだが、石油・ガスを豊富に産出するだけでなくウラン、クロムなど多くの鉱物資源の埋蔵量が世界トップクラスで、人口増とともに市場および若く活気ある人材の規模が拡大し、近年はモバイル決済などIT化が急速に進んでいる国として、さらなる発展の可能性を持っている。遊牧の歴史を背景とする独自の文化とその現代的な展開も魅力である。日本としても、ユーラシア大陸の中央という地政学・地経学的に重要な位置にあるこの国との関係強化の必要性を、より強く意識する必要があるだろう。
【参考文献】
宇山智彦、藤本透子編著『カザフスタンを知るための60章』明石書店、2015年。
野田仁『露清帝国とカザフ=ハン国』東京大学出版会、2011年。
小野亮介、宇山智彦「カザフ自治政府アラシュ・オルダとシベリア出兵期日本の邂逅と齟齬:マルセコフ要請書と関連史料から見る背景」小野亮介、海野典子編『近代日本と中東・イスラーム圏:ヒト・モノ・情報の交錯から見る』東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、2022年、127–199頁。https://doi.org/10.15026/120719
宇山智彦「カザフスタンのナザルバエフ「院政」:旧ソ連諸国における権力継承の新モデル?」『ロシアNIS調査月報』2019年6月号、43–56頁。
宇山智彦「カザフスタン動乱にみる国民の不満と権力闘争:ナザルバエフ体制解体の試練」『外交』Vol. 71、2022年、73–77頁。http://www.gaiko-web.jp/test/wp-content/uploads/2022/01/Vol71_73-77_Kazakhstan.pdf
書誌情報
宇山智彦「《総説》カザフスタンという国」『《アジア・日本研究 Webマガジン》アジア・マップ』1, KZ.1.04(2023年9月5日掲載)
リンク: https://www.ritsumei.ac.jp/research/aji/asia_map_vol01/kazakhstan/country/