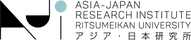アジア・マップ Vol.01 | レバノン
《エッセイ》
レバノンという国
レバノン共和国は、地中海の東岸に位置するアラブ諸国の1つである。北はトルコ、南はパレスチナ/イスラエル、東はシリアと接する、日本の岐阜県ほどの大きさ(10,452平方キロメートル)の小国である。人口は529万人(2022年)、その半数近くが首都ベイルートとその近郊で暮らしている。
レバノンの国家形成は、20世紀初頭の第一次世界大戦後に本格化した「歴史的シリア」の領域分割の時期に遡り、戦勝国となった英仏両国による領域分割と国境線の画定が発端となった。「歴史的シリア」とは、ダマスカス(アラビア語では「シャーム」)を中心とした広大な領域を指す言葉であり、現在のシリア、レバノン、ヨルダン、パレスチナ/イスラエル、イラクとトルコの一部を含む緩やかな地理的概念であった。
この「歴史的シリア」(アラビア語で「ビラード・アッシャーム(シャームのくにぐに)」)は、16 世紀以降オスマン帝国による支配を受けていたが、第一次世界大戦での帝国の敗北・解体後に英仏による委任統治下に置かれた際に現在の国境線が創出された。こうして上記の諸国の国家形成が進んだが、この地に暮らす人々の意思よりも西洋列強の思惑が強く働いた結果、いずれの国においても領域、国民、主権をめぐるポストコロニアルな問題を抱えることとなった。このような西洋列強による「歴史的シリア」の領域分割の問題が最も悲劇的なかたちで露呈したのが、21世紀の今日まで続くパレスチナ/イスラエル紛争であろう。
この領域分割の結果、レバノンは、イスラーム教徒が圧倒的多数を占める中東地域において非イスラーム教徒の住民を多く抱える数少ない国として「創出」された。多様な宗教・宗派の権利を尊重するために17(1989年の憲法改正以降は18)の公認宗派を設定し、その平和的・民主的な共存のために「宗派制度」と呼ばれる独自の政治体制を採用してきた。
「宗派制度」とは、1943年の独立時にマロン派キリスト教徒とスンナ派イスラーム教徒のあいだでかわされた不文律「国民協約」を根拠に、政治的ポストや公職を宗派別の人口比に応じて配分する制度であった。フランスによる委任統治下の1932年に行われたセンサス(人口調査)によれば、主要三宗派について見れば、総人口においてマロン派が28.8パーセント、スンナ派が22.4パーセント、シーア派が19.6パーセントであり、キリスト教徒であるマロン派が人口面での最大宗派であった。
レバノンは議会制民主主義を採用したため、国民議会の議席も人口比に基づき各宗派に割り当てられた。その配分は1932年のセンサスに依拠し、1990年に改正されるまでキリスト教各派とイスラーム教各派の議席数の配分は6:5とされた(現在は5:5)。さらには、重要な政治的ポストに関しては、大統領はマロン派、首相はスンナ派、国会議長はシーア派出身者が就任する慣例が生まれた。
宗教、宗派、エスニシティに基づく少数派を国民統合の名のもとに弾圧してきた多くの中東諸国―――そのほとんどが権威主義体制―――のなかで、レバノンは人間どうしの差異を前提とする多元社会の実現に取り組んできた希有な国である。事実、この多様性を基礎とした独自の「多極共存型民主主義」はレバノンに経済的な繁栄をもたらし、1945年の独立から30年ものあいだ中東における「近代化の優等生」となった。首都ベイルートは、中東で西洋的な近代化が最も進んだ街として、「中東のパリ」と呼ばれた。
だが、宗派間の権力分有に基づく共存のシステムは、宗派の利権集団化という副産物を生んだ。近代化に伴う社会変容や国際情勢の変化によって宗派間のパワーバランスが崩れたとき、その副産物は内戦という劇的なかたちでレバノンに破壊と暴力の嵐をもたらした。特に、1960年代から70年代にかけてパレスチナ難民やパレスチナ解放機構(PLO)のゲリラが大量に流入したことに対して、国内の政治勢力間の政策上・イデオロギー上の不和が拡大した。これが、1975年から1990年まで続いた未曾有の内戦の引き金となった。
つまり、レバノンは、中東における宗派・宗教の平和的・民主的な共存の壮大な実験場であり、その成功と失敗の両方を体現してきたのである。
レバノンは、しばしば「中東の縮図」と言われる。すなわち、国内と国外のアクターが結びつくかたちで複雑な構図の政治対立や紛争を発生させる特徴を持っている。レバノンでの利権集団化した宗派間の権力闘争は、米国、フランス、イスラエル、シリア、イラン、エジプト、サウジアラビアなどの国外アクターの介入を招いてきた。こうした介入は1990年の内戦の終結といった安定と秩序をもたらす反面、特定の国内アクターと癒着することによって対立を助長し、政治の不安定化を促進する場合もあった。
例えば、イランはいわゆる「革命の輸出」戦略の一貫として、シーア派のイスラーム主義運動であるヒズブッラー(ヒズボラ)への支援を通してレバノンでの影響力の拡大につとめてきた。これに対して、米国やイスラエル、サウジアラビアといったイランの影響力の拡大を危惧する諸外国が、ヒズブッラーと敵対する国内アクターを陰に陽に支えるといった事態が見られてきた。
つまり、レバノンの安定と不安定の両方が国際政治の動静に委ねられており、その結果、国内問題が国際問題化し、国際問題が国内問題化するいわば「メビウスの輪」のような状態が続いてきた。
国際問題のなかでも特にレバノンに影響を与えてきたのは、上述の内戦の引き金ともなったパレスチナ問題である。レバノンは、中東戦争で四度にわたってイスラエルと戦火を交えたことに加えて、1978年、1982年、1993年、1996年、2006年の五度に及ぶ同国による軍事侵攻を受けてきた。エジプト、ヨルダン、パレスチナが次々とイスラエルと和平に向かうなか、レバノンはいまだにイスラエルとの戦時体制にある。戦時下という点においては東の隣国シリアも同様であるが、シリアが1973年の第四次中東戦争以来イスラエルと「冷戦」状態にあるのに対して、レバノンは紛れもなく「熱戦」の最中にある。
こうした「メビウスの輪」のようなレバノンの状態は、1975年からの15年間の「内戦の時代」はもちろんのこと、1990年の内戦終結以降も続いている。とはいえ、レバノンが少しずつではあるが、その姿を変えてきたのも事実である。特に政治のあり方については、大きな変化を経験している。
「内戦の時代」の後に訪れたのは、「疑似権威主義の時代」であった。1990年に内戦を戦った民兵組織が停戦に合意し、宗派制度に基づく民主政治が再開したことから、この時代は、内戦以前の「第一共和制」に対して「第二共和制」と呼ばれる。しかし、実際には隣国シリアによる実効支配下(軍事的・政治的・経済的支配)に置かれ、政府の意思決定がシリア政府に大きく委ねられていた。形式的には民主主義的な議会制をとっていながら、シリアと密接なつながりを持った一部の集団が独裁的な権力を行使していたという点において、この時期のレバノン政治は、疑似的な権威主義に分類できる。
このシリアによる実効支配は、2005年の民衆革命、通称「杉の木革命」によって終焉を迎えた。「民主化の時代」の到来であった。シリアの政治的影響力が後退したことでレバノン独自の多極共存型民主主義が再び花開いたものの、しかしながら、結果、大統領、内閣、国民議会の全てが機能を麻痺させた。それだけではなく、長引く政治対立は武装した市民や民兵による武力衝突を引き起こし、内戦の再発すら囁かれるような事態になった。この時期のレバノン政治は、民主主議に分類できるものの、平和や繁栄を約束するものにはならなかった。
こうして、政府の機能が麻痺し続けることで、レバノンの社会は荒廃し、人々の間に深刻な不安と亀裂が生じるのは必然であった。2019年末には、権力闘争に明け暮れる旧来からの政治家に対する全国規模の抗議デモが発生し、無党派や独立系の政治家の台頭が見られるようになった。しかし、それでも、レバノンを長年主導してきた政治家の地位を切り崩すまでには至っておらず、事態は好転していない。2020年春には、レバノン史上初のデフォルト(債務不履行)の宣言を余儀なくされ、その後も、内戦終結後最悪の社会経済的危機期が続いている。
書誌情報
末近浩太「《総説》レバノンという国」『《アジア・日本研究 Webマガジン》アジア・マップ』1, LB.1.03(2023年7月20日掲載)
リンク: https://www.ritsumei.ac.jp/research/aji/asia_map_vol01/lebanon/country/